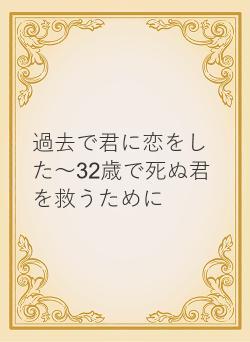その日も男は、仕事の帰りに砂浜へと立ち寄っていた。陽はすでに傾き、空の端には朱色が広がっていた。潮風が頬を撫でる中、彼はいつものように浜辺に腰を下ろし、波の寄せては返す音に耳を澄ませていた。特に目的があるわけではない。ただ、こうして海を眺めることが、彼にとっては日々の中のささやかな習慣だった。
波打ち際には、ところどころに海藻が打ち上げられ、白い泡が砂の上でかすかに弾けていた。その時、ふと視界の端に人影が入った。
若い女性だった。
彼女は浜の向こうから、裸足のまま波間を歩いていた。年の頃は、男より少し若く見えた。二十歳前後だろうか。海から吹いてくる風に髪を揺らし、細い足で、濡れた砂を踏みしめている。その姿にはどこか浮世離れした静けさがあり、まるで海そのものが形を変えて現れたかのようだった。
男は不思議と目を離せなかった。彼女の装いは控えめで、白っぽいワンピースに、軽い上着を羽織っているだけだったが、その素朴さがかえって際立つほどの美しさがあった。肌は透けるように白く、足元を洗う波の冷たさを感じていないかのように、無表情にも見える穏やかな顔で海を見つめていた。
ふと、彼女と男の視線が交わった。
彼女は軽く会釈をした。それはほんの小さな動きだったが、なぜか男の胸にすっと入り込んできた。無理に笑うでもなく、照れるでもなく、ただ、そこにいた人間に対して自然に向けられた仕草だった。
「こんばんは」と男が声をかけた。
彼女は一瞬だけ戸惑ったように見えたが、すぐにかすかに微笑んで、「こんばんは」と返した。その声は驚くほど静かで、しかし波音にも消えずに耳に残った。
男は、なぜ彼女がこんな夕暮れ時にひとりで海を歩いていたのか、聞こうとは思わなかった。ただ、彼女の足元に小さな巻貝があるのが見えた。その貝は、まるで彼女が歩いたあとの印のようにそこにあり、彼女はそれを拾い上げると、しばらく見つめてからポケットにそっとしまった。
それが、彼女との最初の出会いだった。
男はなぜか、あの貝の持つ光沢が、海そのものの記憶を閉じ込めているような気がしてならなかった。
波打ち際には、ところどころに海藻が打ち上げられ、白い泡が砂の上でかすかに弾けていた。その時、ふと視界の端に人影が入った。
若い女性だった。
彼女は浜の向こうから、裸足のまま波間を歩いていた。年の頃は、男より少し若く見えた。二十歳前後だろうか。海から吹いてくる風に髪を揺らし、細い足で、濡れた砂を踏みしめている。その姿にはどこか浮世離れした静けさがあり、まるで海そのものが形を変えて現れたかのようだった。
男は不思議と目を離せなかった。彼女の装いは控えめで、白っぽいワンピースに、軽い上着を羽織っているだけだったが、その素朴さがかえって際立つほどの美しさがあった。肌は透けるように白く、足元を洗う波の冷たさを感じていないかのように、無表情にも見える穏やかな顔で海を見つめていた。
ふと、彼女と男の視線が交わった。
彼女は軽く会釈をした。それはほんの小さな動きだったが、なぜか男の胸にすっと入り込んできた。無理に笑うでもなく、照れるでもなく、ただ、そこにいた人間に対して自然に向けられた仕草だった。
「こんばんは」と男が声をかけた。
彼女は一瞬だけ戸惑ったように見えたが、すぐにかすかに微笑んで、「こんばんは」と返した。その声は驚くほど静かで、しかし波音にも消えずに耳に残った。
男は、なぜ彼女がこんな夕暮れ時にひとりで海を歩いていたのか、聞こうとは思わなかった。ただ、彼女の足元に小さな巻貝があるのが見えた。その貝は、まるで彼女が歩いたあとの印のようにそこにあり、彼女はそれを拾い上げると、しばらく見つめてからポケットにそっとしまった。
それが、彼女との最初の出会いだった。
男はなぜか、あの貝の持つ光沢が、海そのものの記憶を閉じ込めているような気がしてならなかった。