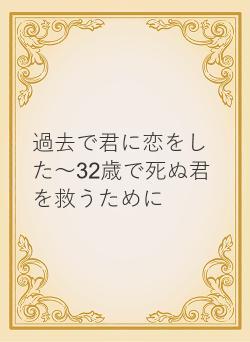その夜も、月は静かに満ちていた。
男はひとり、砂浜に立っていた。手には、あの貝殻。波打ち際の光をすくい取るように、そっと抱えている。
夜の海は、昼間よりもずっと近くに感じられた。ざわめきは低く、深く、どこかで名を呼んでいるようでもあった。風はほとんど吹いていなかった。ただ月の光だけが、まっすぐに海へ降りていた。
男は足元の砂を見下ろした。その粒の一つひとつが、すべて彼女と出会った日からここまでを覚えているような気がした。
忘れようとしたこと。忘れられなかったこと。声も、笑みも、沈黙も、目を伏せたときの仕草も。彼女のすべてが、まるで潮のように心の内で押し寄せては引いていった。
彼女が戻っていった海は、すぐそこにあった。
手の中の貝殻が、ふいに温もりを帯びた気がした。それは錯覚だったかもしれない。ただの冷たい貝殻かもしれない。でも、男にはわかった。この中に、彼女がいるのだと。
気づけば、男は靴を脱ぎ、波打ち際へ歩き出していた。
一歩ごとに、砂の感触が変わる。水の冷たさが足をなぞっていく。
それでも止まらなかった。彼女の声が呼ぶわけでもなく、姿が見えるわけでもない。それでも、海の奥に彼女がいると、なぜか疑う余地がなかった。
膝まで水に浸かったとき、男は月を仰いだ。その光が、まるで道しるべのように海面に続いていた。
心の中には恐れもあった。けれど、それ以上に確かな何かがあった。
行かなければならない、という感情ではなかった。
ただ、彼女がそこにいるなら、自分もそこにいたい。
それだけだった。
そして男は、ゆっくりと水の中へ入っていった。
肩が沈み、胸が隠れ、やがて顔までもが月の影に溶けていった。
波がひとつ、静かに打ち寄せ、去っていったあとには、男の姿はもうどこにもなかった。
男は海の国に辿り着いたのか、女と再び出会えたのか。
それは、誰にもわからない。
男はひとり、砂浜に立っていた。手には、あの貝殻。波打ち際の光をすくい取るように、そっと抱えている。
夜の海は、昼間よりもずっと近くに感じられた。ざわめきは低く、深く、どこかで名を呼んでいるようでもあった。風はほとんど吹いていなかった。ただ月の光だけが、まっすぐに海へ降りていた。
男は足元の砂を見下ろした。その粒の一つひとつが、すべて彼女と出会った日からここまでを覚えているような気がした。
忘れようとしたこと。忘れられなかったこと。声も、笑みも、沈黙も、目を伏せたときの仕草も。彼女のすべてが、まるで潮のように心の内で押し寄せては引いていった。
彼女が戻っていった海は、すぐそこにあった。
手の中の貝殻が、ふいに温もりを帯びた気がした。それは錯覚だったかもしれない。ただの冷たい貝殻かもしれない。でも、男にはわかった。この中に、彼女がいるのだと。
気づけば、男は靴を脱ぎ、波打ち際へ歩き出していた。
一歩ごとに、砂の感触が変わる。水の冷たさが足をなぞっていく。
それでも止まらなかった。彼女の声が呼ぶわけでもなく、姿が見えるわけでもない。それでも、海の奥に彼女がいると、なぜか疑う余地がなかった。
膝まで水に浸かったとき、男は月を仰いだ。その光が、まるで道しるべのように海面に続いていた。
心の中には恐れもあった。けれど、それ以上に確かな何かがあった。
行かなければならない、という感情ではなかった。
ただ、彼女がそこにいるなら、自分もそこにいたい。
それだけだった。
そして男は、ゆっくりと水の中へ入っていった。
肩が沈み、胸が隠れ、やがて顔までもが月の影に溶けていった。
波がひとつ、静かに打ち寄せ、去っていったあとには、男の姿はもうどこにもなかった。
男は海の国に辿り着いたのか、女と再び出会えたのか。
それは、誰にもわからない。