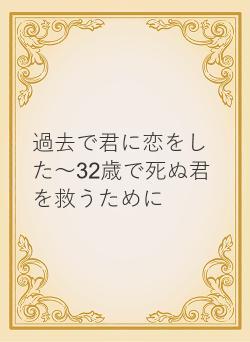日々は、何事もなかったような顔をして過ぎていった。
男はいつも通りに朝起き、顔を洗い、仕事へ向かった。通勤電車の窓の外に流れる街の景色も、職場で交わされる会話も、何一つ変わってはいなかった。誰もが、それぞれの日常を静かに演じるように生きている。男もその一人だった。
けれど、心の奥には、ぽっかりと空いた空白があった。
あの夜の記憶は、夢だったのではないかと何度も思った。けれど、部屋の片隅にある小さな木箱を開けるたび、夢ではないという現実に引き戻された。そこには、あの鱗が静かに眠っていた。海の色を秘めた、たった一枚の鱗。その美しさは、日を追うごとに深みを増しているようにさえ思えた。
彼女がいなくなったあと、男は何度か砂浜に足を運んだ。けれど、もうあの姿はなかった。夕暮れの光の中に、似た後ろ姿を探しては落胆し、波打ち際に立って風を受けながら、ただ空を見つめるしかなかった。
「忘れよう」と思った。
それが、男にできる唯一の防衛だった。思い出せば思い出すほどに、彼女の声や手のぬくもりが、胸に痛みとして蘇ってくる。だから、考えないようにした。仕事に没頭し、早めに寝て、必要以上に余白をつくらないよう心がけた。誰かと話すときも、気丈にふるまい、できる限り明るい表情を装った。
けれど、それは長くは続かなかった。
夜、静かな部屋でひとりになると、彼女のことばかりが浮かんだ。あのとき交わした言葉、抱きしめた感触、そして、月明かりの中で海へと帰っていった姿。そのどれもが、彼の中で生きていた。むしろ、時が経つほどに、彼女の存在はより鮮明に、より美しく蘇ってきた。
「本当に、これでよかったんだろうか」
男は何度も自分に問いかけた。彼女が選んだ道を尊重しようと思ったはずだった。けれど、尊重の裏に隠れていたのは、諦めという名の無力感だったのかもしれない。
そう思うようになってから、心の奥底に、小さな火種のような感情が芽を出した。
——自分も、あの海の国で暮らせるのではないか。
最初はあり得ないことだと笑い飛ばした。人間が人魚の世界で暮らせるわけがないと、理屈で否定した。けれど、理屈では心を納得させることはできなかった。彼女がいたあの世界を、自分も知りたいと思った。あの深い海の奥で、彼女が今どんなふうに過ごしているのか。それを想像するたびに、胸の奥が締めつけられた。
彼女にもう一度会いたい。
ただそれだけだった。理由も、意味も、もうどうでもよかった。ただ、もう一度、あの目を、あの声を、確かめたかった。
もしかしたら、海の国で人間が暮らすことなんて不可能かもしれない。けれど、彼女がいた。彼女は確かにこの世界に姿を現し、言葉を交わし、心を通わせてくれた。あれほどの奇跡が起きたのなら、自分が海の国に生きることも、決して不可能ではないのかもしれない。
男は、鱗の入った木箱を手に取り、ゆっくりと開けた。
中で、青く光るその一枚の鱗は、まるで呼吸するかのように、淡く光を返していた。
男はその光をじっと見つめながら、胸の奥に確かな想いを抱いた。
男はいつも通りに朝起き、顔を洗い、仕事へ向かった。通勤電車の窓の外に流れる街の景色も、職場で交わされる会話も、何一つ変わってはいなかった。誰もが、それぞれの日常を静かに演じるように生きている。男もその一人だった。
けれど、心の奥には、ぽっかりと空いた空白があった。
あの夜の記憶は、夢だったのではないかと何度も思った。けれど、部屋の片隅にある小さな木箱を開けるたび、夢ではないという現実に引き戻された。そこには、あの鱗が静かに眠っていた。海の色を秘めた、たった一枚の鱗。その美しさは、日を追うごとに深みを増しているようにさえ思えた。
彼女がいなくなったあと、男は何度か砂浜に足を運んだ。けれど、もうあの姿はなかった。夕暮れの光の中に、似た後ろ姿を探しては落胆し、波打ち際に立って風を受けながら、ただ空を見つめるしかなかった。
「忘れよう」と思った。
それが、男にできる唯一の防衛だった。思い出せば思い出すほどに、彼女の声や手のぬくもりが、胸に痛みとして蘇ってくる。だから、考えないようにした。仕事に没頭し、早めに寝て、必要以上に余白をつくらないよう心がけた。誰かと話すときも、気丈にふるまい、できる限り明るい表情を装った。
けれど、それは長くは続かなかった。
夜、静かな部屋でひとりになると、彼女のことばかりが浮かんだ。あのとき交わした言葉、抱きしめた感触、そして、月明かりの中で海へと帰っていった姿。そのどれもが、彼の中で生きていた。むしろ、時が経つほどに、彼女の存在はより鮮明に、より美しく蘇ってきた。
「本当に、これでよかったんだろうか」
男は何度も自分に問いかけた。彼女が選んだ道を尊重しようと思ったはずだった。けれど、尊重の裏に隠れていたのは、諦めという名の無力感だったのかもしれない。
そう思うようになってから、心の奥底に、小さな火種のような感情が芽を出した。
——自分も、あの海の国で暮らせるのではないか。
最初はあり得ないことだと笑い飛ばした。人間が人魚の世界で暮らせるわけがないと、理屈で否定した。けれど、理屈では心を納得させることはできなかった。彼女がいたあの世界を、自分も知りたいと思った。あの深い海の奥で、彼女が今どんなふうに過ごしているのか。それを想像するたびに、胸の奥が締めつけられた。
彼女にもう一度会いたい。
ただそれだけだった。理由も、意味も、もうどうでもよかった。ただ、もう一度、あの目を、あの声を、確かめたかった。
もしかしたら、海の国で人間が暮らすことなんて不可能かもしれない。けれど、彼女がいた。彼女は確かにこの世界に姿を現し、言葉を交わし、心を通わせてくれた。あれほどの奇跡が起きたのなら、自分が海の国に生きることも、決して不可能ではないのかもしれない。
男は、鱗の入った木箱を手に取り、ゆっくりと開けた。
中で、青く光るその一枚の鱗は、まるで呼吸するかのように、淡く光を返していた。
男はその光をじっと見つめながら、胸の奥に確かな想いを抱いた。