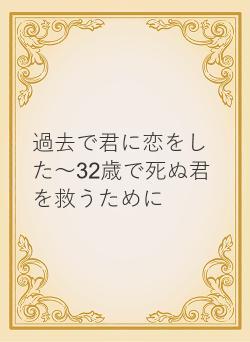月は、波打ち際の白い線を静かに照らしていた。
ふたりは海の前に立っていた。もう言葉はなかった。ただ、並んで立っているだけで、互いの心にあるものがゆっくりと染み出していくような、そんな静かな時間だった。
女は、男の方へ体を向けた。微笑んでいるようにも見えたが、その顔に浮かぶ表情は、どこかこの世のものではない静けさをたたえていた。
「ありがとう」
それだけを、ほんの小さく、女は言った。声は風に溶けるようにして消えていった。
男は何も言えなかった。言いたい言葉は胸の奥にあった。けれど、それを言葉にした瞬間、何かが壊れてしまう気がして、唇は閉じられたままだった。
女はひとつ小さく息を吸ってから、ゆっくりと海の方へ歩き出した。裸足の足が、波打ち際の濡れた砂に静かに沈んでいく。
男はその後ろ姿をじっと見つめていた。声をかけたいという衝動が一瞬、喉元までこみあげたが、それを飲み込んだ。いま呼び止めることは、彼女を縛ることになる。彼女が自分の場所に帰るという決意を、何より彼は尊重したかった。
水面が、女の足首を、やがて膝を、静かに包んでいく。
そのときだった。月の光が差し込む水の中で、彼女の脚の輪郭がふと揺らいだ。膝まで水に浸かった彼女の脚が、なめらかな一続きの線に変わっていくのが見えた。光を受けてきらきらと反射する細かな鱗が、まるで海と一体になるように広がっていく。
腰から下が、しなやかで流線形の姿に変わっていく。
男は思わず息を呑んだ。夢を見ているようだった。しかし、これはたしかに現実だった。波間にゆらぐその姿は、彼女のもうひとつの真実――人魚としての姿だった。
けれど、それまでの彼女の優しさや静けさとまったく同じ、美しさをたたえた姿だった。
彼女は一度だけ振り返った。瞳が月の光を受けて揺れていた。その目に、言葉はなかったが、男にはたしかに伝わってきた。「さようなら」と「ありがとう」と「忘れないで」という、いくつもの想いが重なったまなざしだった。
男は、無言のまま、ただ深くうなずいた。
そして彼女は、さらに海の奥へと進み、波間にその姿が沈んでいった。尾ひれが水をすべり、白い飛沫がひとしずく宙に舞った。
やがてその姿も、波とともに見えなくなった。
残された男は、海を見つめたまま、しばらくその場を動けなかった。
心のどこかで、まだ彼女が水面から顔を出し、あの笑みを見せるのではないかという気持ちが残っていた。けれど、波はただ同じ調子で寄せては返し、海は何も語らなかった。
男は、そっと胸元のポケットに手を入れた。そこには、あの小さな鱗が、今もひんやりとした感触のまま収まっていた。
彼女はもういない。けれど、ここにいる。たしかに、この鱗のひとひらに、その想いが宿っている。
男は目を閉じた。そして胸の奥に、彼女のぬくもりを深く感じながら、月に照らされた海を、静かに見つめ続けていた。
ふたりは海の前に立っていた。もう言葉はなかった。ただ、並んで立っているだけで、互いの心にあるものがゆっくりと染み出していくような、そんな静かな時間だった。
女は、男の方へ体を向けた。微笑んでいるようにも見えたが、その顔に浮かぶ表情は、どこかこの世のものではない静けさをたたえていた。
「ありがとう」
それだけを、ほんの小さく、女は言った。声は風に溶けるようにして消えていった。
男は何も言えなかった。言いたい言葉は胸の奥にあった。けれど、それを言葉にした瞬間、何かが壊れてしまう気がして、唇は閉じられたままだった。
女はひとつ小さく息を吸ってから、ゆっくりと海の方へ歩き出した。裸足の足が、波打ち際の濡れた砂に静かに沈んでいく。
男はその後ろ姿をじっと見つめていた。声をかけたいという衝動が一瞬、喉元までこみあげたが、それを飲み込んだ。いま呼び止めることは、彼女を縛ることになる。彼女が自分の場所に帰るという決意を、何より彼は尊重したかった。
水面が、女の足首を、やがて膝を、静かに包んでいく。
そのときだった。月の光が差し込む水の中で、彼女の脚の輪郭がふと揺らいだ。膝まで水に浸かった彼女の脚が、なめらかな一続きの線に変わっていくのが見えた。光を受けてきらきらと反射する細かな鱗が、まるで海と一体になるように広がっていく。
腰から下が、しなやかで流線形の姿に変わっていく。
男は思わず息を呑んだ。夢を見ているようだった。しかし、これはたしかに現実だった。波間にゆらぐその姿は、彼女のもうひとつの真実――人魚としての姿だった。
けれど、それまでの彼女の優しさや静けさとまったく同じ、美しさをたたえた姿だった。
彼女は一度だけ振り返った。瞳が月の光を受けて揺れていた。その目に、言葉はなかったが、男にはたしかに伝わってきた。「さようなら」と「ありがとう」と「忘れないで」という、いくつもの想いが重なったまなざしだった。
男は、無言のまま、ただ深くうなずいた。
そして彼女は、さらに海の奥へと進み、波間にその姿が沈んでいった。尾ひれが水をすべり、白い飛沫がひとしずく宙に舞った。
やがてその姿も、波とともに見えなくなった。
残された男は、海を見つめたまま、しばらくその場を動けなかった。
心のどこかで、まだ彼女が水面から顔を出し、あの笑みを見せるのではないかという気持ちが残っていた。けれど、波はただ同じ調子で寄せては返し、海は何も語らなかった。
男は、そっと胸元のポケットに手を入れた。そこには、あの小さな鱗が、今もひんやりとした感触のまま収まっていた。
彼女はもういない。けれど、ここにいる。たしかに、この鱗のひとひらに、その想いが宿っている。
男は目を閉じた。そして胸の奥に、彼女のぬくもりを深く感じながら、月に照らされた海を、静かに見つめ続けていた。