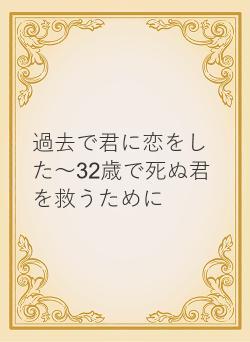海沿いの町のはずれに、ひとりの若い男が暮らしていた。潮風に晒された木造の一軒家は、小さな入り江を見下ろすように建っていて、周囲には背の高い草と、ごつごつとした岩場が広がっていた。観光地からは外れており、町の喧騒も届かないその場所は、波の音と風のざわめきだけが支配する、静かな世界だった。
男は二十代前半。物静かで、実直な性格をしていた。町の工務店で働き、朝は早くに家を出て、夕方には真っ直ぐ帰ってきた。派手な交友関係もなく、休日にはよく浜辺を歩きながら、空や海をじっと見つめていた。何かを探すような、あるいは何かを思い出そうとしているような、そのまなざしは、通りすがりの誰かの心にも静かな余韻を残すようだった。
町の人々は、彼のことを「真面目すぎて損な役回りをするタイプ」と口にすることが多かったが、それが悪口になることはなかった。彼は誰にでも礼儀正しく、頼まれた仕事には手を抜かず、ひとつずつ丁寧に仕上げた。
家には一人で住んでいた。両親とは別々に暮らしていて、食事も洗濯もすべて自分でこなしていた。質素な部屋には余計な飾りもなく、唯一目を引くのは、窓際の棚に並べられた色とりどりの貝殻と、古びた写真立てだった。
彼にとって、海はただの風景ではなかった。仕事の疲れを静かに溶かしてくれる場所であり、心を空にするための場所だった。波の音は言葉のいらない対話のようで、砂浜に立ち尽くしていると、ひとりでいることが少しだけやわらぐような気がしていた。
男は二十代前半。物静かで、実直な性格をしていた。町の工務店で働き、朝は早くに家を出て、夕方には真っ直ぐ帰ってきた。派手な交友関係もなく、休日にはよく浜辺を歩きながら、空や海をじっと見つめていた。何かを探すような、あるいは何かを思い出そうとしているような、そのまなざしは、通りすがりの誰かの心にも静かな余韻を残すようだった。
町の人々は、彼のことを「真面目すぎて損な役回りをするタイプ」と口にすることが多かったが、それが悪口になることはなかった。彼は誰にでも礼儀正しく、頼まれた仕事には手を抜かず、ひとつずつ丁寧に仕上げた。
家には一人で住んでいた。両親とは別々に暮らしていて、食事も洗濯もすべて自分でこなしていた。質素な部屋には余計な飾りもなく、唯一目を引くのは、窓際の棚に並べられた色とりどりの貝殻と、古びた写真立てだった。
彼にとって、海はただの風景ではなかった。仕事の疲れを静かに溶かしてくれる場所であり、心を空にするための場所だった。波の音は言葉のいらない対話のようで、砂浜に立ち尽くしていると、ひとりでいることが少しだけやわらぐような気がしていた。