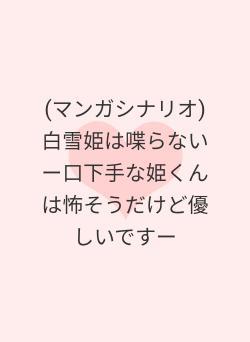「私があんなこと言ったから佐藤くん学校辞めれないんだよね……」
「……勝手に背負って勝手に落ち込まないでくれる?」
勝手に自責の念にかられている相沢に俺は一度わざと大袈裟にため息を吐いてから声をかける。
多分、あの時相沢が俺に声をかけなかったら学校なんてとうに辞めてたと思う。
でも、あの時相沢が声をかけてくれたから、俺は学校を辞めなかった。
まぁ相沢の言った通りに停学が終わっても暫くは休んでいたのも事実だけど、それでもちゃんと在学はしている。
ただ、戻るタイミングを見失っていただけで。
「佐藤、くん……?」
俺はそっと相沢の頬に手を添える。
こんな真冬に外に立っていたから相沢の頬は冷たく冷えていて、でも触れている部分は二人の体温で少しずつ暖かくなっていく。
「……待っててよ、ちゃんと行くから、待ってて、ね?」
俺はそのまま少し屈んで相沢の顔を覗き込む。
そして出来る限り優しい口調を努めて言いきると最後には笑って見せる。
誰かに笑いかけるのなんて久しぶり過ぎて上手く笑えていたかは分からないけれど。
「あ、もう踏み切りの鐘止まってるな、それじゃ、また明日」
その頃には踏み切りはすっかり静かになっていて、俺はいつものように手を振りながら相沢と別れた。
「……勝手に背負って勝手に落ち込まないでくれる?」
勝手に自責の念にかられている相沢に俺は一度わざと大袈裟にため息を吐いてから声をかける。
多分、あの時相沢が俺に声をかけなかったら学校なんてとうに辞めてたと思う。
でも、あの時相沢が声をかけてくれたから、俺は学校を辞めなかった。
まぁ相沢の言った通りに停学が終わっても暫くは休んでいたのも事実だけど、それでもちゃんと在学はしている。
ただ、戻るタイミングを見失っていただけで。
「佐藤、くん……?」
俺はそっと相沢の頬に手を添える。
こんな真冬に外に立っていたから相沢の頬は冷たく冷えていて、でも触れている部分は二人の体温で少しずつ暖かくなっていく。
「……待っててよ、ちゃんと行くから、待ってて、ね?」
俺はそのまま少し屈んで相沢の顔を覗き込む。
そして出来る限り優しい口調を努めて言いきると最後には笑って見せる。
誰かに笑いかけるのなんて久しぶり過ぎて上手く笑えていたかは分からないけれど。
「あ、もう踏み切りの鐘止まってるな、それじゃ、また明日」
その頃には踏み切りはすっかり静かになっていて、俺はいつものように手を振りながら相沢と別れた。