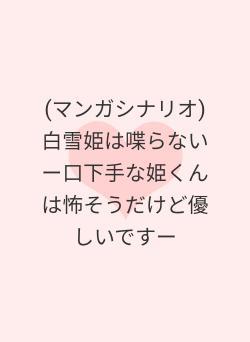「俺、嫌いなんだよねそういうの」
「……え」
ふと、いつものように目の前の踏み切りを眺めていたらそんな風に声をかけられた。
驚いて声のしたほうを向けばフードを目深に被った人が立っていて、なぜか怖いよりもいつ来たのかそれが先立った。
「別に死ぬのは勝手だけどさ、せめて人の迷惑にならない方法にしなよ」
男性はちらりと一瞬こちらに視線を向けて、それからまた目の前の降りた踏み切りに視線を戻す。
「なんで……そう思ったんですか?」
死ぬ、その言葉で私がこの踏み切りで飛び込み自殺をする、この人はそう考えてわざわざ声をかけてくれたのだろうと察するには余りあった。
確かにそれなりに永い時間ここに立ってはいたけどどうしてその答えに至ったのか、不思議に思って聞き返す。
この人はいつから私を見ていたのか、それも気にはなったけど。
「学校でいじめられててこんな時間に独りで踏み切りの前にずっと立ってる、それもここ一週間くらい毎回、さすがに分かるって」
「……」
呆れたようにそうぼやく男性に返す言葉を失う。
学校でいじめられていることも、ここに一週間以上通っていることも、ただの通りすがりの人なら知りえない情報だったからだ。
「あれ? 俺のこと分からない? 同じ学校どころか同じ学年なのに、ま、分かるわけないか、俺不登校だし」
「……もしかして佐藤くん?」
黙り込んでしまった私にその人はそんなことを言いながらフードを軽く持ちあげて見せた。
暗闇の中ちらりと見えた顔は見覚えがあるとかそんなレベルではなかった。
佐藤くんは同じ学校の同じ学年、所謂同級生というやつだった。
しかもクラスは違うけどそれなりに話したこともある。
彼が不登校になったことにだって関わりがあるくらいには深い関係。
聞きなれた声だったから、怖くなかったのかとそれで合点がいった。
「よく分かったね、ちなみに家はそこ」
佐藤くんは持ち上げていたフードを下ろすと踏み切りを越えたところの一棟のマンションを指差した。
「ここの踏み切りって一回鳴り出すと永いよね、いつもうるさくて仕方ない、それなのに人身事故とか起きたら余計に騒がしくって仕方ない、俺引きこもりだからずっと家にいるのにさ」
それから佐藤くんはただ淡々とそんなことを語る。
「……じゃあ、ここにはもう来ない、迷惑かけてごめんね」
ここはそれなりにお気に入りの場所だったけどそれが佐藤くんに迷惑をかけるのなら止めてまた別の場所を探せばいい。
「三分間くらいかな」
「何が?」
足早にこの場を去ろうとした私に向かって佐藤くんは三本指を立てて見せる。
「この踏み切りが一度降りた後に上がるまでの時間、俺の家この踏み切りの向こう側だからこの踏み切りが上がるまでの三分間くらいだけなら話聞いてあげるって言ってんの」
「別に何か誰かに話したいわけじゃ……」
「ないんだろうね、でもどうせ君の家も向こう側なわけだしさ、このまま無言で立ってるだけじゃ暇じゃない?」
「……別に、死のうとしてたわけじゃない」
一度は佐藤くんの提案を断ろうとしたけど、確かに私の家も向こう側だしカンカンと鳴り響く踏み切りはきっとまだ上がらない。
私は一間置いてから佐藤くんに事実を告白する。
「ふーん」
「佐藤くん信じてないでしょ、本当なんだよ、ただ……いじめられてた子を助けてから今度は私がターゲットになって、毎日無視とか嫌がらせとか、少し疲れただけ、最近ここに来るのは、この永い踏み切りを見るのが好きなだけだよ、ここの電車沢山人が乗ってるからその人達それぞれに色んな世界があって色んな壁にぶつかりながら生きてる、そう思うと少しだけ、元気が出るような気がするの、私だけじゃないんだなーって」
佐藤くんは信じてないみたいだったけどこれは本当のこと。
確かにいじめは辛いけど、だからって死ぬ気は今のところない。
ただ生きていて息苦しくはなるからたまにこうして息抜きをしているだけに他ならない。
「……あんたは変わらないんだね、いつになっても、どこからそんなポジティブ思考出てくるんだか」
佐藤くんは言いながら、もの憂いげに空に顔を向ける。
「変わらないって……私佐藤くんとそんなこと話したことあったっけ?」
佐藤くんが学校にまだ来ていた頃、何度か話をしたことはある。
でもその時にそんな私の根本に関わるようなことを話した覚えはなかった。
「別に特別何か聞いたわけじゃないよ、ただ俺がまだ学校行ってた時にした会話でそう思っただけだし」
佐藤くんは言いながら、目深に被っていたフードを外してこちらを向く。
「あんたも、学校なんか行くのやめちゃえば? 今時学校なんて行っても行かなくてもたいした問題じゃないし」
それから名案とでもいうようにそんなことを言いながら大袈裟に手を開いて見せる。
「うーん、でも我が家いわゆる教育熱心な母親? ってやつだからそんなことしたら家追い出されちゃうかもーなんて」
高校を変えるとか、辞めるとか考えたことがなかったわけじゃない。
でもその度にちらつくのは親の顔。
絶対に私の意思が通らないのは一目瞭然だった。
「いじめられても学校行けなんて怒る親毒親じゃん」
「そういうこと言わないの、それにあんたって呼ぶの止めてよ、一応同級生なわけだし」
私は建前上怒ったように咎めながら話題を別の場所にふる。
前話していた時はちゃんと名前を呼んでくれたのに今日会ってからは一度も名前を呼んでくれていない。
私の名前を知らないわけはないし、それは少しだけ不服だった。
「……」
「ま、いいや、そろそろ私行かないと、踏み切りも上がったし、これ以上ここにいてこんな時間に家抜け出してるのバレちゃったらお母さんに殺されちゃう、それじゃあね」
だけど佐藤くんは何か考えるように黙り込んでしまって、その間に大きく鳴り響いていた警告音は止まって降りていたバーもゆっくりとあがりきる。
残念、時間切れだ。
あまり長く家を抜け出ていれば親にバレる可能性も上がる。
「…………相沢」
「……何?」
踏み切りを渡ろうとする私に、佐藤くんは後ろから呼び掛ける。
名前を呼ばれたのが少しだけ嬉しくて、佐藤くんのほうを振り向いて聞き返す。
「もう来ないって言ってたけどさ、また来れば? ここから見る電車好きなんでしょ? 俺部屋から踏み切り鳴る度に外確認するからさ、それであんた……相沢がいたらまた出てくる、それこそ独りでこんなとこいるの危ないし、そしたら話ししよ、踏み切りが鳴り止むまでの三分間だけ、だから今度来る時はちゃんと向こう側で待っててよ」
そして、佐藤くんは言いきると踏み切りの向こう側、私が今渡ろうとしているその先を指差して見せる。
「……何それ、佐藤くんに何のメリットもないじゃん」
確かに夜も深くなってからこんな場所に一人で立っているのは危ないかもしれない、だとしても佐藤くんが付き合ってくれる利点はひとつもない。
「ある、相沢と話せる口実が出来る」
だけど佐藤くんはすぐにそう断言してみせるから
「それ、メリットなの? 別に私と話しても楽しくないよ」
少しだけ自虐を含んだ返事をする。
「楽しいか楽しくないかは自分で決められる、だから相沢が嫌じゃなかったらまた相手してよ、俺も引きこもってばかりで誰とも話さない毎日にも飽きてきたし」
佐藤くんはそれだけ言うと足早に歩きだして私を追い越すと踏み切りを渡りきってしまった。
「……分かった、じゃあ、またね」
「うん、また」
私はそんな佐藤くんの後ろ姿に声をかけたけど、佐藤くんが振り返ることはなかった。
「……え」
ふと、いつものように目の前の踏み切りを眺めていたらそんな風に声をかけられた。
驚いて声のしたほうを向けばフードを目深に被った人が立っていて、なぜか怖いよりもいつ来たのかそれが先立った。
「別に死ぬのは勝手だけどさ、せめて人の迷惑にならない方法にしなよ」
男性はちらりと一瞬こちらに視線を向けて、それからまた目の前の降りた踏み切りに視線を戻す。
「なんで……そう思ったんですか?」
死ぬ、その言葉で私がこの踏み切りで飛び込み自殺をする、この人はそう考えてわざわざ声をかけてくれたのだろうと察するには余りあった。
確かにそれなりに永い時間ここに立ってはいたけどどうしてその答えに至ったのか、不思議に思って聞き返す。
この人はいつから私を見ていたのか、それも気にはなったけど。
「学校でいじめられててこんな時間に独りで踏み切りの前にずっと立ってる、それもここ一週間くらい毎回、さすがに分かるって」
「……」
呆れたようにそうぼやく男性に返す言葉を失う。
学校でいじめられていることも、ここに一週間以上通っていることも、ただの通りすがりの人なら知りえない情報だったからだ。
「あれ? 俺のこと分からない? 同じ学校どころか同じ学年なのに、ま、分かるわけないか、俺不登校だし」
「……もしかして佐藤くん?」
黙り込んでしまった私にその人はそんなことを言いながらフードを軽く持ちあげて見せた。
暗闇の中ちらりと見えた顔は見覚えがあるとかそんなレベルではなかった。
佐藤くんは同じ学校の同じ学年、所謂同級生というやつだった。
しかもクラスは違うけどそれなりに話したこともある。
彼が不登校になったことにだって関わりがあるくらいには深い関係。
聞きなれた声だったから、怖くなかったのかとそれで合点がいった。
「よく分かったね、ちなみに家はそこ」
佐藤くんは持ち上げていたフードを下ろすと踏み切りを越えたところの一棟のマンションを指差した。
「ここの踏み切りって一回鳴り出すと永いよね、いつもうるさくて仕方ない、それなのに人身事故とか起きたら余計に騒がしくって仕方ない、俺引きこもりだからずっと家にいるのにさ」
それから佐藤くんはただ淡々とそんなことを語る。
「……じゃあ、ここにはもう来ない、迷惑かけてごめんね」
ここはそれなりにお気に入りの場所だったけどそれが佐藤くんに迷惑をかけるのなら止めてまた別の場所を探せばいい。
「三分間くらいかな」
「何が?」
足早にこの場を去ろうとした私に向かって佐藤くんは三本指を立てて見せる。
「この踏み切りが一度降りた後に上がるまでの時間、俺の家この踏み切りの向こう側だからこの踏み切りが上がるまでの三分間くらいだけなら話聞いてあげるって言ってんの」
「別に何か誰かに話したいわけじゃ……」
「ないんだろうね、でもどうせ君の家も向こう側なわけだしさ、このまま無言で立ってるだけじゃ暇じゃない?」
「……別に、死のうとしてたわけじゃない」
一度は佐藤くんの提案を断ろうとしたけど、確かに私の家も向こう側だしカンカンと鳴り響く踏み切りはきっとまだ上がらない。
私は一間置いてから佐藤くんに事実を告白する。
「ふーん」
「佐藤くん信じてないでしょ、本当なんだよ、ただ……いじめられてた子を助けてから今度は私がターゲットになって、毎日無視とか嫌がらせとか、少し疲れただけ、最近ここに来るのは、この永い踏み切りを見るのが好きなだけだよ、ここの電車沢山人が乗ってるからその人達それぞれに色んな世界があって色んな壁にぶつかりながら生きてる、そう思うと少しだけ、元気が出るような気がするの、私だけじゃないんだなーって」
佐藤くんは信じてないみたいだったけどこれは本当のこと。
確かにいじめは辛いけど、だからって死ぬ気は今のところない。
ただ生きていて息苦しくはなるからたまにこうして息抜きをしているだけに他ならない。
「……あんたは変わらないんだね、いつになっても、どこからそんなポジティブ思考出てくるんだか」
佐藤くんは言いながら、もの憂いげに空に顔を向ける。
「変わらないって……私佐藤くんとそんなこと話したことあったっけ?」
佐藤くんが学校にまだ来ていた頃、何度か話をしたことはある。
でもその時にそんな私の根本に関わるようなことを話した覚えはなかった。
「別に特別何か聞いたわけじゃないよ、ただ俺がまだ学校行ってた時にした会話でそう思っただけだし」
佐藤くんは言いながら、目深に被っていたフードを外してこちらを向く。
「あんたも、学校なんか行くのやめちゃえば? 今時学校なんて行っても行かなくてもたいした問題じゃないし」
それから名案とでもいうようにそんなことを言いながら大袈裟に手を開いて見せる。
「うーん、でも我が家いわゆる教育熱心な母親? ってやつだからそんなことしたら家追い出されちゃうかもーなんて」
高校を変えるとか、辞めるとか考えたことがなかったわけじゃない。
でもその度にちらつくのは親の顔。
絶対に私の意思が通らないのは一目瞭然だった。
「いじめられても学校行けなんて怒る親毒親じゃん」
「そういうこと言わないの、それにあんたって呼ぶの止めてよ、一応同級生なわけだし」
私は建前上怒ったように咎めながら話題を別の場所にふる。
前話していた時はちゃんと名前を呼んでくれたのに今日会ってからは一度も名前を呼んでくれていない。
私の名前を知らないわけはないし、それは少しだけ不服だった。
「……」
「ま、いいや、そろそろ私行かないと、踏み切りも上がったし、これ以上ここにいてこんな時間に家抜け出してるのバレちゃったらお母さんに殺されちゃう、それじゃあね」
だけど佐藤くんは何か考えるように黙り込んでしまって、その間に大きく鳴り響いていた警告音は止まって降りていたバーもゆっくりとあがりきる。
残念、時間切れだ。
あまり長く家を抜け出ていれば親にバレる可能性も上がる。
「…………相沢」
「……何?」
踏み切りを渡ろうとする私に、佐藤くんは後ろから呼び掛ける。
名前を呼ばれたのが少しだけ嬉しくて、佐藤くんのほうを振り向いて聞き返す。
「もう来ないって言ってたけどさ、また来れば? ここから見る電車好きなんでしょ? 俺部屋から踏み切り鳴る度に外確認するからさ、それであんた……相沢がいたらまた出てくる、それこそ独りでこんなとこいるの危ないし、そしたら話ししよ、踏み切りが鳴り止むまでの三分間だけ、だから今度来る時はちゃんと向こう側で待っててよ」
そして、佐藤くんは言いきると踏み切りの向こう側、私が今渡ろうとしているその先を指差して見せる。
「……何それ、佐藤くんに何のメリットもないじゃん」
確かに夜も深くなってからこんな場所に一人で立っているのは危ないかもしれない、だとしても佐藤くんが付き合ってくれる利点はひとつもない。
「ある、相沢と話せる口実が出来る」
だけど佐藤くんはすぐにそう断言してみせるから
「それ、メリットなの? 別に私と話しても楽しくないよ」
少しだけ自虐を含んだ返事をする。
「楽しいか楽しくないかは自分で決められる、だから相沢が嫌じゃなかったらまた相手してよ、俺も引きこもってばかりで誰とも話さない毎日にも飽きてきたし」
佐藤くんはそれだけ言うと足早に歩きだして私を追い越すと踏み切りを渡りきってしまった。
「……分かった、じゃあ、またね」
「うん、また」
私はそんな佐藤くんの後ろ姿に声をかけたけど、佐藤くんが振り返ることはなかった。