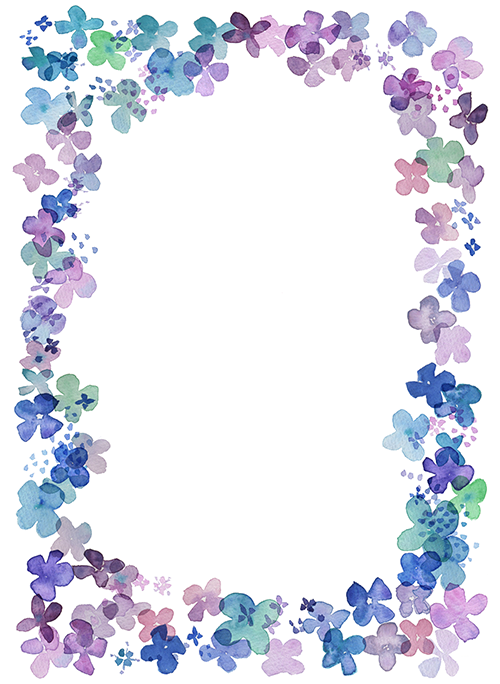過密なスケジュールをこなしていた令嬢時代と違い、何もすることがなくなってしまった。作法や令嬢としての教養は完璧に学んだものの、世話をされて当然だったから生活スキルは皆無である。家事を担うことはできないから、せめてもとクライヴの手伝いを申し出たが足手まといにしかならず自己嫌悪に陥る日々。クライヴが生きてさえいてくれればいいというから、ただ生きているだけ。さらに今までは健康で病気と無縁の生活を送ってきたレベッカだが、環境の変化と大きな精神負担のせいか、気温の変化などですぐに体調を崩すようになっていた。その度に世話を焼いてくれるクライヴに対して、有難いやら情けないやらでさらに気分が落ちていく。
ある日、レベッカは雨の降る冷え込んだ春先に風邪をこじらせてしまい、なかなか回復できずにいた。気力も湧かずにベッドの上で変わらぬ天井を眺めるしかない日々は、レベッカの心を知らずに蝕んでいた。もういい加減、こんな情けない日々をお終いにしたかった。そうすればクライヴも自然と解放されるだろう。レベッカは決意した。
「私、マーサの作ったリンゴのコンポートが食べたいわ」
マーサとはバートン公爵家の侍女長である。レベッカの乳母でもあったマーサは、幼い頃に風邪をひくと自らコンポートを作ってくれた。王都のタウンハウスは管理の者がわずかに残っているだけで、両親と殆どの使用人も領地の本邸に戻っている。肩身が狭くて王都にはいられなくなってしまったのだろうか? それもまたレベッカが自分を責める一因でもあった。
同じ領内といえどここからは離れていて、丸一日は移動にかかる。マーサも本邸に戻っているので、そこへ向かうとなるとクライヴは二日ほどレベッカの傍を離れることになる。知らせを出して持ってくるよう頼むこともできるが、さらに数日は多く掛かってしまうだろう。
「お嬢様……しかし、お一人にさせるわけには……」
「大丈夫。寝ているだけだもの。お腹もすいてないから二日くらいならお水だけあれば十分よ」
「そういうわけにはまいりません。何か口にしていただかなければ私はここから離れませんよ」
「分かったわ。一人でも何か口にするって約束するわ。だからお願い、クライヴ。マーサのところに行ってきて欲しいの」
逡巡するクライヴだったが、ずっと食欲のないレベッカが初めて食べたいと口にした料理。懇願すれば優しい彼は首を縦に振るしかない。結局後ろ髪をひかれつつも、クライヴは二人の家を後にした。それが元公爵令嬢のレベッカが、彼を見た最後だった。
レベッカは大きく息を吸いこんで、細く長く吐いた。少し震えているのは恐怖ではないはず。だってもう何もかも捨てて楽になりたかったのだ。粉々にされた公爵令嬢としてのプライドも、縛り付けているクライヴへの罪悪感や気付いてしまった彼への恋心も。それら全てを抱えて、これから先を乗り越えていける気がしなかった。クライヴに捨てられたら今度こそ狂ってしまう。
震える足を叱責してタンスに向かい、引き出しから簡素な木箱を取り出すと蓋を開けた。中には金貨と、幼い頃から宝物だった女神像の髪飾り。それらを取り出して、底の小さな穴にヘアピンを差し込むとカチリと音が鳴った。蓋の金具を手前に引けば、引き出しのように底がスライドする。レベッカはそこに隠されていた小さな箱を取り出して蓋を開けた。クッション性のある内張りにリボンで括りつけられた小瓶をそっと指先でなぞっていると、いつのまにか震えは止まっていた。
これは、もし辱められることがあれば飲むように、と別れ際に母から手渡された毒薬だった。これ以上娘に惨めな思いをさせたくないという母心だろう。涙で碌に話せずにいる母が声を振り絞るように、できれば使うことがないよう祈っていると話してくれたのが、随分と昔に思えた。
リボンを解くと落とさないよう丁寧に両手で持ってダイニングテーブルへと向かう。
小瓶をそっと置き、この家の後始末をしてもらう羽目になるクライヴに手紙を書くためにペンを取った。このままここで住んでもらってもいいし、売りに出してもらっても構わない。公爵家から持たされたものや、木箱の金貨は自由にしていいから、髪飾りはできればこの家の庭にある大きな木の根元に埋めて欲しいと綴った。
封筒にしまうと、今までの恩とありったけの愛情を込めて『愛しのクライヴへ』と宛名に書いた。レベッカにできる最大限の告白だ。
小瓶を持って立ち上がると、レベッカは家を出た。空を見上げると青く澄んで雲ひとつなく、時折涼やかな風が心地よく吹いて前髪を遊ばせた。いつの間にかレベッカの心も晴れ晴れとしていた。こんなにも爽快なのはいつぶりだろう。物心ついたころから、感じたことなどなかったように思える。なんて寂しい人生なのか。
大きな木を見上げて、レベッカは次こそは静かな人生を送りたいと願った。手の中の小瓶を握りしめ、踵を返した。向かうは少し離れた所にある森の中。そこでならばクライヴに迷惑はかからないだろう。
悪寒と頭痛もいつの間にかなくなっていて、レベッカは今なら走れそうな気がした。幼少期以降は走ったことなどなかったけれど。豪華なドレスじゃない今ならできるかもしれない。ワンピースを少し持ち上げて、足を大きく踏み出し大地を蹴る。少しふらついたものの、レベッカの足はゆっくりとだがしっかりと駆け出してくれた。
顔に風が当たり、緩く編み込んだ髪の束が跳ねて背中を軽く叩く。まるで鞭を打たれた馬のようだと思った。とてもじゃないが馬に申し訳ないレベルの走りではあるが。
ああ、許されるならば、このままここでクライヴと二人で暮らしたかった。けれど何もできないレベッカが、有能な彼をこれ以上縛り付けることなどできないから。
闇雲に走ったレベッカだったが、いつの間にか静かな川にたどり着いた。この川べりをクライヴと散歩をした記憶がある。心を閉ざしていたレベッカに、穏やかな自然が優しかった。草の上に座り込むと、レベッカは暫し息を整えたが、緊張も相まってなかなか荒い息は治まらない。大切な人との惜別の念を振り切って、小瓶の蓋を開けて一気に煽る。
トロリとした液体が喉を通ると焼けるように熱くなり、吐き出しそうになったが何とか飲み込んだ。瞬間、真っ暗闇に覆われた視界。顔の横にチクチクとした草を感じて倒れているのだと、ぼんやりと思った。意識が遠くなる瞬間、クライヴの声を聴いたような気がした。
凛香が思い出した、レベッカ・バートンとしての記憶はここまでである。
ある日、レベッカは雨の降る冷え込んだ春先に風邪をこじらせてしまい、なかなか回復できずにいた。気力も湧かずにベッドの上で変わらぬ天井を眺めるしかない日々は、レベッカの心を知らずに蝕んでいた。もういい加減、こんな情けない日々をお終いにしたかった。そうすればクライヴも自然と解放されるだろう。レベッカは決意した。
「私、マーサの作ったリンゴのコンポートが食べたいわ」
マーサとはバートン公爵家の侍女長である。レベッカの乳母でもあったマーサは、幼い頃に風邪をひくと自らコンポートを作ってくれた。王都のタウンハウスは管理の者がわずかに残っているだけで、両親と殆どの使用人も領地の本邸に戻っている。肩身が狭くて王都にはいられなくなってしまったのだろうか? それもまたレベッカが自分を責める一因でもあった。
同じ領内といえどここからは離れていて、丸一日は移動にかかる。マーサも本邸に戻っているので、そこへ向かうとなるとクライヴは二日ほどレベッカの傍を離れることになる。知らせを出して持ってくるよう頼むこともできるが、さらに数日は多く掛かってしまうだろう。
「お嬢様……しかし、お一人にさせるわけには……」
「大丈夫。寝ているだけだもの。お腹もすいてないから二日くらいならお水だけあれば十分よ」
「そういうわけにはまいりません。何か口にしていただかなければ私はここから離れませんよ」
「分かったわ。一人でも何か口にするって約束するわ。だからお願い、クライヴ。マーサのところに行ってきて欲しいの」
逡巡するクライヴだったが、ずっと食欲のないレベッカが初めて食べたいと口にした料理。懇願すれば優しい彼は首を縦に振るしかない。結局後ろ髪をひかれつつも、クライヴは二人の家を後にした。それが元公爵令嬢のレベッカが、彼を見た最後だった。
レベッカは大きく息を吸いこんで、細く長く吐いた。少し震えているのは恐怖ではないはず。だってもう何もかも捨てて楽になりたかったのだ。粉々にされた公爵令嬢としてのプライドも、縛り付けているクライヴへの罪悪感や気付いてしまった彼への恋心も。それら全てを抱えて、これから先を乗り越えていける気がしなかった。クライヴに捨てられたら今度こそ狂ってしまう。
震える足を叱責してタンスに向かい、引き出しから簡素な木箱を取り出すと蓋を開けた。中には金貨と、幼い頃から宝物だった女神像の髪飾り。それらを取り出して、底の小さな穴にヘアピンを差し込むとカチリと音が鳴った。蓋の金具を手前に引けば、引き出しのように底がスライドする。レベッカはそこに隠されていた小さな箱を取り出して蓋を開けた。クッション性のある内張りにリボンで括りつけられた小瓶をそっと指先でなぞっていると、いつのまにか震えは止まっていた。
これは、もし辱められることがあれば飲むように、と別れ際に母から手渡された毒薬だった。これ以上娘に惨めな思いをさせたくないという母心だろう。涙で碌に話せずにいる母が声を振り絞るように、できれば使うことがないよう祈っていると話してくれたのが、随分と昔に思えた。
リボンを解くと落とさないよう丁寧に両手で持ってダイニングテーブルへと向かう。
小瓶をそっと置き、この家の後始末をしてもらう羽目になるクライヴに手紙を書くためにペンを取った。このままここで住んでもらってもいいし、売りに出してもらっても構わない。公爵家から持たされたものや、木箱の金貨は自由にしていいから、髪飾りはできればこの家の庭にある大きな木の根元に埋めて欲しいと綴った。
封筒にしまうと、今までの恩とありったけの愛情を込めて『愛しのクライヴへ』と宛名に書いた。レベッカにできる最大限の告白だ。
小瓶を持って立ち上がると、レベッカは家を出た。空を見上げると青く澄んで雲ひとつなく、時折涼やかな風が心地よく吹いて前髪を遊ばせた。いつの間にかレベッカの心も晴れ晴れとしていた。こんなにも爽快なのはいつぶりだろう。物心ついたころから、感じたことなどなかったように思える。なんて寂しい人生なのか。
大きな木を見上げて、レベッカは次こそは静かな人生を送りたいと願った。手の中の小瓶を握りしめ、踵を返した。向かうは少し離れた所にある森の中。そこでならばクライヴに迷惑はかからないだろう。
悪寒と頭痛もいつの間にかなくなっていて、レベッカは今なら走れそうな気がした。幼少期以降は走ったことなどなかったけれど。豪華なドレスじゃない今ならできるかもしれない。ワンピースを少し持ち上げて、足を大きく踏み出し大地を蹴る。少しふらついたものの、レベッカの足はゆっくりとだがしっかりと駆け出してくれた。
顔に風が当たり、緩く編み込んだ髪の束が跳ねて背中を軽く叩く。まるで鞭を打たれた馬のようだと思った。とてもじゃないが馬に申し訳ないレベルの走りではあるが。
ああ、許されるならば、このままここでクライヴと二人で暮らしたかった。けれど何もできないレベッカが、有能な彼をこれ以上縛り付けることなどできないから。
闇雲に走ったレベッカだったが、いつの間にか静かな川にたどり着いた。この川べりをクライヴと散歩をした記憶がある。心を閉ざしていたレベッカに、穏やかな自然が優しかった。草の上に座り込むと、レベッカは暫し息を整えたが、緊張も相まってなかなか荒い息は治まらない。大切な人との惜別の念を振り切って、小瓶の蓋を開けて一気に煽る。
トロリとした液体が喉を通ると焼けるように熱くなり、吐き出しそうになったが何とか飲み込んだ。瞬間、真っ暗闇に覆われた視界。顔の横にチクチクとした草を感じて倒れているのだと、ぼんやりと思った。意識が遠くなる瞬間、クライヴの声を聴いたような気がした。
凛香が思い出した、レベッカ・バートンとしての記憶はここまでである。