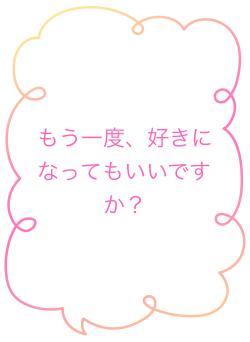私は、教室のざわめきのど真ん中でため息をついた。
——今日も、だ。
「ねぇ柏見くんってさ、ああいう笑い方するんだね!」
「分かる、なんか癖になるよね〜!」
「席近い奏ちゃん羨まし〜!」
そんな女子達の声が、わざとらしく聞こえる距離で飛んでくる。
(いや、羨ましくないから……全然。)
むしろ――困る。
だって蓮(れん)は、人気者のくせに、昔から距離が近すぎる。
私の気持ちを知らないで、なんでグイグイくるんだろう。
そして今日も例外じゃなかった。
「奏〜、弁当一緒に食べよ?おれのここ置いとくね」
当然みたいに奏の机へ腕を伸ばしてくる蓮。
その腕が、昔と変わらず温かくて。
だけど、周りの女子の視線が刺さりまくる。
「ねえ柏見くん、私も一緒にいい?」
スクールカースト上位の女子が声をかける。
私に向けられた視線は、完全に“蓮から離れろ”だ。
「じゃあ、私は今日屋上で…」
けれど蓮は、私の言葉を遮り、にこっと笑ったまま、さらっと断った。
「んー、今日は奏と食べるな。また今度食べよ」
その瞬間、女子達の心の声が聞こえそうだった。
(なにそれ、あの子ばっかり)
奏は慌てて蓮の腕を押し戻す。
「べ、別に1人でも食べれるし……!
蓮は他の子のとこ行ってよ!」
強めに言ったつもりなのに、声は震えていた。
蓮は少しだけ目を細める。
昔から奏の変化には敏感だった。
「……なんか嫌なこと言われた?」
その声音が、低い。
優しいけど、底に熱がある。
「言ってくれたらさ、全部俺がなんとかするよ」
「や、やめてよ……そういうの……」
奏は咄嗟に視線をそらした。
蓮は知らない。
“守られる”ことが、奏にはいちばん怖いってこと。
——中学のとき。
奏がクラスで孤立した原因も、“守られたせい”だったから。
奏の沈黙に気づいたのか、蓮は少し困ったような表情をした。
「奏、俺さ……ずっと思ってたんだけど」
教室のざわめきが遠くなる。
蓮の声だけが近くて、苦しい。
「なんで俺から離れようとするの?」
言葉が喉につかえる。
(だって……また、誰かを怒らせたら……)
幼い日の記憶——
“奏のせいで”と怒鳴られた昼休みの空気は、いまでも胸の奥に残っていた。
蓮は、奏の目の奥を読んだように、そっと声を落とした。
「……俺が、そんな簡単に手放すわけないだろ」
ほんの一瞬だけ、誰にも見せない色がのぞいた。
「昔みたいに、ちゃんと俺のそばにいてよ」
胸が跳ねて、息が詰まった。
なのにその直後、ホームルームのチャイムが鳴り、
蓮はいつもの飄々とした笑顔で席へ戻っていった。
残された奏は、顔が熱くてどうしたらいいか分からなかった。
(蓮……なんでそんな顔するの。)
でも、分かってる。
蓮は昔から、誰かの特別になりたいんだ。
——その優しさが、少し過保護で、時々重くて。
だけど、胸の奥があったかくなるのも事実で。
奏は、揺れていた。
(私は、また守られるだけでいいの?)
答えの出ないまま、チャイムの音だけが教室に溶けていった。
——今日も、だ。
「ねぇ柏見くんってさ、ああいう笑い方するんだね!」
「分かる、なんか癖になるよね〜!」
「席近い奏ちゃん羨まし〜!」
そんな女子達の声が、わざとらしく聞こえる距離で飛んでくる。
(いや、羨ましくないから……全然。)
むしろ――困る。
だって蓮(れん)は、人気者のくせに、昔から距離が近すぎる。
私の気持ちを知らないで、なんでグイグイくるんだろう。
そして今日も例外じゃなかった。
「奏〜、弁当一緒に食べよ?おれのここ置いとくね」
当然みたいに奏の机へ腕を伸ばしてくる蓮。
その腕が、昔と変わらず温かくて。
だけど、周りの女子の視線が刺さりまくる。
「ねえ柏見くん、私も一緒にいい?」
スクールカースト上位の女子が声をかける。
私に向けられた視線は、完全に“蓮から離れろ”だ。
「じゃあ、私は今日屋上で…」
けれど蓮は、私の言葉を遮り、にこっと笑ったまま、さらっと断った。
「んー、今日は奏と食べるな。また今度食べよ」
その瞬間、女子達の心の声が聞こえそうだった。
(なにそれ、あの子ばっかり)
奏は慌てて蓮の腕を押し戻す。
「べ、別に1人でも食べれるし……!
蓮は他の子のとこ行ってよ!」
強めに言ったつもりなのに、声は震えていた。
蓮は少しだけ目を細める。
昔から奏の変化には敏感だった。
「……なんか嫌なこと言われた?」
その声音が、低い。
優しいけど、底に熱がある。
「言ってくれたらさ、全部俺がなんとかするよ」
「や、やめてよ……そういうの……」
奏は咄嗟に視線をそらした。
蓮は知らない。
“守られる”ことが、奏にはいちばん怖いってこと。
——中学のとき。
奏がクラスで孤立した原因も、“守られたせい”だったから。
奏の沈黙に気づいたのか、蓮は少し困ったような表情をした。
「奏、俺さ……ずっと思ってたんだけど」
教室のざわめきが遠くなる。
蓮の声だけが近くて、苦しい。
「なんで俺から離れようとするの?」
言葉が喉につかえる。
(だって……また、誰かを怒らせたら……)
幼い日の記憶——
“奏のせいで”と怒鳴られた昼休みの空気は、いまでも胸の奥に残っていた。
蓮は、奏の目の奥を読んだように、そっと声を落とした。
「……俺が、そんな簡単に手放すわけないだろ」
ほんの一瞬だけ、誰にも見せない色がのぞいた。
「昔みたいに、ちゃんと俺のそばにいてよ」
胸が跳ねて、息が詰まった。
なのにその直後、ホームルームのチャイムが鳴り、
蓮はいつもの飄々とした笑顔で席へ戻っていった。
残された奏は、顔が熱くてどうしたらいいか分からなかった。
(蓮……なんでそんな顔するの。)
でも、分かってる。
蓮は昔から、誰かの特別になりたいんだ。
——その優しさが、少し過保護で、時々重くて。
だけど、胸の奥があったかくなるのも事実で。
奏は、揺れていた。
(私は、また守られるだけでいいの?)
答えの出ないまま、チャイムの音だけが教室に溶けていった。