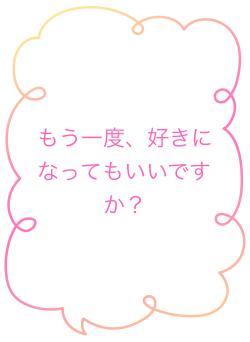六月の夕方、校舎の影が少し伸び始める頃だった。
下駄箱の前で靴を履き替えていた私は、ふと入口の方に気配を感じて顔を上げた。
――そこに立っていたのは、二年前に突然いなくなった幼馴染、柏見蓮だった。
「……ひさしぶり」
変わったようで、変わっていない。
背は少し伸びて、声は少し低くなった。
でも、目が合った瞬間のあの感じは、昔のままだった。
胸がぎゅっとなる。
会いたかったのに、会える日なんてもう来ないと思っていたのに――
蓮は、まるで昨日別れたみたいな顔で笑う。
「転校してきた。……また、よろしくな」
ただの挨拶なのに、その“また”を聞いただけで心が揺れた。
いなくなった時、本当は言えなかった言葉たちが、全部こぼれそうになる。
でも、その日の放課後。
屋上に呼び出された私を待っていたのは、懐かしさじゃなくて、あまりにも唐突な一言だった。
「なあ、一か月だけ。
俺の“彼女役”をやってくれない?」
風が止まったように感じた。
「……え?」
「頼む。理由はそのうち話すから。とりあえず一か月だけでいい。
放課後いっしょに帰ったり、クラスでも隣にいたり……そういう“フリ”をしてほしい」
幼馴染が言うにはあまりにも不自然で、
冗談にしては真剣で、
意味が分からないのに、心臓だけが痛いくらい跳ねた。
昔から好きだった。
だからこそ、こんな“フリ”に頷いていいわけがない。
――なのに。
「……一か月だけ、でしょ? ……わかった」
その言葉が、勝手に口からこぼれていた。
一緒にいられるなら、なんでもいい。
そういう気持ちが溢れたのだろう。
蓮はほっとしたように笑う。
その笑顔が、胸を掴んで離さなかった。
そして、その日から始まった。
期限つきの恋人ごっこ。
終わりが決まっている恋。
一か月後、私たちはどこに立っているんだろう。
――それは、まだ誰も知らなかった。
下駄箱の前で靴を履き替えていた私は、ふと入口の方に気配を感じて顔を上げた。
――そこに立っていたのは、二年前に突然いなくなった幼馴染、柏見蓮だった。
「……ひさしぶり」
変わったようで、変わっていない。
背は少し伸びて、声は少し低くなった。
でも、目が合った瞬間のあの感じは、昔のままだった。
胸がぎゅっとなる。
会いたかったのに、会える日なんてもう来ないと思っていたのに――
蓮は、まるで昨日別れたみたいな顔で笑う。
「転校してきた。……また、よろしくな」
ただの挨拶なのに、その“また”を聞いただけで心が揺れた。
いなくなった時、本当は言えなかった言葉たちが、全部こぼれそうになる。
でも、その日の放課後。
屋上に呼び出された私を待っていたのは、懐かしさじゃなくて、あまりにも唐突な一言だった。
「なあ、一か月だけ。
俺の“彼女役”をやってくれない?」
風が止まったように感じた。
「……え?」
「頼む。理由はそのうち話すから。とりあえず一か月だけでいい。
放課後いっしょに帰ったり、クラスでも隣にいたり……そういう“フリ”をしてほしい」
幼馴染が言うにはあまりにも不自然で、
冗談にしては真剣で、
意味が分からないのに、心臓だけが痛いくらい跳ねた。
昔から好きだった。
だからこそ、こんな“フリ”に頷いていいわけがない。
――なのに。
「……一か月だけ、でしょ? ……わかった」
その言葉が、勝手に口からこぼれていた。
一緒にいられるなら、なんでもいい。
そういう気持ちが溢れたのだろう。
蓮はほっとしたように笑う。
その笑顔が、胸を掴んで離さなかった。
そして、その日から始まった。
期限つきの恋人ごっこ。
終わりが決まっている恋。
一か月後、私たちはどこに立っているんだろう。
――それは、まだ誰も知らなかった。