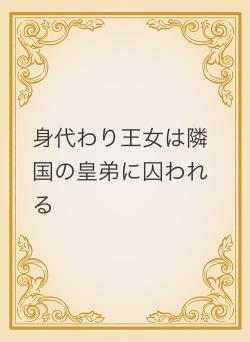初めてカイルと結ばれて以降、クリスティはますます結婚を心待ちにするようになっていた。大して悲しくもない両親の喪に服している間、婚約式もまだだと言うのに結婚式のことばかり考えるぐらいに。夢にすら見たことのなかった、大好きな人と愛し合うささやかで幸せな生活。まさか自分にそんな幸せが訪れるなんて、物心ついたときから一度も思わなかったのだ。
カイルへの恋慕は日に日に増すばかりだ。叔父以外で初めて自分を大事にしてくれて、しかも叔父とは違って毎日一緒にいてくれる。少しでも彼の力になりたい、彼に恥じぬ伯爵夫人でありたいと願うクリスティは積極的に領地へ出るようになった。良い人でも良い親でもなかった先代伯爵夫妻が、当然のように良い領主であるはずもない。杜撰な領地経営を立て直してくれたのもやはり、カイルと叔父の二人だった。
道路整備などの公共事業を増やして失業者を減らし、浮浪児を救済するために孤児院で職業訓練ができるように教師を配置し、衛生状態の悪かった病院の設備を新しくして清潔に保つ。先代当主の急死は伯爵領に良き変化をもたらし、立役者である次期当主と当主代行は領民からの感謝と共に迎えられることになった。その様子を間近で見ていたクリスティに湧いたのは、申し訳なさや感謝以上に、自分にもできることをしなければならないという使命感。自分には何もない情けなさをカイルに吐露していたことを考えれば、信じられないほどの進歩だ。
何もないと嘆いていたクリスティだけれど、朝から晩までみっちり授業漬けだった二十年は無駄ではなかった。授業を受けるたびに叱られていた刺繍や裁縫の腕は、知らないだけでそれなりに誇れるものだったらしい。刺繍を施したハンカチや靴下を初めて届けに行った日、孤児院の子供達やシスターの喜ぶ姿はクリスティに衝撃を与えた。裁縫も刺繍も、なんなら編み物も好きだけれど、ずっと下手の横好きだと思っていたのだ。家庭教師の先生が褒めてくれたことはほとんどなく、両親にも何度か渡したことがあるけれど使ってもらえたことは一度もない。自分の作ったものを初めて誰かに喜んでもらえたときの、クリスティの喜びようときたら。その日から寝食も忘れる勢いでせっせと量産し続け、カイルが心配になって止めたほどだ。
そんなある日。
「孤児院の子達に刺繍を教えるのはどうかな?」
「え……?」
なんでもないように告げられたカイルの提案はクリスティにとって青天の霹靂だった。刺繍の手を止めて隣に座るカイルを見ると、真剣な面持ちでクリスティを見つめている。「手に職をつけるのは、孤児院を出てからの助けになるからね」と言うカイルの説明には納得したけれど、それでも随分と突拍子もない。カイルのことを全面的に信頼しているクリスティと言えど、先生役にクリスティを選ぶのはちょっと信じられなかった。仕掛かり途中の刺繍をテーブルの上に置き、ゆっくりと首を横に振る。
「そんな、誰かに教えられるほどじゃありません」
「そうかな? 仕事柄、刺繍の施された商品だって取り扱うけれど、そのどれにも見劣りしないよ」
「でも、私なんかが誰かに何かを教えるなんて無理です……」
心からの本音だった。子供達やシスターは喜んでくれるけれど、それでも自信を持つほどの腕前ではない。人と満足に関わったこともないのだから、人前でうまく話せる気もしない。膝に置いた手をぎゅう、と握りしめる。せっかくの申し出だけれど、失敗する未来しか見えなかった。
「クリスティは『私なんか』じゃない」
カイルの手がクリスティの膝に置かれた手に重なる。握りしめているのを解くように指を絡めて握られると、肩に入っていた力が抜けていくのがわかる。顔を上げると、榛色の瞳はいつものようにクリスティだけを映していた。
「うまくできなくてもいい。けど、やる前から無理だなんて決めつけたらダメだ」
ぐ、と胸に熱いものが込み上げる。カイルは、どうしてこんなにクリスティの欲しい言葉ばかりくれるのだろう。どうして、クリスティをここまで信頼してくれるのだろう。何にもできなくて、なんの取り柄もないのに。どうして大事にしてくれるのだろう。
「わ、私がうまく教えられなくて失敗、したら……カイル様にご迷惑が、かかりませんか?」
「かからない」
端的に即答するカイル。クリスティが納得できる根拠なんて一つもないのに、それだけで十分だと思ってしまった。握られている手を恐る恐る握り返す。
「私でよければ……頑張り、ます」
「本当? ありがとう。早速シスターに伝えておくよ」
嬉しそうに笑うカイルを見て、まだ何もしていないのに引き受けて良かったと思う。結局お膳立てしてくれるのはカイルで、いらない手間だって増やしてしまうけれど、その分子供達の刺繍の腕が上達するように頑張ろうと心に決めた。
「……それで、さ、クリスティ。一つ、個人的なお願いがあるんだけど」
俯いてクリスティの手をにぎにぎと弄ぶカイルは、なんだか言いにくそうに口を開く。子供達の刺繍の先生をしてほしい、ということ以上に言いにくいお願いなのだろうか。そもそも個人的なお願いとは、と思いつつ、「はい」と返す。お願いの内容がなんだったとしてもクリスティは喜んで叶えるつもりだった。
「その……私にも、作ってくれないかな」
「何をでしょう?」
「刺繍を入れたハンカチ」
「え……」
そんなものでいいのか、と思わず拍子抜けしてしまった。恋人に刺繍入りのハンカチ、特に自分のイニシャルを入れたものを送るのは、この国において割と一般的な風習だ。クリスティももちろん知っていたけれど、なんとなくカイルはそういうものは欲しがらないだろうと思い込んでいた。商人である彼は先ほど自分でも言っていたように刺繍の入った商品を取り扱うことが多い。当然その中にはハンカチだって含まれている。上等な刺繍入りのハンカチを日頃見慣れているような彼が、素人のクリスティが刺したものを欲しがるとは思えなかったのだ。
「図柄はなんでもいいし、糸もなんだって取り寄せる。その、無理にとは言わないけど……」
けれど、カイルは欲しがってくれるらしい。よっぽど頼みにくいと思ったのか、暗褐色の髪の隙間から覗く耳が真っ赤だ。握られている手も、心なしかいつもより熱い。
――私が刺したものなんかで、いいんだ……。
ぱち、と目を瞬いた後、顔に熱が集まるのを自覚する。心臓がドキドキして、今すぐにカイルに抱きついてしまいたい衝動に駆られた。
「わ、私でよければ」
答えた声は震えていたけれど、カイルはバカにしなかった。顔を上げた彼は真っ赤な顔で嬉しそうに笑っていて、「愛おしい」とはこういうときに感じるものなのだと知った。
*
カイルの提案を受け、子供達の刺繍の先生になってから幾許か。できるわけがないと最初から決めてかかっていたクリスティだったが、信じてくれたカイルは正しかったらしい。最初は拙かった教え方も回を重ねるごとに上達し、今ではすっかり先生役が板についている。子供達の飲み込みも早く、日に日に上達していく様子を見届けるのは最近のクリスティの楽しみの一つだ。そろそろ刺繍だけでなく本格的な裁縫も教えるのはどうかと、カイルやシスターに相談するつもりでいる。
「喜んでくれるかなあ……」
手に持つ紙袋を見下ろし、思わず笑みがこぼれる。使用人たちと朝から大量に焼いたマドレーヌやクッキーは、紙袋越しでも香ばしくいい匂いが漂っている。今日は授業がないけれど、一日中予定がなかったので差し入れを持っていくことにしたのだ。少し前までクリスティに対してよそよそしかった使用人たちも、伯爵夫人として頑張ろうとするクリスティの努力を認めてくれたのだろうか。朝からのお菓子作りも、楽しそうに手伝ってくれた。
馬車を使わず、伯爵家から孤児院への道のりを歩く。教会に併設された孤児院までは歩いて二十分ほど。両親の生前は馴染みのなかった道のりも、ここ最近ですっかり見慣れた。以前は道がでこぼこで歩きづらかったのが、カイルと叔父が手配した公共事業のおかげで舗装されている。たまにすれ違う住民に挨拶されるのは、二人のおかげでクリスティの評価も一緒に引っ張り上げられたからだろう。二人には、やはり感謝してもし尽くせない。カイルに頼まれたハンカチへの刺繍は、図案から考えている上に刺繍の先生をするのに時間が取られているせいでまだ完成していないけれど、あと数日で刺し終わるだろう。渡す日のことを思うと、今から顔が綻んでしまう。
てくてく歩いていると、孤児院がようやく見えてくる。教会に併設された孤児院からは、子供達の声が聞こえて賑々しい。お菓子を渡すついでに様子も見ていこう、と思っていると入り口付近から誰かが出てくるのが見えた。修道服に身を包んだ女性、シスターだ。朗らかでしっかり物の彼女はクリスティと同年代で、自身もこの孤児院出身なのだという。子供達の面倒を見る姿はまるで本当の母親のようで、同年代なのにクリスティも甘えたくなってしまうほどだ。姿を見かけたことが嬉しくて思わず駆け寄ろうとすると、後ろからさらに誰かが出てくるのが見える。誰かが来ていたのだろうか、と呑気なことを思ったクリスティの足が止まる。
「え……」
見慣れた暗褐色の髪に榛色の瞳。今朝も見たばかりの、見間違えるわけのないクリスティの大好きな人。孤児院から出てきたのは、カイルだった。
――なんでカイル様が……?
思わず、建物近くの物陰に隠れる。カイルが孤児院を訪れることは珍しいことではない。支援の話や、それこそクリスティが刺繍を教える段取りをつけに訪れているのは当然知っている。が、孤児院を訪れるなら出かけるときにいつも言ってくれるのが、今日は何も言われていない。嫌にドキドキする心臓のあたりを片手で押さえながら、息を潜めて様子を伺う。
「何回見ても慣れないわ、カイルのその感じ」
「うるせーな、慣れろ。お前この間もクリスティの前で笑いそうになってただろ」
「だって今こんな感じなのに必死に猫かぶってるんだからそりゃ笑うでしょ」
「笑うなって」
心臓が痛いぐらいに音を立てる。目の前の光景が信じられなくて目を擦ってみたけれど、変わらなかった。カイルとシスターはまるで昔からの知り合いのように気安くやり取りを続けているけれど、二人が昔馴染みだなんて話は聞いたことがない。クリスティと一緒に孤児院を尋ねたときに会話している様子はもちろん見たことがあるけれど、事務的なやり取りを交わすだけで仲の良さなんてものは伺えなかった。二人に私的な交流があるだなんて、想像すらしたことがない。それに、普段の穏やかで紳士的な口調からは考えられないほど乱れた口調は、たまに聞いたことのあるものだ。なんとなく、普段は紳士的に取り繕っているのかなとは思っていたけれど、シスターには素で話しているということなのだろうか。けれど、一体どうして。
「じゃあ、また何かあったらよろしく」
「はーい、こちらこそよろしくね」
クリスティが衝撃を受けて動けなくなっているうちに、二人の会話は終わっていたらしい。カイルが孤児院から出るのを見て、慌ててさらに身を隠す。堂々と出ていくカイルからは、やましさなんてものは微塵も感じられない。物陰に隠れるクリスティには最後まで気づかないままだった。
――今の、なんだったのだろう。
いつの間にか浅くなっていた呼吸をどうにか整えながら、孤児院の方へと歩いていく。ぐるぐると頭の中で様々なことが回って、なんだか気持ちが悪い。出迎えてくれたシスターがクリスティを見てギョッとしたのは、先ほどの出来事が原因かと思ったけれどそうではなかった。あまりに顔色が悪かったせいらしい。
「どうされたんですか、クリスティ様!?」
「ぁ……」
はく、と口を動かすけれど何も言葉にならない。聞きたいことはたくさんあるはずなのに、何一つとして聞ける気がしなかった。聞いてしまうと、何かが終わってしまう気がした。
「なんでも、ないです……」
結局その日、家に帰ってからもカイルには何も聞けなかった。自室に置いてある仕掛かり途中の刺繍を眺め、息を吐く。とてもじゃないけれど、続きに取りかかれる気がしなかった。
カイルへの恋慕は日に日に増すばかりだ。叔父以外で初めて自分を大事にしてくれて、しかも叔父とは違って毎日一緒にいてくれる。少しでも彼の力になりたい、彼に恥じぬ伯爵夫人でありたいと願うクリスティは積極的に領地へ出るようになった。良い人でも良い親でもなかった先代伯爵夫妻が、当然のように良い領主であるはずもない。杜撰な領地経営を立て直してくれたのもやはり、カイルと叔父の二人だった。
道路整備などの公共事業を増やして失業者を減らし、浮浪児を救済するために孤児院で職業訓練ができるように教師を配置し、衛生状態の悪かった病院の設備を新しくして清潔に保つ。先代当主の急死は伯爵領に良き変化をもたらし、立役者である次期当主と当主代行は領民からの感謝と共に迎えられることになった。その様子を間近で見ていたクリスティに湧いたのは、申し訳なさや感謝以上に、自分にもできることをしなければならないという使命感。自分には何もない情けなさをカイルに吐露していたことを考えれば、信じられないほどの進歩だ。
何もないと嘆いていたクリスティだけれど、朝から晩までみっちり授業漬けだった二十年は無駄ではなかった。授業を受けるたびに叱られていた刺繍や裁縫の腕は、知らないだけでそれなりに誇れるものだったらしい。刺繍を施したハンカチや靴下を初めて届けに行った日、孤児院の子供達やシスターの喜ぶ姿はクリスティに衝撃を与えた。裁縫も刺繍も、なんなら編み物も好きだけれど、ずっと下手の横好きだと思っていたのだ。家庭教師の先生が褒めてくれたことはほとんどなく、両親にも何度か渡したことがあるけれど使ってもらえたことは一度もない。自分の作ったものを初めて誰かに喜んでもらえたときの、クリスティの喜びようときたら。その日から寝食も忘れる勢いでせっせと量産し続け、カイルが心配になって止めたほどだ。
そんなある日。
「孤児院の子達に刺繍を教えるのはどうかな?」
「え……?」
なんでもないように告げられたカイルの提案はクリスティにとって青天の霹靂だった。刺繍の手を止めて隣に座るカイルを見ると、真剣な面持ちでクリスティを見つめている。「手に職をつけるのは、孤児院を出てからの助けになるからね」と言うカイルの説明には納得したけれど、それでも随分と突拍子もない。カイルのことを全面的に信頼しているクリスティと言えど、先生役にクリスティを選ぶのはちょっと信じられなかった。仕掛かり途中の刺繍をテーブルの上に置き、ゆっくりと首を横に振る。
「そんな、誰かに教えられるほどじゃありません」
「そうかな? 仕事柄、刺繍の施された商品だって取り扱うけれど、そのどれにも見劣りしないよ」
「でも、私なんかが誰かに何かを教えるなんて無理です……」
心からの本音だった。子供達やシスターは喜んでくれるけれど、それでも自信を持つほどの腕前ではない。人と満足に関わったこともないのだから、人前でうまく話せる気もしない。膝に置いた手をぎゅう、と握りしめる。せっかくの申し出だけれど、失敗する未来しか見えなかった。
「クリスティは『私なんか』じゃない」
カイルの手がクリスティの膝に置かれた手に重なる。握りしめているのを解くように指を絡めて握られると、肩に入っていた力が抜けていくのがわかる。顔を上げると、榛色の瞳はいつものようにクリスティだけを映していた。
「うまくできなくてもいい。けど、やる前から無理だなんて決めつけたらダメだ」
ぐ、と胸に熱いものが込み上げる。カイルは、どうしてこんなにクリスティの欲しい言葉ばかりくれるのだろう。どうして、クリスティをここまで信頼してくれるのだろう。何にもできなくて、なんの取り柄もないのに。どうして大事にしてくれるのだろう。
「わ、私がうまく教えられなくて失敗、したら……カイル様にご迷惑が、かかりませんか?」
「かからない」
端的に即答するカイル。クリスティが納得できる根拠なんて一つもないのに、それだけで十分だと思ってしまった。握られている手を恐る恐る握り返す。
「私でよければ……頑張り、ます」
「本当? ありがとう。早速シスターに伝えておくよ」
嬉しそうに笑うカイルを見て、まだ何もしていないのに引き受けて良かったと思う。結局お膳立てしてくれるのはカイルで、いらない手間だって増やしてしまうけれど、その分子供達の刺繍の腕が上達するように頑張ろうと心に決めた。
「……それで、さ、クリスティ。一つ、個人的なお願いがあるんだけど」
俯いてクリスティの手をにぎにぎと弄ぶカイルは、なんだか言いにくそうに口を開く。子供達の刺繍の先生をしてほしい、ということ以上に言いにくいお願いなのだろうか。そもそも個人的なお願いとは、と思いつつ、「はい」と返す。お願いの内容がなんだったとしてもクリスティは喜んで叶えるつもりだった。
「その……私にも、作ってくれないかな」
「何をでしょう?」
「刺繍を入れたハンカチ」
「え……」
そんなものでいいのか、と思わず拍子抜けしてしまった。恋人に刺繍入りのハンカチ、特に自分のイニシャルを入れたものを送るのは、この国において割と一般的な風習だ。クリスティももちろん知っていたけれど、なんとなくカイルはそういうものは欲しがらないだろうと思い込んでいた。商人である彼は先ほど自分でも言っていたように刺繍の入った商品を取り扱うことが多い。当然その中にはハンカチだって含まれている。上等な刺繍入りのハンカチを日頃見慣れているような彼が、素人のクリスティが刺したものを欲しがるとは思えなかったのだ。
「図柄はなんでもいいし、糸もなんだって取り寄せる。その、無理にとは言わないけど……」
けれど、カイルは欲しがってくれるらしい。よっぽど頼みにくいと思ったのか、暗褐色の髪の隙間から覗く耳が真っ赤だ。握られている手も、心なしかいつもより熱い。
――私が刺したものなんかで、いいんだ……。
ぱち、と目を瞬いた後、顔に熱が集まるのを自覚する。心臓がドキドキして、今すぐにカイルに抱きついてしまいたい衝動に駆られた。
「わ、私でよければ」
答えた声は震えていたけれど、カイルはバカにしなかった。顔を上げた彼は真っ赤な顔で嬉しそうに笑っていて、「愛おしい」とはこういうときに感じるものなのだと知った。
*
カイルの提案を受け、子供達の刺繍の先生になってから幾許か。できるわけがないと最初から決めてかかっていたクリスティだったが、信じてくれたカイルは正しかったらしい。最初は拙かった教え方も回を重ねるごとに上達し、今ではすっかり先生役が板についている。子供達の飲み込みも早く、日に日に上達していく様子を見届けるのは最近のクリスティの楽しみの一つだ。そろそろ刺繍だけでなく本格的な裁縫も教えるのはどうかと、カイルやシスターに相談するつもりでいる。
「喜んでくれるかなあ……」
手に持つ紙袋を見下ろし、思わず笑みがこぼれる。使用人たちと朝から大量に焼いたマドレーヌやクッキーは、紙袋越しでも香ばしくいい匂いが漂っている。今日は授業がないけれど、一日中予定がなかったので差し入れを持っていくことにしたのだ。少し前までクリスティに対してよそよそしかった使用人たちも、伯爵夫人として頑張ろうとするクリスティの努力を認めてくれたのだろうか。朝からのお菓子作りも、楽しそうに手伝ってくれた。
馬車を使わず、伯爵家から孤児院への道のりを歩く。教会に併設された孤児院までは歩いて二十分ほど。両親の生前は馴染みのなかった道のりも、ここ最近ですっかり見慣れた。以前は道がでこぼこで歩きづらかったのが、カイルと叔父が手配した公共事業のおかげで舗装されている。たまにすれ違う住民に挨拶されるのは、二人のおかげでクリスティの評価も一緒に引っ張り上げられたからだろう。二人には、やはり感謝してもし尽くせない。カイルに頼まれたハンカチへの刺繍は、図案から考えている上に刺繍の先生をするのに時間が取られているせいでまだ完成していないけれど、あと数日で刺し終わるだろう。渡す日のことを思うと、今から顔が綻んでしまう。
てくてく歩いていると、孤児院がようやく見えてくる。教会に併設された孤児院からは、子供達の声が聞こえて賑々しい。お菓子を渡すついでに様子も見ていこう、と思っていると入り口付近から誰かが出てくるのが見えた。修道服に身を包んだ女性、シスターだ。朗らかでしっかり物の彼女はクリスティと同年代で、自身もこの孤児院出身なのだという。子供達の面倒を見る姿はまるで本当の母親のようで、同年代なのにクリスティも甘えたくなってしまうほどだ。姿を見かけたことが嬉しくて思わず駆け寄ろうとすると、後ろからさらに誰かが出てくるのが見える。誰かが来ていたのだろうか、と呑気なことを思ったクリスティの足が止まる。
「え……」
見慣れた暗褐色の髪に榛色の瞳。今朝も見たばかりの、見間違えるわけのないクリスティの大好きな人。孤児院から出てきたのは、カイルだった。
――なんでカイル様が……?
思わず、建物近くの物陰に隠れる。カイルが孤児院を訪れることは珍しいことではない。支援の話や、それこそクリスティが刺繍を教える段取りをつけに訪れているのは当然知っている。が、孤児院を訪れるなら出かけるときにいつも言ってくれるのが、今日は何も言われていない。嫌にドキドキする心臓のあたりを片手で押さえながら、息を潜めて様子を伺う。
「何回見ても慣れないわ、カイルのその感じ」
「うるせーな、慣れろ。お前この間もクリスティの前で笑いそうになってただろ」
「だって今こんな感じなのに必死に猫かぶってるんだからそりゃ笑うでしょ」
「笑うなって」
心臓が痛いぐらいに音を立てる。目の前の光景が信じられなくて目を擦ってみたけれど、変わらなかった。カイルとシスターはまるで昔からの知り合いのように気安くやり取りを続けているけれど、二人が昔馴染みだなんて話は聞いたことがない。クリスティと一緒に孤児院を尋ねたときに会話している様子はもちろん見たことがあるけれど、事務的なやり取りを交わすだけで仲の良さなんてものは伺えなかった。二人に私的な交流があるだなんて、想像すらしたことがない。それに、普段の穏やかで紳士的な口調からは考えられないほど乱れた口調は、たまに聞いたことのあるものだ。なんとなく、普段は紳士的に取り繕っているのかなとは思っていたけれど、シスターには素で話しているということなのだろうか。けれど、一体どうして。
「じゃあ、また何かあったらよろしく」
「はーい、こちらこそよろしくね」
クリスティが衝撃を受けて動けなくなっているうちに、二人の会話は終わっていたらしい。カイルが孤児院から出るのを見て、慌ててさらに身を隠す。堂々と出ていくカイルからは、やましさなんてものは微塵も感じられない。物陰に隠れるクリスティには最後まで気づかないままだった。
――今の、なんだったのだろう。
いつの間にか浅くなっていた呼吸をどうにか整えながら、孤児院の方へと歩いていく。ぐるぐると頭の中で様々なことが回って、なんだか気持ちが悪い。出迎えてくれたシスターがクリスティを見てギョッとしたのは、先ほどの出来事が原因かと思ったけれどそうではなかった。あまりに顔色が悪かったせいらしい。
「どうされたんですか、クリスティ様!?」
「ぁ……」
はく、と口を動かすけれど何も言葉にならない。聞きたいことはたくさんあるはずなのに、何一つとして聞ける気がしなかった。聞いてしまうと、何かが終わってしまう気がした。
「なんでも、ないです……」
結局その日、家に帰ってからもカイルには何も聞けなかった。自室に置いてある仕掛かり途中の刺繍を眺め、息を吐く。とてもじゃないけれど、続きに取りかかれる気がしなかった。