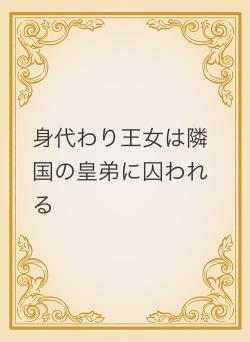本当にごめん、とカイルは頭を下げたままもう一度謝罪の言葉を口にした。普段は見ることのないつむじを見ながら、逡巡する。朧げながら蘇ってきた昔の記憶。カイルの父親が亡くなったこともそのせいでカイルが屋敷を追い出されることも、クリスティは何も知らなかった。全てを知ったのは彼が出ていく日の朝だったけれど、知っていたとして何ができたわけでもなかっただろう。両親の言うことを聞いているだけの、待っているだけの自分に王子様なんて現れるわけがないことは、紛れもない事実。幼き日のカイルが幼き日のクリスティに投げつけた言葉は、確かに酷い言葉だ。けれど、それで怒ろうと言う気にはなれなかった。
「……顔をあげてください」
そう告げると、カイルはゆっくりと顔を上げる。傷ついたような、ほんの少し怯えているような表情はいつも冷静で悠然としているカイルにしては珍しい。酷いことを言ってしまったことも、それを謝れなかったことも、ずっと後悔していたのだろうかと思った。
「私、カイル様に言われたこと、怒ってません」
「けど、俺が酷いことを言ったから、だから俺のことも忘れたんじゃないのか?」
俺と一緒にいたことが嫌な思い出になるから、と続けるカイルに反射的に首を振る。そのことは以前にカスミソウを眺めながら考えて、もう答えの出たことだ。
「酷いことを言われたのと、一緒にいてくれたのが嬉しかったことは別、ですから」
「クリスティ……」
「カイル様のことをずっと忘れていたのは、酷いことを言われて悲しかったから、かもしれません。でも、それでも、やっぱり私にとってカイル様が大切な人であることには変わりありません、から、……っわ!?」
飛びつくようにして抱きしめられたせいで、告げようとした言葉は遮られてしまった。耳元でずっと、「ごめん、本当にごめん」と謝るばかりのカイルに、「私も、ごめんなさい。カイル様のお父様が亡くなったとき、何もできなくて」と謝罪する。きっとあの頃のクリスティがどう頑張ったところでどうにもならなかったのだろう。けれど、何もしなかったことも、何もしようとしなかったこともまた事実だ。けれど、カイルは頭を振ってそれを遮る。体を離したカイルは、目元がほんの少し赤くなっていた。
「この家を出てから、孤児院に行ったり、遍歴商人の一座に入ったり、レイモンド様の領地にいたり、いろいろあったんだ」
ポツポツと話し始めたカイルに、「あ……だからシスターのことを……」と合点がいく。クリスティの前では他人のふりを取り繕っていたけれど、やはり二人は昔からの知り合いだったらしい。なるほど、と頷くクリスティの肩をカイルは再びガシリと掴む。
「それに関しては本当に否定させてほしいんだけど、あいつのことは好きじゃない」
「で、でも、すごく親しげに話してらして……」
「昔馴染みだからな。今も昔も、誓って、あいつのことを友人以上に見たことはない。いい?」
「は、はい」
あまりの圧に気圧されるようにして頷いた。それに満足したのか、カイルは肩から手を離すと、膝に置いていたクリスティの手を握る。逃すまいとしているわけではない触れ方に、なんとなく心臓が高鳴った。そんなクリスティに構うことなく、「辛いことも大変だったこともたくさんあったし、忙しくて父さんが死んだ悲しさなんてすぐに薄れていった」とカイルは続ける。想像するだけで、胸が苦しい。カイルが伯爵家を出されたのは十数年は昔の話。伯爵家で小間使いのように働いていたとはいえ、一人で市井に放り出されて生きていくのは大変だっただろう。暗く俯くクリスティに気づいたのか、顔にかかる髪をカイルが払う。顔を上げると、驚くほど穏やかな顔でクリスティを見つめていた。
「けど、クリスティのことは忘れられなかった」
「え……」
「酷いことを言ったことをずっと謝りたかったのもあるし……何より、俺のお手本だったからさ」
「お、お手本?」
「そ、礼儀とか行儀作法とか。平民の俺は貴族のマナーだとかそういうのわかんねえから覚えるの苦労したんだよ」
平民出身で礼儀のなっていない若造が、足元を見られて舐められないわけがない。商談の場で何度も苦い思いをしたと語るカイルを、クリスティは黙り込んでじっと見つめる。
「その度に、お嬢様はどうしてたっけって思い出してさ。酷いこと言ったくせに、ずっと拠り所にしてたんだ」
「私、なんかが、そんな」
「私なんかじゃない。クリスティだからこそ、俺はずっと助けられてたんだよ」
クリスティを見つめる榛色の瞳は、どこまでもまっすぐだ。抑圧的な両親が決して見出してくれなかった価値を、カイルだけは見つけ出して大袈裟なぐらい大事にしてくれる。クリスティに誇れるものなんて、伯爵位ぐらいしかないのに。そう思い込んでいたのに。
「わ、私には、爵位しかないのに?」
「え?」
「伯爵位がほしいから、私と結婚したくて、それで、そのために販路を手放してまで縁談の破棄をお願いしにいったんじゃ、ないんですか?」
引っ込んでいたはずの涙が再び滲み始める。カイルが告げてくれる言葉に嘘はないと思うからこそ、あのとき言っていた言葉もそうなんじゃないかと思ってしまう。カイルにそこまで言ってもらえるほどの自信がないからこそ、爵位以外に結婚のメリットはないのではないかと思ってしまう。クリスティの言葉にぽかんと口を開けていたカイルだけれど、急に思い当たったのだろう。ハッとしたような顔で、「もしかして、あのときの会話聞いてたのか!?」と叫んだ。
「ご、ごめんなさい」
「いや、そうじゃなくて……あっ、だから避けられてたのか」
クリスティに避けられていた理由をようやく理解したらしい。納得したように頷いた後、「あの老人はレイモンド様も言っていた通り、いい噂がない。下手にクリスティのことを褒めて興味を持たれたくなかったんだ」と告げる。その言葉にも嘘はなさそうだ。クリスティが信じ込んでいたことは全て勘違いで、全て一人相撲だったらしい。友達がいなかったせいで、対人スキルが磨かれなかった弊害がここぞとばかりに出てしまったようだ。「あ、あの、カイル様」と謝罪を重ねようと名前を呼ぶと、手のひらを突き出して制される。
「つまり、俺がシスターのことを好きで、爵位目当ての結婚だと思ってたから俺のこと避けてたってこと?」
「そ、そう、です」
頷くと、「はあー……」と深いため息をつく。肺の中の息を全て絞り出したのでは、と思うぐらいに長かった。
「怒れよ……」
「ど、どうして?」
「どうしてじゃなくて。もし俺が本当にそんなやつだとしたら、クリスティのことを利用するだけの最低な男だろ」
怒れよ、と非難するような目で見つめるカイル。実際にされたわけではないのだから、怒ることは難しい。それに、爵位目当ての結婚も、結婚後に愛人を囲うこともよくあることだ。特別目くじらを立てるようなことではない。それに。
「でも、そうだとしても、カイル様は私のことを大事にしてくれましたから」
老人の後妻として生を終えるのだろうと諦めていたクリスティを救ってくれて、婚約者として大事に扱ってくれたのだ。その事実を知ってしまったときは悲しかったし、つい数十分前までそのことでメソメソと泣いてしまったけれど。それでもやっぱり、怒る気にはなれなかっただろう。そう告げると、カイルは何も言わずにクリスティの手を握る。されるがままでいると、そのまま手を取り口元まで近づけた。まるで王子様がお姫様の手を取って口づけるみたいに。手にキスされるのなんて、人生で経験したことがない。一度プロポーズされたときは手を取るだけだった。俄かに騒ぎ始めた心臓の音を聞きながら、その光景をじっと見つめる。
「……」
けれど、指に唇が触れることはない。あと少し、と思ったところでぴたりと動きは止まった。「……やっぱ、柄じゃねえよな」と呟くのが聞こえる。屈めていた身を起こし、眉を下げて笑う様子は、昔のことを彷彿とさせるぐらいにはどこか幼い。その様子に、なぜか心臓が一際大きく脈打った。
「俺は王子様って柄じゃない。クリスティの王子様にはなれない。けど」
ぎゅう、と指を絡めて手を握る。榛色の瞳が射抜くようにクリスティを見つめるせいで、動けない。
「クリスティのことが好きだ。初めて会ったときから」
「カイル、様……」
「だから、俺と婚約してほしい」
――お前に王子様なんて現れない。
呪いのように自分に言い聞かせてきた言葉が頭をよぎる。ずっと、その通りだと思っていた。待っているだけで、何もできないクリスティの目の前に都合よく現れるはずがない。それが世の理だと、思っていた。それはきっと、今も変わらない。
ふと視界の端に、サイドテーブルに置かれたハンカチが映る。カスミソウをあしらったイニシャルの「K」は中途半端なところで刺繍が終わっていて、泣きじゃくっていたせいで涙のしみができている。とても今から人に渡せる状態にするのは難しいだろう。けれど。
「……カイル様、私、刺繍と裁縫は得意なんです」
「えっ? うん、それは知ってる」
「頼んでくれたハンカチは、また最初から繕います。喪が明けるまでに」
「クリスティ……」
「だから……だから、私と結婚、してください」
お願いします、と重ねようとした言葉は続かなかった。勢いよく飛びついてきたカイルに、唇ごと塞がれてしまったから。目を閉じて口づけを受け入れていると、すとんと胸の辺りに何かが落ちる。
――ああ、なんだ。
王子様なんて現れない。現れるのを願うまでもなく、目の前にいたのだ。ずっと気付けなかっただけで。
クリスティを抱きしめる腕は力強い。もう離すまいとするように。その力に負けないように、応えるように、クリスティもまた背中に腕を回した。
「……顔をあげてください」
そう告げると、カイルはゆっくりと顔を上げる。傷ついたような、ほんの少し怯えているような表情はいつも冷静で悠然としているカイルにしては珍しい。酷いことを言ってしまったことも、それを謝れなかったことも、ずっと後悔していたのだろうかと思った。
「私、カイル様に言われたこと、怒ってません」
「けど、俺が酷いことを言ったから、だから俺のことも忘れたんじゃないのか?」
俺と一緒にいたことが嫌な思い出になるから、と続けるカイルに反射的に首を振る。そのことは以前にカスミソウを眺めながら考えて、もう答えの出たことだ。
「酷いことを言われたのと、一緒にいてくれたのが嬉しかったことは別、ですから」
「クリスティ……」
「カイル様のことをずっと忘れていたのは、酷いことを言われて悲しかったから、かもしれません。でも、それでも、やっぱり私にとってカイル様が大切な人であることには変わりありません、から、……っわ!?」
飛びつくようにして抱きしめられたせいで、告げようとした言葉は遮られてしまった。耳元でずっと、「ごめん、本当にごめん」と謝るばかりのカイルに、「私も、ごめんなさい。カイル様のお父様が亡くなったとき、何もできなくて」と謝罪する。きっとあの頃のクリスティがどう頑張ったところでどうにもならなかったのだろう。けれど、何もしなかったことも、何もしようとしなかったこともまた事実だ。けれど、カイルは頭を振ってそれを遮る。体を離したカイルは、目元がほんの少し赤くなっていた。
「この家を出てから、孤児院に行ったり、遍歴商人の一座に入ったり、レイモンド様の領地にいたり、いろいろあったんだ」
ポツポツと話し始めたカイルに、「あ……だからシスターのことを……」と合点がいく。クリスティの前では他人のふりを取り繕っていたけれど、やはり二人は昔からの知り合いだったらしい。なるほど、と頷くクリスティの肩をカイルは再びガシリと掴む。
「それに関しては本当に否定させてほしいんだけど、あいつのことは好きじゃない」
「で、でも、すごく親しげに話してらして……」
「昔馴染みだからな。今も昔も、誓って、あいつのことを友人以上に見たことはない。いい?」
「は、はい」
あまりの圧に気圧されるようにして頷いた。それに満足したのか、カイルは肩から手を離すと、膝に置いていたクリスティの手を握る。逃すまいとしているわけではない触れ方に、なんとなく心臓が高鳴った。そんなクリスティに構うことなく、「辛いことも大変だったこともたくさんあったし、忙しくて父さんが死んだ悲しさなんてすぐに薄れていった」とカイルは続ける。想像するだけで、胸が苦しい。カイルが伯爵家を出されたのは十数年は昔の話。伯爵家で小間使いのように働いていたとはいえ、一人で市井に放り出されて生きていくのは大変だっただろう。暗く俯くクリスティに気づいたのか、顔にかかる髪をカイルが払う。顔を上げると、驚くほど穏やかな顔でクリスティを見つめていた。
「けど、クリスティのことは忘れられなかった」
「え……」
「酷いことを言ったことをずっと謝りたかったのもあるし……何より、俺のお手本だったからさ」
「お、お手本?」
「そ、礼儀とか行儀作法とか。平民の俺は貴族のマナーだとかそういうのわかんねえから覚えるの苦労したんだよ」
平民出身で礼儀のなっていない若造が、足元を見られて舐められないわけがない。商談の場で何度も苦い思いをしたと語るカイルを、クリスティは黙り込んでじっと見つめる。
「その度に、お嬢様はどうしてたっけって思い出してさ。酷いこと言ったくせに、ずっと拠り所にしてたんだ」
「私、なんかが、そんな」
「私なんかじゃない。クリスティだからこそ、俺はずっと助けられてたんだよ」
クリスティを見つめる榛色の瞳は、どこまでもまっすぐだ。抑圧的な両親が決して見出してくれなかった価値を、カイルだけは見つけ出して大袈裟なぐらい大事にしてくれる。クリスティに誇れるものなんて、伯爵位ぐらいしかないのに。そう思い込んでいたのに。
「わ、私には、爵位しかないのに?」
「え?」
「伯爵位がほしいから、私と結婚したくて、それで、そのために販路を手放してまで縁談の破棄をお願いしにいったんじゃ、ないんですか?」
引っ込んでいたはずの涙が再び滲み始める。カイルが告げてくれる言葉に嘘はないと思うからこそ、あのとき言っていた言葉もそうなんじゃないかと思ってしまう。カイルにそこまで言ってもらえるほどの自信がないからこそ、爵位以外に結婚のメリットはないのではないかと思ってしまう。クリスティの言葉にぽかんと口を開けていたカイルだけれど、急に思い当たったのだろう。ハッとしたような顔で、「もしかして、あのときの会話聞いてたのか!?」と叫んだ。
「ご、ごめんなさい」
「いや、そうじゃなくて……あっ、だから避けられてたのか」
クリスティに避けられていた理由をようやく理解したらしい。納得したように頷いた後、「あの老人はレイモンド様も言っていた通り、いい噂がない。下手にクリスティのことを褒めて興味を持たれたくなかったんだ」と告げる。その言葉にも嘘はなさそうだ。クリスティが信じ込んでいたことは全て勘違いで、全て一人相撲だったらしい。友達がいなかったせいで、対人スキルが磨かれなかった弊害がここぞとばかりに出てしまったようだ。「あ、あの、カイル様」と謝罪を重ねようと名前を呼ぶと、手のひらを突き出して制される。
「つまり、俺がシスターのことを好きで、爵位目当ての結婚だと思ってたから俺のこと避けてたってこと?」
「そ、そう、です」
頷くと、「はあー……」と深いため息をつく。肺の中の息を全て絞り出したのでは、と思うぐらいに長かった。
「怒れよ……」
「ど、どうして?」
「どうしてじゃなくて。もし俺が本当にそんなやつだとしたら、クリスティのことを利用するだけの最低な男だろ」
怒れよ、と非難するような目で見つめるカイル。実際にされたわけではないのだから、怒ることは難しい。それに、爵位目当ての結婚も、結婚後に愛人を囲うこともよくあることだ。特別目くじらを立てるようなことではない。それに。
「でも、そうだとしても、カイル様は私のことを大事にしてくれましたから」
老人の後妻として生を終えるのだろうと諦めていたクリスティを救ってくれて、婚約者として大事に扱ってくれたのだ。その事実を知ってしまったときは悲しかったし、つい数十分前までそのことでメソメソと泣いてしまったけれど。それでもやっぱり、怒る気にはなれなかっただろう。そう告げると、カイルは何も言わずにクリスティの手を握る。されるがままでいると、そのまま手を取り口元まで近づけた。まるで王子様がお姫様の手を取って口づけるみたいに。手にキスされるのなんて、人生で経験したことがない。一度プロポーズされたときは手を取るだけだった。俄かに騒ぎ始めた心臓の音を聞きながら、その光景をじっと見つめる。
「……」
けれど、指に唇が触れることはない。あと少し、と思ったところでぴたりと動きは止まった。「……やっぱ、柄じゃねえよな」と呟くのが聞こえる。屈めていた身を起こし、眉を下げて笑う様子は、昔のことを彷彿とさせるぐらいにはどこか幼い。その様子に、なぜか心臓が一際大きく脈打った。
「俺は王子様って柄じゃない。クリスティの王子様にはなれない。けど」
ぎゅう、と指を絡めて手を握る。榛色の瞳が射抜くようにクリスティを見つめるせいで、動けない。
「クリスティのことが好きだ。初めて会ったときから」
「カイル、様……」
「だから、俺と婚約してほしい」
――お前に王子様なんて現れない。
呪いのように自分に言い聞かせてきた言葉が頭をよぎる。ずっと、その通りだと思っていた。待っているだけで、何もできないクリスティの目の前に都合よく現れるはずがない。それが世の理だと、思っていた。それはきっと、今も変わらない。
ふと視界の端に、サイドテーブルに置かれたハンカチが映る。カスミソウをあしらったイニシャルの「K」は中途半端なところで刺繍が終わっていて、泣きじゃくっていたせいで涙のしみができている。とても今から人に渡せる状態にするのは難しいだろう。けれど。
「……カイル様、私、刺繍と裁縫は得意なんです」
「えっ? うん、それは知ってる」
「頼んでくれたハンカチは、また最初から繕います。喪が明けるまでに」
「クリスティ……」
「だから……だから、私と結婚、してください」
お願いします、と重ねようとした言葉は続かなかった。勢いよく飛びついてきたカイルに、唇ごと塞がれてしまったから。目を閉じて口づけを受け入れていると、すとんと胸の辺りに何かが落ちる。
――ああ、なんだ。
王子様なんて現れない。現れるのを願うまでもなく、目の前にいたのだ。ずっと気付けなかっただけで。
クリスティを抱きしめる腕は力強い。もう離すまいとするように。その力に負けないように、応えるように、クリスティもまた背中に腕を回した。