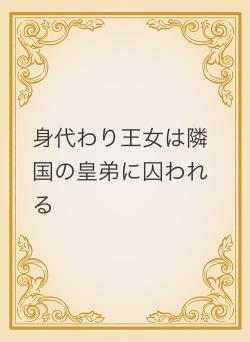クリスティは伯爵令嬢だ。
輝く銀色の髪に透き通った翡翠の瞳。控えめで可愛らしい容姿の彼女だが、その人生が幸福に満ちたものだったかと言われるとそんなことはない。理由は至極簡単、伯爵夫妻でもある彼らが決していい人とは言えず、娘に対してもいい親ではないからだ。
見栄っ張りで浪費癖が激しく、どこまでも自己中心的。呆れるほどの厚かましさにより、社交界中から煙たがられていたのは言うまでもないだろう。彼らの一人娘に対する関心事と言えば、「どれだけ良い家柄の子息に嫁がせられるか」ということだけ。行儀作法を厳しく躾け、少しでもいい家に嫁げるようにと朝から晩までみっちり授業を詰め込む。そんな無駄なことをするなら刺繍の一つでも完成させろと娯楽は与えない。
「この出来損ないが」
「どうしてこんな簡単なことも覚えられないのかしら」
「ごめんなさい、お父様、お母様」
教えられたことができなければ罵られた。食事を抜かれたことだってあった。同じようにちょっとした粗相でいびられている使用人たちは、見て見ぬふりで誰も助けてはくれない。クリスティは両親に抱きしめられた記憶も、頭を撫でられた覚えもなかった。
それでも両親の言うことに反抗せず、大人しく従っていたのは親への愛情からではない。単に、その生き方しか知らなかったからだ。両親の悪評のせいで、伯爵家とまともに付き合いのある家は昔からほとんどなかった。そのせいでクリスティは同年代の子供と交流する機会が極端に少なく、友人と呼べる存在は一人もいない。両親に禁じられるまでは歳の近い使用人の子供とこっそり遊ぶこともあったけれど、品格が落ちるからと禁じられてしまった。他人と関わることを許されなかったクリスティが、一般的な貴族令嬢の暮らしを知る術はほとんどない。自分がどれだけ窮屈で孤独な生活を強いられているのか、よくわかっていなかった。
そんなクリスティに現状を正しく教えてくれたのは父親の腹違いの弟である叔父、レイモンドだ。辺境に住み、国境沿いの防衛を任されている叔父とは年に一度か二年に一度程度しか会えなかったけれど、何かと気にかけてくれた。クリスティの拙い話をいつでも真剣に聞いてくれる叔父は、心の支えと言っても過言ではない。叔父の訪問はいつでもクリスティを喜ばせたのだけれど、本や小説をたくさん買い与えてくれたことが何よりも喜ばせた。冒険物語、騎士道物語、詩集、植物図鑑や歴史本など、両親がくだらないものだと唾棄して買い与えてくれなかったものばかり。その中でも夢中で読み耽ったのは、囚われのお姫様が、迎えにきてくれた王子様の手を取り末長く幸せに暮らすお話。表紙が擦り切れ、ページがボロボロになり、中身を誦じられるまでになるまで、繰り返し読んだものだ。
――いつか、王子様が現れたら。
物語のように、自分にもそんな出来事が起きないかと願ったけれど。それも今は昔の話。王子様なんて現れないし、願うだけ無駄だと言うことは痛いほどわかっている。
叔父が買い与えてくれた本は、クリスティの先生だった。少しずつ知識を蓄えたクリスティは、ようやく理解する。自分がどれだけ窮屈で孤独な生活を強いられているのかを。自分の両親が、どれだけ領主としても親としても酷い人なのかを。けれど、理解したところで何かが変わるわけでもない。理解したのと同時に悟ってしまったのは、どうしようもない無力さだ。非力な両手は繕い物一つできず、頼りにできそうな叔父の家にまで辿り着くためにどうやって辻馬車に乗ればいいかもわからない。曲がりなりにも両親の庇護のもと暮らしているクリスティは、伯爵家を出て両親から逃げ出したところで一人で生きていけるわけがないのだ。
クリスティ自身には興味のない高圧的な両親に二十年も育てられて、自己肯定感が正しく育つはずもない。楽しい時を分かち合う友人も、孤独を慰めてくれる娯楽も。何一つ満足に得られないまま成長してしまった彼女は、親の言いなりになるだけのお人形のようになっていた。最近は叔父がくれた本を読む暇もなく、専らパーティーに参加して社交の場に顔を出すことで忙しい。
娘の恵まれた容姿に自信を持っていたらしい両親は、クリスティの社交界デビュー後一年は高みの見物だった。やれ男爵家は持参金が少なそうだ、やれ金があるだけの平民なんてごめんだと寄ってくる求婚者を選り好みしていたのだけれど。そもそも贅沢を言える立場でないことはわかっていなかったらしい。社交界の鼻つまみ者の娘と婚約して縁続きになろうとするまともな貴族は、国中のどこを探しても存在しない。寄ってきた求婚者だってクリスティの外見だけが目当てか、伯爵という爵位が欲しいだけだった。
次第に減っていく求婚者、当たり前に歳を重ねるクリスティ。娘が世間では行き遅れと指さされるような年齢に達して、ようやく両親は焦りを覚えた。自分たちの不評は棚に上げ、婚約できないのはクリスティの努力不足だと罵りそれでもこの後に及んで高位貴族との縁談を望んで躍起になる両親。足繁くパーティーに通ったところで、伯爵家の悪評は社交界中に広まっている。いくらクリスティの見た目が良くとも、話しかけてくれるような貴族などいないのだ。しかも両親が望むような高位貴族は尚更。悪評以外で目を引くところのないクリスティが待っているだけでは、手を取って連れ出してくれるような王子様は現れない。
今日もパーティーにいく準備をしながら、行ったところで意味なんてないのに、と思うけれど口にはできない。生まれたときから押さえつけられ続けたクリスティに反抗の術はないのだ。今日こそは侯爵家嫡男の一人や二人捕まえてこい、そうでなければ明日の食事は抜きだと脅しをかけられても、望む結果にはならない。両親の望むような殿方に自ら話しかけることがマナー違反であることは、当然のように知っている。せっかく侍女に手伝ってもらって準備を進めても、好奇と侮蔑の視線に晒されながら壁の花になるだけなのだから着飾り甲斐がないというものだろう。両親に準備の手際が悪いだのなんだのといびられている侍女に、心の底から申し訳ないと思った。
――これからも、ずっとこういう感じなんだろうな。
行き遅れの娘に焦った両親はなりふり構っていられないらしい。土地を余らせている高齢の貴族もしくは資産家に、娘を当てがえばいいことにようやく気がついたのだ。二人のクリスティに対する扱いを考えれば、思いつくのがむしろ遅いぐらいだろう。伯爵家の悪評を気にしない人が見つかれば、きっと近いうちにお金持ちのご老人の後妻になる。クリスティの意思が聞き入れられることはもちろんない。重要なのは両親にどれだけの利益をもたらせるかということだけなのだから。
けれど結婚させられる当人であるクリスティは、もはやなんでもいいとさえ思っていた。両親かまだ見ぬご老人か、従う相手が変わるだけの話。どっちの地獄がマシかクリスティにはわからない。願わくば両親の連れてくるご老人が、両親ほども非道な人でないことを祈るばかりだ。
準備を進めてくれる侍女にバレないように、こっそりと息を吐く。これからもずっとこういう感じなのはきっと変わらない。だって、何かを変えるだけの努力をしていないのだから。ただただ待っているだけのクリスティを助けてくれる存在が、都合よく現れるはずがないのだ。
――王子様なんて、現れない。
呪いをかけるように、自分にずっと言い聞かせていた。それがこの世の理なのだと思っていた。両親が事故で亡くなるまでは。
輝く銀色の髪に透き通った翡翠の瞳。控えめで可愛らしい容姿の彼女だが、その人生が幸福に満ちたものだったかと言われるとそんなことはない。理由は至極簡単、伯爵夫妻でもある彼らが決していい人とは言えず、娘に対してもいい親ではないからだ。
見栄っ張りで浪費癖が激しく、どこまでも自己中心的。呆れるほどの厚かましさにより、社交界中から煙たがられていたのは言うまでもないだろう。彼らの一人娘に対する関心事と言えば、「どれだけ良い家柄の子息に嫁がせられるか」ということだけ。行儀作法を厳しく躾け、少しでもいい家に嫁げるようにと朝から晩までみっちり授業を詰め込む。そんな無駄なことをするなら刺繍の一つでも完成させろと娯楽は与えない。
「この出来損ないが」
「どうしてこんな簡単なことも覚えられないのかしら」
「ごめんなさい、お父様、お母様」
教えられたことができなければ罵られた。食事を抜かれたことだってあった。同じようにちょっとした粗相でいびられている使用人たちは、見て見ぬふりで誰も助けてはくれない。クリスティは両親に抱きしめられた記憶も、頭を撫でられた覚えもなかった。
それでも両親の言うことに反抗せず、大人しく従っていたのは親への愛情からではない。単に、その生き方しか知らなかったからだ。両親の悪評のせいで、伯爵家とまともに付き合いのある家は昔からほとんどなかった。そのせいでクリスティは同年代の子供と交流する機会が極端に少なく、友人と呼べる存在は一人もいない。両親に禁じられるまでは歳の近い使用人の子供とこっそり遊ぶこともあったけれど、品格が落ちるからと禁じられてしまった。他人と関わることを許されなかったクリスティが、一般的な貴族令嬢の暮らしを知る術はほとんどない。自分がどれだけ窮屈で孤独な生活を強いられているのか、よくわかっていなかった。
そんなクリスティに現状を正しく教えてくれたのは父親の腹違いの弟である叔父、レイモンドだ。辺境に住み、国境沿いの防衛を任されている叔父とは年に一度か二年に一度程度しか会えなかったけれど、何かと気にかけてくれた。クリスティの拙い話をいつでも真剣に聞いてくれる叔父は、心の支えと言っても過言ではない。叔父の訪問はいつでもクリスティを喜ばせたのだけれど、本や小説をたくさん買い与えてくれたことが何よりも喜ばせた。冒険物語、騎士道物語、詩集、植物図鑑や歴史本など、両親がくだらないものだと唾棄して買い与えてくれなかったものばかり。その中でも夢中で読み耽ったのは、囚われのお姫様が、迎えにきてくれた王子様の手を取り末長く幸せに暮らすお話。表紙が擦り切れ、ページがボロボロになり、中身を誦じられるまでになるまで、繰り返し読んだものだ。
――いつか、王子様が現れたら。
物語のように、自分にもそんな出来事が起きないかと願ったけれど。それも今は昔の話。王子様なんて現れないし、願うだけ無駄だと言うことは痛いほどわかっている。
叔父が買い与えてくれた本は、クリスティの先生だった。少しずつ知識を蓄えたクリスティは、ようやく理解する。自分がどれだけ窮屈で孤独な生活を強いられているのかを。自分の両親が、どれだけ領主としても親としても酷い人なのかを。けれど、理解したところで何かが変わるわけでもない。理解したのと同時に悟ってしまったのは、どうしようもない無力さだ。非力な両手は繕い物一つできず、頼りにできそうな叔父の家にまで辿り着くためにどうやって辻馬車に乗ればいいかもわからない。曲がりなりにも両親の庇護のもと暮らしているクリスティは、伯爵家を出て両親から逃げ出したところで一人で生きていけるわけがないのだ。
クリスティ自身には興味のない高圧的な両親に二十年も育てられて、自己肯定感が正しく育つはずもない。楽しい時を分かち合う友人も、孤独を慰めてくれる娯楽も。何一つ満足に得られないまま成長してしまった彼女は、親の言いなりになるだけのお人形のようになっていた。最近は叔父がくれた本を読む暇もなく、専らパーティーに参加して社交の場に顔を出すことで忙しい。
娘の恵まれた容姿に自信を持っていたらしい両親は、クリスティの社交界デビュー後一年は高みの見物だった。やれ男爵家は持参金が少なそうだ、やれ金があるだけの平民なんてごめんだと寄ってくる求婚者を選り好みしていたのだけれど。そもそも贅沢を言える立場でないことはわかっていなかったらしい。社交界の鼻つまみ者の娘と婚約して縁続きになろうとするまともな貴族は、国中のどこを探しても存在しない。寄ってきた求婚者だってクリスティの外見だけが目当てか、伯爵という爵位が欲しいだけだった。
次第に減っていく求婚者、当たり前に歳を重ねるクリスティ。娘が世間では行き遅れと指さされるような年齢に達して、ようやく両親は焦りを覚えた。自分たちの不評は棚に上げ、婚約できないのはクリスティの努力不足だと罵りそれでもこの後に及んで高位貴族との縁談を望んで躍起になる両親。足繁くパーティーに通ったところで、伯爵家の悪評は社交界中に広まっている。いくらクリスティの見た目が良くとも、話しかけてくれるような貴族などいないのだ。しかも両親が望むような高位貴族は尚更。悪評以外で目を引くところのないクリスティが待っているだけでは、手を取って連れ出してくれるような王子様は現れない。
今日もパーティーにいく準備をしながら、行ったところで意味なんてないのに、と思うけれど口にはできない。生まれたときから押さえつけられ続けたクリスティに反抗の術はないのだ。今日こそは侯爵家嫡男の一人や二人捕まえてこい、そうでなければ明日の食事は抜きだと脅しをかけられても、望む結果にはならない。両親の望むような殿方に自ら話しかけることがマナー違反であることは、当然のように知っている。せっかく侍女に手伝ってもらって準備を進めても、好奇と侮蔑の視線に晒されながら壁の花になるだけなのだから着飾り甲斐がないというものだろう。両親に準備の手際が悪いだのなんだのといびられている侍女に、心の底から申し訳ないと思った。
――これからも、ずっとこういう感じなんだろうな。
行き遅れの娘に焦った両親はなりふり構っていられないらしい。土地を余らせている高齢の貴族もしくは資産家に、娘を当てがえばいいことにようやく気がついたのだ。二人のクリスティに対する扱いを考えれば、思いつくのがむしろ遅いぐらいだろう。伯爵家の悪評を気にしない人が見つかれば、きっと近いうちにお金持ちのご老人の後妻になる。クリスティの意思が聞き入れられることはもちろんない。重要なのは両親にどれだけの利益をもたらせるかということだけなのだから。
けれど結婚させられる当人であるクリスティは、もはやなんでもいいとさえ思っていた。両親かまだ見ぬご老人か、従う相手が変わるだけの話。どっちの地獄がマシかクリスティにはわからない。願わくば両親の連れてくるご老人が、両親ほども非道な人でないことを祈るばかりだ。
準備を進めてくれる侍女にバレないように、こっそりと息を吐く。これからもずっとこういう感じなのはきっと変わらない。だって、何かを変えるだけの努力をしていないのだから。ただただ待っているだけのクリスティを助けてくれる存在が、都合よく現れるはずがないのだ。
――王子様なんて、現れない。
呪いをかけるように、自分にずっと言い聞かせていた。それがこの世の理なのだと思っていた。両親が事故で亡くなるまでは。