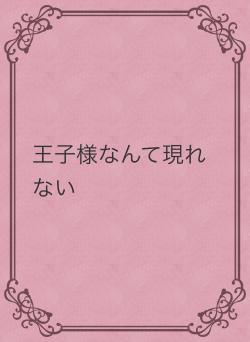「に、ニグラス、お願い、はなしてっ」
「あはは、エメリのお願いでもそれは聞けないかな」
楽しそうな声に反して、金色の瞳は笑っていない。必死の抵抗も懇願も虚しく、服は一枚一枚剥ぎ取られていく。いつもはこんなに強引にしないのに。聞かなくていいと言っても、脱がしていいか毎回聞いてくれるのに。いつだってエメリの意思を尊重して、壊れ物に触れるかのように触れてくれるニグラスとはまるで別人だ。あっという間に生まれたままの姿にされ、鷲掴むようにして胸を揉まれる。両手は頭上でまとめられ、左手一本で押さえつけられているせいで抵抗はできない。痛みに顔を顰めていると、首筋に噛みつかれた。
「いっ!?」
「……肉、柔らか。こんなの、僕でも噛みちぎれる」
物騒なことを言いながら噛み跡に舌を這わせる。鋭い牙があるようには見えないけれど、エメリの皮膚を食い破るぐらいの鋭利さはあったのだろうか。舐められるたびにヒリヒリとした痛みが走った。かぷりと甘噛みしたかと思えば、ちゅうっと痛いぐらいに吸いつく。文字通り、喉元に刃物を当てられているような感覚は心臓に悪い。喘ぐどころか、上手く声を出すことすらできない。
「怖いの? 震えてる」
「ひっ……」
「大丈夫、エメリのこと食べないから」
喉のあたりを親指でなぞられ、引き攣った声が出る。何が大丈夫なのだろうか。少しでもこの指に力が加われば、エメリの喉はポッキリと折れてしまうのに。食べられないのだとしても、エメリの生死は完全に握られている。心臓の音が、どくどくといつになく忙しない。首筋に埋めていた顔を離したニグラスは、少しだけ体を起こしてエメリをじっと見つめる。見慣れた金色が今日は意味がわからないぐらいに怖い。衝動的に逃げ出そうとしたけれど、両手が使えないせいで失敗に終わった。ジタバタともがくエメリを無表情に見下ろしていたニグラスは不意に口角を上げる。
「それで抵抗してるつもり? 可愛いね」
「っ、は、はなして」
「やぁだ。僕がエメリのこと大好きなんだって、まだ伝わってないでしょ?」
だからだめ、と呟くと、エメリの足の間に体を割り入れる。下半身に手が伸びるので思わず足を閉じようとしたけれど、当然意味はなかった。いつもなら抵抗なんてしないけれど、今日は違う。このまま強引に抱かれるなんて、したくなかった。
「もー……仕方ないなあ」
「っあ……!」
けれど抵抗は完全に裏目に出たらしい。鬱陶しそうに指をパチンと鳴らす音がしたかと思うと、エメリの両手は布で結ばれ自由を奪われた。布をどうにかして外せないかともがいている隙に、ニグラスの指がエメリの秘部に触れる。
「あは、濡れてる」
「や、やだっ、触らないでっ」
「やだ」
ちゅぷ、とニグラスの指がエメリの中に侵入する。長い指がお腹の内側をとんとんと刺激するたび、情けないぐらいに喘ぎ声が漏れた。初夜以降、ニグラスに夜な夜な快楽を教え込まれていたせいで、いつもより強引な愛撫でも簡単に快楽を拾い上げてしまう。身を捩って悶えるエメリを、ニグラスは嬉しそうに見下ろした。
「気持ちいい? 僕の指ぎゅーって締め付けてるのわかる?」
「ひぁっ、そ、それやめっ」
いつの間にか二本に増えた指がお腹の中でバラバラと動き、陰核に吸い付かれる。頭がビリビリして、目の前がチカチカした。軽くイってしまったのに、ニグラスが止まってくれることはない。縛られた手を伸ばして頭を押したけれど、大した抵抗にはならなかった。弱々しく押し返す手に当たるのは髪の毛のふわふわした感触と、何か固いもの。角だ、とわかる前に熱い何かが指先を通って全身へと伝わった。
「えぁっ……!?」
「ああ、角?」
道の感覚に思わず手を引っ込めるエメリとは対照的に、ニグラスは落ち着いたものだ。中に埋め込む指はそのままに、空いた方の手でエメリの手を自分の角に誘導する。両手でしっかりと握らされると、手のひらが火傷しそうなぐらい熱い。
「角はね、僕の魔力の源なんだ。触れると感情が伝わるし、食べると寿命と記憶が得られる」
知らなかった。角や耳、それから時には翼。それらが魔力の源というのは実家にあった書物に書いてあった気がするけれど、感情や記憶が伝わることまでは知らなかった。手のひらが熱くてたまらないのに、どうしてか離すことができない。どろどろに蕩けた愛情と、燃えたぎるような嫉妬、それから胸が張り裂けそうな悲壮。どういう仕組みでそんな感情が伝わってくるのかは、微塵もわからない。けれど、ニグラスがエメリに対して抱いている感情の激しさだけは、十分すぎるほどに理解した。
「伝わった?」
「……っ」
ニンマリと嬉しそうに笑うニグラス。思わず手を引っ込めると、ようやく指がエメリの中から引き抜かれた。抜かれる余韻で悶えていると、抱き上げてお腹の上に乗せられる。押し倒されていたのが、押し倒しているような体勢だ。枕を背もたれにしたニグラスはくったりと力の抜けたエメリの両頬を手で挟む。「僕がエメリを好きで好きでたまらないの、わかった?」と尋ねられ、思わず目を逸らした。伝わった、と思うけれどそれを口にすることはなんだか恥ずかしい。
「素直じゃないなあ」
「ひっ、ぅえっ!?」
ぐちゅり、とぬるついた感触と共にニグラスのものが、散々いじめられて潤んだところに宛てがわれる。興奮しているのかだろうか、いつもより熱くて固い。思わず逃げようとするけれど、腰をガッチリ掴まれているせいで叶わなかった。エメリが上で身じろぐのなんて気にも留めず、ニグラスは自身をずぷずぷと埋め込んでいく。
「あっ、や、あぁっ……」
「あー……いつもよりもきっついね」
縛られた両手をニグラスの胸に置き、圧迫感で荒くなる息を整える。自重のせいで、深いところに突き刺さるようだ。お腹がいっぱいで苦しい。早く抜いて欲しいのに、ニグラスにそのつもりはないらしい。ニンマリと笑ったまま、「エメリが動いて」と恐ろしいことを告げた。
「はっ、えっ!?」
「エメリが素直じゃないからお仕置き」
「な、や、やだ」
「やだじゃないよ。僕がイくまで抜いちゃだめだからね」
そう言うニグラスは、自分で動くつもりはないらしい。エメリの太ももを撫でているけれど、腰が動く気配は微塵もない。「う、うそ」と思わず溢すと、「嘘じゃないよ」とだけ返ってくる。両手は縛られたままで、楔を打ち込まれたように埋め込まれているせいで、自分で抜くことすらできない。ぼろ、と涙が溢れた。
「泣いてもだぁめ」
「……っ」
「終わりたいんなら早く動いて」
突き放すような口調に、目の前が真っ暗になる。いつもはエメリが泣いたら、おろおろしながら止まってくれるのに。ぽろぽろとこぼれ落ちる涙を拭ってくれる手つきは優しいのに、ちっとも優しくない。本当に、エメリが動いてニグラスのことをイかせるまでこのままでいるつもりらしい。
「……んっ、あっ……」
どう足掻いても終わってもらえないのなら、と逡巡した末に、ゆるゆると腰を前後に動かし始める。こんな児戯にも満たないような動き方でイくわけがないと思うけれど、どうしたらいいのかはわからない。一生懸命に動いていると、陰核が擦れて気持ちがいい。エメリの痴態をじっと見つめるニグラスの視線が、突き刺さるように痛い。
「それ、気持ちいいの?」
「あっ、んっんっ……きもち、いっ……」
「ふうん。なんかエメリが僕でオナニーしてるみたいで興奮する」
「やぁ……」
「わ、締まった。可愛いね、エメリ」
一向にイく気配のないニグラスは、エメリの下で楽しそうにしている。必死で動くうちに、エメリだけが上り詰めていくようだ。自分だけがイっても意味がないのに、ニグラスをイかせないといけないのに。絶頂を迎えてしまわないよう、一度落ち着こうと腰の動きを止める。終わりが見えなくて、どうしたらいいのかわからない。
「休んじゃダメだよ」
「ひぁっ!?」
まるでサボっているのを咎めるように、ニグラスがエメリの乳首を摘む。親指の腹で擦ったり、ぎゅうっと強く摘まれたり。思わぬ刺激から逃れようともがくけれど、そのせいで埋め込まれたものの当たる場所が変わった。気持ちがいいのに、上り詰められる状況ではないせいでもどかしさばかりが募る。心臓が痛い。いつもよりずっと酷くされているのに、それでも気持ちいいと感じてしまうのが悲しかった。
「や、ひ、引っ張るの、だめっ、も、やだって、ばっ」
「まだ僕いってないから休んじゃだめ。いい子だから、動けるでしょ?」
ほら、とゆるく腰を突き上げられたのが、だめだった。脳天から背骨にかけて、駆け抜けるような快感が走る。びくびくと全身を震わせると、ぐしゃりとニグラスの上に頽れる。図らずも焦らされていたせいで、簡単な刺激を与えられるだけで絶頂を迎えてしまったようだ。はあ、はあ、と荒い呼吸を整えようとするけれど。勇者をいじめ抜く魔王がそれを許してくれるはずもない。
「あれ、エメリが先にイっちゃった? しょうがないな」
「ま、まって、おねがい、い、今だめなのっ」
「まだ僕はイってないんだってば」
そう言うと、下からガツガツと容赦なく突き上げる。エメリに動かせるのはもうやめたらしい。イったせいでうまく体に力の入らないエメリに、抵抗のすべなどなく。されるがままに何度も何度も絶頂へと導かれる。
「も、やだっ、やだぁっ……ゆる、してっ……」
「あはは、必死だね。かーわい」
どれだけ泣いても、ニグラスがエメリの懇願を聞いてくれることはなかった。結局、ニグラスが一度イくまでにエメリがイかされた数は数え切れず。夕方ごろから始まった行為が終わったのは、夜明け過ぎだった。
*
「んっ……」
目が覚めると同時に、全身の痛みを自覚する。お腹のあたりがなんだか熱い。初夜の比ではなく、とても起き上がれそうにない。カーテンからうっすら日が差しているのを見るに、もうすぐで朝になるのだろう。今日一日ベッドから出られるのだろうか、と不安を覚えた。
「起きた?」
「! に、にぐ、げほっ」
顔を覗き込むニグラスの名前を呼ぼうとしたところで、喉が酷く枯れていることに気がついた。げほげほと咳き込んでいると、「わ、ちょっと待ってね」と慌てた様子でエメリの視界から引っ込む。顔を動かして見てみると、サイドテーブルに置いてあった水差しから水を注いでいるところだった。水の入ったグラスを置き、エメリを起き上がらせる。背中に添えられた手はいつものように優しくて、それだけで涙が滲んでしまいそうだ。エメリが泣きそうなことに、ニグラスは気づいたようだけれど何も言わない。そっと渡されたグラスを受け取り、枯れた喉を潤す。飲み干すとグラスは手から抜き取られ、サイドテーブルに戻された。ニグラスはいつも以上に甲斐甲斐しい。ぼんやりしていると、ニグラスが心底申し訳なさそうに頭を下げた。
「ごめん、やりすぎた」
まず思ったのが、魔王が勇者に頭を下げてる……ということ。夜通しいじめ抜かれたけれど、本来魔王とはそういうものだろう。いつの間にか両手の拘束も解かれているけれど、本当なら魔王城で勇者が自由にうろちょろできることの方がおかしい。昼夜問わず丁寧に優しくされていたことに慣れきっていたけれど、ある意味魔王に敗北した勇者としての立場をわからされたと言ってもいい。
けれど、昨日の行為はきっとそういうのではない。大事なのは、そういうことじゃない。あのとき、火傷しそうな手のひらから伝わったのは、痛くて苦しくなるほどの愛情と嫉妬と、それから。
「……私、マルコって人にドキドキしてたわけじゃないよ」
「え」
「あんまり男の人と喋ったことないから、距離が近くてびっくりしたってだけで。ニグラスが悲しむようなことは何もないよ」
そもそもの発端を思い返す。パーソナルスペースというものをまるで無視した距離感に思わず顔を赤くしてしまっただけで、それ以上の感情はこれっぽっちもない。ぱち、と目を瞬かせるニグラスは罰が悪そうにそっぽを向く。
「わかってるよ」
「え」
「僕が心配するようなこと、何もないんだろうなってわかってる」
「だったら……」
「けど、好きな子が他のやつに押し倒されて真っ赤になってるの見て、冷静でいられるわけないじゃんか」
なんで僕だけにその顔見せてくれないの、と呟いてニグラスはエメリの膝に頭を乗せる。拗ねているような、縋り付くような様子はとても魔王には見えない。角がある以外、どこにでもいる普通の男の人みたいだ。ふわふわの髪の毛に手を伸ばし、甘やかすように撫でてみる。自分でもどうしてそうしているのかはわからない。ただ、触れずにはいられなかった。
「角、触ってもいい?」
「いいよ。エメリになら、何されたっていいよ」
それは重たいな、と思いつつ角に手を伸ばす。昨夜のように焼け付くような熱さはなかったけれど、それでもぽかぽかと暖かい。眩しいぐらいの恋慕と、苦しいぐらいの渇望。手のひらから伝わる感情が、エメリの全身へと流れ込む。
「伝わった?」
「……うん」
素直にそう頷くと、角からささやかな喜びが伝わる。魔族の角というのは、思った以上に感情を表すらしい。思わず手を引っ込めると、「エメリのことが好きだよ、大好き」と今度は言葉にして告げられた。直球に愛を告げられるのは初めてではないけれど、いつもドギマギしてしまう。何も言えずにもごもごしていると、ニグラスは再び口を開く。
「酷いことしてごめんね、エメリ」
そう言って謝ると、ニグラスの手がエメリの左手を掴む。鋭い爪のない、エメリより一回りは大きな手。ぎゅう、と握られたところで感情は伝わらないはずなのに、どうしてか何かが伝わってくるような気がした。掴まれた左手の薬指には、今日も揃いの指輪が輝いている。
「でも、あのね。お願い、いつかは僕のこと好きになって」
「え……」
「僕と同じぐらいじゃなくてもいいの。ほんのちょっとでいいから」
僕のこと好きになって、と念を押すように呟く声は随分と小さい。けれど、その囁きのような懇願は、エメリの心臓に深く突き刺さった。勇者であるエメリは魔王であるニグラスに負けて、今は王国に対する人質だ。結婚して家族になったとはいえ、その上下関係のようなものが覆ることはない。ニグラスはエメリを優しく丁寧に扱う義務なんてないし、酷いことをしたって謝る必要もない。魔王らしく、好きなようにすればいいのだ。
――けど、そうしないのは。
そうしないのは、エメリのことが好きだから。エメリに、ほんの少しでも自分のことを好きになってもらいたいから。だから優しく丁寧に扱うし、酷いことをしたら謝るし、好きになってほしいだなんて健気にも懇願する。それが、その事実が、どうしてか今更エメリの胸に響いた。
「うん」
「えっ?」
ニグラスの角に触れながら、そう頷く。顔を上げたニグラスは驚いたように目を丸くしてエメリを見上げている。その表情が、なんだかすごく愛おしく思えた。
「ニグラスのこと、好きになる」
そう告げて、身を屈める。前髪を掻き分けて額に唇を落とすと、発火したかのように角が熱を持つ。手のひらから伝わるのは、狂おしいほどの歓喜だった。
「あはは、エメリのお願いでもそれは聞けないかな」
楽しそうな声に反して、金色の瞳は笑っていない。必死の抵抗も懇願も虚しく、服は一枚一枚剥ぎ取られていく。いつもはこんなに強引にしないのに。聞かなくていいと言っても、脱がしていいか毎回聞いてくれるのに。いつだってエメリの意思を尊重して、壊れ物に触れるかのように触れてくれるニグラスとはまるで別人だ。あっという間に生まれたままの姿にされ、鷲掴むようにして胸を揉まれる。両手は頭上でまとめられ、左手一本で押さえつけられているせいで抵抗はできない。痛みに顔を顰めていると、首筋に噛みつかれた。
「いっ!?」
「……肉、柔らか。こんなの、僕でも噛みちぎれる」
物騒なことを言いながら噛み跡に舌を這わせる。鋭い牙があるようには見えないけれど、エメリの皮膚を食い破るぐらいの鋭利さはあったのだろうか。舐められるたびにヒリヒリとした痛みが走った。かぷりと甘噛みしたかと思えば、ちゅうっと痛いぐらいに吸いつく。文字通り、喉元に刃物を当てられているような感覚は心臓に悪い。喘ぐどころか、上手く声を出すことすらできない。
「怖いの? 震えてる」
「ひっ……」
「大丈夫、エメリのこと食べないから」
喉のあたりを親指でなぞられ、引き攣った声が出る。何が大丈夫なのだろうか。少しでもこの指に力が加われば、エメリの喉はポッキリと折れてしまうのに。食べられないのだとしても、エメリの生死は完全に握られている。心臓の音が、どくどくといつになく忙しない。首筋に埋めていた顔を離したニグラスは、少しだけ体を起こしてエメリをじっと見つめる。見慣れた金色が今日は意味がわからないぐらいに怖い。衝動的に逃げ出そうとしたけれど、両手が使えないせいで失敗に終わった。ジタバタともがくエメリを無表情に見下ろしていたニグラスは不意に口角を上げる。
「それで抵抗してるつもり? 可愛いね」
「っ、は、はなして」
「やぁだ。僕がエメリのこと大好きなんだって、まだ伝わってないでしょ?」
だからだめ、と呟くと、エメリの足の間に体を割り入れる。下半身に手が伸びるので思わず足を閉じようとしたけれど、当然意味はなかった。いつもなら抵抗なんてしないけれど、今日は違う。このまま強引に抱かれるなんて、したくなかった。
「もー……仕方ないなあ」
「っあ……!」
けれど抵抗は完全に裏目に出たらしい。鬱陶しそうに指をパチンと鳴らす音がしたかと思うと、エメリの両手は布で結ばれ自由を奪われた。布をどうにかして外せないかともがいている隙に、ニグラスの指がエメリの秘部に触れる。
「あは、濡れてる」
「や、やだっ、触らないでっ」
「やだ」
ちゅぷ、とニグラスの指がエメリの中に侵入する。長い指がお腹の内側をとんとんと刺激するたび、情けないぐらいに喘ぎ声が漏れた。初夜以降、ニグラスに夜な夜な快楽を教え込まれていたせいで、いつもより強引な愛撫でも簡単に快楽を拾い上げてしまう。身を捩って悶えるエメリを、ニグラスは嬉しそうに見下ろした。
「気持ちいい? 僕の指ぎゅーって締め付けてるのわかる?」
「ひぁっ、そ、それやめっ」
いつの間にか二本に増えた指がお腹の中でバラバラと動き、陰核に吸い付かれる。頭がビリビリして、目の前がチカチカした。軽くイってしまったのに、ニグラスが止まってくれることはない。縛られた手を伸ばして頭を押したけれど、大した抵抗にはならなかった。弱々しく押し返す手に当たるのは髪の毛のふわふわした感触と、何か固いもの。角だ、とわかる前に熱い何かが指先を通って全身へと伝わった。
「えぁっ……!?」
「ああ、角?」
道の感覚に思わず手を引っ込めるエメリとは対照的に、ニグラスは落ち着いたものだ。中に埋め込む指はそのままに、空いた方の手でエメリの手を自分の角に誘導する。両手でしっかりと握らされると、手のひらが火傷しそうなぐらい熱い。
「角はね、僕の魔力の源なんだ。触れると感情が伝わるし、食べると寿命と記憶が得られる」
知らなかった。角や耳、それから時には翼。それらが魔力の源というのは実家にあった書物に書いてあった気がするけれど、感情や記憶が伝わることまでは知らなかった。手のひらが熱くてたまらないのに、どうしてか離すことができない。どろどろに蕩けた愛情と、燃えたぎるような嫉妬、それから胸が張り裂けそうな悲壮。どういう仕組みでそんな感情が伝わってくるのかは、微塵もわからない。けれど、ニグラスがエメリに対して抱いている感情の激しさだけは、十分すぎるほどに理解した。
「伝わった?」
「……っ」
ニンマリと嬉しそうに笑うニグラス。思わず手を引っ込めると、ようやく指がエメリの中から引き抜かれた。抜かれる余韻で悶えていると、抱き上げてお腹の上に乗せられる。押し倒されていたのが、押し倒しているような体勢だ。枕を背もたれにしたニグラスはくったりと力の抜けたエメリの両頬を手で挟む。「僕がエメリを好きで好きでたまらないの、わかった?」と尋ねられ、思わず目を逸らした。伝わった、と思うけれどそれを口にすることはなんだか恥ずかしい。
「素直じゃないなあ」
「ひっ、ぅえっ!?」
ぐちゅり、とぬるついた感触と共にニグラスのものが、散々いじめられて潤んだところに宛てがわれる。興奮しているのかだろうか、いつもより熱くて固い。思わず逃げようとするけれど、腰をガッチリ掴まれているせいで叶わなかった。エメリが上で身じろぐのなんて気にも留めず、ニグラスは自身をずぷずぷと埋め込んでいく。
「あっ、や、あぁっ……」
「あー……いつもよりもきっついね」
縛られた両手をニグラスの胸に置き、圧迫感で荒くなる息を整える。自重のせいで、深いところに突き刺さるようだ。お腹がいっぱいで苦しい。早く抜いて欲しいのに、ニグラスにそのつもりはないらしい。ニンマリと笑ったまま、「エメリが動いて」と恐ろしいことを告げた。
「はっ、えっ!?」
「エメリが素直じゃないからお仕置き」
「な、や、やだ」
「やだじゃないよ。僕がイくまで抜いちゃだめだからね」
そう言うニグラスは、自分で動くつもりはないらしい。エメリの太ももを撫でているけれど、腰が動く気配は微塵もない。「う、うそ」と思わず溢すと、「嘘じゃないよ」とだけ返ってくる。両手は縛られたままで、楔を打ち込まれたように埋め込まれているせいで、自分で抜くことすらできない。ぼろ、と涙が溢れた。
「泣いてもだぁめ」
「……っ」
「終わりたいんなら早く動いて」
突き放すような口調に、目の前が真っ暗になる。いつもはエメリが泣いたら、おろおろしながら止まってくれるのに。ぽろぽろとこぼれ落ちる涙を拭ってくれる手つきは優しいのに、ちっとも優しくない。本当に、エメリが動いてニグラスのことをイかせるまでこのままでいるつもりらしい。
「……んっ、あっ……」
どう足掻いても終わってもらえないのなら、と逡巡した末に、ゆるゆると腰を前後に動かし始める。こんな児戯にも満たないような動き方でイくわけがないと思うけれど、どうしたらいいのかはわからない。一生懸命に動いていると、陰核が擦れて気持ちがいい。エメリの痴態をじっと見つめるニグラスの視線が、突き刺さるように痛い。
「それ、気持ちいいの?」
「あっ、んっんっ……きもち、いっ……」
「ふうん。なんかエメリが僕でオナニーしてるみたいで興奮する」
「やぁ……」
「わ、締まった。可愛いね、エメリ」
一向にイく気配のないニグラスは、エメリの下で楽しそうにしている。必死で動くうちに、エメリだけが上り詰めていくようだ。自分だけがイっても意味がないのに、ニグラスをイかせないといけないのに。絶頂を迎えてしまわないよう、一度落ち着こうと腰の動きを止める。終わりが見えなくて、どうしたらいいのかわからない。
「休んじゃダメだよ」
「ひぁっ!?」
まるでサボっているのを咎めるように、ニグラスがエメリの乳首を摘む。親指の腹で擦ったり、ぎゅうっと強く摘まれたり。思わぬ刺激から逃れようともがくけれど、そのせいで埋め込まれたものの当たる場所が変わった。気持ちがいいのに、上り詰められる状況ではないせいでもどかしさばかりが募る。心臓が痛い。いつもよりずっと酷くされているのに、それでも気持ちいいと感じてしまうのが悲しかった。
「や、ひ、引っ張るの、だめっ、も、やだって、ばっ」
「まだ僕いってないから休んじゃだめ。いい子だから、動けるでしょ?」
ほら、とゆるく腰を突き上げられたのが、だめだった。脳天から背骨にかけて、駆け抜けるような快感が走る。びくびくと全身を震わせると、ぐしゃりとニグラスの上に頽れる。図らずも焦らされていたせいで、簡単な刺激を与えられるだけで絶頂を迎えてしまったようだ。はあ、はあ、と荒い呼吸を整えようとするけれど。勇者をいじめ抜く魔王がそれを許してくれるはずもない。
「あれ、エメリが先にイっちゃった? しょうがないな」
「ま、まって、おねがい、い、今だめなのっ」
「まだ僕はイってないんだってば」
そう言うと、下からガツガツと容赦なく突き上げる。エメリに動かせるのはもうやめたらしい。イったせいでうまく体に力の入らないエメリに、抵抗のすべなどなく。されるがままに何度も何度も絶頂へと導かれる。
「も、やだっ、やだぁっ……ゆる、してっ……」
「あはは、必死だね。かーわい」
どれだけ泣いても、ニグラスがエメリの懇願を聞いてくれることはなかった。結局、ニグラスが一度イくまでにエメリがイかされた数は数え切れず。夕方ごろから始まった行為が終わったのは、夜明け過ぎだった。
*
「んっ……」
目が覚めると同時に、全身の痛みを自覚する。お腹のあたりがなんだか熱い。初夜の比ではなく、とても起き上がれそうにない。カーテンからうっすら日が差しているのを見るに、もうすぐで朝になるのだろう。今日一日ベッドから出られるのだろうか、と不安を覚えた。
「起きた?」
「! に、にぐ、げほっ」
顔を覗き込むニグラスの名前を呼ぼうとしたところで、喉が酷く枯れていることに気がついた。げほげほと咳き込んでいると、「わ、ちょっと待ってね」と慌てた様子でエメリの視界から引っ込む。顔を動かして見てみると、サイドテーブルに置いてあった水差しから水を注いでいるところだった。水の入ったグラスを置き、エメリを起き上がらせる。背中に添えられた手はいつものように優しくて、それだけで涙が滲んでしまいそうだ。エメリが泣きそうなことに、ニグラスは気づいたようだけれど何も言わない。そっと渡されたグラスを受け取り、枯れた喉を潤す。飲み干すとグラスは手から抜き取られ、サイドテーブルに戻された。ニグラスはいつも以上に甲斐甲斐しい。ぼんやりしていると、ニグラスが心底申し訳なさそうに頭を下げた。
「ごめん、やりすぎた」
まず思ったのが、魔王が勇者に頭を下げてる……ということ。夜通しいじめ抜かれたけれど、本来魔王とはそういうものだろう。いつの間にか両手の拘束も解かれているけれど、本当なら魔王城で勇者が自由にうろちょろできることの方がおかしい。昼夜問わず丁寧に優しくされていたことに慣れきっていたけれど、ある意味魔王に敗北した勇者としての立場をわからされたと言ってもいい。
けれど、昨日の行為はきっとそういうのではない。大事なのは、そういうことじゃない。あのとき、火傷しそうな手のひらから伝わったのは、痛くて苦しくなるほどの愛情と嫉妬と、それから。
「……私、マルコって人にドキドキしてたわけじゃないよ」
「え」
「あんまり男の人と喋ったことないから、距離が近くてびっくりしたってだけで。ニグラスが悲しむようなことは何もないよ」
そもそもの発端を思い返す。パーソナルスペースというものをまるで無視した距離感に思わず顔を赤くしてしまっただけで、それ以上の感情はこれっぽっちもない。ぱち、と目を瞬かせるニグラスは罰が悪そうにそっぽを向く。
「わかってるよ」
「え」
「僕が心配するようなこと、何もないんだろうなってわかってる」
「だったら……」
「けど、好きな子が他のやつに押し倒されて真っ赤になってるの見て、冷静でいられるわけないじゃんか」
なんで僕だけにその顔見せてくれないの、と呟いてニグラスはエメリの膝に頭を乗せる。拗ねているような、縋り付くような様子はとても魔王には見えない。角がある以外、どこにでもいる普通の男の人みたいだ。ふわふわの髪の毛に手を伸ばし、甘やかすように撫でてみる。自分でもどうしてそうしているのかはわからない。ただ、触れずにはいられなかった。
「角、触ってもいい?」
「いいよ。エメリになら、何されたっていいよ」
それは重たいな、と思いつつ角に手を伸ばす。昨夜のように焼け付くような熱さはなかったけれど、それでもぽかぽかと暖かい。眩しいぐらいの恋慕と、苦しいぐらいの渇望。手のひらから伝わる感情が、エメリの全身へと流れ込む。
「伝わった?」
「……うん」
素直にそう頷くと、角からささやかな喜びが伝わる。魔族の角というのは、思った以上に感情を表すらしい。思わず手を引っ込めると、「エメリのことが好きだよ、大好き」と今度は言葉にして告げられた。直球に愛を告げられるのは初めてではないけれど、いつもドギマギしてしまう。何も言えずにもごもごしていると、ニグラスは再び口を開く。
「酷いことしてごめんね、エメリ」
そう言って謝ると、ニグラスの手がエメリの左手を掴む。鋭い爪のない、エメリより一回りは大きな手。ぎゅう、と握られたところで感情は伝わらないはずなのに、どうしてか何かが伝わってくるような気がした。掴まれた左手の薬指には、今日も揃いの指輪が輝いている。
「でも、あのね。お願い、いつかは僕のこと好きになって」
「え……」
「僕と同じぐらいじゃなくてもいいの。ほんのちょっとでいいから」
僕のこと好きになって、と念を押すように呟く声は随分と小さい。けれど、その囁きのような懇願は、エメリの心臓に深く突き刺さった。勇者であるエメリは魔王であるニグラスに負けて、今は王国に対する人質だ。結婚して家族になったとはいえ、その上下関係のようなものが覆ることはない。ニグラスはエメリを優しく丁寧に扱う義務なんてないし、酷いことをしたって謝る必要もない。魔王らしく、好きなようにすればいいのだ。
――けど、そうしないのは。
そうしないのは、エメリのことが好きだから。エメリに、ほんの少しでも自分のことを好きになってもらいたいから。だから優しく丁寧に扱うし、酷いことをしたら謝るし、好きになってほしいだなんて健気にも懇願する。それが、その事実が、どうしてか今更エメリの胸に響いた。
「うん」
「えっ?」
ニグラスの角に触れながら、そう頷く。顔を上げたニグラスは驚いたように目を丸くしてエメリを見上げている。その表情が、なんだかすごく愛おしく思えた。
「ニグラスのこと、好きになる」
そう告げて、身を屈める。前髪を掻き分けて額に唇を落とすと、発火したかのように角が熱を持つ。手のひらから伝わるのは、狂おしいほどの歓喜だった。