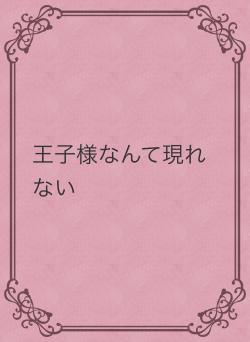魔王城にやってきて、魔王に嫁いで早一週間。勇者としてはあるまじきことだが、魔王城での生活にもそこそこ慣れてしまった。温室と小屋を往復して楽しく過ごすほどに。
図書室から自分が読める言語の書物を探し出したエメリは、まず探し当てた本を使って黒い森に生えている草花の種類を調べることから始めた。温室にも黒い森にも、エメリが王国で見たことのない草花や薬草が生えている。図鑑を見ながら薬草を採取するのに丸一日かかったほどだ。採取した薬草は、図書室で見つけ出した薬草書に従って薬を調合するのに使った。趣味の延長のような薬師の真似事で、勇者としての責務の領分からは完全に外れている。けれど、今までの人生で一番充実しているとさえ思えた。
「ふう……」
ヒヨスを煮出した煎液を、布で漉したところで一息つく。鎮痛薬に使えるので便利な反面、その毒性は強い。万一にも汁が口に入らないよう、手拭いで口を覆っての作業はなかなかに神経を使う。けれど、それでも好きなように薬を調合できるのは楽しくて仕方がない。
「エメリ様〜?」
「やっぱりここにいた」
「あ、リリとリム」
ノックの音が響いたかと思えば、双子の侍女がドアを開ける。小屋には入らない二人は外から匂いを嗅いで、「ヒヨスじゃん」「どしたのエメリ様、媚薬でも作るの」と好き勝手呟いた。煮出しているのがヒヨスであることも、その効能が何なのかも、匂いだけでわかるものらしい。黒い森で生まれ育ってきたからなのだろうか。
「ち、違うよ!? 鎮痛薬を作ろうと思って!」
「なんだ」
「ニグラスと使うのかと思ったのに」
「違うってば!」
顔を真っ赤にして否定するエメリを、双子はニヨニヨと楽しそうに揶揄う。侍女らしくせっせと世話を焼いてくれる二人だけれど、基本的に距離は近い。ことあるごとにニグラスとのことを揶揄ってくるし、定期的に温室と小屋を尋ねてきてはエメリをお茶会へと誘い出す。今日やってきたのもそのためで、両腕を組んでホールドされたかと思えば、あれよあれよと中庭に連れ出された。まだやることはたくさんあるのに、と思ったけれど作業は一段落している。続きはお茶会の後にでもすればいいし、何より、生まれて初めての友人の誘いを断るのは忍びない。
「ニグラスとはどーお?」
「いちゃいちゃしてる?」
「ぶっ」
明け透けにものを言う双子に、思わず紅茶を吹き出す。実家にいた頃ならはしたないと目くじらを立てられただろうけれど、ここでは誰も咎めることはしない。顔を赤くするエメリを双子がニヨニヨと眺めるだけだ。双子は、入れすぎなんじゃないかと思うほどの牛乳を紅茶に注ぐと、楽しそうに口を開いた。
「顔真っ赤〜」
「どうなのどうなの?」
「ぼ、ぼちぼち……」
「おおー!」
「ニグラスやるう」
きゃっきゃと湧き立つ二人に、もっとしっかり話をはぐらかせばよかったと後悔した。ぼちぼち、だなんて。どうしてそんな、いちゃいちゃしていることを認める答えを返してしまったのか。ニグラスがびっくりするほど優しくて、どれだけ忙しくてもせっせとエメリを甘やかすから、絆されてしまったのかもしれない。恥ずかしいのを少しでも紛らわすために、「二人はニグラスのことどう思ってるの?」と話を逸らした。
「魔王」
「それ」
「そうじゃなくて」
分かってはいたことだけれど、双子は思っている以上にニグラスに異性としての興味がないらしい。魔王としてしか認識していない割に、「ニグラス」と呼び捨てにしているけれど。
「えーと、魔王って勝手になんかこう、ハーレムを築いているというか、女の子侍らせてるのかなってイメージがあって」
「ああ〜そういう魔王もいなかったことはないけど」
「ニグラスはないね。あいつモテないし」
「そうなんだ……」
以前、女の子が寄ってきたことなんてないとニグラスが自分で言っていたけれど、どうやら本当だったらしい。うんうんと頷きあう双子の顔に嘘はない。かっこいいのになあ、と思ってしまった自分にハッとして、ぶんぶんと頭を振った。
「それなら、魔族の間ではどういう人が人気なの?」
「マルコとか?」
「ああ〜エメリ様が言ってる魔王像はマルコが近いかも」
「マルコ?」
初めて聞く名前だ。マルコ、とは一体。首を傾げていると、「本名マルコシアスだけど、みんなマルコって呼んでる」「エメリ様もマルコって呼んだらいいよ」と話している。あまり情報は増えなかった。
「マルコには気をつけてね」
「うん。あいつは女好きだし女から好かれるから」
「そうなんだ」
「あいつは容赦なくエメリ様に手出すかもだけど」
「そうなったらニグラスブチ切れで魔王城血の海になっちゃうから」
「えっ!?」
唐突な物騒な言葉に動揺を隠せない。魔王城が血の海ってどういうこと、と聞こうとしたけれど双子が急に真剣な顔をするものだから何も言えなくなってしまった。
「気をつけてね」
「本当に気をつけてね」
一体何をどうやって、と問い返せるような空気ではなく。よくわからないままに、ただただ念だけ押された。
*
そんな双子からの忠告も忘れた頃のことだった。
「……あれ?」
今日は何を調合しようか、まずは温室の様子を見て収穫の時期になっているものを見つけないと、とルンルンで温室に向かっているところで異変に気がつく。温室の扉の前に、何か大きな黒い塊が横たわっている。もふもふした、毛玉のような何か。生き物なのだろうか、呼吸しているかのように上下している。なんとなく見覚えのある毛並みに、記憶の引き出しから何かが引っ張り出された。
――も、もしかして魔犬……!?
先日のトラウマが蘇り、足が竦む。丸められた剣は未だどこかに打ち捨てられたままだ。護身用の短剣すら持たないエメリは、今日も今日とて丸腰である。この魔犬が目を覚ましたところで、また腰を抜かしてメソメソ泣くことしかできないだろう。
――逃げるしかない。
起こさないように、そっと後退りする。温室の様子が見られないのも、調合できないのも残念だけれど、自分の命は何より惜しい。今日は諦めて図書室にでも篭ろう、と思ったときだった。黒い犬が唐突に目を覚まし、頭を上げる。よく見ると犬ではなく、狼だ。ぺたん、と驚きのあまりまたも尻餅をついたエメリは、「ひえっ……」と情けない声を漏らしてしまった。どうしよう、ニグラスが来てくれるわけないし今度こそ死んだ、と悲壮な覚悟を決める、が。
『誰だお前、食っちまうぞ』
「へっ!?」
狼から聞こえたのは、聞き覚えのない男の人の低い声。思わず目を擦ると、瞬く間に狼は見知らぬ男へと姿を変えた。背はニグラスよりも高く、体格はガッチリしていて、頭には獣の耳が生えていて、背中には翼がある。あと、目つきがとんでもなく悪い。この人も魔族なのだろう、と言うことはすぐに分かった。
「なんで人間がこんなとこにいんだよ」
尻餅を付いたままのエメリを見下ろし、聞くともなしに尋ねるその男の威圧感たるや。ニグラスに斬りかかったときや、魔犬に襲われかけたときほどではないが、エメリの心中に緊張が走る。会話はできそうだけれど、果たして話の通じる相手なのだろうか。ニグラスの名前を出せばどうにかなるのだろうか。いつの間にか魔王に頼ることを厭わなくなった自分に呆れるのを無視していると、しゃがみ込んだ男はくんっと鼻を鳴らす。
「この匂い、お前ニグラスの番か?」
「へ」
番、とは。匂い、とは。自分にそんなものがついているのだろうか。思い当たる節がなくきょとんとしていると、納得したように男は笑った。
「あー……わかった。お前あれだ、ニグラスのあれだろ。あいつとうとうやったのか」
「な、なんの話ですか?」
絶対にエメリの話なのに、指示語が多すぎて何の話なのかさっぱりわからない。匂いは何のことで、あれとはどれのことなのか。エメリの疑問に答えない彼は、「名前は?」と尋ねる。
「エメリ、です」
「エメリね。俺はマルコシアス」
「あ、あなたが……!」
リリとリムが物騒な忠告をしてきたのはこの人だったらしい。思っていたよりは話が通じそうな気もするけれど、どちらにしろ逃げ出すのが賢明だろう。腰が抜けて上手く立てないので、一生懸命に後ずさるけれど、面白いとでも思われたのだろうか。「双子あたりから余計なこと吹き込まれたか?」と楽しそうに距離を詰めてくる。尻餅をついたままのエメリに、ほぼ覆い被さるような体勢だ。
「ちょっ、近い! 近いです!」
「お前がニグラスのねえー……あいつやることちゃんとやってんじゃねえか」
「話聞いてます!?」
唇が触れ合いそうなほどの顔の近さで顔に熱が集まる。男性経験はニグラスしかないのだ、ときめいているわけでなくとも心臓がドキドキしてしまうのは仕方がない。あと数ミリ近づけば本当にキスされてしまうのでは、というところまで距離が縮まったとき。突如、マルコが何かに弾かれ、吹っ飛んだ末に大木にぶつかった。
「ねえ、マルコ。何してんの」
背筋がぞくりとするほどの冷たい声。聞き慣れた声のはずなのに、そんなに冷たい声音をしているのを聞いたことはない。本気で怒っているのが感じ取れて、エメリはますます動けなくなってしまう。
「よ、よおニグラス。元気そうじゃねえか」
「人の奥さんに手出しといて第一声がそれ? もう一回いっとく?」
結構な勢いで張り飛ばされたと思ったのに、意外と動けるものらしい。起き上がったマルコは、「悪かったって」とそんなに悪かったと思っていなさそうな声で謝る。
「手出してねえよそんなちんちくりんに」
「ちんちくっ、」
これでも成人してるのに、とずいぶんな言われように衝撃を受けるのと、マルコの頭に触手が直撃するのは同時だった。地面に倒れ伏してピクピクと痙攣しているマルコを一瞥するとニグラスは、未だ尻餅をついたままのエメリに視線を移す。いつも慈しむように、愛おしそうにエメリを見つめる金色の瞳。それが今はどうだろう。ゾッとするほどに感情が読めず、底知れないほどに恐ろしい。そんな目で見られたことなんて、今まで一度もなかったのに。思わず後ずさったのをニグラスは見逃さなかったのだろう。一瞬だけ顔を強張らせると、触手をしまい込んでエメリに近づく。
「行くよ」
「あ、わっ」
座り込んだエメリの膝裏と肩に手を回して軽々と抱き抱え、いつぞやと同じように指をパチンと鳴らす。瞬きの間に景色が変わり、最近ではすっかり見慣れてしまった寝室に移動した。そのままツカツカとベッドへと歩み寄ると、エメリを乱暴にベッドに落とす。こんな雑な運ばれ方したことない、と衝撃を受ける前に両手首を掴まれてベッドに縫い付けられてしまった。
「顔、赤いね。マルコにドキドキした?」
「えっ?」
「エメリもああいう男の方が好き?」
「な、なんの話?」
びっくりするほど会話になっていない。困惑するエメリに対してい苛立っているのを、ニグラスは隠すつもりがないらしい。手首に込められた力がさらに強くなり、思わず顔を顰める。エメリを見下ろすニグラスの瞳は相変わらず冷たく、抵抗できる気がまったくしない。
「あいつが温室の前にいるのに気づかなかった僕が悪いけどさあ、エメリは僕のお嫁さんでしょ?」
「て、手、放して……」
「なんで違うやつに押し倒されて、顔赤くしてんの?」
それでもどうにか抵抗を試みるけれど、聞いてはくれない。ニグラスがどうしてそんなに怒っているのかも、どうしたら離してくれるのかもわからない。心臓が嫌な意味でドキドキする。こんなふうに、抵抗できないように押し倒されたのは初めてだった。
「エメリのこと好きなのは僕だよ。あいつじゃない」
「に、ニグ、んむっ」
名前を呼ぶ前にキスされ、性急に口をこじ開けられる。蹂躙するかのように口内を荒らされ、息が上手く吸えない。もがくほどに手首を押さえつける力は強くなり、痛くて折れてしまいそうだ。けれど、それよりも心臓が痛い。今までずっと優しくされていたのに。甘ったるさに絆されてしまいそうなほど、甘やかされてきたのに。そういう行為をするのは構わない、ニグラスはいつだって優しく抱いてくれるから。けれど、今日に限っては絶対に優しくしてくれないのだということが、キスだけでわかったのが悲しかった。
図書室から自分が読める言語の書物を探し出したエメリは、まず探し当てた本を使って黒い森に生えている草花の種類を調べることから始めた。温室にも黒い森にも、エメリが王国で見たことのない草花や薬草が生えている。図鑑を見ながら薬草を採取するのに丸一日かかったほどだ。採取した薬草は、図書室で見つけ出した薬草書に従って薬を調合するのに使った。趣味の延長のような薬師の真似事で、勇者としての責務の領分からは完全に外れている。けれど、今までの人生で一番充実しているとさえ思えた。
「ふう……」
ヒヨスを煮出した煎液を、布で漉したところで一息つく。鎮痛薬に使えるので便利な反面、その毒性は強い。万一にも汁が口に入らないよう、手拭いで口を覆っての作業はなかなかに神経を使う。けれど、それでも好きなように薬を調合できるのは楽しくて仕方がない。
「エメリ様〜?」
「やっぱりここにいた」
「あ、リリとリム」
ノックの音が響いたかと思えば、双子の侍女がドアを開ける。小屋には入らない二人は外から匂いを嗅いで、「ヒヨスじゃん」「どしたのエメリ様、媚薬でも作るの」と好き勝手呟いた。煮出しているのがヒヨスであることも、その効能が何なのかも、匂いだけでわかるものらしい。黒い森で生まれ育ってきたからなのだろうか。
「ち、違うよ!? 鎮痛薬を作ろうと思って!」
「なんだ」
「ニグラスと使うのかと思ったのに」
「違うってば!」
顔を真っ赤にして否定するエメリを、双子はニヨニヨと楽しそうに揶揄う。侍女らしくせっせと世話を焼いてくれる二人だけれど、基本的に距離は近い。ことあるごとにニグラスとのことを揶揄ってくるし、定期的に温室と小屋を尋ねてきてはエメリをお茶会へと誘い出す。今日やってきたのもそのためで、両腕を組んでホールドされたかと思えば、あれよあれよと中庭に連れ出された。まだやることはたくさんあるのに、と思ったけれど作業は一段落している。続きはお茶会の後にでもすればいいし、何より、生まれて初めての友人の誘いを断るのは忍びない。
「ニグラスとはどーお?」
「いちゃいちゃしてる?」
「ぶっ」
明け透けにものを言う双子に、思わず紅茶を吹き出す。実家にいた頃ならはしたないと目くじらを立てられただろうけれど、ここでは誰も咎めることはしない。顔を赤くするエメリを双子がニヨニヨと眺めるだけだ。双子は、入れすぎなんじゃないかと思うほどの牛乳を紅茶に注ぐと、楽しそうに口を開いた。
「顔真っ赤〜」
「どうなのどうなの?」
「ぼ、ぼちぼち……」
「おおー!」
「ニグラスやるう」
きゃっきゃと湧き立つ二人に、もっとしっかり話をはぐらかせばよかったと後悔した。ぼちぼち、だなんて。どうしてそんな、いちゃいちゃしていることを認める答えを返してしまったのか。ニグラスがびっくりするほど優しくて、どれだけ忙しくてもせっせとエメリを甘やかすから、絆されてしまったのかもしれない。恥ずかしいのを少しでも紛らわすために、「二人はニグラスのことどう思ってるの?」と話を逸らした。
「魔王」
「それ」
「そうじゃなくて」
分かってはいたことだけれど、双子は思っている以上にニグラスに異性としての興味がないらしい。魔王としてしか認識していない割に、「ニグラス」と呼び捨てにしているけれど。
「えーと、魔王って勝手になんかこう、ハーレムを築いているというか、女の子侍らせてるのかなってイメージがあって」
「ああ〜そういう魔王もいなかったことはないけど」
「ニグラスはないね。あいつモテないし」
「そうなんだ……」
以前、女の子が寄ってきたことなんてないとニグラスが自分で言っていたけれど、どうやら本当だったらしい。うんうんと頷きあう双子の顔に嘘はない。かっこいいのになあ、と思ってしまった自分にハッとして、ぶんぶんと頭を振った。
「それなら、魔族の間ではどういう人が人気なの?」
「マルコとか?」
「ああ〜エメリ様が言ってる魔王像はマルコが近いかも」
「マルコ?」
初めて聞く名前だ。マルコ、とは一体。首を傾げていると、「本名マルコシアスだけど、みんなマルコって呼んでる」「エメリ様もマルコって呼んだらいいよ」と話している。あまり情報は増えなかった。
「マルコには気をつけてね」
「うん。あいつは女好きだし女から好かれるから」
「そうなんだ」
「あいつは容赦なくエメリ様に手出すかもだけど」
「そうなったらニグラスブチ切れで魔王城血の海になっちゃうから」
「えっ!?」
唐突な物騒な言葉に動揺を隠せない。魔王城が血の海ってどういうこと、と聞こうとしたけれど双子が急に真剣な顔をするものだから何も言えなくなってしまった。
「気をつけてね」
「本当に気をつけてね」
一体何をどうやって、と問い返せるような空気ではなく。よくわからないままに、ただただ念だけ押された。
*
そんな双子からの忠告も忘れた頃のことだった。
「……あれ?」
今日は何を調合しようか、まずは温室の様子を見て収穫の時期になっているものを見つけないと、とルンルンで温室に向かっているところで異変に気がつく。温室の扉の前に、何か大きな黒い塊が横たわっている。もふもふした、毛玉のような何か。生き物なのだろうか、呼吸しているかのように上下している。なんとなく見覚えのある毛並みに、記憶の引き出しから何かが引っ張り出された。
――も、もしかして魔犬……!?
先日のトラウマが蘇り、足が竦む。丸められた剣は未だどこかに打ち捨てられたままだ。護身用の短剣すら持たないエメリは、今日も今日とて丸腰である。この魔犬が目を覚ましたところで、また腰を抜かしてメソメソ泣くことしかできないだろう。
――逃げるしかない。
起こさないように、そっと後退りする。温室の様子が見られないのも、調合できないのも残念だけれど、自分の命は何より惜しい。今日は諦めて図書室にでも篭ろう、と思ったときだった。黒い犬が唐突に目を覚まし、頭を上げる。よく見ると犬ではなく、狼だ。ぺたん、と驚きのあまりまたも尻餅をついたエメリは、「ひえっ……」と情けない声を漏らしてしまった。どうしよう、ニグラスが来てくれるわけないし今度こそ死んだ、と悲壮な覚悟を決める、が。
『誰だお前、食っちまうぞ』
「へっ!?」
狼から聞こえたのは、聞き覚えのない男の人の低い声。思わず目を擦ると、瞬く間に狼は見知らぬ男へと姿を変えた。背はニグラスよりも高く、体格はガッチリしていて、頭には獣の耳が生えていて、背中には翼がある。あと、目つきがとんでもなく悪い。この人も魔族なのだろう、と言うことはすぐに分かった。
「なんで人間がこんなとこにいんだよ」
尻餅を付いたままのエメリを見下ろし、聞くともなしに尋ねるその男の威圧感たるや。ニグラスに斬りかかったときや、魔犬に襲われかけたときほどではないが、エメリの心中に緊張が走る。会話はできそうだけれど、果たして話の通じる相手なのだろうか。ニグラスの名前を出せばどうにかなるのだろうか。いつの間にか魔王に頼ることを厭わなくなった自分に呆れるのを無視していると、しゃがみ込んだ男はくんっと鼻を鳴らす。
「この匂い、お前ニグラスの番か?」
「へ」
番、とは。匂い、とは。自分にそんなものがついているのだろうか。思い当たる節がなくきょとんとしていると、納得したように男は笑った。
「あー……わかった。お前あれだ、ニグラスのあれだろ。あいつとうとうやったのか」
「な、なんの話ですか?」
絶対にエメリの話なのに、指示語が多すぎて何の話なのかさっぱりわからない。匂いは何のことで、あれとはどれのことなのか。エメリの疑問に答えない彼は、「名前は?」と尋ねる。
「エメリ、です」
「エメリね。俺はマルコシアス」
「あ、あなたが……!」
リリとリムが物騒な忠告をしてきたのはこの人だったらしい。思っていたよりは話が通じそうな気もするけれど、どちらにしろ逃げ出すのが賢明だろう。腰が抜けて上手く立てないので、一生懸命に後ずさるけれど、面白いとでも思われたのだろうか。「双子あたりから余計なこと吹き込まれたか?」と楽しそうに距離を詰めてくる。尻餅をついたままのエメリに、ほぼ覆い被さるような体勢だ。
「ちょっ、近い! 近いです!」
「お前がニグラスのねえー……あいつやることちゃんとやってんじゃねえか」
「話聞いてます!?」
唇が触れ合いそうなほどの顔の近さで顔に熱が集まる。男性経験はニグラスしかないのだ、ときめいているわけでなくとも心臓がドキドキしてしまうのは仕方がない。あと数ミリ近づけば本当にキスされてしまうのでは、というところまで距離が縮まったとき。突如、マルコが何かに弾かれ、吹っ飛んだ末に大木にぶつかった。
「ねえ、マルコ。何してんの」
背筋がぞくりとするほどの冷たい声。聞き慣れた声のはずなのに、そんなに冷たい声音をしているのを聞いたことはない。本気で怒っているのが感じ取れて、エメリはますます動けなくなってしまう。
「よ、よおニグラス。元気そうじゃねえか」
「人の奥さんに手出しといて第一声がそれ? もう一回いっとく?」
結構な勢いで張り飛ばされたと思ったのに、意外と動けるものらしい。起き上がったマルコは、「悪かったって」とそんなに悪かったと思っていなさそうな声で謝る。
「手出してねえよそんなちんちくりんに」
「ちんちくっ、」
これでも成人してるのに、とずいぶんな言われように衝撃を受けるのと、マルコの頭に触手が直撃するのは同時だった。地面に倒れ伏してピクピクと痙攣しているマルコを一瞥するとニグラスは、未だ尻餅をついたままのエメリに視線を移す。いつも慈しむように、愛おしそうにエメリを見つめる金色の瞳。それが今はどうだろう。ゾッとするほどに感情が読めず、底知れないほどに恐ろしい。そんな目で見られたことなんて、今まで一度もなかったのに。思わず後ずさったのをニグラスは見逃さなかったのだろう。一瞬だけ顔を強張らせると、触手をしまい込んでエメリに近づく。
「行くよ」
「あ、わっ」
座り込んだエメリの膝裏と肩に手を回して軽々と抱き抱え、いつぞやと同じように指をパチンと鳴らす。瞬きの間に景色が変わり、最近ではすっかり見慣れてしまった寝室に移動した。そのままツカツカとベッドへと歩み寄ると、エメリを乱暴にベッドに落とす。こんな雑な運ばれ方したことない、と衝撃を受ける前に両手首を掴まれてベッドに縫い付けられてしまった。
「顔、赤いね。マルコにドキドキした?」
「えっ?」
「エメリもああいう男の方が好き?」
「な、なんの話?」
びっくりするほど会話になっていない。困惑するエメリに対してい苛立っているのを、ニグラスは隠すつもりがないらしい。手首に込められた力がさらに強くなり、思わず顔を顰める。エメリを見下ろすニグラスの瞳は相変わらず冷たく、抵抗できる気がまったくしない。
「あいつが温室の前にいるのに気づかなかった僕が悪いけどさあ、エメリは僕のお嫁さんでしょ?」
「て、手、放して……」
「なんで違うやつに押し倒されて、顔赤くしてんの?」
それでもどうにか抵抗を試みるけれど、聞いてはくれない。ニグラスがどうしてそんなに怒っているのかも、どうしたら離してくれるのかもわからない。心臓が嫌な意味でドキドキする。こんなふうに、抵抗できないように押し倒されたのは初めてだった。
「エメリのこと好きなのは僕だよ。あいつじゃない」
「に、ニグ、んむっ」
名前を呼ぶ前にキスされ、性急に口をこじ開けられる。蹂躙するかのように口内を荒らされ、息が上手く吸えない。もがくほどに手首を押さえつける力は強くなり、痛くて折れてしまいそうだ。けれど、それよりも心臓が痛い。今までずっと優しくされていたのに。甘ったるさに絆されてしまいそうなほど、甘やかされてきたのに。そういう行為をするのは構わない、ニグラスはいつだって優しく抱いてくれるから。けれど、今日に限っては絶対に優しくしてくれないのだということが、キスだけでわかったのが悲しかった。