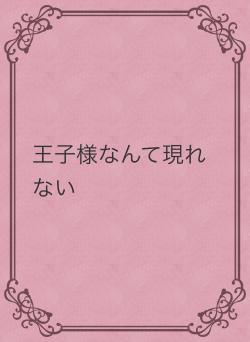去っていったニグラスの背中が完全に見えなくなっても、エメリはその場を動くことができなかった。
――家族じゃない!
そう叫んだのは心からの本音だ。エメリはニグラスと結婚したけれど、家族や夫婦と呼べるものになったつもりはない。結婚しないと王国を滅ぼすだなんて馬鹿げた脅しをかけられたから従っているだけで、愛し合っているわけでも情があるわけでもない。そもそも人間と魔族で婚姻関係を結ぶことができるのかもわからないのだ。エメリが叫んだことは何一つ間違っていない。そのはずなのに。
「なんなの……」
胸の辺りがなんだかもやもやする。ニグラスが去り際に見せた顔がこびりついたように、頭から離れない。寂しくて悲しくて仕方がないのを隠すかのような、そんな笑い方。魔王である彼がそんな表情を浮かべるだなんて、思いもしなかった。エメリとニグラスの初対面はたった数日前のこと。ニグラスが初対面で結婚を申し込んでくる理由も、家族だなんだと形容する根拠も、全くわからない。
「はあー……」
ずるずると沈み込むようにしてその場にしゃがみ込む。数日前に黒い森に一人でやってきたときには何も感じなかったのに、今はなんだか肌寒いし心細い。ニグラスも双子の侍女も良くしてくれるから忘れていたけれど、ここは敵の本拠地。魔族の住む黒い森。日が差さないせいで相変わらず薄暗い。夢のような温室も、立派な調合小屋も。気になって仕方がないのに、入ってみる気力も湧かない。気が済んだら戻ってくるように言っていたけれど、一体どんな顔で会えばいいのだろう。
そうしてしゃがみ込んで悶々として、どれぐらい経ったのだろうか。不意に、ざくりと土を踏む音が聞こえた。もしかしてニグラスが戻ってきたのだろうか。心臓が気まずさにどくりと脈打つ。まだどんな顔で会えばいいのかわからないのに。そう思いながらノロノロ顔を上げて――心臓が止まったと思った。
グルルル……と歯を剥き出しにして唸るのは真っ黒い体毛に覆われた大きな犬、魔犬だ。魔王城に来るまでに襲いかかってきたのは、エメリでも十分に斬り伏せることができるぐらいに小ぶりだった。ところが目の前の魔犬は、確実に小ぶりだなんて形容することはできない。体の大きさはエメリと同じぐらいか、それ以上だろうか。こんな大きさの魔獣と戦ったことなど、ない。おまけに。
――剣がない……!
おまけに、魔王城にやってきた初日に剣は奪われた挙句に丸められてしまったのだ。今のエメリは丸腰で、武器といえば徒手空拳しかないのだけれど。こんな、鋭い牙も爪もある魔獣相手に素手でどうやって立ち向かえばいいのか。じりじりと距離を少しずつ詰める魔犬は、エメリの守護の力を警戒しているのだろうか。一気に襲いかかってくることはしない。この隙に立ち上がって全力で逃げればいい。頭では分かっている、のに。
「あ、あ……」
ぺたん、と尻餅をついてしまう。腰が抜けて、立てそうにない。怖い、無理だ。剣もないのに勝てるわけがないし、逃げ出したところで追いつかれる可能性の方が高い。逃げるにも一体どこへ、助けを求めるにも一体誰に。ここは魔王城で、敵の本拠地なのに。エメリを助けてくれる誰かがいるわけなんてないのに。
――怖い。
ニグラスを前にしたときとはまた別の種類の恐怖。その重みを煩わしいとすら思っていたのに、剣のない自分がこうも弱いだなんて。あまりの情けなさに、鼻の奥がツンとする。心臓がうるさくて、うまく息が吸えない。ずり、と無意識に後ずさったエメリを見て、目の前の獲物が大したことないと悟ったのだろう。魔犬が地面を蹴るのがやけにスローモーションに見えた。
「……っ!」
死ぬ、痛い思いをしてここで死ぬんだ、と腕で自分を守るようにして目を瞑ったけれど、痛みは一向にやってこない。代わりに、バシンっと何かを弾くような大きな音と、次いでドシンッと衝突したような衝撃音、それからキャウンッと犬のような鳴き声が続け様に聞こえる。
「エメリ、大丈夫?」
ここ数日ですっかり聞き慣れてしまった声に、恐る恐る目を開けた。しゃがみ込んだニグラスが、エメリの顔を心配そうに覗き込んでいる。背後では触手が蠢いていて、衝突音が聞こえた方を見ると魔犬が伸びているのが見えた。どうやら、触手の一撃で魔犬を伸したらしい。魔王らしくない、と散々思っていたのだけれど。やはり彼は魔王らしい。
「ごめんね、エメリから離れちゃだめだった。怪我してない?」
問いかけに頷くと、「よかった」と安心したように呟いて、ニグラスはエメリを抱え上げる。大した力も込めず、軽々と抱き上げられたことに驚く間もない。指をパチンと鳴らす音が聞こえたかと思うと、瞬きの間に景色が変わっていた。慣れない魔王城の中で数少ない見慣れた場所、寝室だ。ニグラスはエメリを抱えたままベッドに腰掛ける。膝に乗せたエメリを抱きしめながら、「本当にごめん」と繰り返した。
「な、んで、謝るの」
「僕がエメリを置いてったせいで、エメリが怪我するところだった」
エメリの背中を撫でながら謝罪を繰り返すニグラス。背中に触れる手のひらは暖かくて、徐々に落ち着きを取り戻す。寝室は黒い森とは違って肌寒くないし、心細くもない。安心を覚えているのだろうか、よりにもよって魔王の腕の中で。
――なにそれ。
うるさい心臓とうまく吸えない息がどうにかなったかと思えば、急に視界がぼやけた。目の奥が熱くて、喉の奥が焼け付くように痛い。ぐず、と鼻を鳴らしたせいでエメリの異変に気付いたのだろう。ニグラスが体を離し、エメリを見てギョッとする。
「ど、どうしたの? やっぱりどっか怪我した? 怖かった?」
「……る、さい」
「え?」
「うるさいっ……!」
ジタバタと暴れてもがいて、どうにかニグラスの膝の上から退く。が、変な体勢で飛び降りてしまったせいか、着地には盛大に失敗してしまった。ベシャリとニグラスの足元に崩れ落ちるエメリを見て、ニグラスは慌ててしゃがみ込む。その仕草がやけに腹立たしかった。
「エメリ……」
「さ、触らないでっ」
そう叫ぶと同時に、瞳に溜まっていた海がとうとう決壊する。ぼろ、と涙がこぼれ落ちるのを見られたくなくて、丸くなって蹲った。ミノムシみたいで、みっともない体勢。とても、勇者が魔王の前で取る体勢には思えない。剣があっても魔王は討伐できなくて、剣がなかったら魔獣相手に腰を抜かす。エメリは勇者なのに。やりたくなくても、向いてなくても、勇者としての責務を果たさなければならないのに。王国の平和のために、戦わないといけないのに。何一つ成し遂げられず、魔王に命を助けてもらい、挙げ句の果てには慰められる始末。エメリの一体どこが「勇者」と言えるのだろう。
「エメリ、泣かないで」
おろおろ、という形容詞がぴったりな声音でニグラスは声をかける。背中に何かが触れそうな感触があったが、寸前で引っ込められた。エメリが、「触らないで」といったのを律儀に聞いているのかもしれない。根拠のわからない優しさが、エメリを一層惨めにした。「な、んで……」と思わず疑問がこぼれる。のろのろと起き上がって床にへたり込むと、「うん?」と聞き返すニグラスも同じように床にしゃがみ込んでいるのが見えた。ぐず、と鼻を啜りながらエメリは口を開く。
「なんで、私のこと、殺さないの?」
「えっ」
ギョッとしたように目を見開くニグラス。そんなことを聞かれるだなんて思いもしなかった、とでも言いたげな顔だ。
「さっき、怖くて動けなかった。剣は取られて、丸腰だと何にもできなくて……勇者らしいこと何にもできなくて、人質の価値すらない、のに」
どうして殺さないの、と責め立てるように尋ねる。殺されたいわけではないし、できるならば生きていたい。けれど、エメリは勇者であり魔王の敵なのだ。守護の力を持つエメリがこうも弱いとわかった今、エメリを殺して王国に攻め入ることは赤子の首を捻るかのように簡単だろう。そうしない理由がわからなかった。ニグラスは目を見開いたままエメリの言葉を聞き、やがて俯いて息を吐き出した。
「なんで、そんなこと言うかなあ……」
絞り出すような声でそう呟く。エメリの質問はそれほど予想外だったようだ。膝を立ててベッドにもたれるようにして座ると、エメリをじっと見つめる。金色の虹彩は相変わらず底知れなくて、この人が魔族であることをエメリに思い知らせるようだ。ドギマギしていると、エメリの腕をぐい、と引っ張り、自身の腕の中に閉じ込めた。
「エメリのことは殺さないよ。殺そうと思ったこともない」
「なんで、」
「好きだからに決まってるでしょ」
「え……」
「それ以外に、理由なんてある?」
ていうか昨夜散々言ったじゃんか、と拗ねるような口調に顔が熱くなる。たしかに初夜の最中に好きだのなんだのと言われた気がするが、その場の勢いというか、盛り上がった末の戯言だと思っていたのだ。そもそも魔王が勇者に愛の告白をするだなんて、信じられるはずがない。怪訝そうな表情がわかりやすかったのだろう、ニグラスは困ったように笑う。
「めちゃくちゃ疑ってるね」
「だって……だって、初対面、だし。好きになられる理由がわかんない」
もしニグラスの言っていることが本当だとして、エメリのことが好きだから結婚して家族になると言い出し、温室と小屋をプレゼントしてくれたのだろうか。だとしても、エメリの夢が薬師であることを知っている理由にはならないけれど。困惑するエメリの手のひらを掴んで自分の頬に当てながら、ニグラスは口を開く。
「エメリは覚えてないけど、小さいときに会ったことがあるんだよ」
「……は? どこで?」
口をあんぐりと開ける。予想もしなかった返答に、開いた口が塞がらない。幼少期に魔王と会ったことがあるだなんて、一体いつどこで。全く思い出せないエメリにニグラスは、「うーん……」と少しだけ迷ったように考え込む。
「内緒」
「なんで!?」
「思い出せないことは、無理に思い出さないほうがいいよ」
そう言ってニグラスはエメリの手のひらに口付ける。そわり、と心臓のあたりが疼いた。エメリを見つめる金色の瞳はどうしてか後悔と悲壮に満ちていて、それ以上の追求をエメリに許さない。代わりに、別の気になっていたことを尋ねた。
「昔、会ったときに」
「うん?」
「本当は薬師になりたいって、私が言ったの?」
「うん、そうだよ」
「嘘だ……」
「嘘じゃないよ」
ムッとしたようなニグラス。ニグラスと会ったのがいつのことなのかわからないけれど、初対面の人に本当の夢を自分が話すとは思えない。けれど、自分が教えたのでなければ、ニグラスが知っていることに説明がつかない。思い出せない記憶の中で、エメリは相当ニグラスと仲良くなったのだろうか。
「よいしょ、っと」
「うわっ!?」
唐突な浮遊感。エメリを抱き上げたニグラスはそのままベッドに寝転ぶ。「なんで!?」と困惑するエメリに、「疲れたでしょ? ちょっと寝よっか」となんでもないように返すとエメリを抱き寄せた。昨日の行為を思い出してぎくりとしたのだけれど、体が強張ったのを察知したのだろう。「しないよ」と告げられ、安心してしまった。たった一度しかしていない行為に、エメリはまだ慣れていない。
「寝るまでいっぱいおしゃべりしよ」
「ま、まだ湯浴みもしてないし、着替えだって」
「全部起きてからでいいじゃん。リリとリムがなんとかしてくれるよ」
「人使いが荒い……」
「魔王だからね」
とってつけたかのような理由にぽかんと口を開けてしまう。魔王らしくないのに、魔王の特権を変なところで振り翳すらしい。ぼんやり見ているとニグラスの左手がエメリの左手を取る。愛おしそうに指輪をなぞっているのを眺めていると、視界いっぱいに顔が広がる。あ、と思う間もなく唇が触れ合っていた。
「しないって、言ったのに」
「しないよ。でもキスはしたい」
「なにそれ……」
横暴だ、と呆れたけれどそれ以上のことをしてくるわけでもないので容認した。エメリを抱きしめたまま、ニグラスはぽそぽそと尋ねてくる。好きな食べ物、王国のお気に入りの場所、休日はなにをして過ごすのが好きか。魔王と勇者が交わすとは思えない、なんでもない会話。こんなことを聞き出して何の意味があるのだろう。よくわからないけれど、不快ではなかった。
「エメリは、勇者になりたかった?」
なんでもないことを聞かれていたのに、急に核心を突くようなことを尋ねられる。少なからず動揺してしまい、答えがうまく出てこない。勇者として任命され、魔王討伐の使命を任された。そこに拒否権はなかった。「……私は、勇者の一族に生まれたの」と、口を開く。ニグラスは黙って耳を傾けている。それがなんだか、ありがたかった。
「だから、勇者になりたくないとか、向いてないとか、そういう問題じゃない。勇者にならないといけないの」
勇者になりたいと思ったことも、向いていると思ったことも一度もない。それでも、エメリは勇者にならないといけない。そういう家に生まれてしまったのだから。王国に平和をもたらすことが、エメリのやるべきことなのだから。決して前向きではない答えをニグラスはどう思ったのだろう。「そっか」と短く返す言葉から、感情は伺えない。けれどそれでも、「やっぱり、エメリはすごいね」と前髪をかき分ける左手は暖かくて優しい。硬い指輪の感触に、自分の指輪を思わず撫でる。「もう大丈夫だよ」と何が大丈夫なのかわからない言葉に、途方もなく安心してしまう。額に落とされた唇の感触は柔らかくて、なんだか泣きそうになった。
――家族じゃない!
そう叫んだのは心からの本音だ。エメリはニグラスと結婚したけれど、家族や夫婦と呼べるものになったつもりはない。結婚しないと王国を滅ぼすだなんて馬鹿げた脅しをかけられたから従っているだけで、愛し合っているわけでも情があるわけでもない。そもそも人間と魔族で婚姻関係を結ぶことができるのかもわからないのだ。エメリが叫んだことは何一つ間違っていない。そのはずなのに。
「なんなの……」
胸の辺りがなんだかもやもやする。ニグラスが去り際に見せた顔がこびりついたように、頭から離れない。寂しくて悲しくて仕方がないのを隠すかのような、そんな笑い方。魔王である彼がそんな表情を浮かべるだなんて、思いもしなかった。エメリとニグラスの初対面はたった数日前のこと。ニグラスが初対面で結婚を申し込んでくる理由も、家族だなんだと形容する根拠も、全くわからない。
「はあー……」
ずるずると沈み込むようにしてその場にしゃがみ込む。数日前に黒い森に一人でやってきたときには何も感じなかったのに、今はなんだか肌寒いし心細い。ニグラスも双子の侍女も良くしてくれるから忘れていたけれど、ここは敵の本拠地。魔族の住む黒い森。日が差さないせいで相変わらず薄暗い。夢のような温室も、立派な調合小屋も。気になって仕方がないのに、入ってみる気力も湧かない。気が済んだら戻ってくるように言っていたけれど、一体どんな顔で会えばいいのだろう。
そうしてしゃがみ込んで悶々として、どれぐらい経ったのだろうか。不意に、ざくりと土を踏む音が聞こえた。もしかしてニグラスが戻ってきたのだろうか。心臓が気まずさにどくりと脈打つ。まだどんな顔で会えばいいのかわからないのに。そう思いながらノロノロ顔を上げて――心臓が止まったと思った。
グルルル……と歯を剥き出しにして唸るのは真っ黒い体毛に覆われた大きな犬、魔犬だ。魔王城に来るまでに襲いかかってきたのは、エメリでも十分に斬り伏せることができるぐらいに小ぶりだった。ところが目の前の魔犬は、確実に小ぶりだなんて形容することはできない。体の大きさはエメリと同じぐらいか、それ以上だろうか。こんな大きさの魔獣と戦ったことなど、ない。おまけに。
――剣がない……!
おまけに、魔王城にやってきた初日に剣は奪われた挙句に丸められてしまったのだ。今のエメリは丸腰で、武器といえば徒手空拳しかないのだけれど。こんな、鋭い牙も爪もある魔獣相手に素手でどうやって立ち向かえばいいのか。じりじりと距離を少しずつ詰める魔犬は、エメリの守護の力を警戒しているのだろうか。一気に襲いかかってくることはしない。この隙に立ち上がって全力で逃げればいい。頭では分かっている、のに。
「あ、あ……」
ぺたん、と尻餅をついてしまう。腰が抜けて、立てそうにない。怖い、無理だ。剣もないのに勝てるわけがないし、逃げ出したところで追いつかれる可能性の方が高い。逃げるにも一体どこへ、助けを求めるにも一体誰に。ここは魔王城で、敵の本拠地なのに。エメリを助けてくれる誰かがいるわけなんてないのに。
――怖い。
ニグラスを前にしたときとはまた別の種類の恐怖。その重みを煩わしいとすら思っていたのに、剣のない自分がこうも弱いだなんて。あまりの情けなさに、鼻の奥がツンとする。心臓がうるさくて、うまく息が吸えない。ずり、と無意識に後ずさったエメリを見て、目の前の獲物が大したことないと悟ったのだろう。魔犬が地面を蹴るのがやけにスローモーションに見えた。
「……っ!」
死ぬ、痛い思いをしてここで死ぬんだ、と腕で自分を守るようにして目を瞑ったけれど、痛みは一向にやってこない。代わりに、バシンっと何かを弾くような大きな音と、次いでドシンッと衝突したような衝撃音、それからキャウンッと犬のような鳴き声が続け様に聞こえる。
「エメリ、大丈夫?」
ここ数日ですっかり聞き慣れてしまった声に、恐る恐る目を開けた。しゃがみ込んだニグラスが、エメリの顔を心配そうに覗き込んでいる。背後では触手が蠢いていて、衝突音が聞こえた方を見ると魔犬が伸びているのが見えた。どうやら、触手の一撃で魔犬を伸したらしい。魔王らしくない、と散々思っていたのだけれど。やはり彼は魔王らしい。
「ごめんね、エメリから離れちゃだめだった。怪我してない?」
問いかけに頷くと、「よかった」と安心したように呟いて、ニグラスはエメリを抱え上げる。大した力も込めず、軽々と抱き上げられたことに驚く間もない。指をパチンと鳴らす音が聞こえたかと思うと、瞬きの間に景色が変わっていた。慣れない魔王城の中で数少ない見慣れた場所、寝室だ。ニグラスはエメリを抱えたままベッドに腰掛ける。膝に乗せたエメリを抱きしめながら、「本当にごめん」と繰り返した。
「な、んで、謝るの」
「僕がエメリを置いてったせいで、エメリが怪我するところだった」
エメリの背中を撫でながら謝罪を繰り返すニグラス。背中に触れる手のひらは暖かくて、徐々に落ち着きを取り戻す。寝室は黒い森とは違って肌寒くないし、心細くもない。安心を覚えているのだろうか、よりにもよって魔王の腕の中で。
――なにそれ。
うるさい心臓とうまく吸えない息がどうにかなったかと思えば、急に視界がぼやけた。目の奥が熱くて、喉の奥が焼け付くように痛い。ぐず、と鼻を鳴らしたせいでエメリの異変に気付いたのだろう。ニグラスが体を離し、エメリを見てギョッとする。
「ど、どうしたの? やっぱりどっか怪我した? 怖かった?」
「……る、さい」
「え?」
「うるさいっ……!」
ジタバタと暴れてもがいて、どうにかニグラスの膝の上から退く。が、変な体勢で飛び降りてしまったせいか、着地には盛大に失敗してしまった。ベシャリとニグラスの足元に崩れ落ちるエメリを見て、ニグラスは慌ててしゃがみ込む。その仕草がやけに腹立たしかった。
「エメリ……」
「さ、触らないでっ」
そう叫ぶと同時に、瞳に溜まっていた海がとうとう決壊する。ぼろ、と涙がこぼれ落ちるのを見られたくなくて、丸くなって蹲った。ミノムシみたいで、みっともない体勢。とても、勇者が魔王の前で取る体勢には思えない。剣があっても魔王は討伐できなくて、剣がなかったら魔獣相手に腰を抜かす。エメリは勇者なのに。やりたくなくても、向いてなくても、勇者としての責務を果たさなければならないのに。王国の平和のために、戦わないといけないのに。何一つ成し遂げられず、魔王に命を助けてもらい、挙げ句の果てには慰められる始末。エメリの一体どこが「勇者」と言えるのだろう。
「エメリ、泣かないで」
おろおろ、という形容詞がぴったりな声音でニグラスは声をかける。背中に何かが触れそうな感触があったが、寸前で引っ込められた。エメリが、「触らないで」といったのを律儀に聞いているのかもしれない。根拠のわからない優しさが、エメリを一層惨めにした。「な、んで……」と思わず疑問がこぼれる。のろのろと起き上がって床にへたり込むと、「うん?」と聞き返すニグラスも同じように床にしゃがみ込んでいるのが見えた。ぐず、と鼻を啜りながらエメリは口を開く。
「なんで、私のこと、殺さないの?」
「えっ」
ギョッとしたように目を見開くニグラス。そんなことを聞かれるだなんて思いもしなかった、とでも言いたげな顔だ。
「さっき、怖くて動けなかった。剣は取られて、丸腰だと何にもできなくて……勇者らしいこと何にもできなくて、人質の価値すらない、のに」
どうして殺さないの、と責め立てるように尋ねる。殺されたいわけではないし、できるならば生きていたい。けれど、エメリは勇者であり魔王の敵なのだ。守護の力を持つエメリがこうも弱いとわかった今、エメリを殺して王国に攻め入ることは赤子の首を捻るかのように簡単だろう。そうしない理由がわからなかった。ニグラスは目を見開いたままエメリの言葉を聞き、やがて俯いて息を吐き出した。
「なんで、そんなこと言うかなあ……」
絞り出すような声でそう呟く。エメリの質問はそれほど予想外だったようだ。膝を立ててベッドにもたれるようにして座ると、エメリをじっと見つめる。金色の虹彩は相変わらず底知れなくて、この人が魔族であることをエメリに思い知らせるようだ。ドギマギしていると、エメリの腕をぐい、と引っ張り、自身の腕の中に閉じ込めた。
「エメリのことは殺さないよ。殺そうと思ったこともない」
「なんで、」
「好きだからに決まってるでしょ」
「え……」
「それ以外に、理由なんてある?」
ていうか昨夜散々言ったじゃんか、と拗ねるような口調に顔が熱くなる。たしかに初夜の最中に好きだのなんだのと言われた気がするが、その場の勢いというか、盛り上がった末の戯言だと思っていたのだ。そもそも魔王が勇者に愛の告白をするだなんて、信じられるはずがない。怪訝そうな表情がわかりやすかったのだろう、ニグラスは困ったように笑う。
「めちゃくちゃ疑ってるね」
「だって……だって、初対面、だし。好きになられる理由がわかんない」
もしニグラスの言っていることが本当だとして、エメリのことが好きだから結婚して家族になると言い出し、温室と小屋をプレゼントしてくれたのだろうか。だとしても、エメリの夢が薬師であることを知っている理由にはならないけれど。困惑するエメリの手のひらを掴んで自分の頬に当てながら、ニグラスは口を開く。
「エメリは覚えてないけど、小さいときに会ったことがあるんだよ」
「……は? どこで?」
口をあんぐりと開ける。予想もしなかった返答に、開いた口が塞がらない。幼少期に魔王と会ったことがあるだなんて、一体いつどこで。全く思い出せないエメリにニグラスは、「うーん……」と少しだけ迷ったように考え込む。
「内緒」
「なんで!?」
「思い出せないことは、無理に思い出さないほうがいいよ」
そう言ってニグラスはエメリの手のひらに口付ける。そわり、と心臓のあたりが疼いた。エメリを見つめる金色の瞳はどうしてか後悔と悲壮に満ちていて、それ以上の追求をエメリに許さない。代わりに、別の気になっていたことを尋ねた。
「昔、会ったときに」
「うん?」
「本当は薬師になりたいって、私が言ったの?」
「うん、そうだよ」
「嘘だ……」
「嘘じゃないよ」
ムッとしたようなニグラス。ニグラスと会ったのがいつのことなのかわからないけれど、初対面の人に本当の夢を自分が話すとは思えない。けれど、自分が教えたのでなければ、ニグラスが知っていることに説明がつかない。思い出せない記憶の中で、エメリは相当ニグラスと仲良くなったのだろうか。
「よいしょ、っと」
「うわっ!?」
唐突な浮遊感。エメリを抱き上げたニグラスはそのままベッドに寝転ぶ。「なんで!?」と困惑するエメリに、「疲れたでしょ? ちょっと寝よっか」となんでもないように返すとエメリを抱き寄せた。昨日の行為を思い出してぎくりとしたのだけれど、体が強張ったのを察知したのだろう。「しないよ」と告げられ、安心してしまった。たった一度しかしていない行為に、エメリはまだ慣れていない。
「寝るまでいっぱいおしゃべりしよ」
「ま、まだ湯浴みもしてないし、着替えだって」
「全部起きてからでいいじゃん。リリとリムがなんとかしてくれるよ」
「人使いが荒い……」
「魔王だからね」
とってつけたかのような理由にぽかんと口を開けてしまう。魔王らしくないのに、魔王の特権を変なところで振り翳すらしい。ぼんやり見ているとニグラスの左手がエメリの左手を取る。愛おしそうに指輪をなぞっているのを眺めていると、視界いっぱいに顔が広がる。あ、と思う間もなく唇が触れ合っていた。
「しないって、言ったのに」
「しないよ。でもキスはしたい」
「なにそれ……」
横暴だ、と呆れたけれどそれ以上のことをしてくるわけでもないので容認した。エメリを抱きしめたまま、ニグラスはぽそぽそと尋ねてくる。好きな食べ物、王国のお気に入りの場所、休日はなにをして過ごすのが好きか。魔王と勇者が交わすとは思えない、なんでもない会話。こんなことを聞き出して何の意味があるのだろう。よくわからないけれど、不快ではなかった。
「エメリは、勇者になりたかった?」
なんでもないことを聞かれていたのに、急に核心を突くようなことを尋ねられる。少なからず動揺してしまい、答えがうまく出てこない。勇者として任命され、魔王討伐の使命を任された。そこに拒否権はなかった。「……私は、勇者の一族に生まれたの」と、口を開く。ニグラスは黙って耳を傾けている。それがなんだか、ありがたかった。
「だから、勇者になりたくないとか、向いてないとか、そういう問題じゃない。勇者にならないといけないの」
勇者になりたいと思ったことも、向いていると思ったことも一度もない。それでも、エメリは勇者にならないといけない。そういう家に生まれてしまったのだから。王国に平和をもたらすことが、エメリのやるべきことなのだから。決して前向きではない答えをニグラスはどう思ったのだろう。「そっか」と短く返す言葉から、感情は伺えない。けれどそれでも、「やっぱり、エメリはすごいね」と前髪をかき分ける左手は暖かくて優しい。硬い指輪の感触に、自分の指輪を思わず撫でる。「もう大丈夫だよ」と何が大丈夫なのかわからない言葉に、途方もなく安心してしまう。額に落とされた唇の感触は柔らかくて、なんだか泣きそうになった。