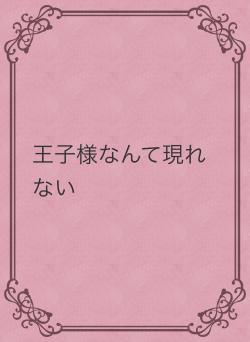唇に何か柔らかいものが触れている気がする。昨日散々触れていた気のする感触。
「おはよう、エメリ。よく眠れた?」
重たい瞼をゆっくり開けると、触れ合いそうなほど近くにニグラスの顔があった。
「わっ……」
驚いて一気に頭が覚醒した。思わず仰け反るエメリとは対照的に、ニグラスはニコニコと嬉しそうにしている。一体いつから起きていたのだろう。魔王の隣で呑気に寝こける勇者の寝顔を、この人はいつから見ていたのだろうか。
「体、大丈夫?」
「あ、うん……」
昨夜、最終的に気を失うようにして眠りについたせいだろうか、気だるさの残る体をゆっくりと起こす。背中に手を添えて手伝ってくれるニグラスは、びっくりするほど甲斐甲斐しい。とても魔王には見えない。
「朝ごはん食べようと思うんだけど、お腹空いてる?」
「ちょっとだけ」
「わかったー」
そう言うとニグラスは指をパチンと鳴らす。どこからともなく軽食の乗ったワゴンが現れた。ワゴンにはサンドイッチ、紅茶、フルーツ、スープなど実家でもよく見たような食事が乗っている。魔法だ、とすぐにわかったけれど、王国で見るような魔法とはまるで違う。詠唱も媒介もない、指を鳴らすだけで魔法が使えるだなんて。確かに書物にはそう書いてあったけれど、直面すると驚きを禁じ得ない。あんぐりと口を開けているエメリに、ニグラスは水差しから水を注いで手渡す。ありがたく水を飲みながら考えた末に出て来た質問は、最初に考えていたものとは違う最初に考えていたのとは違うものだった。
「魔族も、こういう食事をとるの?」
「うん。こういうのを食べるやつもいるし、食べないやつもいる」
「食べないやつは何を食べるの?」
「人間の精気」
「え」
絶句。思わず顔を引き攣らせるエメリを見て失言だと思ったのだろう。「僕は違うよ!?」と慌てて言い訳し始めた。
「サキュバスとかインキュバスは人間の精気を食べてるけど、僕は違う。普通にエメリと同じご飯を食べるよ」
「そうなんだ」
魔族のことは家にある文献でしか知らない。書物にあるのは角が生えて、大きな牙と鋭い爪のある、おどろおどろしい姿。それから、詠唱も媒介もなしに魔法が使える。目の前の彼には角と魔法以外当てはまらない。まじまじ見つめていると、「朝からそんなに見つめられたら照れちゃうよ」とニマニマ笑われたので慌てて、「み、見てない」と否定したけれどどう考えても苦しい。けれどニグラスはそれ以上突っ込むことはなく、「食べよ〜」と促す。
勧められるがまま、サンドイッチを口に運ぶ。よっぽどお腹が空いていたのか、寝起きだと言うことも忘れて夢中で咀嚼してしまった。ほのかに湯気のたつ紅茶を飲むと、胃の辺りが落ち着く気がする。実家にいたときに食べていたものと変わらない美味しさ。ここが魔王城だということを忘れてしまいそうだ。もそもそ食べていると不意に、「昨日はごめんね」とニグラスが申し訳なさそうに告げた。何に対する謝罪だろう、と首を傾げるエメリにニグラスは困ったように笑う。
「人間は弱いから優しくしなきゃって思ったのに、僕も初めてだからさ。興奮して全然手加減できなかった」
「ぶっ、えっ、あっ、初めてだったの!?」
「そうだよ。なんで?」
「ま、魔王ってこう、モテるのかなって……」
「ええー? 女の子が寄ってきたことなんてないよ」
「そうなんだ……」
魔族の美醜の基準はわからないけれど、エメリから見てニグラスの顔は整っていると思う。羊の角や金色の渦巻く虹彩が魔族であることを知らしめるけれど、それを抜きにすれば社交界で女の子からの視線を十分に集めるだろう。おまけに魔力が強くて、魔族の頂点である魔王なのだ。さぞや魔王城でも女の子に囲まれた生活を送っているのだろう、と勝手に思い込んでいたのだけれど。別にそんなことはなかったらしい。魔族と人間とでは重視する魅力が違うのかもしれない。
「今日は午後からお城を案内しようと思うんだけど、どう?」
「あ、うん、お願いします」
もう食べ終わったらしいニグラスがエメリにそう提案する。仮にも人質である勇者に城の構造を教えていいのだろうか、と思ったけれど。武器もない丸腰の勇者一人ぐらいどうにでもなるのだろう。紅茶を飲みながら、万が一のために逃げ道でも探そうと思った。
*
「あ、エメリ様だ」
「ニグラスもいる。おはよお」
「おはよ〜」
「お、おはようございます」
部屋を出て廊下を歩いていると、遭遇したのは双子の侍女、リリとリム。相変わらず砕けた態度だけれど、結婚式のときも初夜のときも舌を巻く程の手際の良さでエメリを磨き上げてくれた。「朝ごはん美味しかった?」「よく眠れた?」と聞いてくれる二人にお礼とよく眠れたことを告げる。
「ていうかエメリ様大丈夫?」
「そこの浮かれ魔王に抱き潰されなかった?」
「ぶっ」
朝からとんでもないことを尋ねられている。あまりに明け透けな物言いに吹き出してしまったけれど、浮かれ魔王は慣れているらしい。「ちょっとやめてよ〜」と軽くいなしている。
「でもちょっとよろよろしてるじゃん」
「それをいいことに密着して歩いてるじゃん」
「エメリは僕のお嫁さんだからね。夫として当然」
「うわ浮かれてる」
「これだから浮かれ魔王は」
エメリを置いて交わされる会話は気安い。とても魔王とその部下が話しているようには見えないけれど、昔からの付き合いがあるのだろうか。ぼんやり見ていると、「あ、エメリ様が固まってる」「奥さんを放って他の女と話すなんて分かってないなあ」と侍女が魔王を非難し始める。不敬罪にはならないのだろうか、と呑気なことを思った。
「きみらが話しかけてきたんでしょうが。ごめん、エメリ」
「あ、いや……えっと、仲良いんだね」
「嫉妬した?」
「いや全然」
「なんだあ」
しょんぼりと肩を落とすニグラス。リリとリムは、「幼馴染? 腐れ縁?」「そんな感じだよねえ」と緩やかな会話を交わしている。
「魔王はうちらの中で一番偉い人だし、従わなきゃいけないけど」
「でも上下関係? みたいなのはないよね」
「へえ……」
従わないといけないのならそれは上下関係では、と思ったけれど。人間にはわからない価値観かもしれないので黙っておいた。「ニグラスのことかっこいいと思ったことないよ」「うん、ないない。だから安心してね」となかなかに酷い言い草なのも、魔族ならではなのかもしれない。
「酷いなあ。もっと僕がかっこいいって話してよ」
「なんで?」
「何のために?」
「エメリが嫉妬してくれるかもしれないじゃん。私の旦那様なのにって」
「うわ」
「うーわ」
心底引いたような声を上げる二人は抱き合ってドン引きしている。「女の子に嫉妬させて不安にさせるような男はゴブリン以下だからね」「その考え悔い改めた方がいいよ」となか中に物言いは厳しい。魔族なのに悔い改めるとか言う概念あるんだ、と思ったけれど口を挟むことはできず呆気に取られる。これは流石に不敬罪では、と思ったのだけれど、「うっ、ごめんなさい」と素直に謝っているあたり問題ないらしい。
「じゃあうちら仕事があるから」
「エメリ様またね」
「あ、はい、また」
言いたいことだけ言うと双子は颯爽と去っていった。嵐のようだったな、と去り行く背中を見て思う。あんなによく喋る人とは王国で関わったことがなかったので、圧倒されてしまった。人間の女の子もエメリが知らないだけでみんなあれだけポンポンと言葉が出てくるものなのだろうか。そんなことを考えていると、「……ごめん、エメリ」と申し訳なさそうな声が聞こえる。朝に聞いたものよりも深刻そうだ。
「えっ、なんで?」
「嫉妬してほしいとか思って無神経なことを……」
「き、気にしないで」
わかりやすくしおしおと萎れるニグラス。嫉妬なんて感情は一つも覚えなかったし、双子とニグラスが仲良さそうに話しているのを見ても心にさざなみひとつ立たなかった。しょんぼりされる方が逆に罪悪感を覚える。
「本当になんとも思ってないから、気にしないで」
「それはそれで……」
ニグラスはほんの少し悲しそうにしたけれど、「まあいいや」と息を吐く。眉を下げたニグラスに、一昨日見たような敵わなさは覚えない。結婚式を挙げてからずっと、この人が魔王であることを疑うことばかりだ。「行こっか」と手を引くニグラスは、初夜のせいで足元が覚束ないエメリに歩幅を合わせてくれる。こういうところも、魔王らしくなくて優しいと思う。エメリの右手と繋がる左手には揃いの指輪が嵌められているのが感触でわかって、言い様のないむず痒さに襲われた。
*
手を引くニグラスは、城の外に出ても足を止めない。城を案内すると言っていたけれど、まずは庭から案内でもするつもりなのだろうか。というか、人質なのに勝手に外に出てもいいのだろうか。すれ違う魔族は魔王であるニグラスと、その結婚相手であるエメリにも頭を下げる。その視線に侮蔑も警戒もなく、本当にただ「魔王の嫁」として見られているようだ。結婚式でも思った通り、敵意を向け続けられるよりはずっとマシだけれど、「勇者」としてのエメリは微塵も警戒されていないのだと思い知らされるようだった。
「着いたよ」
いつの間にか目的地についていたらしい。足を止めたニグラスに促されて顔を上げ、心臓が跳ねた。
「! ここって……」
目の前にあるのは立派な温室。王城で見たことのあるものと、大きさは遜色ないだろう。ガラス張りの建物は、日の差さない黒い森にあってもキラキラと輝いているようだ。温室の隣にはこぢんまりとしたログハウスがあり、それが調合に使える小屋だということは想像に難くない。
ソワソワと足元から興奮が走り出す。魔王城に来てから初めて、浮き足立っていると言ってもいい。物心つく前から勇者になることが義務付けられていたエメリだけれど、この年になるまでついぞ将来の夢を捨てられなかった。
エメリの夢は、薬師になることだ。勇者になることではない。薬師になって、素敵な人と結婚して、小さな家で穏やかに暮らす。そんなことを、物心ついてからずっと夢見ていた。
いつか誰かが、もう勇者になんてならなくてもいいよ、普通の女の子として生きていいよと言ってくれないだろうか。そんなあり得ないもしものために、稽古の合間を縫って庭の花壇をいじり、草花を育て、薬草を摘み、書物を見ながら薬を調合していた。魔王が誕生し、正式に勇者として任命されてしまった今、諦めなければならないと思っていたのだけれど。
「ここ、エメリの好きに使っていいよ」
「えっ!? ほ、ほんと!?」
「うん。エメリのために作らせたし。僕とエメリ以外は入れないから」
嬉しい? とニコニコと尋ねるニグラス。嬉しいに決まっている、と即答で頷きかけたけれど寸前でエメリの中の何かがストップをかける。
――どうして私が薬師になりたがってるって知ってるの?
エメリとニグラスは数日前に初めて会ったばかりだ。エメリが薬草を育てたり薬を調合したりしていることを、家の人間は知っているけれど、ニグラスには教えていない。ましてや、密かに将来の夢としていることだなんて今まで誰にも言ったことはないのだ。尚更ニグラスが知っているはずがない。
だというのにこんなに立派な温室と調合小屋をエメリのためと言って与えてくれるだなんて。嬉しいよりも、どうしてという疑問と不審感が募る。王国への人質に対して、魔王がここまでする必要はあるのだろうか。一体何の目的があって、エメリにとって都合の良すぎることばかり告げるのだろうか。
「黒い森に生えてる草は好きに摘んでいいし、育てた薬草は隣の小屋で調合してね。それから――」
「待って!」
「うん?」
「な、なんで?」
「なんでって?」
首を傾げるニグラスは、エメリが怪訝そうにしている理由が思い当たらないらしい。ますます真意が読めない。
「どうして、人質にここまでするの?」
「だから人質じゃなくて、」
「家族じゃない!」
遮るようにして叫び、繋がれていた手を振り払う。理由のない優しさが怖くて、心臓のあたりがズキズキと痛い。左手の指輪に締め付けられているようだ。エメリは勇者で、ニグラスは魔王。エメリは魔王を倒すべく、幼少期から勇者として鍛えられた。友達もできず、好きなこともできず、夢なんか見れるはずもなく。来る日も来る日も父親に厳しい稽古をつけられた。全ては魔王を倒して王国に平和をもたらす、その本願を果たすためだけに。
だというのに。魔王城についてからというもの、何もかもが想定外だ。討伐には失敗して、結婚しようだなんて言われて、あっという間に結婚式から初夜まで済ませ、挙げ句の果てには温室までプレゼントされる。エメリは魔王を討伐に来たのであって、嫁入りしに来たわけではない。優しくされるために来たんじゃないのに、こんなに夢みたいなことが続いていいはずがないのだ。
「ごめんね、エメリ」
全身で拒絶を表すエメリの耳に届いたのは、本日三回目の謝罪の言葉。せっかく温室と小屋をプレゼントしてくれたのに、お礼も言わないで怒り出すエメリにがっかりもしない。心臓のズキズキとした痛みが増していくようだ。何も言えないエメリに、ニグラスは言葉を続ける。
「エメリが会いに来てくれたのが嬉しくて、浮かれてた。エメリは僕を倒しに来ただけなのにね」
「……」
「先にお城に戻ってるから、気が済んだら戻ってきてね」
そう言って笑うニグラスの顔はやっぱり魔王らしくない。魔王はきっと、そんなふうに傷ついたように笑うことはしない。踵を返して城へと戻っていくニグラスにエメリは何も言えない。足は鉛のように重たくて、追いかけることもできない。去っていくニグラスの背中はあまりに無防備だ。
けれど、たとえ今、手元に剣があったとしても、斬りかかることはできなかっただろう。罪悪感から目を逸らすように、エメリは俯いて靴先を見つめた。
「おはよう、エメリ。よく眠れた?」
重たい瞼をゆっくり開けると、触れ合いそうなほど近くにニグラスの顔があった。
「わっ……」
驚いて一気に頭が覚醒した。思わず仰け反るエメリとは対照的に、ニグラスはニコニコと嬉しそうにしている。一体いつから起きていたのだろう。魔王の隣で呑気に寝こける勇者の寝顔を、この人はいつから見ていたのだろうか。
「体、大丈夫?」
「あ、うん……」
昨夜、最終的に気を失うようにして眠りについたせいだろうか、気だるさの残る体をゆっくりと起こす。背中に手を添えて手伝ってくれるニグラスは、びっくりするほど甲斐甲斐しい。とても魔王には見えない。
「朝ごはん食べようと思うんだけど、お腹空いてる?」
「ちょっとだけ」
「わかったー」
そう言うとニグラスは指をパチンと鳴らす。どこからともなく軽食の乗ったワゴンが現れた。ワゴンにはサンドイッチ、紅茶、フルーツ、スープなど実家でもよく見たような食事が乗っている。魔法だ、とすぐにわかったけれど、王国で見るような魔法とはまるで違う。詠唱も媒介もない、指を鳴らすだけで魔法が使えるだなんて。確かに書物にはそう書いてあったけれど、直面すると驚きを禁じ得ない。あんぐりと口を開けているエメリに、ニグラスは水差しから水を注いで手渡す。ありがたく水を飲みながら考えた末に出て来た質問は、最初に考えていたものとは違う最初に考えていたのとは違うものだった。
「魔族も、こういう食事をとるの?」
「うん。こういうのを食べるやつもいるし、食べないやつもいる」
「食べないやつは何を食べるの?」
「人間の精気」
「え」
絶句。思わず顔を引き攣らせるエメリを見て失言だと思ったのだろう。「僕は違うよ!?」と慌てて言い訳し始めた。
「サキュバスとかインキュバスは人間の精気を食べてるけど、僕は違う。普通にエメリと同じご飯を食べるよ」
「そうなんだ」
魔族のことは家にある文献でしか知らない。書物にあるのは角が生えて、大きな牙と鋭い爪のある、おどろおどろしい姿。それから、詠唱も媒介もなしに魔法が使える。目の前の彼には角と魔法以外当てはまらない。まじまじ見つめていると、「朝からそんなに見つめられたら照れちゃうよ」とニマニマ笑われたので慌てて、「み、見てない」と否定したけれどどう考えても苦しい。けれどニグラスはそれ以上突っ込むことはなく、「食べよ〜」と促す。
勧められるがまま、サンドイッチを口に運ぶ。よっぽどお腹が空いていたのか、寝起きだと言うことも忘れて夢中で咀嚼してしまった。ほのかに湯気のたつ紅茶を飲むと、胃の辺りが落ち着く気がする。実家にいたときに食べていたものと変わらない美味しさ。ここが魔王城だということを忘れてしまいそうだ。もそもそ食べていると不意に、「昨日はごめんね」とニグラスが申し訳なさそうに告げた。何に対する謝罪だろう、と首を傾げるエメリにニグラスは困ったように笑う。
「人間は弱いから優しくしなきゃって思ったのに、僕も初めてだからさ。興奮して全然手加減できなかった」
「ぶっ、えっ、あっ、初めてだったの!?」
「そうだよ。なんで?」
「ま、魔王ってこう、モテるのかなって……」
「ええー? 女の子が寄ってきたことなんてないよ」
「そうなんだ……」
魔族の美醜の基準はわからないけれど、エメリから見てニグラスの顔は整っていると思う。羊の角や金色の渦巻く虹彩が魔族であることを知らしめるけれど、それを抜きにすれば社交界で女の子からの視線を十分に集めるだろう。おまけに魔力が強くて、魔族の頂点である魔王なのだ。さぞや魔王城でも女の子に囲まれた生活を送っているのだろう、と勝手に思い込んでいたのだけれど。別にそんなことはなかったらしい。魔族と人間とでは重視する魅力が違うのかもしれない。
「今日は午後からお城を案内しようと思うんだけど、どう?」
「あ、うん、お願いします」
もう食べ終わったらしいニグラスがエメリにそう提案する。仮にも人質である勇者に城の構造を教えていいのだろうか、と思ったけれど。武器もない丸腰の勇者一人ぐらいどうにでもなるのだろう。紅茶を飲みながら、万が一のために逃げ道でも探そうと思った。
*
「あ、エメリ様だ」
「ニグラスもいる。おはよお」
「おはよ〜」
「お、おはようございます」
部屋を出て廊下を歩いていると、遭遇したのは双子の侍女、リリとリム。相変わらず砕けた態度だけれど、結婚式のときも初夜のときも舌を巻く程の手際の良さでエメリを磨き上げてくれた。「朝ごはん美味しかった?」「よく眠れた?」と聞いてくれる二人にお礼とよく眠れたことを告げる。
「ていうかエメリ様大丈夫?」
「そこの浮かれ魔王に抱き潰されなかった?」
「ぶっ」
朝からとんでもないことを尋ねられている。あまりに明け透けな物言いに吹き出してしまったけれど、浮かれ魔王は慣れているらしい。「ちょっとやめてよ〜」と軽くいなしている。
「でもちょっとよろよろしてるじゃん」
「それをいいことに密着して歩いてるじゃん」
「エメリは僕のお嫁さんだからね。夫として当然」
「うわ浮かれてる」
「これだから浮かれ魔王は」
エメリを置いて交わされる会話は気安い。とても魔王とその部下が話しているようには見えないけれど、昔からの付き合いがあるのだろうか。ぼんやり見ていると、「あ、エメリ様が固まってる」「奥さんを放って他の女と話すなんて分かってないなあ」と侍女が魔王を非難し始める。不敬罪にはならないのだろうか、と呑気なことを思った。
「きみらが話しかけてきたんでしょうが。ごめん、エメリ」
「あ、いや……えっと、仲良いんだね」
「嫉妬した?」
「いや全然」
「なんだあ」
しょんぼりと肩を落とすニグラス。リリとリムは、「幼馴染? 腐れ縁?」「そんな感じだよねえ」と緩やかな会話を交わしている。
「魔王はうちらの中で一番偉い人だし、従わなきゃいけないけど」
「でも上下関係? みたいなのはないよね」
「へえ……」
従わないといけないのならそれは上下関係では、と思ったけれど。人間にはわからない価値観かもしれないので黙っておいた。「ニグラスのことかっこいいと思ったことないよ」「うん、ないない。だから安心してね」となかなかに酷い言い草なのも、魔族ならではなのかもしれない。
「酷いなあ。もっと僕がかっこいいって話してよ」
「なんで?」
「何のために?」
「エメリが嫉妬してくれるかもしれないじゃん。私の旦那様なのにって」
「うわ」
「うーわ」
心底引いたような声を上げる二人は抱き合ってドン引きしている。「女の子に嫉妬させて不安にさせるような男はゴブリン以下だからね」「その考え悔い改めた方がいいよ」となか中に物言いは厳しい。魔族なのに悔い改めるとか言う概念あるんだ、と思ったけれど口を挟むことはできず呆気に取られる。これは流石に不敬罪では、と思ったのだけれど、「うっ、ごめんなさい」と素直に謝っているあたり問題ないらしい。
「じゃあうちら仕事があるから」
「エメリ様またね」
「あ、はい、また」
言いたいことだけ言うと双子は颯爽と去っていった。嵐のようだったな、と去り行く背中を見て思う。あんなによく喋る人とは王国で関わったことがなかったので、圧倒されてしまった。人間の女の子もエメリが知らないだけでみんなあれだけポンポンと言葉が出てくるものなのだろうか。そんなことを考えていると、「……ごめん、エメリ」と申し訳なさそうな声が聞こえる。朝に聞いたものよりも深刻そうだ。
「えっ、なんで?」
「嫉妬してほしいとか思って無神経なことを……」
「き、気にしないで」
わかりやすくしおしおと萎れるニグラス。嫉妬なんて感情は一つも覚えなかったし、双子とニグラスが仲良さそうに話しているのを見ても心にさざなみひとつ立たなかった。しょんぼりされる方が逆に罪悪感を覚える。
「本当になんとも思ってないから、気にしないで」
「それはそれで……」
ニグラスはほんの少し悲しそうにしたけれど、「まあいいや」と息を吐く。眉を下げたニグラスに、一昨日見たような敵わなさは覚えない。結婚式を挙げてからずっと、この人が魔王であることを疑うことばかりだ。「行こっか」と手を引くニグラスは、初夜のせいで足元が覚束ないエメリに歩幅を合わせてくれる。こういうところも、魔王らしくなくて優しいと思う。エメリの右手と繋がる左手には揃いの指輪が嵌められているのが感触でわかって、言い様のないむず痒さに襲われた。
*
手を引くニグラスは、城の外に出ても足を止めない。城を案内すると言っていたけれど、まずは庭から案内でもするつもりなのだろうか。というか、人質なのに勝手に外に出てもいいのだろうか。すれ違う魔族は魔王であるニグラスと、その結婚相手であるエメリにも頭を下げる。その視線に侮蔑も警戒もなく、本当にただ「魔王の嫁」として見られているようだ。結婚式でも思った通り、敵意を向け続けられるよりはずっとマシだけれど、「勇者」としてのエメリは微塵も警戒されていないのだと思い知らされるようだった。
「着いたよ」
いつの間にか目的地についていたらしい。足を止めたニグラスに促されて顔を上げ、心臓が跳ねた。
「! ここって……」
目の前にあるのは立派な温室。王城で見たことのあるものと、大きさは遜色ないだろう。ガラス張りの建物は、日の差さない黒い森にあってもキラキラと輝いているようだ。温室の隣にはこぢんまりとしたログハウスがあり、それが調合に使える小屋だということは想像に難くない。
ソワソワと足元から興奮が走り出す。魔王城に来てから初めて、浮き足立っていると言ってもいい。物心つく前から勇者になることが義務付けられていたエメリだけれど、この年になるまでついぞ将来の夢を捨てられなかった。
エメリの夢は、薬師になることだ。勇者になることではない。薬師になって、素敵な人と結婚して、小さな家で穏やかに暮らす。そんなことを、物心ついてからずっと夢見ていた。
いつか誰かが、もう勇者になんてならなくてもいいよ、普通の女の子として生きていいよと言ってくれないだろうか。そんなあり得ないもしものために、稽古の合間を縫って庭の花壇をいじり、草花を育て、薬草を摘み、書物を見ながら薬を調合していた。魔王が誕生し、正式に勇者として任命されてしまった今、諦めなければならないと思っていたのだけれど。
「ここ、エメリの好きに使っていいよ」
「えっ!? ほ、ほんと!?」
「うん。エメリのために作らせたし。僕とエメリ以外は入れないから」
嬉しい? とニコニコと尋ねるニグラス。嬉しいに決まっている、と即答で頷きかけたけれど寸前でエメリの中の何かがストップをかける。
――どうして私が薬師になりたがってるって知ってるの?
エメリとニグラスは数日前に初めて会ったばかりだ。エメリが薬草を育てたり薬を調合したりしていることを、家の人間は知っているけれど、ニグラスには教えていない。ましてや、密かに将来の夢としていることだなんて今まで誰にも言ったことはないのだ。尚更ニグラスが知っているはずがない。
だというのにこんなに立派な温室と調合小屋をエメリのためと言って与えてくれるだなんて。嬉しいよりも、どうしてという疑問と不審感が募る。王国への人質に対して、魔王がここまでする必要はあるのだろうか。一体何の目的があって、エメリにとって都合の良すぎることばかり告げるのだろうか。
「黒い森に生えてる草は好きに摘んでいいし、育てた薬草は隣の小屋で調合してね。それから――」
「待って!」
「うん?」
「な、なんで?」
「なんでって?」
首を傾げるニグラスは、エメリが怪訝そうにしている理由が思い当たらないらしい。ますます真意が読めない。
「どうして、人質にここまでするの?」
「だから人質じゃなくて、」
「家族じゃない!」
遮るようにして叫び、繋がれていた手を振り払う。理由のない優しさが怖くて、心臓のあたりがズキズキと痛い。左手の指輪に締め付けられているようだ。エメリは勇者で、ニグラスは魔王。エメリは魔王を倒すべく、幼少期から勇者として鍛えられた。友達もできず、好きなこともできず、夢なんか見れるはずもなく。来る日も来る日も父親に厳しい稽古をつけられた。全ては魔王を倒して王国に平和をもたらす、その本願を果たすためだけに。
だというのに。魔王城についてからというもの、何もかもが想定外だ。討伐には失敗して、結婚しようだなんて言われて、あっという間に結婚式から初夜まで済ませ、挙げ句の果てには温室までプレゼントされる。エメリは魔王を討伐に来たのであって、嫁入りしに来たわけではない。優しくされるために来たんじゃないのに、こんなに夢みたいなことが続いていいはずがないのだ。
「ごめんね、エメリ」
全身で拒絶を表すエメリの耳に届いたのは、本日三回目の謝罪の言葉。せっかく温室と小屋をプレゼントしてくれたのに、お礼も言わないで怒り出すエメリにがっかりもしない。心臓のズキズキとした痛みが増していくようだ。何も言えないエメリに、ニグラスは言葉を続ける。
「エメリが会いに来てくれたのが嬉しくて、浮かれてた。エメリは僕を倒しに来ただけなのにね」
「……」
「先にお城に戻ってるから、気が済んだら戻ってきてね」
そう言って笑うニグラスの顔はやっぱり魔王らしくない。魔王はきっと、そんなふうに傷ついたように笑うことはしない。踵を返して城へと戻っていくニグラスにエメリは何も言えない。足は鉛のように重たくて、追いかけることもできない。去っていくニグラスの背中はあまりに無防備だ。
けれど、たとえ今、手元に剣があったとしても、斬りかかることはできなかっただろう。罪悪感から目を逸らすように、エメリは俯いて靴先を見つめた。