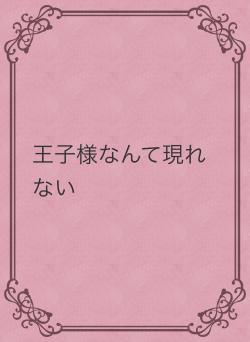――魔王討伐に来てウェディングドレスを着ることってあるんだ。
慌ただしく着飾られながら、エメリは現実から逃避するように思いを馳せる。魔王討伐のために単身黒い森に乗り込んで早三日。今日は結婚式だ。
*
「僕は魔王ニグラス。結婚しよう」
「……は?」
沈黙が二人を包んだ。あんぐりと口を開け、信じられないものを見るような目で魔王を見つめるエメリとは対照的に、魔王は何故か頬を染めている。まるで、好きな人に告白して照れているかのように。
――結婚? 誰と誰が?
唐突な提案を脳内で反芻し、理解した瞬間――力の限りもがいて腕の中から抜け出し、後ろに飛び退く。今度はよろけなかった。剣が取り上げられてしまったのなら、と武術の構えを取る。無駄な抵抗だとは思ったが、この体勢の方が声は出しやすい。
「無理!!」
「えー……」
即答かあ、と残念そうにする魔王。気の抜けるような言葉は、真意が掴めなくて油断ならない。そもそも、昔から父親に稽古をつけられてきたのだ。対峙すれば相手の強さはなんとなくわかるのだが、目の前の男に敵うはずがないのはなんとなくどころではなくわかる。今までの魔王もこんなに強かったのだろうか。ふと魔王の背後を見ると相変わらず触手は蠢いていて、そのうちの一本がエメリの剣をくるくると丸めているところだった。
「わ、私の剣……!」
「あ、ごめん。さすがに勇者の剣は危ないから没収ね」
没収なら丸める必要はなかったのでは、と思ったけれどそうではない。そもそも鉄鋼でできた剣を丸めるなんて、あの触手は一体なんなのか。ロールケーキのように丸くなってしまった剣を見ながら呆気に取られる。丸腰のエメリは、近寄る魔王を前に逃げ出すことすらできない。ここで死ぬんだ、と悲壮な覚悟を決めた。
「そんな顔しないでよ。食べないからさ」
けれど、予想に反して魔王はエメリを殺そうとはしない。眉を下げてエメリの手を取ると、ふにふにと優しく握った。年頃の女の子の柔らかくてスベスベした手からは程遠い、マメだらけでガサついた手。愛おしそうに触れる手つきは、とても魔王のものとは思えない。なにが由来かもわからない心臓の音を聞きながら、「な、何が目的?」と一生懸命に絞り出す。情けないほどに震えていて、虚勢を張っていることはバレバレだろう。けれど魔王はそれには触れず、きょとんと首を傾げてエメリを見た。
「目的って、エメリと家族になりたいから以外にある?」
「か、家族!?」
予想もしていなかった答えにエメリは目を剥く。まさか魔王の口から、「家族になりたい」だなんてささやかな願いを聞くとは夢にも思わない。ますます魔王の目的がわからなくなり、「そういうのいいから! 本当のことを言って!」と叫ぶ。魔王城に来てからなにも想定通りにいっていないせいで、ただでさえ混乱しているのだ。これ以上混乱させないでほしい、という心からの叫びだったのだけれど、しかし魔王は心外だと言わんばかりに顔を顰めた。
「本当のことなんだけど」
「そんなわけないでしょ! 魔族が人間と家族!? 絶対ありえない!」
未だかつて、魔族と婚姻関係を結んだ人間は王国にいない。王国に住む人間にとって魔族は忌むべき存在で、魔王はそれの最たるものだ。家族になる対象では決してない。魔王討伐に行ったはずの勇者が魔王と結婚して帰ってくるだなんて、エメリの家にある文献のどれにも記されていなかった。至極当たり前の指摘をしたつもりだったのだけれど、魔王はどうしてか傷ついたように顔を歪める。意外なリアクションに何か言う前に、口を開いた。
「どうしても信じてくれない?」
「信じてくれない、って……そもそも信じる根拠も何もないし。なんていうか、王国に対する人質とか言われたほうがまだ信じられるっていうか」
「じゃあそれで」
「は?」
じゃあそれで、とは。軽い調子で返された言葉に困惑し通しのエメリをよそに、魔王はなんでもないように言葉を続ける。
「エメリがお嫁さんになって、僕と家族になってくれるなら王国には手を出さないであげる」
「はあ?」
「エメリがお嫁さんになってくれないなら、王国は滅ぼす」
「はあ!?」
「ね、これならいい? 僕のこと信じてくれる?」
「し、信じるって、何それ脅迫?!」
無邪気な笑顔でとんでもないことを提案する魔王は、エメリがどれだけ引っ込めようとしても手を離さない。どうやら、今ここで魔王の嫁になるかどうかが王国存亡の分水嶺となるらしい。なんの利益があってエメリと家族になりたいだなんて世迷言をいっているのだろうか。わからないけれど、ここで見逃してもらったとしても、魔王を倒せずにのこのこと帰るエメリに居場所はきっとない。それならば魔族の本拠地で人質として生きる方がマシなのではないか。
「僕と結婚してくれるなら、エメリの願いはなんでも叶えてあげる」
「……」
悪魔が取引を持ちかけるような甘い囁き。難しい顔で考え込むエメリとは対照的に、魔王はいつの間にかご機嫌そうにニコニコと笑っている。先ほどの傷ついたような顔は一体なんだったのか。何一つとしてエメリの理解の範疇にはないけれど、選ぶべき道が一つしかないということだけは理解できた。
「……わかった。あなたと結婚する」
「ほんと?」
「その代わり、王国には手を出さないで」
「もちろん」
飛び跳ねる勢いで魔王はエメリの両手を握りしめて喜ぶ。魔族は鋭い牙や角があるのが定説だと本で学んだのだけれど。顔をまじまじ見てみると、牙らしきものも生えていないし耳も丸い。羽根はマントに隠れているのか、それとも映えていないのだろうか。よくわからないけれど、頭から生えている角と虹彩の渦巻いた瞳、それから背後で蠢く触手以外はほとんど人間と変わりないように見える。エメリが観察していることに気づいているのかいないのか、魔王は嬉しそうに口を開いた。
「よろしくね、エメリ。結婚式は明後日だから」
「は?」
*
それからの二日間は怒涛だった。慌ただしすぎて、現状を伝える手紙すら王国に送れなかったほどに。
「エメリ様、綺麗〜」
「可愛い〜」
「あ、ありがとう」
エメリを褒めるのは、魔王との結婚が決まってすぐに紹介された双子の侍女。背中から蝙蝠のような羽が生えている二人はお仕着せ姿がよく似合うが、当然魔族である。「リリとリムだよ。身の回りのことは二人にやってもらってね」と魔王に紹介されたときには、世話と称してどんな扱いを受けたものかと身構えたのだが。想像に反して二人はキャッキャと楽しそうに世話を焼いてくれた。
「結婚式とかいうの、魔王城でやるの初めて見る」
「ね、楽しみだよね」
「そうなんだ……」
どうやら魔族に結婚式という文化はないらしい。ドレスもベールも王国で見たものと変わりないように見えるけれど、どうやって用意したのだろうか。そう思っていると、「夜なべで準備した甲斐があったよね」「ね、似合ってるし」と言われたので、二人が作ってくれたのだと悟った。魔王城で働く侍女は、裁縫の能力も高いらしい。二人にお礼を告げると、「いいよお」「これが仕事だし」と返ってきた。
生まれてこの方、こんなに着飾らせてもらったのはデビュタントの時以来だ、と不意に思い出す。一応貴族令嬢だけれど、おおよそ貴族令嬢らしくない生活を送ってきたエメリには、着飾った記憶がほとんどない。物心がつく前から稽古漬けの毎日だったから。けれど、唯一デビュタントのときだけは父親も許してくれたので、侍女が張り切って着飾らせてくれた。今頃、家の人たちや王国の人たちはどうしているのだろう。王国に手は出さないと言ってくれたけれど、立ち込める暗雲も晴らしてくれただろうか。平和が戻っているといいのだけれど。
「エメリ、準備できた?」
控え室に夫となる人――魔王ニグラスがやってきた。何やら忙しくしていたらしい魔王とはこの二日間、食事のときにしか顔を合わせなかった。聞きたいことも言いたいこともたくさんあるのだけれど、式の後なら話せるのだろうか。そんなことを考えているエメリとは裏腹に、ニグラスは顔をぱあっと綻ばせて駆け寄ってくる。あまりにも眩しい笑顔に、この人が魔王であることが頭から吹き飛んでしまった。
「すっごく綺麗! こんな可愛い子が僕のお嫁さんになるの? 嬉しい!」
「え、あ、ありがとう……」
勢いに押され、思わずお礼を言ってしまう。今までの人生で着飾ることがなければ、可愛いと言われた記憶もほとんどないに等しい。討伐対象とはいえ、こんなにストレートに褒められて嬉しくならないわけがないのだ。背後で双子の侍女が、「浮かれ花婿だ」「浮かれ魔王だ」と呟いているのが聞こえる。顔が見えなくても、ニヤニヤしているのが丸わかりだ。
「ね、僕の格好はどう? 似合う?」
双子に揶揄うような視線を向けられていることにも気づかず、魔王はソワソワとエメリの反応を気にしている。この人は本当に魔王なのだろうか、と魔王城に来てから何度覚えたかわからない疑問を覚えた。
「えっと……」
言葉を探しながら魔王を上から下まで眺める。魔王の身を包むのは、見慣れた黒づくめの服とマントではなく白いタキシード。無造作な黒髪は後ろに撫で付けられていて、形のいい額が顕になっている。触手は収納可能なのか、背後で蠢くものもない。似合うかどうかでいえば確実に似合っていた。
「うん、似合うと思う」
「ほんと? 嬉しい」
魔王がかけてくれた褒め言葉には及ぶべくもない言葉だけれど、それでも満足したらしい。双子に、「準備ありがとー」と告げている様子は、やっぱり魔王には見えない。エメリとの結婚式に、心の底から浮かれているように見えてソワソワしてしまう。
「行こっか」
「あ、うん」
差し出された手を取り、立ち上がる。今から勇者エメリは、魔王ニグラスと結婚するらしい。実感は一つも湧かない。
*
エメリは結婚式に参列したことがない。結婚式の知識は全て小説や文献から得たのだけれど、魔族で初めて行われるという結婚式は驚くほど知識通りのものだった。
――魔王城に教会みたいな場所ってあるんだ。
元からあるのか、それとも急拵えで作られたのかはわからない。けれど、十字架にステンドグラス、祭壇があるのは王国の教会と変わりないと思えた。魔王城に十字架があってもいいのか、ということは甚だ疑問だけれど気にしないことにする。王国の結婚式と決定的に違うのは、参列者全員が魔族だということぐらいだろう。修道服に身を包む神父も含めて、角か牙か羽根が生えている。改めて、魔族の本拠地に人間一人でいる状況に恐れを感じた。参列している魔族たちは、人間の花嫁をもらう魔王のことをどう思っているのだろう。結婚式に参列しているとは思えないほどの真顔の魔族たち。敵意は感じないけれど、歓迎されているとも思えない。命じられたから渋々参列しているというのがよくわかる。
「大丈夫だよ」
知らず体が震えるのが、肘のあたりを掴む手から伝わったのだろうか。魔王はエメリに小声で告げる。
「エメリに手出すやつは僕が殺すから」
「えぇー……」
安心してね、とウインク付きで言われたけれどあまりに物騒で乾いた笑いしか出ない。さすが魔王というべきだろうか、やると言ったら本当にやれるのだろう。目の前の神父は死んだ目で分厚い本を開いていて、チラリと中を覗き見ると白紙だった。
「魔王ニグラス、あなたは勇者エメリを一生の伴侶とすることを誓いますか」
「はい、誓います」
抑揚のない声で紡がれる誓いの言葉は、聞いたことがない類のものだ。あまりに短く、端的な言葉。考えたのは魔王なのだろうか。なんにせよ、王国と全く同じ様式というわけではないらしい。どちらかといえば葬式寄りの空気が漂う空間において、魔王だけが生き生きと返事をしている。
「勇者エメリ、あなたは魔王ニグラスを一生の伴侶とすることを誓いますか」
「……はい、誓います」
誓ってたまるか、という本音は置いておく。王国のためを考えれば、今は形だけでも誓うしかない。指輪の交換は、何の感慨もなく進んだ。魔王がエメリの左手の薬指に指輪を嵌めるのを、何の感慨もなく見つめる。こんな短期間でどうやって用意したんだろう、ということだけが気になったけれどどうでもいい。神父もどきに促され、魔王の指にも同じように指輪を嵌める。エメリより一回りほど大きい手に生える爪は短い。魔族と言えば武器にもなりそうな爪が生えているものだと思っていたのだけれど、人間の成人男性の手と言われても信じてしまいそうだ。
「ふふ」
「……」
ニコニコと嬉しそうな視線が突き刺さるのを、一生懸命気づかないふりをする。薬指に嵌められた指輪は、一体いつサイズを図ったのかエメリの指にぴったりだ。勇者と魔王の結婚式ってこういう感じなんだ、と他人事のように思った。
慌ただしく着飾られながら、エメリは現実から逃避するように思いを馳せる。魔王討伐のために単身黒い森に乗り込んで早三日。今日は結婚式だ。
*
「僕は魔王ニグラス。結婚しよう」
「……は?」
沈黙が二人を包んだ。あんぐりと口を開け、信じられないものを見るような目で魔王を見つめるエメリとは対照的に、魔王は何故か頬を染めている。まるで、好きな人に告白して照れているかのように。
――結婚? 誰と誰が?
唐突な提案を脳内で反芻し、理解した瞬間――力の限りもがいて腕の中から抜け出し、後ろに飛び退く。今度はよろけなかった。剣が取り上げられてしまったのなら、と武術の構えを取る。無駄な抵抗だとは思ったが、この体勢の方が声は出しやすい。
「無理!!」
「えー……」
即答かあ、と残念そうにする魔王。気の抜けるような言葉は、真意が掴めなくて油断ならない。そもそも、昔から父親に稽古をつけられてきたのだ。対峙すれば相手の強さはなんとなくわかるのだが、目の前の男に敵うはずがないのはなんとなくどころではなくわかる。今までの魔王もこんなに強かったのだろうか。ふと魔王の背後を見ると相変わらず触手は蠢いていて、そのうちの一本がエメリの剣をくるくると丸めているところだった。
「わ、私の剣……!」
「あ、ごめん。さすがに勇者の剣は危ないから没収ね」
没収なら丸める必要はなかったのでは、と思ったけれどそうではない。そもそも鉄鋼でできた剣を丸めるなんて、あの触手は一体なんなのか。ロールケーキのように丸くなってしまった剣を見ながら呆気に取られる。丸腰のエメリは、近寄る魔王を前に逃げ出すことすらできない。ここで死ぬんだ、と悲壮な覚悟を決めた。
「そんな顔しないでよ。食べないからさ」
けれど、予想に反して魔王はエメリを殺そうとはしない。眉を下げてエメリの手を取ると、ふにふにと優しく握った。年頃の女の子の柔らかくてスベスベした手からは程遠い、マメだらけでガサついた手。愛おしそうに触れる手つきは、とても魔王のものとは思えない。なにが由来かもわからない心臓の音を聞きながら、「な、何が目的?」と一生懸命に絞り出す。情けないほどに震えていて、虚勢を張っていることはバレバレだろう。けれど魔王はそれには触れず、きょとんと首を傾げてエメリを見た。
「目的って、エメリと家族になりたいから以外にある?」
「か、家族!?」
予想もしていなかった答えにエメリは目を剥く。まさか魔王の口から、「家族になりたい」だなんてささやかな願いを聞くとは夢にも思わない。ますます魔王の目的がわからなくなり、「そういうのいいから! 本当のことを言って!」と叫ぶ。魔王城に来てからなにも想定通りにいっていないせいで、ただでさえ混乱しているのだ。これ以上混乱させないでほしい、という心からの叫びだったのだけれど、しかし魔王は心外だと言わんばかりに顔を顰めた。
「本当のことなんだけど」
「そんなわけないでしょ! 魔族が人間と家族!? 絶対ありえない!」
未だかつて、魔族と婚姻関係を結んだ人間は王国にいない。王国に住む人間にとって魔族は忌むべき存在で、魔王はそれの最たるものだ。家族になる対象では決してない。魔王討伐に行ったはずの勇者が魔王と結婚して帰ってくるだなんて、エメリの家にある文献のどれにも記されていなかった。至極当たり前の指摘をしたつもりだったのだけれど、魔王はどうしてか傷ついたように顔を歪める。意外なリアクションに何か言う前に、口を開いた。
「どうしても信じてくれない?」
「信じてくれない、って……そもそも信じる根拠も何もないし。なんていうか、王国に対する人質とか言われたほうがまだ信じられるっていうか」
「じゃあそれで」
「は?」
じゃあそれで、とは。軽い調子で返された言葉に困惑し通しのエメリをよそに、魔王はなんでもないように言葉を続ける。
「エメリがお嫁さんになって、僕と家族になってくれるなら王国には手を出さないであげる」
「はあ?」
「エメリがお嫁さんになってくれないなら、王国は滅ぼす」
「はあ!?」
「ね、これならいい? 僕のこと信じてくれる?」
「し、信じるって、何それ脅迫?!」
無邪気な笑顔でとんでもないことを提案する魔王は、エメリがどれだけ引っ込めようとしても手を離さない。どうやら、今ここで魔王の嫁になるかどうかが王国存亡の分水嶺となるらしい。なんの利益があってエメリと家族になりたいだなんて世迷言をいっているのだろうか。わからないけれど、ここで見逃してもらったとしても、魔王を倒せずにのこのこと帰るエメリに居場所はきっとない。それならば魔族の本拠地で人質として生きる方がマシなのではないか。
「僕と結婚してくれるなら、エメリの願いはなんでも叶えてあげる」
「……」
悪魔が取引を持ちかけるような甘い囁き。難しい顔で考え込むエメリとは対照的に、魔王はいつの間にかご機嫌そうにニコニコと笑っている。先ほどの傷ついたような顔は一体なんだったのか。何一つとしてエメリの理解の範疇にはないけれど、選ぶべき道が一つしかないということだけは理解できた。
「……わかった。あなたと結婚する」
「ほんと?」
「その代わり、王国には手を出さないで」
「もちろん」
飛び跳ねる勢いで魔王はエメリの両手を握りしめて喜ぶ。魔族は鋭い牙や角があるのが定説だと本で学んだのだけれど。顔をまじまじ見てみると、牙らしきものも生えていないし耳も丸い。羽根はマントに隠れているのか、それとも映えていないのだろうか。よくわからないけれど、頭から生えている角と虹彩の渦巻いた瞳、それから背後で蠢く触手以外はほとんど人間と変わりないように見える。エメリが観察していることに気づいているのかいないのか、魔王は嬉しそうに口を開いた。
「よろしくね、エメリ。結婚式は明後日だから」
「は?」
*
それからの二日間は怒涛だった。慌ただしすぎて、現状を伝える手紙すら王国に送れなかったほどに。
「エメリ様、綺麗〜」
「可愛い〜」
「あ、ありがとう」
エメリを褒めるのは、魔王との結婚が決まってすぐに紹介された双子の侍女。背中から蝙蝠のような羽が生えている二人はお仕着せ姿がよく似合うが、当然魔族である。「リリとリムだよ。身の回りのことは二人にやってもらってね」と魔王に紹介されたときには、世話と称してどんな扱いを受けたものかと身構えたのだが。想像に反して二人はキャッキャと楽しそうに世話を焼いてくれた。
「結婚式とかいうの、魔王城でやるの初めて見る」
「ね、楽しみだよね」
「そうなんだ……」
どうやら魔族に結婚式という文化はないらしい。ドレスもベールも王国で見たものと変わりないように見えるけれど、どうやって用意したのだろうか。そう思っていると、「夜なべで準備した甲斐があったよね」「ね、似合ってるし」と言われたので、二人が作ってくれたのだと悟った。魔王城で働く侍女は、裁縫の能力も高いらしい。二人にお礼を告げると、「いいよお」「これが仕事だし」と返ってきた。
生まれてこの方、こんなに着飾らせてもらったのはデビュタントの時以来だ、と不意に思い出す。一応貴族令嬢だけれど、おおよそ貴族令嬢らしくない生活を送ってきたエメリには、着飾った記憶がほとんどない。物心がつく前から稽古漬けの毎日だったから。けれど、唯一デビュタントのときだけは父親も許してくれたので、侍女が張り切って着飾らせてくれた。今頃、家の人たちや王国の人たちはどうしているのだろう。王国に手は出さないと言ってくれたけれど、立ち込める暗雲も晴らしてくれただろうか。平和が戻っているといいのだけれど。
「エメリ、準備できた?」
控え室に夫となる人――魔王ニグラスがやってきた。何やら忙しくしていたらしい魔王とはこの二日間、食事のときにしか顔を合わせなかった。聞きたいことも言いたいこともたくさんあるのだけれど、式の後なら話せるのだろうか。そんなことを考えているエメリとは裏腹に、ニグラスは顔をぱあっと綻ばせて駆け寄ってくる。あまりにも眩しい笑顔に、この人が魔王であることが頭から吹き飛んでしまった。
「すっごく綺麗! こんな可愛い子が僕のお嫁さんになるの? 嬉しい!」
「え、あ、ありがとう……」
勢いに押され、思わずお礼を言ってしまう。今までの人生で着飾ることがなければ、可愛いと言われた記憶もほとんどないに等しい。討伐対象とはいえ、こんなにストレートに褒められて嬉しくならないわけがないのだ。背後で双子の侍女が、「浮かれ花婿だ」「浮かれ魔王だ」と呟いているのが聞こえる。顔が見えなくても、ニヤニヤしているのが丸わかりだ。
「ね、僕の格好はどう? 似合う?」
双子に揶揄うような視線を向けられていることにも気づかず、魔王はソワソワとエメリの反応を気にしている。この人は本当に魔王なのだろうか、と魔王城に来てから何度覚えたかわからない疑問を覚えた。
「えっと……」
言葉を探しながら魔王を上から下まで眺める。魔王の身を包むのは、見慣れた黒づくめの服とマントではなく白いタキシード。無造作な黒髪は後ろに撫で付けられていて、形のいい額が顕になっている。触手は収納可能なのか、背後で蠢くものもない。似合うかどうかでいえば確実に似合っていた。
「うん、似合うと思う」
「ほんと? 嬉しい」
魔王がかけてくれた褒め言葉には及ぶべくもない言葉だけれど、それでも満足したらしい。双子に、「準備ありがとー」と告げている様子は、やっぱり魔王には見えない。エメリとの結婚式に、心の底から浮かれているように見えてソワソワしてしまう。
「行こっか」
「あ、うん」
差し出された手を取り、立ち上がる。今から勇者エメリは、魔王ニグラスと結婚するらしい。実感は一つも湧かない。
*
エメリは結婚式に参列したことがない。結婚式の知識は全て小説や文献から得たのだけれど、魔族で初めて行われるという結婚式は驚くほど知識通りのものだった。
――魔王城に教会みたいな場所ってあるんだ。
元からあるのか、それとも急拵えで作られたのかはわからない。けれど、十字架にステンドグラス、祭壇があるのは王国の教会と変わりないと思えた。魔王城に十字架があってもいいのか、ということは甚だ疑問だけれど気にしないことにする。王国の結婚式と決定的に違うのは、参列者全員が魔族だということぐらいだろう。修道服に身を包む神父も含めて、角か牙か羽根が生えている。改めて、魔族の本拠地に人間一人でいる状況に恐れを感じた。参列している魔族たちは、人間の花嫁をもらう魔王のことをどう思っているのだろう。結婚式に参列しているとは思えないほどの真顔の魔族たち。敵意は感じないけれど、歓迎されているとも思えない。命じられたから渋々参列しているというのがよくわかる。
「大丈夫だよ」
知らず体が震えるのが、肘のあたりを掴む手から伝わったのだろうか。魔王はエメリに小声で告げる。
「エメリに手出すやつは僕が殺すから」
「えぇー……」
安心してね、とウインク付きで言われたけれどあまりに物騒で乾いた笑いしか出ない。さすが魔王というべきだろうか、やると言ったら本当にやれるのだろう。目の前の神父は死んだ目で分厚い本を開いていて、チラリと中を覗き見ると白紙だった。
「魔王ニグラス、あなたは勇者エメリを一生の伴侶とすることを誓いますか」
「はい、誓います」
抑揚のない声で紡がれる誓いの言葉は、聞いたことがない類のものだ。あまりに短く、端的な言葉。考えたのは魔王なのだろうか。なんにせよ、王国と全く同じ様式というわけではないらしい。どちらかといえば葬式寄りの空気が漂う空間において、魔王だけが生き生きと返事をしている。
「勇者エメリ、あなたは魔王ニグラスを一生の伴侶とすることを誓いますか」
「……はい、誓います」
誓ってたまるか、という本音は置いておく。王国のためを考えれば、今は形だけでも誓うしかない。指輪の交換は、何の感慨もなく進んだ。魔王がエメリの左手の薬指に指輪を嵌めるのを、何の感慨もなく見つめる。こんな短期間でどうやって用意したんだろう、ということだけが気になったけれどどうでもいい。神父もどきに促され、魔王の指にも同じように指輪を嵌める。エメリより一回りほど大きい手に生える爪は短い。魔族と言えば武器にもなりそうな爪が生えているものだと思っていたのだけれど、人間の成人男性の手と言われても信じてしまいそうだ。
「ふふ」
「……」
ニコニコと嬉しそうな視線が突き刺さるのを、一生懸命気づかないふりをする。薬指に嵌められた指輪は、一体いつサイズを図ったのかエメリの指にぴったりだ。勇者と魔王の結婚式ってこういう感じなんだ、と他人事のように思った。