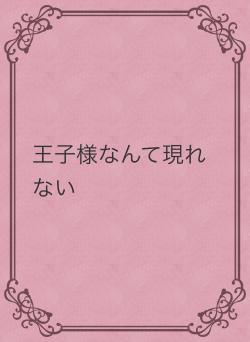スープで満たされた大鍋をかき混ぜながらふと、そういえばパセリが残り少ないんだった、と気がついた。なくてもいいけれど、あったほうが香りがいいし見栄えもいい。戸棚を漁ってみると、ドライパセリの瓶は案の定底が見えている。エメリに頼んで買ってきてもらおうか、と思ったけれど連絡手段がないので諦めた。今日の分は十分あるし、明日以降頼めばいいだろう。
魔力の源を失い、魔法が使えなくなってから数ヶ月。側頭部のざらりとした硬い感触には、いまだに慣れそうにない。根本から切られているが、引っこ抜かれたわけではない。根っこが残っているのならいけるかも、と思ったけれど考えは甘かった。魔法を使おうとした瞬間、立っていられないほどの激痛が走ったのでもう二度とやらないと決めた。
「人間は魔法なしでよくやるよねー……」
火を止め、器にスープを装う。自分も同じ立場になってようやく知ったけれど、魔法を使えないのはそれなりに不便だ。ニグラスの場合、今まで魔法でどうにでもできたことがどうにもできなくなったのだから余計である。盛り付けた料理は手で運ばないといけないし、どこに移動するにも時間がかかる。好きな子が絡まれているのを見ても、触手で張り倒すこともできない。数百年は生きられたはずの命は、残り数十年しかないだろう。人間というのは不便で、弱くて、儚い存在だ。
けれど不思議と、もう一度魔法を使えるようになりたいと思うことはなかった。
「ただいまー」
ちょうど全ての料理を机に並べたところで、最愛の人が帰ってきた。待ちきれずに玄関まで出迎えると、「いい匂いする」と嬉しそうにニコニコとしている。心臓のあたりがきゅん、と締め付けられるような気がしてほとんど無意識に手を伸ばしていた。
「おかえり、エメリ」
「ただいま、ニグラス」
ぎゅう、と抱きしめると躊躇うことなく背中に腕を回される。初めて魔王と勇者として出会ったとき、抱きしめるのを全力で拒絶されたことを思い出してなんだか感慨深い。丸い後頭部を撫でながら、「ご飯できてるよー」と呟くと、「今日は何?」と尋ねられた。
「スープとチキンのソテー」
「本当? 今日チキン食べたい気分だった」
「ふふ」
今日というか、割といつもチキンのソテーを食べたがっていることに彼女は気づいていないのだろうか。魔法を使わなくても、好きな子の食べたいものを用意することぐらい朝飯前である。早くご飯にしようと手を引くと、「あ」とエメリは声を上げた。どうしたのか尋ねる前に、紙袋を掲げられる。
「何それ?」
「パセリ。なくなりそうだったから買ってきたよ」
「……魔法使った?」
「えっ、使えないよ」
妙な質問に首を傾げながら、「忘れないうちにしまっとくね」と言い置いてダイニングへと向かう。魔法がなくても、好きな子が相手なら通じ合えるのだろうか。よくわからない感動に震えるニグラスは、「冷めちゃうよー?」と呼びかけられるまでその場に立ち尽くしていた。
*
エメリの尽力によって目覚めたニグラスは、魔法を使えなくなり、長大な寿命も失った。人間になったわけではないけれど、魔族と呼ぶことはできない。当然、玉座に座ることもできないので、魔王でもなくなってしまった。魔力の源である角を切られたせいか、瘴気を長時間吸っていると眩暈や吐き気がしてくる。守護の力を失ったエメリが瘴気に耐えられないことを考えても、二人が黒い森を出るしかないことは明白だった。眉を下げる双子とエメリが、調合小屋の敷居越しに手を繋いでいたのをよく覚えている。
黒い森から出ていき、隣国に行くことになったけれど当然瘴気に耐えられない二人ではどうすることもできない。エメリに寿命を差し出させて、黒い森からの脱出をマルコに頼るしかないことは不本意でしかなかった。魔法が使えたらエメリを抱えて隣国に行くなんて一瞬なのに。魔法が使えなくなったことを、一番悔やんだ瞬間だった。
ぶわりと風が吹き、隣国へと移動する。降り立った先でエメリが更に自身の寿命を差し出して王国に手を出さないことを願うのを、ニグラスは唇をかみしめて見つめることしかできない。あのときの悔しさと羨望を、どう形容したら良かったのだろうか。エメリの願いを叶えるのは自分だけのはずだったのに、と考えても仕方のないことが頭を占める。元魔王は現魔王への嫉妬で喉の奥が焼けつきそうだった。そんなニグラスを見てマルコは笑う。しょうがないやつとでも言いたげな顔は、遥か昔の幼い頃から変わらない。マルコはニグラスの方を叩いて、「元気でいろよ」とだけ告げ、ぶわりと吹いた風とともに姿を消した。
「マルコってニグラスのことすごく大事にしてるよね」
「……友達だからかな」
「ふうん?」
それ以上何も言わなかったけれど、微笑ましそうな視線がくすぐったかったのをよく覚えている。不意にニグラスの手を取ったエメリは、「まずは家を探すところからだね」と明るく口を開いた。土地勘があるわけでもなく、身寄りや知り合いがいるわけでもない。二人が元魔王と元勇者だとは、街を行き交う誰もわからないだろう。家も仕事もないけれど、エメリが隣で笑っているだけで幸せだと思った。
そうして始まった二人の暮らしは、これ以上なく穏やかだ。仮にも元魔王と、仮にも元勇者かつ元貴族令嬢。今までの人生からは考えもつかないほど質素な生活だけれど、二人は驚くほどあっさりと順応した。元貴族令嬢といえど鍛錬続きで甘やかされることがなかったこと、魔王といえど贅沢という文化がなかったことはおそらく大きい。
これまでに培ってきた薬草や調合の知識を活かして、エメリは街の小さな薬屋で働き始めた。老夫婦が二人で営んでいて、街の住民に長年親しまれてきた薬屋。後継者がいないことから閉めようとしていたところに、幸運にも巡り会えたのだ。今はまだ見習いだけれど、あと数年もすれば正式に薬師として認めてもらい、店を継がせてもらえるらしい。朝から晩まで忙しく楽しそうに働くエメリを、ニグラスは生活面から支えることにした。魔族として生きてきたニグラスは、そもそも人間社会でどう立ち回るべきかがあまりわかっていない。働くのならせめて最低限の常識を身につけてからにしよう、ということになったのだ。
元魔王に家のことなんてできるのだろうか、と不安に思っていたエメリだけれど。意外や意外、ニグラスの家事能力は高かった。
「まあ魔族って基本的に自分のことは自分でするしね」
「そうなんだ」
「うん。あと、リリとリムが料理とか好きだから、たまに付き合わされてた」
こだわりのないニグラスは、食べられればそれでいいし、不快でなければ掃除もたまにしかしない、というスタンス。リリとリムに野菜の皮剥きだとかみじん切りだとかを手伝わされるのを、面倒だなあと思いながら付き合っていたけれど今となっては感謝しかない。
「二人とも元気にしてるかなあ。あとマルコも」
「元気だと思うよ。昔から具合悪そうにしてるの見たことないし」
「そうなんだ」
魔族って健康なんだねえ、としみじみ呟くエメリ。魔族に対するどこかずれた感想すらも可愛い。エメリの健康は僕が絶対守るからね、と決意を胸に見つめる。警戒心のかけらもなく、ニグラスの用意した料理を美味しそうに頬張るエメリ。あまりにも可愛い。
*
空腹を満たして、湯浴みも済ませ、ベッドで本を読んでいるうち、そういう空気になる。魔王城にいた頃はいつまで経っても懐かない子猫のようだったエメリは、二人で暮らすようになってから随分素直にくっついてくれるようになった。その変化がニグラスにとってどれだけ嬉しいことか、彼女はわかっているのだろうか。
組み敷いたエメリは悩ましげに、眉間に皺を寄せている。与えられる快楽を、どうしたらいいのかわからないのだろう。身を捩って逃れようとするのを、腰を掴んで抑える。散々蕩してどろどろに解したあわいに、張り詰めた自身を宛てがった。びくり、と細い肩が震えるので、宥めるように頭を撫でて口付ける。首に腕を回して、一生懸命に舌を絡めてくるのが可愛くてたまらない。ずぷ、と腰を押し進めるごとに生まれる微かな嬌声は、空気に触れる前にニグラスが食べてしまった。唇を離すと、潤んだ瞳でニグラスを見上げるエメリと目が合う。
「痛い?」
「い、たく、ない」
「ほんと? 気持ちいい?」
「あぅ、んっ、きもちぃ」
「ふふ、いい子」
「ひぁっ……」
ふるふると震える乳首をきゅう、と摘むと甲高くて甘ったるい声をあげる。身を屈めて首筋に吸い付き、跡を残す。白い肌にはニグラスが残した跡がいくつも散らばっていて、独占欲が満たされるような高揚感を覚えた。ゆるゆると揺さぶっていると、不意にエメリが手を伸ばす。なんだろう、と頭を寄せると小さな手は側頭部に触れた。
「あ、角?」
そういえば魔王城にいたときから角をよく触ってたな、と思い出しす。角から伝わる感情を、エメリはどう思っていたのだろう。無くしてしまった今となっては、なんとなく聞けない。あのときもう少し聞いておけばよかった、と思っているとエメリが顔を歪めたことに気がついた。なんだか泣きそうにも見える。その理由に、なんとなく心当たりはあった。
ニグラスの角を切ってしまったことを、魔法を使えなくして寿命を縮めてしまったことを、エメリはいまだに悔やんでいる。自分は守護の力を失い、寿命も十数年分は削ってまで、ニグラスの命を助けてくれたのに。トゥルシーに侵された右腕も、何の支障もなく動かせるようにしてくれたのに。それだけじゃ償いきれないと思っているらしい。
「角がなくて困るのは、エメリに感情が伝わらないことぐらいかな」
「っ……」
「それ以外は困ってないよ。魔法を使えなくても、できることはいっぱいあるし」
角の跡地に触れる手を取り、自身の頬に当てる。小さな手は、エメリの努力の証であるマメだらけで固い。それでもこの暖かい手に触れるのが何よりも好きだった。大丈夫、泣かないで、大好きだよ、と軽薄に聞こえるぐらい言葉を重ねる。普段は気にしていなさそうなエメリだけれど、不意に気にしては落ち込んでしまう。気にしなくていいのにと思う一方で、そういう律儀なところが愛おしいとも思う。
「……ニグラス、あのね」
ポツリ、とか細い声でエメリが言葉を紡ぐ。どう話そうか迷っているのか、視線をうろうろと彷徨わせている。「うん」とエメリから目を離すことなく頷いた。「角を切ったこと、多分私は一生後悔すると思う」と話し始めた声は震えている。
「もっといいやり方はなかったのか、私がもっとちゃんとしてれば、って。ずっと、ずっとそう思うんだと思う」
「……」
震えているけれど、確かにそこには芯があった。ニグラスに、気にしないでと軽々に言わせないような芯の強さが。ニグラスが眠りについている間、エメリがどれだけ頑張ってくれたのかは全て知っている。ニグラスから魔力を奪ってしまったというのなら、エメリだって守護の力を奪われてしまったのだ。お互いに失ったものは同等のはずなのに、まるで自分は何の代償も支払っていないとばかりに、ニグラスの失ったものばかりを数える。そんなところが危うくて、眩しくて、どうしようもないほど愛おしかった。再び口づけようと身を屈めると、「でもね」とエメリが続ける。先ほどより幾分か声が明るい。
「あの、あのね、ニグラス」
「なあに?」
赤い顔でニグラスを見上げるエメリは、「私の願いを叶えてくれて、ありがとう」と泣きそうな顔で笑う。どくり、と心臓が跳ねた。ずっと昔、眠るエメリに口付けたときのことを思い出す。どうしてか、あのときのエメリが、今組み敷いているエメリと重なった。ニグラスの心拍数が急に跳ね上がったことに気づかないエメリは、金色の瞳を見つめて口を開く。
「私と、家族になってくれてありがとう。幸せにしてくれて、ありがとう」
「エ、メリ……」
「大好きよ、ニグラス」
そう告げると、空いていた方の手もニグラスの頬に当て、自分の方に寄せて口付ける。ほんの一瞬触れただけの唇はすぐに離れた。気づけば頬からも手は離れ、首に腕を回して強く抱きしめられる。お互いの境界がなくなって混ざり合うぐらいに隙間なく抱きしめられる間、ニグラスは動けなかった。
――くすしになって、クロと家族になって、ずっとしあわせにくらしたい。
山羊のクロを抱きしめ、わんわん泣いていた小さな女の子。初めて触れた唇の感触をいまだに覚えていると言ったら、きっとまた気持ちが悪いとドン引きされるのだろう。そう思うとおかしくて、「ははっ……」と笑った拍子にうっかり涙が出た。縋り付くようにして抱きつくと、背中に腕が回され、頭を撫でられる。
「大好きだよ、エメリ」
魔法を使えなくても、数百年を生きられなくても、魔王でなくなっても、好きな子が腕の中で幸せだと言ってくれるのなら、それは二グラスにとっての幸福だった。
魔力の源を失い、魔法が使えなくなってから数ヶ月。側頭部のざらりとした硬い感触には、いまだに慣れそうにない。根本から切られているが、引っこ抜かれたわけではない。根っこが残っているのならいけるかも、と思ったけれど考えは甘かった。魔法を使おうとした瞬間、立っていられないほどの激痛が走ったのでもう二度とやらないと決めた。
「人間は魔法なしでよくやるよねー……」
火を止め、器にスープを装う。自分も同じ立場になってようやく知ったけれど、魔法を使えないのはそれなりに不便だ。ニグラスの場合、今まで魔法でどうにでもできたことがどうにもできなくなったのだから余計である。盛り付けた料理は手で運ばないといけないし、どこに移動するにも時間がかかる。好きな子が絡まれているのを見ても、触手で張り倒すこともできない。数百年は生きられたはずの命は、残り数十年しかないだろう。人間というのは不便で、弱くて、儚い存在だ。
けれど不思議と、もう一度魔法を使えるようになりたいと思うことはなかった。
「ただいまー」
ちょうど全ての料理を机に並べたところで、最愛の人が帰ってきた。待ちきれずに玄関まで出迎えると、「いい匂いする」と嬉しそうにニコニコとしている。心臓のあたりがきゅん、と締め付けられるような気がしてほとんど無意識に手を伸ばしていた。
「おかえり、エメリ」
「ただいま、ニグラス」
ぎゅう、と抱きしめると躊躇うことなく背中に腕を回される。初めて魔王と勇者として出会ったとき、抱きしめるのを全力で拒絶されたことを思い出してなんだか感慨深い。丸い後頭部を撫でながら、「ご飯できてるよー」と呟くと、「今日は何?」と尋ねられた。
「スープとチキンのソテー」
「本当? 今日チキン食べたい気分だった」
「ふふ」
今日というか、割といつもチキンのソテーを食べたがっていることに彼女は気づいていないのだろうか。魔法を使わなくても、好きな子の食べたいものを用意することぐらい朝飯前である。早くご飯にしようと手を引くと、「あ」とエメリは声を上げた。どうしたのか尋ねる前に、紙袋を掲げられる。
「何それ?」
「パセリ。なくなりそうだったから買ってきたよ」
「……魔法使った?」
「えっ、使えないよ」
妙な質問に首を傾げながら、「忘れないうちにしまっとくね」と言い置いてダイニングへと向かう。魔法がなくても、好きな子が相手なら通じ合えるのだろうか。よくわからない感動に震えるニグラスは、「冷めちゃうよー?」と呼びかけられるまでその場に立ち尽くしていた。
*
エメリの尽力によって目覚めたニグラスは、魔法を使えなくなり、長大な寿命も失った。人間になったわけではないけれど、魔族と呼ぶことはできない。当然、玉座に座ることもできないので、魔王でもなくなってしまった。魔力の源である角を切られたせいか、瘴気を長時間吸っていると眩暈や吐き気がしてくる。守護の力を失ったエメリが瘴気に耐えられないことを考えても、二人が黒い森を出るしかないことは明白だった。眉を下げる双子とエメリが、調合小屋の敷居越しに手を繋いでいたのをよく覚えている。
黒い森から出ていき、隣国に行くことになったけれど当然瘴気に耐えられない二人ではどうすることもできない。エメリに寿命を差し出させて、黒い森からの脱出をマルコに頼るしかないことは不本意でしかなかった。魔法が使えたらエメリを抱えて隣国に行くなんて一瞬なのに。魔法が使えなくなったことを、一番悔やんだ瞬間だった。
ぶわりと風が吹き、隣国へと移動する。降り立った先でエメリが更に自身の寿命を差し出して王国に手を出さないことを願うのを、ニグラスは唇をかみしめて見つめることしかできない。あのときの悔しさと羨望を、どう形容したら良かったのだろうか。エメリの願いを叶えるのは自分だけのはずだったのに、と考えても仕方のないことが頭を占める。元魔王は現魔王への嫉妬で喉の奥が焼けつきそうだった。そんなニグラスを見てマルコは笑う。しょうがないやつとでも言いたげな顔は、遥か昔の幼い頃から変わらない。マルコはニグラスの方を叩いて、「元気でいろよ」とだけ告げ、ぶわりと吹いた風とともに姿を消した。
「マルコってニグラスのことすごく大事にしてるよね」
「……友達だからかな」
「ふうん?」
それ以上何も言わなかったけれど、微笑ましそうな視線がくすぐったかったのをよく覚えている。不意にニグラスの手を取ったエメリは、「まずは家を探すところからだね」と明るく口を開いた。土地勘があるわけでもなく、身寄りや知り合いがいるわけでもない。二人が元魔王と元勇者だとは、街を行き交う誰もわからないだろう。家も仕事もないけれど、エメリが隣で笑っているだけで幸せだと思った。
そうして始まった二人の暮らしは、これ以上なく穏やかだ。仮にも元魔王と、仮にも元勇者かつ元貴族令嬢。今までの人生からは考えもつかないほど質素な生活だけれど、二人は驚くほどあっさりと順応した。元貴族令嬢といえど鍛錬続きで甘やかされることがなかったこと、魔王といえど贅沢という文化がなかったことはおそらく大きい。
これまでに培ってきた薬草や調合の知識を活かして、エメリは街の小さな薬屋で働き始めた。老夫婦が二人で営んでいて、街の住民に長年親しまれてきた薬屋。後継者がいないことから閉めようとしていたところに、幸運にも巡り会えたのだ。今はまだ見習いだけれど、あと数年もすれば正式に薬師として認めてもらい、店を継がせてもらえるらしい。朝から晩まで忙しく楽しそうに働くエメリを、ニグラスは生活面から支えることにした。魔族として生きてきたニグラスは、そもそも人間社会でどう立ち回るべきかがあまりわかっていない。働くのならせめて最低限の常識を身につけてからにしよう、ということになったのだ。
元魔王に家のことなんてできるのだろうか、と不安に思っていたエメリだけれど。意外や意外、ニグラスの家事能力は高かった。
「まあ魔族って基本的に自分のことは自分でするしね」
「そうなんだ」
「うん。あと、リリとリムが料理とか好きだから、たまに付き合わされてた」
こだわりのないニグラスは、食べられればそれでいいし、不快でなければ掃除もたまにしかしない、というスタンス。リリとリムに野菜の皮剥きだとかみじん切りだとかを手伝わされるのを、面倒だなあと思いながら付き合っていたけれど今となっては感謝しかない。
「二人とも元気にしてるかなあ。あとマルコも」
「元気だと思うよ。昔から具合悪そうにしてるの見たことないし」
「そうなんだ」
魔族って健康なんだねえ、としみじみ呟くエメリ。魔族に対するどこかずれた感想すらも可愛い。エメリの健康は僕が絶対守るからね、と決意を胸に見つめる。警戒心のかけらもなく、ニグラスの用意した料理を美味しそうに頬張るエメリ。あまりにも可愛い。
*
空腹を満たして、湯浴みも済ませ、ベッドで本を読んでいるうち、そういう空気になる。魔王城にいた頃はいつまで経っても懐かない子猫のようだったエメリは、二人で暮らすようになってから随分素直にくっついてくれるようになった。その変化がニグラスにとってどれだけ嬉しいことか、彼女はわかっているのだろうか。
組み敷いたエメリは悩ましげに、眉間に皺を寄せている。与えられる快楽を、どうしたらいいのかわからないのだろう。身を捩って逃れようとするのを、腰を掴んで抑える。散々蕩してどろどろに解したあわいに、張り詰めた自身を宛てがった。びくり、と細い肩が震えるので、宥めるように頭を撫でて口付ける。首に腕を回して、一生懸命に舌を絡めてくるのが可愛くてたまらない。ずぷ、と腰を押し進めるごとに生まれる微かな嬌声は、空気に触れる前にニグラスが食べてしまった。唇を離すと、潤んだ瞳でニグラスを見上げるエメリと目が合う。
「痛い?」
「い、たく、ない」
「ほんと? 気持ちいい?」
「あぅ、んっ、きもちぃ」
「ふふ、いい子」
「ひぁっ……」
ふるふると震える乳首をきゅう、と摘むと甲高くて甘ったるい声をあげる。身を屈めて首筋に吸い付き、跡を残す。白い肌にはニグラスが残した跡がいくつも散らばっていて、独占欲が満たされるような高揚感を覚えた。ゆるゆると揺さぶっていると、不意にエメリが手を伸ばす。なんだろう、と頭を寄せると小さな手は側頭部に触れた。
「あ、角?」
そういえば魔王城にいたときから角をよく触ってたな、と思い出しす。角から伝わる感情を、エメリはどう思っていたのだろう。無くしてしまった今となっては、なんとなく聞けない。あのときもう少し聞いておけばよかった、と思っているとエメリが顔を歪めたことに気がついた。なんだか泣きそうにも見える。その理由に、なんとなく心当たりはあった。
ニグラスの角を切ってしまったことを、魔法を使えなくして寿命を縮めてしまったことを、エメリはいまだに悔やんでいる。自分は守護の力を失い、寿命も十数年分は削ってまで、ニグラスの命を助けてくれたのに。トゥルシーに侵された右腕も、何の支障もなく動かせるようにしてくれたのに。それだけじゃ償いきれないと思っているらしい。
「角がなくて困るのは、エメリに感情が伝わらないことぐらいかな」
「っ……」
「それ以外は困ってないよ。魔法を使えなくても、できることはいっぱいあるし」
角の跡地に触れる手を取り、自身の頬に当てる。小さな手は、エメリの努力の証であるマメだらけで固い。それでもこの暖かい手に触れるのが何よりも好きだった。大丈夫、泣かないで、大好きだよ、と軽薄に聞こえるぐらい言葉を重ねる。普段は気にしていなさそうなエメリだけれど、不意に気にしては落ち込んでしまう。気にしなくていいのにと思う一方で、そういう律儀なところが愛おしいとも思う。
「……ニグラス、あのね」
ポツリ、とか細い声でエメリが言葉を紡ぐ。どう話そうか迷っているのか、視線をうろうろと彷徨わせている。「うん」とエメリから目を離すことなく頷いた。「角を切ったこと、多分私は一生後悔すると思う」と話し始めた声は震えている。
「もっといいやり方はなかったのか、私がもっとちゃんとしてれば、って。ずっと、ずっとそう思うんだと思う」
「……」
震えているけれど、確かにそこには芯があった。ニグラスに、気にしないでと軽々に言わせないような芯の強さが。ニグラスが眠りについている間、エメリがどれだけ頑張ってくれたのかは全て知っている。ニグラスから魔力を奪ってしまったというのなら、エメリだって守護の力を奪われてしまったのだ。お互いに失ったものは同等のはずなのに、まるで自分は何の代償も支払っていないとばかりに、ニグラスの失ったものばかりを数える。そんなところが危うくて、眩しくて、どうしようもないほど愛おしかった。再び口づけようと身を屈めると、「でもね」とエメリが続ける。先ほどより幾分か声が明るい。
「あの、あのね、ニグラス」
「なあに?」
赤い顔でニグラスを見上げるエメリは、「私の願いを叶えてくれて、ありがとう」と泣きそうな顔で笑う。どくり、と心臓が跳ねた。ずっと昔、眠るエメリに口付けたときのことを思い出す。どうしてか、あのときのエメリが、今組み敷いているエメリと重なった。ニグラスの心拍数が急に跳ね上がったことに気づかないエメリは、金色の瞳を見つめて口を開く。
「私と、家族になってくれてありがとう。幸せにしてくれて、ありがとう」
「エ、メリ……」
「大好きよ、ニグラス」
そう告げると、空いていた方の手もニグラスの頬に当て、自分の方に寄せて口付ける。ほんの一瞬触れただけの唇はすぐに離れた。気づけば頬からも手は離れ、首に腕を回して強く抱きしめられる。お互いの境界がなくなって混ざり合うぐらいに隙間なく抱きしめられる間、ニグラスは動けなかった。
――くすしになって、クロと家族になって、ずっとしあわせにくらしたい。
山羊のクロを抱きしめ、わんわん泣いていた小さな女の子。初めて触れた唇の感触をいまだに覚えていると言ったら、きっとまた気持ちが悪いとドン引きされるのだろう。そう思うとおかしくて、「ははっ……」と笑った拍子にうっかり涙が出た。縋り付くようにして抱きつくと、背中に腕が回され、頭を撫でられる。
「大好きだよ、エメリ」
魔法を使えなくても、数百年を生きられなくても、魔王でなくなっても、好きな子が腕の中で幸せだと言ってくれるのなら、それは二グラスにとっての幸福だった。