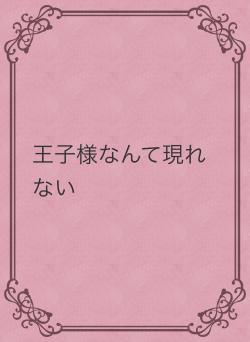十数年前、黒い森でのこと。痛む足を引きずって彷徨うニグラスが見つけたのは、蹲る小さな女の子だった。
「うえぇ……」
膝に顔を埋めて泣きじゃくる少女は、黒い森にいるはずのない人間の女の子。どうしてこんなところに、と思ったのも一瞬。そんなことは気にならなくなるぐらい、少女からは美味しそうな匂いがした。幼いニグラスは、守護の力という概念を知らない。が、魔族としての本能が、目の前の少女を食べれば魔力が上がるということを知らせる。マルコと喧嘩したせいで怪我した足は、指の二、三本食べればすぐに治るだろう。幸い、少女はニグラスの存在に気づいていない。油断させてから食べてしまうのは容易そうだ。人型から獣型に姿を変えて近寄り、服の袖を噛んでぐいぐいと引っ張る。
「へっ!?」
素っ頓狂な声を漏らし、少女は弾かれたように顔を上げた。人間という生き物は小動物に弱く、甘えるように頭を擦り寄せれば大体油断してくれるらしい。図書室で読んだ書物にはそう書いてあった。今こそ実践するときだと目論んだのだけれど、少女の顔を真正面から見て――固まってしまった。
大きな瞳はガラス玉のようで、日の差さない黒い森でも反射してきらきらしい。丸い頬は泣きすぎたせいか、ヤマモモのように赤くて美味しそうだ。驚いているのだろう、これ以上ないぐらいに目をまん丸くしている。ぽかんと口を開けた顔はあどけなくて、どうしてか自分でもわからないぐらい釘付けになってしまった。
「やぎさんだ……」
呆けたように、呟く声が鼓膜に響いてぞくぞくする。当初の狙い通り、今の少女には油断と隙だらけだ。今のうちに指の二、三本、パクッといただいて逃げ出せばいい。だというのに、心臓がバクバクして、顔が熱くて、魔法でもかけられたようにその場から動けない。山羊の姿で良かった、人型だと顔が真っ赤になっているのが一瞬でバレていただろう。
「けがしてるの?」
少女は、血の出ている後ろ足に目を留めた。「いたそう……」と顔を顰める少女だけれど、よくよく見ると彼女も膝から血を流している。だから泣いていたのだろうか、となんとなく思った。少女は、「まっててね」と呟くと、腰に提げていた袋をガサゴソと漁る。水筒から出した水でハンカチを濡らすと、ニグラスの足から流れる血を丁寧に拭った。
「もうだいじょうぶだよ」
そう言って安心させるように微笑む。自分の膝は血が出たままで拭ってもいないのに、通りがかった山羊の手当を優先するなんて。言いようのない感情が胸の奥から湧き上がる。子供の魔獣や、可愛いと周りから言われる幼馴染を見ても抱いたことのない感情。胸がきゅうっと締め付けられて直視できないのに、ずっと見ていたくて目を離すことができない。
――かわいい。
気づけば、吸い寄せられるように膝の傷口に顔を寄せていた。ペロ、と舐めると体中に熱が巡っていくような感覚がする。夢中になって舐めていると、少女の手が頭に触れた。よしよしと撫でられると、鳩尾のあたりが熱い。今、角に触れられたら少女の手は間違いなく火傷してしまうだろう。どうか手が当たりませんように、と一生懸命願った。「やぎさん、かわいい。かわいいね」と、舌足らずに繰り返しながら、少女はニグラスの頭を撫で続ける。
「やぎさん、お名前はなんていうの? わたしはエメリっていうの」
――エメリって言うんだ。僕はニグラス。
「お名前ないならわたしがつけてもいい?」
――うん、好きにしていいよ。
「うーん……くろい毛がすてきだから、クロとか」
――いい名前だね。
語りかけてくれる言葉に返事をするけれど、少女には伝わらない。メエメエと鳴いているだけにしか聞こえないだろう。クロ、だなんて安直な名前だけれど、エメリが名付けてくれるならなんでもいい。今日からクロと名乗ろうと決めた。
「……ねえ、クロ。クロは、迷子?」
ニグラスを撫でるエメリの手が止まる。顔を上げると、大きな瞳からポロポロと涙が溢れるのが見えた。エメリは肩を震わせ、唇を戦慄かせる。眉間にグッと力を込め、「わたし、わたしはね、迷子なんだぁ……」とくちゃくちゃになった顔で笑おうとするのが痛々しい。口にすると不安が増したのか、後から後から雫が溢れる。ニグラスの傷口を拭ってくれたように、頬を濡らす涙を拭ってやりたかったが山羊の姿では叶わない。
――エメリ、泣かないで。
おろおろと慰めようとするけれど、口から出るのはメエメエという鳴き声ばかり。いっそ人型に戻ろうかと悩んだけれど、驚かせてしまうことを危惧した。怖がらせてしまったら、逃げられてしまったら、もう二度と会えなくなってしまったら、どうしよう。そう思うと、戻るに戻れない。小さな黒山羊は泣きじゃくるエメリに一生懸命声をかけるけれど、何の役にも立たない。エメリはぎゅう、とニグラスを抱きしめると耳元で呟いた。
「おうちに、かえりたいなぁ……」
縋り付くようにぎゅうぎゅうと抱きしめられても、その小さな背中に腕を回せないことが悔しい。わんわんと火がついたように泣き出すエメリに、ニグラスは返事をする。とは言っても、口から出るのはやはりメエメエという鳴き声だけなのだけれど。
――いいよ、エメリ。僕がおうちに連れてってあげる。
――エメリの願いはなんでも叶えてあげる。
ぽろぽろとこぼれ落ちる涙がニグラスの顔を濡らした。お腹の奥が熱くなり、どこからか風がぶわりと吹き込む。次の瞬間、エメリとニグラスは黒い森の外にいた。
*
「クロにあいたい」
エメリがどこかでそう願った気がする。慌てて山羊の姿に変身すると、風がぶわりと吹いた瞬きのうちに景色が変わった。掠め取ってしまった寿命を咀嚼すると、魔力が体内で巡る感覚。守護の力を持つ人間の一部を取り込むと、魔力が上がるというのは後から知ったこと。今ではすっかり見慣れてしまった内装を見ていると、「クロ!」と弾むような声で名前を呼ばれた。
「あいたかった、クロ」
ぎゅうっと抱きつかれて顔が熱くなるけれど、山羊の姿だからバレることはない。しばらく抱きついて満足したのか、エメリは体を離す。温もりが離れていくことに名残惜しさを覚えたけれど、メエメエと鳴くことしかできない。「きょうはね、たんぽぽをつんだの。食べる?」と差し出されたたんぽぽをモサモサと食みながらエメリの様子を眺めた。山羊の姿とはいえ、味覚は人型のときと変わらない。たんぽぽを特別美味しいと思ったことはないけれど、エメリがくれるのならなんでもよかった。ニグラスが咀嚼する姿を眺めながら、エメリはぽつぽつと言葉を紡ぎはじめる。
「あのね、きょうもね、いっぱいがんばったの」
ニグラスがたんぽぽを飲み込むのを見届けると膝に抱き上げ、植物図鑑を開く。初めて黒い森で会って以降、度々エメリに呼び出されてはこうして山羊の姿で話を聞いている。瘴気のないところでは生きていけないニグラスが、黒い森の外に出られるのは至極単純。エメリと契約してしまったからだ。名前をつけられて血を飲むと、契約関係を結ぶことになる。人間と魔族の契約について、うっすらと聞いたことはあったけれどまさかその当事者になってしまうとは。ましてや、将来勇者となるかもしれない女の子とだなんて思いもよらなかった。
後から知ったことだけれど、エメリは勇者の一族に生まれた子供だ。あの日黒い森にいたのは、守護の力を伸ばす訓練だったらしい。魔獣を十匹倒すまで戻ってくるなと言いつけられていたのに、一匹も倒せないままに戻ってきたエメリに父親は冷たかった。まだ幼いエメリに、勇者になるための厳しい稽古を来る日も来る日もつけている。ニグラスが呼び出される日は決まって厳しく扱かれたときで、今日も同様であることは顔に貼られた大きなガーゼが物語っていた。ニグラスを撫でるもちもちの手は、マメのせいで初めて会ったときと感触が違う。
――この手に、マメはきっと似合わないのに。
皮が剥けて、血が滲んでいるときだってある。ニグラスにしがみついたまま、泣きじゃくることだってある。けれど、それでもエメリが稽古から逃げることはなかった。逃げ出したいと口にしてさえくれれば、どこへでも連れていくのに。エメリが願うなら、なんだって叶えるのに。エメリは自分が魔族と契約してしまったことを知らないし、ニグラスに会いたいと願うたびに寿命が少しずつ減っていることにも気づいていない。知らないから口にしないのだろうかと思ったけれど、知っていたとしても願ったかどうかはわからない。
「わたしね、勇者にはむいてないの。でも、がんばらないといけないの」
まるで、それが自分の役目だと自らに言い聞かせるようにして呟く。エメリが願っていないのなら、望んでいないのなら、ニグラスにできることはない。できることは、力一杯抱きしめられるのを受け止めることだけだ。ニグラスをぎゅうぎゅうと抱きしめながら、エメリは植物図鑑を無言で捲る。ここ一週間ほど、呼び出されるたびに一緒に読んでいる気がするけれど、最近のお気に入りなのだろうか。
「クロ、くすしって知ってる? お花とか葉っぱとかでくすりをつくるの」
そう言ってぽつぽつと語り始めたのは、初めて聞く話だった。黒い森から戻ってきたときに、テキパキと塗り薬を作ってくれた薬師の姿がかっこよかったといつもより興奮したように語ってくれる。薬師、という存在はニグラスもよく知らなかったけれど、エメリがそこまで褒めるのならきっと素敵な職業なのだろう。相槌のように鳴き声を溢す。ニグラスが反応を返すこと自体が嬉しいのか、ご機嫌に頭を撫でられ心臓がバクバクした。初めて会ったときから、ニグラスの心臓は忙しない。
そうして一緒に過ごすこと数時間。眠気が限界にまで達したらしい。本を開いたままで、うとうとするエメリの腕からそっと抜け出す。契約のおかげで瘴気のないところでも生きていけるとはいえ、なるべく瘴気のあるところで生きていたいし、そもそもニグラスは魔族だ。幼いエメリは気づいていないようだけれど、父親に見られたら確実に魔族だと見抜かれてしまう。正直、返り討ちにするぐらいは容易いけれど、それで魔族であることがバレてエメリと一緒にいられなくなることは嫌だった。
そういうわけで、今日もこっそり帰ろうとしたのだけれど。
「クロ、どっかいっちゃうの?」
今日のエメリはまだ眠らないらしい。瞼を擦りながら、とことことニグラスのところまで歩いてくる。眠たそうにしてるのも可愛い、なんて思っているとぎゅうっと抱きしめられどこにもいけなくなってしまった。
「クロが、家族だったらよかったのに」
ぽそ、と呟く声がニグラスの鼓膜に響く。
「くすしになって、クロと家族になって、ずっとしあわせにくらしたい」
そうだったらいいのに、と呟く声がニグラスの心臓に突き刺さる。今、角に触れられたら溢れんばかりの感情がエメリに流れ込んでしまうだろう。山羊の姿をとっているけれど、こんなに密着していては心臓の音が聞こえてしまうかもしれない。ドキドキとうるさい心臓の音を耳にしながら、ニグラスはとあることを決意した。
ぽそりとエメリが呟いてからどれほど経ったのだろう。急に抱きつく力が弱まったかと思うと、ガクンと体が崩れ落ちる。咄嗟に人型に変身して受け止めたけれど、気づかれることはなかった。どうやら、抱きついたままで眠ってしまったらしい。今日も厳しい稽古に耐えてきたのだ、睡魔に襲われ眠気が限界だったに違いない。寝息が規則正しいのを確認してから、小さな体を抱き上げてベッドに寝かせる。シーツをかけてやりながら、こっそりと名前を呼んだ。
「エメリ……」
すやすやと眠るエメリをじっと見つめる。薬師になって、ニグラスと家族になって、ずっと幸せに暮らすこと。愛おしくてたまらない、大好きな女の子の願い。心臓はずっとうるさくて、顔も熱い。人型なのをいいことに抱きしめてしまいたい気持ちをグッと堪える。
――そんなの、願わなくたって叶えるのに。
けれど、そういうわけにはいかない。人間と魔族の間で契約を結んでいる以上、無償で叶えることはできないのだ。人間が寿命で死ぬまで破棄することはできず、願いを叶える代わりに対価を受け取らなければならない。ニグラスは考えた末に、一つの結論を出す。
「エメリの願いは、なんでも叶えてあげる」
ニグラスは考えた。自分が魔王になれば、必ずエメリは勇者として討伐にやってくる。王国で唯一守護の力を宿した、勇者の一族に生まれた子供なのだから。やってきたエメリと家族になれば、他の魔族も簡単に手出しはできないだろう。王国には帰さないで、もう勇者なんてやらなくていいよと言ってあげて、薬師になれるように手助けをすれば。そうすれば、きっとずっと幸せに暮らせる。エメリの願いは全て叶えることができる。
眠るエメリの額に手をかざす。エメリに呼び出されるたびにこっそり掠め取っていた寿命一ヶ月分。それだけでも魔力が底上げされている感覚はあるのだから、守護の力の威力はあらゆる意味で絶大だ。けれど、問題は受け取る対価が寿命だということ。大切なものなら別になんでもいいのだけれど、エメリにあまり影響のない範囲だとちょうどいいのは寿命ぐらいだったのだ。とはいえ、会う機会が重なれば、貰う寿命も当然積み重なる。ただでさえ人間と魔族の寿命は違うのだ。これ以上、エメリと一緒に過ごせる時間を縮めたくはなかった。
――寿命じゃなくて、例えば。魂と深く結びつく、記憶をもらえたなら。
ニグラスと過ごした時間を全て貰えば、あとはニグラスの努力次第で魔王になれるだろう。絶望的に勇者に向いていないエメリと違って、ニグラスはきっと魔王に向いているのだから。
額にかざす手に魔力を込めると、「んっ……」とエメリが眉を顰める。額からふわふわと溢れる光を吸い取ると、知っている記憶が流れ込んできた。黒い森で迷子になったときのこと、初めて会ったときのこと、この部屋でたくさん話を聞いたこと。ニグラスの視点からでしか知り得なかった思い出が、エメリの視点で流れてくる。
「おやすみ、エメリ。大好きだよ」
――きみのために、僕は魔王になるよ。
――そしたら、会いにきてね。
光が全て体内に入り込むと同時に、今までの非にならない魔力が巡るのを感じる。思った通り、エメリの記憶は守護の力と強く結びついていたらしい。忘れられてしまうのは悲しいけれど、そもそもエメリの中では「クロ」であって「ニグラス」ではない。それなら、初めましてからやり直すのもいいかもしれない。
身を屈め、そっとエメリの唇に自身のそれを重ねる。初めて触れる唇は柔らかくて、一生忘れられないんだろうなと思った。
*
ぱち、と瞬くと周囲は真っ暗だった。目を閉じても開いても変わらない、周囲の様子が何もわからないほどの暗闇。をひたすらに歩く。自分の姿は見えないけれど、右手に何の感覚もない。知らないうちに取れてしまったのだろうか。
――エメリはどこだろう。
ぼんやりと考える。可愛くてたまらない、大好きな女の子。魔王になって会いにきてくれたけれど、当然ニグラスのことなんて知るはずもないし、クロのことも覚えていない。自分で決めてそうしたのに、途方もない寂しさに襲われたけれどそれも一瞬。エメリと結婚して、家族になって、楽しそうに薬を調合している姿を隣で眺めるのは幸福だった。本人は照れくさそうに「薬師の真似事」だなんて言っていたけれど、十分だと思う。
――会いたいな。
「クロ」
突然、何もない暗闇にエメリが――初めて会ったときのエメリが現れた。ガラス玉のような瞳も、まん丸の頬も、ニグラスの記憶と変わりない。ニグラスも小さくなったのだろうか、目線の高さが同じだ。なんで僕だってわかったんだろうと首を傾げていると、小さなエメリはニグラスの右手に手を伸ばす。そこには何もないよ、と言おうとしたけれど。
「もうだいじょうぶだよ」
その言葉通り、というべきか。握られた右手に感覚が戻っていく。痛みはない。その代わり、頭にとてつもない激痛が走ったけれど、それも一瞬だった。ありがとうとお礼を告げる前に、エメリはニグラスの右手をそのまま引く。どこにいくのかわからないけれど、ついていけばいいのだろうか。てくてくと暗闇の中を当てもなく歩いていると、エメリは急に立ち止まって振り返った。もちもちだけれどマメのある両手がニグラスの頬を包む。
「クロ、起きて」
願うようにそう告げると、エメリの顔が徐々に近づく。ばくばくと鳴り始めた心臓の音は、エメリに聞こえているだろうか。あのとき口付けた唇が、目の前にある。あと少しで唇が触れる、というところでそっと目を閉じた。
「うえぇ……」
膝に顔を埋めて泣きじゃくる少女は、黒い森にいるはずのない人間の女の子。どうしてこんなところに、と思ったのも一瞬。そんなことは気にならなくなるぐらい、少女からは美味しそうな匂いがした。幼いニグラスは、守護の力という概念を知らない。が、魔族としての本能が、目の前の少女を食べれば魔力が上がるということを知らせる。マルコと喧嘩したせいで怪我した足は、指の二、三本食べればすぐに治るだろう。幸い、少女はニグラスの存在に気づいていない。油断させてから食べてしまうのは容易そうだ。人型から獣型に姿を変えて近寄り、服の袖を噛んでぐいぐいと引っ張る。
「へっ!?」
素っ頓狂な声を漏らし、少女は弾かれたように顔を上げた。人間という生き物は小動物に弱く、甘えるように頭を擦り寄せれば大体油断してくれるらしい。図書室で読んだ書物にはそう書いてあった。今こそ実践するときだと目論んだのだけれど、少女の顔を真正面から見て――固まってしまった。
大きな瞳はガラス玉のようで、日の差さない黒い森でも反射してきらきらしい。丸い頬は泣きすぎたせいか、ヤマモモのように赤くて美味しそうだ。驚いているのだろう、これ以上ないぐらいに目をまん丸くしている。ぽかんと口を開けた顔はあどけなくて、どうしてか自分でもわからないぐらい釘付けになってしまった。
「やぎさんだ……」
呆けたように、呟く声が鼓膜に響いてぞくぞくする。当初の狙い通り、今の少女には油断と隙だらけだ。今のうちに指の二、三本、パクッといただいて逃げ出せばいい。だというのに、心臓がバクバクして、顔が熱くて、魔法でもかけられたようにその場から動けない。山羊の姿で良かった、人型だと顔が真っ赤になっているのが一瞬でバレていただろう。
「けがしてるの?」
少女は、血の出ている後ろ足に目を留めた。「いたそう……」と顔を顰める少女だけれど、よくよく見ると彼女も膝から血を流している。だから泣いていたのだろうか、となんとなく思った。少女は、「まっててね」と呟くと、腰に提げていた袋をガサゴソと漁る。水筒から出した水でハンカチを濡らすと、ニグラスの足から流れる血を丁寧に拭った。
「もうだいじょうぶだよ」
そう言って安心させるように微笑む。自分の膝は血が出たままで拭ってもいないのに、通りがかった山羊の手当を優先するなんて。言いようのない感情が胸の奥から湧き上がる。子供の魔獣や、可愛いと周りから言われる幼馴染を見ても抱いたことのない感情。胸がきゅうっと締め付けられて直視できないのに、ずっと見ていたくて目を離すことができない。
――かわいい。
気づけば、吸い寄せられるように膝の傷口に顔を寄せていた。ペロ、と舐めると体中に熱が巡っていくような感覚がする。夢中になって舐めていると、少女の手が頭に触れた。よしよしと撫でられると、鳩尾のあたりが熱い。今、角に触れられたら少女の手は間違いなく火傷してしまうだろう。どうか手が当たりませんように、と一生懸命願った。「やぎさん、かわいい。かわいいね」と、舌足らずに繰り返しながら、少女はニグラスの頭を撫で続ける。
「やぎさん、お名前はなんていうの? わたしはエメリっていうの」
――エメリって言うんだ。僕はニグラス。
「お名前ないならわたしがつけてもいい?」
――うん、好きにしていいよ。
「うーん……くろい毛がすてきだから、クロとか」
――いい名前だね。
語りかけてくれる言葉に返事をするけれど、少女には伝わらない。メエメエと鳴いているだけにしか聞こえないだろう。クロ、だなんて安直な名前だけれど、エメリが名付けてくれるならなんでもいい。今日からクロと名乗ろうと決めた。
「……ねえ、クロ。クロは、迷子?」
ニグラスを撫でるエメリの手が止まる。顔を上げると、大きな瞳からポロポロと涙が溢れるのが見えた。エメリは肩を震わせ、唇を戦慄かせる。眉間にグッと力を込め、「わたし、わたしはね、迷子なんだぁ……」とくちゃくちゃになった顔で笑おうとするのが痛々しい。口にすると不安が増したのか、後から後から雫が溢れる。ニグラスの傷口を拭ってくれたように、頬を濡らす涙を拭ってやりたかったが山羊の姿では叶わない。
――エメリ、泣かないで。
おろおろと慰めようとするけれど、口から出るのはメエメエという鳴き声ばかり。いっそ人型に戻ろうかと悩んだけれど、驚かせてしまうことを危惧した。怖がらせてしまったら、逃げられてしまったら、もう二度と会えなくなってしまったら、どうしよう。そう思うと、戻るに戻れない。小さな黒山羊は泣きじゃくるエメリに一生懸命声をかけるけれど、何の役にも立たない。エメリはぎゅう、とニグラスを抱きしめると耳元で呟いた。
「おうちに、かえりたいなぁ……」
縋り付くようにぎゅうぎゅうと抱きしめられても、その小さな背中に腕を回せないことが悔しい。わんわんと火がついたように泣き出すエメリに、ニグラスは返事をする。とは言っても、口から出るのはやはりメエメエという鳴き声だけなのだけれど。
――いいよ、エメリ。僕がおうちに連れてってあげる。
――エメリの願いはなんでも叶えてあげる。
ぽろぽろとこぼれ落ちる涙がニグラスの顔を濡らした。お腹の奥が熱くなり、どこからか風がぶわりと吹き込む。次の瞬間、エメリとニグラスは黒い森の外にいた。
*
「クロにあいたい」
エメリがどこかでそう願った気がする。慌てて山羊の姿に変身すると、風がぶわりと吹いた瞬きのうちに景色が変わった。掠め取ってしまった寿命を咀嚼すると、魔力が体内で巡る感覚。守護の力を持つ人間の一部を取り込むと、魔力が上がるというのは後から知ったこと。今ではすっかり見慣れてしまった内装を見ていると、「クロ!」と弾むような声で名前を呼ばれた。
「あいたかった、クロ」
ぎゅうっと抱きつかれて顔が熱くなるけれど、山羊の姿だからバレることはない。しばらく抱きついて満足したのか、エメリは体を離す。温もりが離れていくことに名残惜しさを覚えたけれど、メエメエと鳴くことしかできない。「きょうはね、たんぽぽをつんだの。食べる?」と差し出されたたんぽぽをモサモサと食みながらエメリの様子を眺めた。山羊の姿とはいえ、味覚は人型のときと変わらない。たんぽぽを特別美味しいと思ったことはないけれど、エメリがくれるのならなんでもよかった。ニグラスが咀嚼する姿を眺めながら、エメリはぽつぽつと言葉を紡ぎはじめる。
「あのね、きょうもね、いっぱいがんばったの」
ニグラスがたんぽぽを飲み込むのを見届けると膝に抱き上げ、植物図鑑を開く。初めて黒い森で会って以降、度々エメリに呼び出されてはこうして山羊の姿で話を聞いている。瘴気のないところでは生きていけないニグラスが、黒い森の外に出られるのは至極単純。エメリと契約してしまったからだ。名前をつけられて血を飲むと、契約関係を結ぶことになる。人間と魔族の契約について、うっすらと聞いたことはあったけれどまさかその当事者になってしまうとは。ましてや、将来勇者となるかもしれない女の子とだなんて思いもよらなかった。
後から知ったことだけれど、エメリは勇者の一族に生まれた子供だ。あの日黒い森にいたのは、守護の力を伸ばす訓練だったらしい。魔獣を十匹倒すまで戻ってくるなと言いつけられていたのに、一匹も倒せないままに戻ってきたエメリに父親は冷たかった。まだ幼いエメリに、勇者になるための厳しい稽古を来る日も来る日もつけている。ニグラスが呼び出される日は決まって厳しく扱かれたときで、今日も同様であることは顔に貼られた大きなガーゼが物語っていた。ニグラスを撫でるもちもちの手は、マメのせいで初めて会ったときと感触が違う。
――この手に、マメはきっと似合わないのに。
皮が剥けて、血が滲んでいるときだってある。ニグラスにしがみついたまま、泣きじゃくることだってある。けれど、それでもエメリが稽古から逃げることはなかった。逃げ出したいと口にしてさえくれれば、どこへでも連れていくのに。エメリが願うなら、なんだって叶えるのに。エメリは自分が魔族と契約してしまったことを知らないし、ニグラスに会いたいと願うたびに寿命が少しずつ減っていることにも気づいていない。知らないから口にしないのだろうかと思ったけれど、知っていたとしても願ったかどうかはわからない。
「わたしね、勇者にはむいてないの。でも、がんばらないといけないの」
まるで、それが自分の役目だと自らに言い聞かせるようにして呟く。エメリが願っていないのなら、望んでいないのなら、ニグラスにできることはない。できることは、力一杯抱きしめられるのを受け止めることだけだ。ニグラスをぎゅうぎゅうと抱きしめながら、エメリは植物図鑑を無言で捲る。ここ一週間ほど、呼び出されるたびに一緒に読んでいる気がするけれど、最近のお気に入りなのだろうか。
「クロ、くすしって知ってる? お花とか葉っぱとかでくすりをつくるの」
そう言ってぽつぽつと語り始めたのは、初めて聞く話だった。黒い森から戻ってきたときに、テキパキと塗り薬を作ってくれた薬師の姿がかっこよかったといつもより興奮したように語ってくれる。薬師、という存在はニグラスもよく知らなかったけれど、エメリがそこまで褒めるのならきっと素敵な職業なのだろう。相槌のように鳴き声を溢す。ニグラスが反応を返すこと自体が嬉しいのか、ご機嫌に頭を撫でられ心臓がバクバクした。初めて会ったときから、ニグラスの心臓は忙しない。
そうして一緒に過ごすこと数時間。眠気が限界にまで達したらしい。本を開いたままで、うとうとするエメリの腕からそっと抜け出す。契約のおかげで瘴気のないところでも生きていけるとはいえ、なるべく瘴気のあるところで生きていたいし、そもそもニグラスは魔族だ。幼いエメリは気づいていないようだけれど、父親に見られたら確実に魔族だと見抜かれてしまう。正直、返り討ちにするぐらいは容易いけれど、それで魔族であることがバレてエメリと一緒にいられなくなることは嫌だった。
そういうわけで、今日もこっそり帰ろうとしたのだけれど。
「クロ、どっかいっちゃうの?」
今日のエメリはまだ眠らないらしい。瞼を擦りながら、とことことニグラスのところまで歩いてくる。眠たそうにしてるのも可愛い、なんて思っているとぎゅうっと抱きしめられどこにもいけなくなってしまった。
「クロが、家族だったらよかったのに」
ぽそ、と呟く声がニグラスの鼓膜に響く。
「くすしになって、クロと家族になって、ずっとしあわせにくらしたい」
そうだったらいいのに、と呟く声がニグラスの心臓に突き刺さる。今、角に触れられたら溢れんばかりの感情がエメリに流れ込んでしまうだろう。山羊の姿をとっているけれど、こんなに密着していては心臓の音が聞こえてしまうかもしれない。ドキドキとうるさい心臓の音を耳にしながら、ニグラスはとあることを決意した。
ぽそりとエメリが呟いてからどれほど経ったのだろう。急に抱きつく力が弱まったかと思うと、ガクンと体が崩れ落ちる。咄嗟に人型に変身して受け止めたけれど、気づかれることはなかった。どうやら、抱きついたままで眠ってしまったらしい。今日も厳しい稽古に耐えてきたのだ、睡魔に襲われ眠気が限界だったに違いない。寝息が規則正しいのを確認してから、小さな体を抱き上げてベッドに寝かせる。シーツをかけてやりながら、こっそりと名前を呼んだ。
「エメリ……」
すやすやと眠るエメリをじっと見つめる。薬師になって、ニグラスと家族になって、ずっと幸せに暮らすこと。愛おしくてたまらない、大好きな女の子の願い。心臓はずっとうるさくて、顔も熱い。人型なのをいいことに抱きしめてしまいたい気持ちをグッと堪える。
――そんなの、願わなくたって叶えるのに。
けれど、そういうわけにはいかない。人間と魔族の間で契約を結んでいる以上、無償で叶えることはできないのだ。人間が寿命で死ぬまで破棄することはできず、願いを叶える代わりに対価を受け取らなければならない。ニグラスは考えた末に、一つの結論を出す。
「エメリの願いは、なんでも叶えてあげる」
ニグラスは考えた。自分が魔王になれば、必ずエメリは勇者として討伐にやってくる。王国で唯一守護の力を宿した、勇者の一族に生まれた子供なのだから。やってきたエメリと家族になれば、他の魔族も簡単に手出しはできないだろう。王国には帰さないで、もう勇者なんてやらなくていいよと言ってあげて、薬師になれるように手助けをすれば。そうすれば、きっとずっと幸せに暮らせる。エメリの願いは全て叶えることができる。
眠るエメリの額に手をかざす。エメリに呼び出されるたびにこっそり掠め取っていた寿命一ヶ月分。それだけでも魔力が底上げされている感覚はあるのだから、守護の力の威力はあらゆる意味で絶大だ。けれど、問題は受け取る対価が寿命だということ。大切なものなら別になんでもいいのだけれど、エメリにあまり影響のない範囲だとちょうどいいのは寿命ぐらいだったのだ。とはいえ、会う機会が重なれば、貰う寿命も当然積み重なる。ただでさえ人間と魔族の寿命は違うのだ。これ以上、エメリと一緒に過ごせる時間を縮めたくはなかった。
――寿命じゃなくて、例えば。魂と深く結びつく、記憶をもらえたなら。
ニグラスと過ごした時間を全て貰えば、あとはニグラスの努力次第で魔王になれるだろう。絶望的に勇者に向いていないエメリと違って、ニグラスはきっと魔王に向いているのだから。
額にかざす手に魔力を込めると、「んっ……」とエメリが眉を顰める。額からふわふわと溢れる光を吸い取ると、知っている記憶が流れ込んできた。黒い森で迷子になったときのこと、初めて会ったときのこと、この部屋でたくさん話を聞いたこと。ニグラスの視点からでしか知り得なかった思い出が、エメリの視点で流れてくる。
「おやすみ、エメリ。大好きだよ」
――きみのために、僕は魔王になるよ。
――そしたら、会いにきてね。
光が全て体内に入り込むと同時に、今までの非にならない魔力が巡るのを感じる。思った通り、エメリの記憶は守護の力と強く結びついていたらしい。忘れられてしまうのは悲しいけれど、そもそもエメリの中では「クロ」であって「ニグラス」ではない。それなら、初めましてからやり直すのもいいかもしれない。
身を屈め、そっとエメリの唇に自身のそれを重ねる。初めて触れる唇は柔らかくて、一生忘れられないんだろうなと思った。
*
ぱち、と瞬くと周囲は真っ暗だった。目を閉じても開いても変わらない、周囲の様子が何もわからないほどの暗闇。をひたすらに歩く。自分の姿は見えないけれど、右手に何の感覚もない。知らないうちに取れてしまったのだろうか。
――エメリはどこだろう。
ぼんやりと考える。可愛くてたまらない、大好きな女の子。魔王になって会いにきてくれたけれど、当然ニグラスのことなんて知るはずもないし、クロのことも覚えていない。自分で決めてそうしたのに、途方もない寂しさに襲われたけれどそれも一瞬。エメリと結婚して、家族になって、楽しそうに薬を調合している姿を隣で眺めるのは幸福だった。本人は照れくさそうに「薬師の真似事」だなんて言っていたけれど、十分だと思う。
――会いたいな。
「クロ」
突然、何もない暗闇にエメリが――初めて会ったときのエメリが現れた。ガラス玉のような瞳も、まん丸の頬も、ニグラスの記憶と変わりない。ニグラスも小さくなったのだろうか、目線の高さが同じだ。なんで僕だってわかったんだろうと首を傾げていると、小さなエメリはニグラスの右手に手を伸ばす。そこには何もないよ、と言おうとしたけれど。
「もうだいじょうぶだよ」
その言葉通り、というべきか。握られた右手に感覚が戻っていく。痛みはない。その代わり、頭にとてつもない激痛が走ったけれど、それも一瞬だった。ありがとうとお礼を告げる前に、エメリはニグラスの右手をそのまま引く。どこにいくのかわからないけれど、ついていけばいいのだろうか。てくてくと暗闇の中を当てもなく歩いていると、エメリは急に立ち止まって振り返った。もちもちだけれどマメのある両手がニグラスの頬を包む。
「クロ、起きて」
願うようにそう告げると、エメリの顔が徐々に近づく。ばくばくと鳴り始めた心臓の音は、エメリに聞こえているだろうか。あのとき口付けた唇が、目の前にある。あと少しで唇が触れる、というところでそっと目を閉じた。