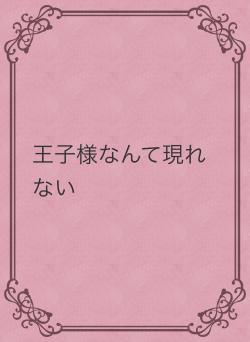「おい」
「……」
「おい!」
「わっ!? あっ、ま、マルコ!?」
どうしてここに、と尋ねる前に額を弾かれた。「痛っ!?」と額を抑えていると、「ほらよ」とバスケットを手渡される。ずしりと重いそれが何か、開ける前からわかっていた。使いっ走りにされた魔王に、「ありがとう」とお礼を告げるけれど眉間の皺は無くならない。ノックの音にも呼びかける声にも気づかなかったから不機嫌なのだろうか。
「食え」
「へ」
「お前が食い終わるのを見届けてから帰ってこいって双子に言われてんだよ」
双子は手が離せないんだとよ、と言いながらマルコはエメリを強引に椅子に座らせると、自身もどかりと腰を下ろす。まだ作業が一段落してないのに、と思ったけれど魔王の威圧感には敵わない。バスケットを開け、サンドイッチをもさもさと頬張る。アイスティーと一緒に流し込むのを、マルコは表情ひとつ変えずに見つめている。魔王に監視されながらの食事って緊張感あるな、とどうでもいいことを考えながら、ここ一週間のことを思い返した。
*
魔王城に着いてすぐ、嘔吐して意識を失ったエメリ。次に目が覚めたときには、どこかのベッドに寝かされていた。ゆっくりと目を瞬かせると、クリアになった視界に見慣れた天井が映る。木目調の天井と、吊り下げられた裸電球は見間違えるはずもない。魔王城で一番多くの時間を過ごしている、調合小屋だ。
――なんで……?
起き上がって辺りを見回してみても、間違いない。薬草棚も、作業台も、薬研も、すり鉢も、小鍋も。見慣れた道具の数々が、この場所がエメリの馴染みの場所だということを教えてくれる。違和感があるのはエメリが寝かされていたベッドと――小屋の一番奥にある扉だけだ。エメリの把握している限り、この小屋に寝具なんてものも、入り口以外の扉もなかったはずだ。誰が作ったものなのだろう。
「やっと起きたか?」
「! マルコ……」
ノックもなしに扉を開けてズカズカと入ってきたのは、つい最近魔王となった男。後ろ手に扉を閉めたマルコは、作業用の椅子を引っ張ってきてベッドの近くに腰掛けた。リリとリムではなく、マルコが様子を見にきたのは契約したからなのだろうか。ベッドと扉を取り付けたのは誰なのだろうか。聞きたいことがたくさんあるけれど、まずは。
「私、どうしてここにいるの?」
「あ?」
「なんで寝室とかじゃなくて調合小屋なのかと思って」
黒い森の瘴気は魔王城中に満ちている。どこに運ばれたところで変わりないのはわかっているが、それにしたってどうして調合小屋だったのか。しかもわざわざベッドを置いてまで。マルコをじっと見つめていると、「お前まさか知らねえのか?」と衝撃を受けたようにに目を丸くした。
「この小屋と温室をニグラスが作ったことは?」
「知ってる」
「じゃあ小屋と温室だけは瘴気が流れ込まないってことは?」
今度はエメリが衝撃を受ける番だった。目を丸くするエメリが何も知らないことを察したのだろう。マルコは、「温室にある薬草の中に、王国に生えてるようなのがあるだろ?」と口を開く。
「う、うん」
「そういう薬草は黒い森では生息できない。瘴気に当てられるのは人間と変わらねえんだよ」
「そうなんだ……」
初耳である。王国でも見かけたような草花があるんだ、としか思っていなかったが、当たり前のことではなかったらしい。だから眩暈も吐き気もしないのか、とホッとするのと同時にこれまでのあれこれが腑に落ちる。エメリの様子を見にきたのが双子でないのは、瘴気のない場所で魔族は活動できないから。マルコが様子を見にきたのは、エメリと契約している影響で瘴気がなくても活動できるから。以前、ニグラスが温室で一人ぶつぶつと何か呟いていたのは、瘴気が流れ込まないように魔法をかけていたからだろう。彼もまた人間の誰かと契約しているようだから、瘴気がなくても温室や小屋に入れたというわけだ。
「ベッドをここに置いてくれたのはマルコ?」
「ああ。床に寝かせようとしたら、双子が扉の外からギャンギャンうるせえのなんの」
顔を顰めるマルコに苦笑する。やいのやいのと扉の外から指示を飛ばしたのであろう双子には後でどうにかして感謝を伝えるとして、「ありがとう」とまずはマルコに感謝する。
「まあ、お前が死にかけたら俺も割を食うからな」
しゃーなしだ、と呟くマルコ。そういえば以前ニグラスが、「契約主が寿命以外で死にかけたら、僕の生命力を渡すことになってる」と言っていた気がする。守護の力で死にかけたエメリは言うなれば、「寿命以外で死にかけた」状態そのものだったはずだ。実際、もう二度と目を覚ますことはないのだろうと薄れゆく意識の中で覚悟したことは覚えている。だというのに、無事に目を覚ましたのはマルコの生命力を大なり小なり奪ってしまったからなのだろうか。
「あの……ごめんなさい」
「はあ? なんでだよ」
「私のせいで、迷惑かけて……」
ごめんなさい、と再び頭を下げるエメリ。契約に応じ、願いを叶えて魔王になってくれたけれど、エメリが死にかけたせいで迷惑をかけてしまった。対価を支払ったとはいえ、本来必要のない契約なのだ。責められても仕方がないと思ったけれど、「別にいい」と意外にもマルコの返答は冷たいものではない。
「それより、とっとと回復してそこで寝こけてる山羊起こせ」
「へ?」
そこ、とマルコが親指で指したのは小屋に突然現れた扉。慌ててベッドから降りて扉を開くと、薄暗い部屋にはベッドが一つ。恐る恐る近づくと、エメリの想い人が以前と変わらずに眠っている。「寝室のままだとお前が入れねえからな。部屋作ってこっちに運んできた」となんでもないように告げるマルコに心の底から感謝した。
双子に飯を用意させる、と言ってマルコはその場を立ち去る。後に残されたエメリは、ニグラスが寝かされているベッドに崩れ落ちるように跪いた。室内が暗いせいか、最後に見たときより心なしか顔色が悪い。が、胸が上下しているのを見てどうしようもなく安堵した。目を覚ます気配もないまま眠り込んでいるけれど、間違いなく生きている。その事実が何より嬉しかった。体の上で組まれている左手をそっと握る。指輪に触れ、誓うように呟いた。
「待っててね、ニグラス」
*
そうして一週間が経った。
守護の力を失ったエメリは魔王城に入れない。図書室の書物を読みたいときはマルコか、双子に頼むしかない。双子は毎日、小屋の入り口まで来てくれる。食料を届けに、頼んでいた書物を届けに、エメリを励ましに。守護の力を失ったエメリが魔族に襲われないかという懸念もあったけれど、新しく魔王となったマルコの契約主だということが幸いした。温室に向かうため外に出るときは毎回緊張が訪れるけれど、どうにか無事に薬草の採取ができている。
しかし、状況は芳しくない。あらゆる国で作られている眠気覚ましの薬や回復薬を片っ端から調合し、ニグラスの口に含ませるけれど。今ひとつ効果はなく、眠るニグラスの瞼はぴくりとも動かない。トゥルシーが魔族にとって毒であるように、ベラドンナが魔族にとっての薬になるのではないかと試してみたけれどそれも意味はない。ヒヨスの鎮痛薬が効いたのは運が良かっただけのようだ。
トゥルシーによる侵食はなんとか抑えられているけれど、根本的な回復には繋がらない。膠着した状態がいつ悪化するかと思うと、焦りは募るばかりだ。朝から晩まで薬草の採取と薬の調合、調べ物に時間を費やす時間はどんどん増えていく。双子が持ってきてくれた食事に手をつけない日もあれば、気絶するようにして床で眠り込む日もある。幼少期から鍛えられたおかげで体力はあるけれど、それでも限界を迎えかけていた。
それを心配した双子が、マルコに頼んだのだろう。エメリがもそもそと食事を摂るのを、椅子に腰掛けたマルコは膝に乗せた片足に頬杖をついて眺めている。まじまじと見つめられながらの食事は、なかなか居心地が悪い。早く食べ終わろう、と掻き込む。
「お前、忙しくても飯食って睡眠取れよ」
急に親のようなことを言い始めた魔王に、「う、うん」と動揺しながら頷く。「お前が死にかけたら俺が困る」と続けるのを聞いて、契約のことだと合点がいった。「ごめん。気をつける。」と謝りながら、一週間前に死にかけたことを改めて思い出す。
「あの、この間のは大丈夫だった?」
「あ?」
「魔王城に帰ってきたとき、死にかけたから。マルコの生命力をだいぶ持っていったのかなって」
契約主に生命力を渡したら、どうなるのだろう。倦怠感だとかがあるのだろうか。そう思ったのだけれど、マルコはどこかピンときていない顔でエメリを見る。「この間……?」と怪訝そうにする様子は、まるで思い当たる節がないようだ。
「そういやあのときは生命力渡してねえな」
「えっ!? じゃあなんで私は無事なの!?」
「……」
顎に手を当てて考え込むマルコ。生命力をくれてありがとうの意味であのときお礼を言ったのに、噛み合っていなかったらしい。それなら、一体どうやってエメリは瀕死の状態から回復したのだろうか。勇者の一族には守護の力以外の特殊体質はない。自然治癒力に優れているという話も聞いたことはない。困惑していると、マルコは不意に立ち上がった。ニグラスの眠る部屋に向かい、ツカツカと大股で歩く。
「えっ、な、なに?」
慌ててエメリも立ち上がってついていくと、マルコは無言で扉を開けた。未だ眠ったままのニグラスを、上から下まで観察するようにマルコは眺める。変わった様子はないように見えるけれど、魔王特権でわかることがあるのだろうか。というか、魔王が二人いる場合の魔王特権はどうなるのだろう。やがて角に触れたマルコは、目を見開いた。
「……ニグラスの生命力が減ってる」
「えっ!?」
魔力の源である角に触れると、生命力の残量までわかるらしい。今まで散々触れてきたのに、エメリは全く気が付かなかった。エメリが衝撃を受けている横で、マルコは黙り込む。じ、と探るような目つきで横たわるニグラスを眺めたかと思うと、ようやく口を開いた。
「お前、こいつと契約してるだろ」
「……は?」
「瀕死のお前を助けたのは俺じゃない、ニグラスだ」
確信したように告げるマルコ。納得、と言わんばかりの表情を浮かべているけれどエメリは納得できない。「け、契約なんてしてない。そんな覚えないよ」と答える。散々肌を重ね合わせ、魔力は注がれたけれど契約はしていない。エメリの血を飲ませたことも、名付けたこともないはずだ。第一、エメリがニグラスと初めて会ったのは魔王城に来たときのはずで――。
――エメリは覚えてないけど、小さいときに会ったことがあるんだよ。
いつだったか、ニグラスに言われた言葉を思い出す。もし、ニグラスと昔会ったことがあるのだとしたら、きっと黒い森でのことだろう。魔族は瘴気のある場所でしか生きていけないのだから。魔王討伐以前、エメリが黒い森に入ったことがあるのはたった一度だけ。十数年前、父親に一人で放り込まれたときだけだ。数日間彷徨った記憶はすっぽり抜け落ちていて、どうやって黒い森から出たのかも覚えていない、のだが。
――もしかして。
突然脳内に浮かんだのは、覚えていないはずの記憶。
幼いエメリは、一人泣きながら黒い森を彷徨っている。今より木々はずっと高く、閉塞的で怖い。もう二度と出られないんじゃないか、お家には帰れないんじゃないかと思うと悲しくてたまらない。ろくに日が差さないせいで、寒くて凍えそうだ。ろくに足元を見ていなかったせいで、木の根っこに躓いて転んでしまった。膝から流れる血を見ると、余計に痛みを感じてしまう。手当できないことはないけれど、その気力すら湧いてこなかった。この森から出られなかったらどうしよう。お父さんは探しに来てくれるだろうか。父親が守護の力を持たず、黒い森に入ることができないのを幼いエメリは知らない。不安と恐怖で座り込み、泣きじゃくるエメリの耳に、ガサリと草木をかき分けるような音が聞こえる。身構えるエメリの前に現れたのは、確か――。
――名前で呼ぶの嫌? それならクロでもいいよ。
「お前がニグラスと契約したのなら、話は早い」
「!」
唐突に聞こえた声で、現実に引っ張り上げられる。気づけば呼吸が浅くなっていたようで、心臓の音がバクバクとうるさい。呼吸を整えながら、マルコの方を向いた。エメリとニグラスの契約を完全に確信しているマルコは、淡々と話を進める。まだ記憶の整理がつかないエメリだけれど、一旦話を聞こうと耳を傾ける。
「ニグラスの角を切れ」
「……は?」
「……」
「おい!」
「わっ!? あっ、ま、マルコ!?」
どうしてここに、と尋ねる前に額を弾かれた。「痛っ!?」と額を抑えていると、「ほらよ」とバスケットを手渡される。ずしりと重いそれが何か、開ける前からわかっていた。使いっ走りにされた魔王に、「ありがとう」とお礼を告げるけれど眉間の皺は無くならない。ノックの音にも呼びかける声にも気づかなかったから不機嫌なのだろうか。
「食え」
「へ」
「お前が食い終わるのを見届けてから帰ってこいって双子に言われてんだよ」
双子は手が離せないんだとよ、と言いながらマルコはエメリを強引に椅子に座らせると、自身もどかりと腰を下ろす。まだ作業が一段落してないのに、と思ったけれど魔王の威圧感には敵わない。バスケットを開け、サンドイッチをもさもさと頬張る。アイスティーと一緒に流し込むのを、マルコは表情ひとつ変えずに見つめている。魔王に監視されながらの食事って緊張感あるな、とどうでもいいことを考えながら、ここ一週間のことを思い返した。
*
魔王城に着いてすぐ、嘔吐して意識を失ったエメリ。次に目が覚めたときには、どこかのベッドに寝かされていた。ゆっくりと目を瞬かせると、クリアになった視界に見慣れた天井が映る。木目調の天井と、吊り下げられた裸電球は見間違えるはずもない。魔王城で一番多くの時間を過ごしている、調合小屋だ。
――なんで……?
起き上がって辺りを見回してみても、間違いない。薬草棚も、作業台も、薬研も、すり鉢も、小鍋も。見慣れた道具の数々が、この場所がエメリの馴染みの場所だということを教えてくれる。違和感があるのはエメリが寝かされていたベッドと――小屋の一番奥にある扉だけだ。エメリの把握している限り、この小屋に寝具なんてものも、入り口以外の扉もなかったはずだ。誰が作ったものなのだろう。
「やっと起きたか?」
「! マルコ……」
ノックもなしに扉を開けてズカズカと入ってきたのは、つい最近魔王となった男。後ろ手に扉を閉めたマルコは、作業用の椅子を引っ張ってきてベッドの近くに腰掛けた。リリとリムではなく、マルコが様子を見にきたのは契約したからなのだろうか。ベッドと扉を取り付けたのは誰なのだろうか。聞きたいことがたくさんあるけれど、まずは。
「私、どうしてここにいるの?」
「あ?」
「なんで寝室とかじゃなくて調合小屋なのかと思って」
黒い森の瘴気は魔王城中に満ちている。どこに運ばれたところで変わりないのはわかっているが、それにしたってどうして調合小屋だったのか。しかもわざわざベッドを置いてまで。マルコをじっと見つめていると、「お前まさか知らねえのか?」と衝撃を受けたようにに目を丸くした。
「この小屋と温室をニグラスが作ったことは?」
「知ってる」
「じゃあ小屋と温室だけは瘴気が流れ込まないってことは?」
今度はエメリが衝撃を受ける番だった。目を丸くするエメリが何も知らないことを察したのだろう。マルコは、「温室にある薬草の中に、王国に生えてるようなのがあるだろ?」と口を開く。
「う、うん」
「そういう薬草は黒い森では生息できない。瘴気に当てられるのは人間と変わらねえんだよ」
「そうなんだ……」
初耳である。王国でも見かけたような草花があるんだ、としか思っていなかったが、当たり前のことではなかったらしい。だから眩暈も吐き気もしないのか、とホッとするのと同時にこれまでのあれこれが腑に落ちる。エメリの様子を見にきたのが双子でないのは、瘴気のない場所で魔族は活動できないから。マルコが様子を見にきたのは、エメリと契約している影響で瘴気がなくても活動できるから。以前、ニグラスが温室で一人ぶつぶつと何か呟いていたのは、瘴気が流れ込まないように魔法をかけていたからだろう。彼もまた人間の誰かと契約しているようだから、瘴気がなくても温室や小屋に入れたというわけだ。
「ベッドをここに置いてくれたのはマルコ?」
「ああ。床に寝かせようとしたら、双子が扉の外からギャンギャンうるせえのなんの」
顔を顰めるマルコに苦笑する。やいのやいのと扉の外から指示を飛ばしたのであろう双子には後でどうにかして感謝を伝えるとして、「ありがとう」とまずはマルコに感謝する。
「まあ、お前が死にかけたら俺も割を食うからな」
しゃーなしだ、と呟くマルコ。そういえば以前ニグラスが、「契約主が寿命以外で死にかけたら、僕の生命力を渡すことになってる」と言っていた気がする。守護の力で死にかけたエメリは言うなれば、「寿命以外で死にかけた」状態そのものだったはずだ。実際、もう二度と目を覚ますことはないのだろうと薄れゆく意識の中で覚悟したことは覚えている。だというのに、無事に目を覚ましたのはマルコの生命力を大なり小なり奪ってしまったからなのだろうか。
「あの……ごめんなさい」
「はあ? なんでだよ」
「私のせいで、迷惑かけて……」
ごめんなさい、と再び頭を下げるエメリ。契約に応じ、願いを叶えて魔王になってくれたけれど、エメリが死にかけたせいで迷惑をかけてしまった。対価を支払ったとはいえ、本来必要のない契約なのだ。責められても仕方がないと思ったけれど、「別にいい」と意外にもマルコの返答は冷たいものではない。
「それより、とっとと回復してそこで寝こけてる山羊起こせ」
「へ?」
そこ、とマルコが親指で指したのは小屋に突然現れた扉。慌ててベッドから降りて扉を開くと、薄暗い部屋にはベッドが一つ。恐る恐る近づくと、エメリの想い人が以前と変わらずに眠っている。「寝室のままだとお前が入れねえからな。部屋作ってこっちに運んできた」となんでもないように告げるマルコに心の底から感謝した。
双子に飯を用意させる、と言ってマルコはその場を立ち去る。後に残されたエメリは、ニグラスが寝かされているベッドに崩れ落ちるように跪いた。室内が暗いせいか、最後に見たときより心なしか顔色が悪い。が、胸が上下しているのを見てどうしようもなく安堵した。目を覚ます気配もないまま眠り込んでいるけれど、間違いなく生きている。その事実が何より嬉しかった。体の上で組まれている左手をそっと握る。指輪に触れ、誓うように呟いた。
「待っててね、ニグラス」
*
そうして一週間が経った。
守護の力を失ったエメリは魔王城に入れない。図書室の書物を読みたいときはマルコか、双子に頼むしかない。双子は毎日、小屋の入り口まで来てくれる。食料を届けに、頼んでいた書物を届けに、エメリを励ましに。守護の力を失ったエメリが魔族に襲われないかという懸念もあったけれど、新しく魔王となったマルコの契約主だということが幸いした。温室に向かうため外に出るときは毎回緊張が訪れるけれど、どうにか無事に薬草の採取ができている。
しかし、状況は芳しくない。あらゆる国で作られている眠気覚ましの薬や回復薬を片っ端から調合し、ニグラスの口に含ませるけれど。今ひとつ効果はなく、眠るニグラスの瞼はぴくりとも動かない。トゥルシーが魔族にとって毒であるように、ベラドンナが魔族にとっての薬になるのではないかと試してみたけれどそれも意味はない。ヒヨスの鎮痛薬が効いたのは運が良かっただけのようだ。
トゥルシーによる侵食はなんとか抑えられているけれど、根本的な回復には繋がらない。膠着した状態がいつ悪化するかと思うと、焦りは募るばかりだ。朝から晩まで薬草の採取と薬の調合、調べ物に時間を費やす時間はどんどん増えていく。双子が持ってきてくれた食事に手をつけない日もあれば、気絶するようにして床で眠り込む日もある。幼少期から鍛えられたおかげで体力はあるけれど、それでも限界を迎えかけていた。
それを心配した双子が、マルコに頼んだのだろう。エメリがもそもそと食事を摂るのを、椅子に腰掛けたマルコは膝に乗せた片足に頬杖をついて眺めている。まじまじと見つめられながらの食事は、なかなか居心地が悪い。早く食べ終わろう、と掻き込む。
「お前、忙しくても飯食って睡眠取れよ」
急に親のようなことを言い始めた魔王に、「う、うん」と動揺しながら頷く。「お前が死にかけたら俺が困る」と続けるのを聞いて、契約のことだと合点がいった。「ごめん。気をつける。」と謝りながら、一週間前に死にかけたことを改めて思い出す。
「あの、この間のは大丈夫だった?」
「あ?」
「魔王城に帰ってきたとき、死にかけたから。マルコの生命力をだいぶ持っていったのかなって」
契約主に生命力を渡したら、どうなるのだろう。倦怠感だとかがあるのだろうか。そう思ったのだけれど、マルコはどこかピンときていない顔でエメリを見る。「この間……?」と怪訝そうにする様子は、まるで思い当たる節がないようだ。
「そういやあのときは生命力渡してねえな」
「えっ!? じゃあなんで私は無事なの!?」
「……」
顎に手を当てて考え込むマルコ。生命力をくれてありがとうの意味であのときお礼を言ったのに、噛み合っていなかったらしい。それなら、一体どうやってエメリは瀕死の状態から回復したのだろうか。勇者の一族には守護の力以外の特殊体質はない。自然治癒力に優れているという話も聞いたことはない。困惑していると、マルコは不意に立ち上がった。ニグラスの眠る部屋に向かい、ツカツカと大股で歩く。
「えっ、な、なに?」
慌ててエメリも立ち上がってついていくと、マルコは無言で扉を開けた。未だ眠ったままのニグラスを、上から下まで観察するようにマルコは眺める。変わった様子はないように見えるけれど、魔王特権でわかることがあるのだろうか。というか、魔王が二人いる場合の魔王特権はどうなるのだろう。やがて角に触れたマルコは、目を見開いた。
「……ニグラスの生命力が減ってる」
「えっ!?」
魔力の源である角に触れると、生命力の残量までわかるらしい。今まで散々触れてきたのに、エメリは全く気が付かなかった。エメリが衝撃を受けている横で、マルコは黙り込む。じ、と探るような目つきで横たわるニグラスを眺めたかと思うと、ようやく口を開いた。
「お前、こいつと契約してるだろ」
「……は?」
「瀕死のお前を助けたのは俺じゃない、ニグラスだ」
確信したように告げるマルコ。納得、と言わんばかりの表情を浮かべているけれどエメリは納得できない。「け、契約なんてしてない。そんな覚えないよ」と答える。散々肌を重ね合わせ、魔力は注がれたけれど契約はしていない。エメリの血を飲ませたことも、名付けたこともないはずだ。第一、エメリがニグラスと初めて会ったのは魔王城に来たときのはずで――。
――エメリは覚えてないけど、小さいときに会ったことがあるんだよ。
いつだったか、ニグラスに言われた言葉を思い出す。もし、ニグラスと昔会ったことがあるのだとしたら、きっと黒い森でのことだろう。魔族は瘴気のある場所でしか生きていけないのだから。魔王討伐以前、エメリが黒い森に入ったことがあるのはたった一度だけ。十数年前、父親に一人で放り込まれたときだけだ。数日間彷徨った記憶はすっぽり抜け落ちていて、どうやって黒い森から出たのかも覚えていない、のだが。
――もしかして。
突然脳内に浮かんだのは、覚えていないはずの記憶。
幼いエメリは、一人泣きながら黒い森を彷徨っている。今より木々はずっと高く、閉塞的で怖い。もう二度と出られないんじゃないか、お家には帰れないんじゃないかと思うと悲しくてたまらない。ろくに日が差さないせいで、寒くて凍えそうだ。ろくに足元を見ていなかったせいで、木の根っこに躓いて転んでしまった。膝から流れる血を見ると、余計に痛みを感じてしまう。手当できないことはないけれど、その気力すら湧いてこなかった。この森から出られなかったらどうしよう。お父さんは探しに来てくれるだろうか。父親が守護の力を持たず、黒い森に入ることができないのを幼いエメリは知らない。不安と恐怖で座り込み、泣きじゃくるエメリの耳に、ガサリと草木をかき分けるような音が聞こえる。身構えるエメリの前に現れたのは、確か――。
――名前で呼ぶの嫌? それならクロでもいいよ。
「お前がニグラスと契約したのなら、話は早い」
「!」
唐突に聞こえた声で、現実に引っ張り上げられる。気づけば呼吸が浅くなっていたようで、心臓の音がバクバクとうるさい。呼吸を整えながら、マルコの方を向いた。エメリとニグラスの契約を完全に確信しているマルコは、淡々と話を進める。まだ記憶の整理がつかないエメリだけれど、一旦話を聞こうと耳を傾ける。
「ニグラスの角を切れ」
「……は?」