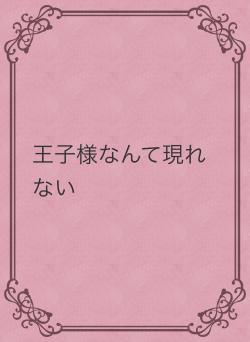玉座の間は、突然現れた魔族にどよめいている。護衛の騎士が国王を守るようにして立ちはだかるけれど、初めて見る魔族に臆しているのだろう。腰が引けている。ただでさえ、マルコは大柄で目つきが悪い。諸々を穏便に進めるため姿を隠してもらっていたのは英断だったけれど、肝心の交渉は全くうまくいかなかった。チラリとマルコの表情を伺うと、こちらもこちらで初めて見る王城を物珍しげに見回している。この状況で呑気なものだと思ったけれど、その緊張感のなさがありがたかった。
「マルコ」
「あ?」
「交渉、失敗した」
「だろうな」
鼻で笑うマルコ。最初からエメリがうまくやれるとは思っていなかったらしい。地味に傷ついたけれど、過度に期待されて失望されるよりマシかも知れない。「それで、願いは?」と尋ねるマルコに、エメリは口を開いた。相変わらず周囲はざわつき、隣の父親は腰を抜かしている。指輪に触れながら、エメリは口を開いた。
「マルコ、魔王になってほしい」
エメリの声は、ざわついた玉座の間にも響き渡ったようだ。しん、と水を打ったように静まり返る。王国との交渉が失敗に終わったときの次善策。魔王になる条件は、魔王城の玉座に座れるだけの魔力を有すること。条件を満たす魔族が複数人現れたときの制約は特に定められていない。人間との契約内容すらふわふわしているのだ、魔族というのは想像の数倍は大雑把なのだろう。その大雑把さを、勇者であるエメリはありがたく活用させてもらう。守護の力以外に何も持たない、脆弱な勇者として切り札を増やすために。
「御意。対価に何を差し出す?」
やりたくなくて、向いてなくて、それでもやらなければならない勇者。誰かがもうやらなくてもいいよと言ってくれることを期待したけれど、そんな都合のいいことは結局起きなかった。だからエメリは今日、自らの意思で勇者をやめる。
「守護の力を、差し出す」
流石に聞き捨てならなかったのだろう。父親が腰を抜かしたまま何か騒いでいるけれど、聞こえないふりをした。エメリの誇れるものは、きっと守護の力だけだ。エメリを食べて得られる魔力を、契約した対価に差し出せばどうなるのだろう。わからないけれど、試す価値はある。黒い森では目を見開いて驚いていたマルコだけれど、エメリの意思が変わらないのを悟ったらしい。
「御意」
ニヤリと笑い、エメリの胸の前に手をかざした。ぐ、と空を掴んで引っ張り出す動きをしたかと思うと、心臓のあたりに火傷しそうな熱が広がった。頭がぐらぐらして、額に脂汗が滲む。心臓を直に握られているのかと錯覚するほどに胸が痛くて息が苦しい。「ぐっ……」と漏れた声を奥歯で噛み殺す。光の玉のような何かが出てくるのを、ぼやける視界に捉えた。周囲の喧騒はどこか遠い。
――痛い、苦しい、もう嫌だ。
もうやめてほしいと喚いてやろうかと思ったけれど、今更途中でやめてもらえるはずもない。左手に爪を立てて耐えていると、包帯越しに傷口が開く。噛み締めすぎて、奥歯がそろそろ真っ平になりそうだ。寿命一ヶ月分は何事もなく掠め取られたのに、守護の力を抜き取られるのはこうも苦痛を伴うものらしい。
「あ、あ……馬鹿なことを……」
「守護の力を、どうして……」
周囲で誰かが呆然としたように呟くのが聞こえるようになった頃。ようやく全て取り出し終わったらしい。とてつもない虚脱感に襲われ、その場に膝をつく。のろのろと顔を上げると、手のひらの上で浮いた光の玉をマルコが丸呑みするところだった。取り出し終わったのならせめて報告してほしいし、そんなあっさり丸呑みしないでほしい、と文句をつけようかと思ったけれど何も言葉にはならなかった。
窓も扉も閉め切られたはずの玉座の間に、ぶわりと風が吹く。晴天だったはずなのに、窓の外では雷が鳴っている。ステンドグラスから差し込んでいたはずの光は全く差し込まない。――魔王が誕生した。
「これが守護の力ねえ……」
どこか愉悦を滲ませながらマルコはそう呟く。気づけば両手を床につき、四つん這いで息も絶え絶えのエメリに合わせてしゃがみ込んだ。魔王になったばかりの男は膝に肘をつき、エメリの顔を覗き込む。
「我が主、魔王になったこの俺に何を望む?」
「げほっ……ち、ちょっと待って」
咳き込むけれど息がなかなか整わない。一人の魔族を魔王にすることがこんなにも苦痛を伴い、体力を削られるものだとは思わなかった。どうにか息を整え、よろよろと立ち上がる。面白そうに眺めるマルコがそれを助けることはない。どうやら命令されない限り何もしてくれないようだ。寿命一週間分ぐらいを差し出して手伝わせればよかったな、とほんの少し思った。
立ち上がったエメリの目に映るのは、相変わらず玉座に座ったままの国王。護衛の騎士の影に隠れる国王は、新たな魔王誕生にすっかり萎縮している。ふんぞり返っている姿しか見たことがないのに、今や縮こまっていた。
「きっ、貴様っ……! 勇者が魔王を誕生させるだと!? ふざけているのか!?」
引っ捕えよ、と叫ぶけれど、護衛の騎士はエメリにすら臆しているらしい。動き出しが鈍いのをいいことに、「マルコ、騎士を無傷で捉えて」と手短に伝える。騎士たちはあっという間にどこからか現れた縄に捕まったけれど、対価はどうなっているのだろう。あとでまとめて寿命を取られるのだろうか。よくわからないけれど、今はそんなことを気にしている場合ではない。国王が短く息を呑む声が聞こえる。大事そうに抱えた王笏が目に入った。嵌め込まれたダイヤモンドの輝きは、出立の日と同じように輝きが鈍い。ほとんど無意識に、口を開いていた。
「マルコ、あの王笏をぶっ壊して」
「御意」
淡々と返事をするマルコは、そう言うや否や炎を吹いた。この人、炎を吹く感じの魔族だったのか、と今更把握している間に炎は細く伸びていく。勢いよく吹き出された炎は的確に王笏に狙いを定め、一瞬で灰にした。
「ひっ……!? 王家の、王家の象徴が……!?」
「陛下、お願いがあります」
狼狽える国王の前に一歩近づく。全身が痛くて怠くて、今すぐにでも床に倒れ込んでしまいたい。寿命一ヶ月分を捧げて、今すぐ魔王城の寝室に帰りたい。そこまで考えたところで、帰りたいと思う場所が王国にある実家ではなく、黒い森にある魔王城だということに気がついた。
――ニグラス、もう少し待っててね。
指輪に触れながら、力を振り絞って口を開く。守護の力をなくしたエメリに、勇者を名乗る資格はない。代わりに得たのが、魔王の主という立場と、魔王夫人という肩書きだ。死にそうな思いで手に入れた切り札を、利用しないわけにはいかない。
「魔王討伐の命を取り下げてください。お願いします」
「貴様っ……勇者の責務を放棄するつもりか!?」
狼狽えつつも怒りで顔を真っ赤にする国王。魔王を味方につけたエメリを見て尚、魔王討伐に固執するらしい。護衛の騎士は捕まり、勇者はもういないのに。隣を見るとエメリの父親は腰を抜かしたままワナワナと震えている。父親が何を考えているのか、エメリにはわからなかった。国王を見据え、首を振る。
「私の勇者としての責務は、王国の平和を守ることであって、魔王を討ち取ることではありません」
国王は、目を見開いたまま何も言わない。「王国が黒い森に手を出さないのであれば、魔族も王国に手を出さないよう約束させます。聞いてもらえないのであれば次は……」と言葉を区切る。
「王笏だけでは済まないと思ってください」
国王は項垂れたように俯く。何も言わないけれど、交渉という名の脅しのようなものは一応成立したのだろうか。わからない。書面にでもして残すべきなのだろうけれど、その元気は残っていない。心臓が馬鹿になったのだろうか、どくどくと脈打って痛いぐらいだ。左手の薬指で輝く指輪に縋り付きながら、マルコの方を振り向く。寿命を一年ほど使っていいから、早く魔王城に連れ帰って欲しかった。
「え、エメリっ」
切羽詰まったように名前を呼んだのは父親だった。ようやく立ち上がれるようになったのか、口をもごもごと動かす父親がエメリを見下ろす。物心つく前からエメリに勇者になることを強制し、一日中勇者として容赦なく鍛えてきた父親。一族の復興を誰よりも願っていた彼は、その夢が潰える瞬間を目にして何を思ったのだろうか。じ、と言葉を待ったけれど、結局何を言ってくれることもなかった。
「お父さん」
代わりに呼びかけると、肩をびくりと跳ねさせる。けれど、それでも何も言ってくれない様子に、失望と落胆が去来した。「体に、気をつけて」とだけ告げると、マルコに近寄る。「魔王城に連れ帰って」と手短に告げると、マルコはエメリを抱え上げた。指を鳴らす音と、ぶわりと風が吹く感覚。ようやく帰れる、と安堵したときに見えたのは、父親が手を伸ばす姿だった。
「エメリ……!」
手を伸ばして何がしたかったのか、何かを言いたかったのか。結局エメリが知ることはない。瞬きの間に景色は、玉座の間から見慣れた黒い森へと変わった。
*
「おら、着いたぞ」
「あ、ありが、っ!?」
ぽすっと中庭に降ろされたエメリは、上手く立てないことに気がついた。守護の力を引っこ抜かれたときの苦痛とは違う、耐え難い吐き気と眩暈が襲ってくる。心臓がバクバクとうるさくて、息がうまく吸えない。深呼吸しようにも、空気を吸い込むたびに眩暈はひどくなる一方だ。視界がぐるぐる回ることに耐えられず、蹲って目を閉じる。胃の中身がそっくりそのまま出てしまいそうなのを、必死で手で押さえたけれど一歩遅かった。
「ぅおぇっ……」
「!? おい!」
指の隙間からこぼれた吐瀉物が、びちゃびちゃと地面を汚していく。マルコが、「リリ! リム!」と叫んでいるが、耳の中に幕が張ったようにボーッと聞こえた。逆流したものが通ったせいで鼻が痛い。びくびくと震えているのが胃なのか全身なのかもわからない。喉が焼け付くように熱く、胃液を吐いているのだと悟るのに時間はかからなかった。
「エメリ様!?」
「えっ、どうしたの!?」
いつの間にか現れた双子が、エメリの背中を摩る。森を出立するまでなんともなかったのに、今になってどうして。そこまで考えたところでようやく気がつき、自らの鈍さを恥じた。
――守護の力を、なくしたからだ……。
黒い森は瘴気で満ちている。呼吸によって体内に入り込み、幻覚や眩暈、嘔吐等の症状を引き起こす瘴気に耐えられるのは、守護の力を宿す勇者だけ。守護の力をマルコに捧げ、勇者でなくなったエメリ。もう黒い森では、呼吸することすらままならない。耳鳴りがずいぶん酷くて、頭上で交わされる三人の会話は頭に入らない。
――ニグラス……。
薄れゆく意識の中、未だ眠ったままの想い人が脳裏に浮かぶ。早く薬を作らないといけないのに、早く助けないといけないのに。何ひとつ成し遂げられていないのに、エメリもニグラスももう二度と目覚めることはないかもしれない。唇を強く噛み締めたけれど、感覚すらない。お腹の奥が熱くなった気がしたけれど、結局そのまま意識を手放した。
「マルコ」
「あ?」
「交渉、失敗した」
「だろうな」
鼻で笑うマルコ。最初からエメリがうまくやれるとは思っていなかったらしい。地味に傷ついたけれど、過度に期待されて失望されるよりマシかも知れない。「それで、願いは?」と尋ねるマルコに、エメリは口を開いた。相変わらず周囲はざわつき、隣の父親は腰を抜かしている。指輪に触れながら、エメリは口を開いた。
「マルコ、魔王になってほしい」
エメリの声は、ざわついた玉座の間にも響き渡ったようだ。しん、と水を打ったように静まり返る。王国との交渉が失敗に終わったときの次善策。魔王になる条件は、魔王城の玉座に座れるだけの魔力を有すること。条件を満たす魔族が複数人現れたときの制約は特に定められていない。人間との契約内容すらふわふわしているのだ、魔族というのは想像の数倍は大雑把なのだろう。その大雑把さを、勇者であるエメリはありがたく活用させてもらう。守護の力以外に何も持たない、脆弱な勇者として切り札を増やすために。
「御意。対価に何を差し出す?」
やりたくなくて、向いてなくて、それでもやらなければならない勇者。誰かがもうやらなくてもいいよと言ってくれることを期待したけれど、そんな都合のいいことは結局起きなかった。だからエメリは今日、自らの意思で勇者をやめる。
「守護の力を、差し出す」
流石に聞き捨てならなかったのだろう。父親が腰を抜かしたまま何か騒いでいるけれど、聞こえないふりをした。エメリの誇れるものは、きっと守護の力だけだ。エメリを食べて得られる魔力を、契約した対価に差し出せばどうなるのだろう。わからないけれど、試す価値はある。黒い森では目を見開いて驚いていたマルコだけれど、エメリの意思が変わらないのを悟ったらしい。
「御意」
ニヤリと笑い、エメリの胸の前に手をかざした。ぐ、と空を掴んで引っ張り出す動きをしたかと思うと、心臓のあたりに火傷しそうな熱が広がった。頭がぐらぐらして、額に脂汗が滲む。心臓を直に握られているのかと錯覚するほどに胸が痛くて息が苦しい。「ぐっ……」と漏れた声を奥歯で噛み殺す。光の玉のような何かが出てくるのを、ぼやける視界に捉えた。周囲の喧騒はどこか遠い。
――痛い、苦しい、もう嫌だ。
もうやめてほしいと喚いてやろうかと思ったけれど、今更途中でやめてもらえるはずもない。左手に爪を立てて耐えていると、包帯越しに傷口が開く。噛み締めすぎて、奥歯がそろそろ真っ平になりそうだ。寿命一ヶ月分は何事もなく掠め取られたのに、守護の力を抜き取られるのはこうも苦痛を伴うものらしい。
「あ、あ……馬鹿なことを……」
「守護の力を、どうして……」
周囲で誰かが呆然としたように呟くのが聞こえるようになった頃。ようやく全て取り出し終わったらしい。とてつもない虚脱感に襲われ、その場に膝をつく。のろのろと顔を上げると、手のひらの上で浮いた光の玉をマルコが丸呑みするところだった。取り出し終わったのならせめて報告してほしいし、そんなあっさり丸呑みしないでほしい、と文句をつけようかと思ったけれど何も言葉にはならなかった。
窓も扉も閉め切られたはずの玉座の間に、ぶわりと風が吹く。晴天だったはずなのに、窓の外では雷が鳴っている。ステンドグラスから差し込んでいたはずの光は全く差し込まない。――魔王が誕生した。
「これが守護の力ねえ……」
どこか愉悦を滲ませながらマルコはそう呟く。気づけば両手を床につき、四つん這いで息も絶え絶えのエメリに合わせてしゃがみ込んだ。魔王になったばかりの男は膝に肘をつき、エメリの顔を覗き込む。
「我が主、魔王になったこの俺に何を望む?」
「げほっ……ち、ちょっと待って」
咳き込むけれど息がなかなか整わない。一人の魔族を魔王にすることがこんなにも苦痛を伴い、体力を削られるものだとは思わなかった。どうにか息を整え、よろよろと立ち上がる。面白そうに眺めるマルコがそれを助けることはない。どうやら命令されない限り何もしてくれないようだ。寿命一週間分ぐらいを差し出して手伝わせればよかったな、とほんの少し思った。
立ち上がったエメリの目に映るのは、相変わらず玉座に座ったままの国王。護衛の騎士の影に隠れる国王は、新たな魔王誕生にすっかり萎縮している。ふんぞり返っている姿しか見たことがないのに、今や縮こまっていた。
「きっ、貴様っ……! 勇者が魔王を誕生させるだと!? ふざけているのか!?」
引っ捕えよ、と叫ぶけれど、護衛の騎士はエメリにすら臆しているらしい。動き出しが鈍いのをいいことに、「マルコ、騎士を無傷で捉えて」と手短に伝える。騎士たちはあっという間にどこからか現れた縄に捕まったけれど、対価はどうなっているのだろう。あとでまとめて寿命を取られるのだろうか。よくわからないけれど、今はそんなことを気にしている場合ではない。国王が短く息を呑む声が聞こえる。大事そうに抱えた王笏が目に入った。嵌め込まれたダイヤモンドの輝きは、出立の日と同じように輝きが鈍い。ほとんど無意識に、口を開いていた。
「マルコ、あの王笏をぶっ壊して」
「御意」
淡々と返事をするマルコは、そう言うや否や炎を吹いた。この人、炎を吹く感じの魔族だったのか、と今更把握している間に炎は細く伸びていく。勢いよく吹き出された炎は的確に王笏に狙いを定め、一瞬で灰にした。
「ひっ……!? 王家の、王家の象徴が……!?」
「陛下、お願いがあります」
狼狽える国王の前に一歩近づく。全身が痛くて怠くて、今すぐにでも床に倒れ込んでしまいたい。寿命一ヶ月分を捧げて、今すぐ魔王城の寝室に帰りたい。そこまで考えたところで、帰りたいと思う場所が王国にある実家ではなく、黒い森にある魔王城だということに気がついた。
――ニグラス、もう少し待っててね。
指輪に触れながら、力を振り絞って口を開く。守護の力をなくしたエメリに、勇者を名乗る資格はない。代わりに得たのが、魔王の主という立場と、魔王夫人という肩書きだ。死にそうな思いで手に入れた切り札を、利用しないわけにはいかない。
「魔王討伐の命を取り下げてください。お願いします」
「貴様っ……勇者の責務を放棄するつもりか!?」
狼狽えつつも怒りで顔を真っ赤にする国王。魔王を味方につけたエメリを見て尚、魔王討伐に固執するらしい。護衛の騎士は捕まり、勇者はもういないのに。隣を見るとエメリの父親は腰を抜かしたままワナワナと震えている。父親が何を考えているのか、エメリにはわからなかった。国王を見据え、首を振る。
「私の勇者としての責務は、王国の平和を守ることであって、魔王を討ち取ることではありません」
国王は、目を見開いたまま何も言わない。「王国が黒い森に手を出さないのであれば、魔族も王国に手を出さないよう約束させます。聞いてもらえないのであれば次は……」と言葉を区切る。
「王笏だけでは済まないと思ってください」
国王は項垂れたように俯く。何も言わないけれど、交渉という名の脅しのようなものは一応成立したのだろうか。わからない。書面にでもして残すべきなのだろうけれど、その元気は残っていない。心臓が馬鹿になったのだろうか、どくどくと脈打って痛いぐらいだ。左手の薬指で輝く指輪に縋り付きながら、マルコの方を振り向く。寿命を一年ほど使っていいから、早く魔王城に連れ帰って欲しかった。
「え、エメリっ」
切羽詰まったように名前を呼んだのは父親だった。ようやく立ち上がれるようになったのか、口をもごもごと動かす父親がエメリを見下ろす。物心つく前からエメリに勇者になることを強制し、一日中勇者として容赦なく鍛えてきた父親。一族の復興を誰よりも願っていた彼は、その夢が潰える瞬間を目にして何を思ったのだろうか。じ、と言葉を待ったけれど、結局何を言ってくれることもなかった。
「お父さん」
代わりに呼びかけると、肩をびくりと跳ねさせる。けれど、それでも何も言ってくれない様子に、失望と落胆が去来した。「体に、気をつけて」とだけ告げると、マルコに近寄る。「魔王城に連れ帰って」と手短に告げると、マルコはエメリを抱え上げた。指を鳴らす音と、ぶわりと風が吹く感覚。ようやく帰れる、と安堵したときに見えたのは、父親が手を伸ばす姿だった。
「エメリ……!」
手を伸ばして何がしたかったのか、何かを言いたかったのか。結局エメリが知ることはない。瞬きの間に景色は、玉座の間から見慣れた黒い森へと変わった。
*
「おら、着いたぞ」
「あ、ありが、っ!?」
ぽすっと中庭に降ろされたエメリは、上手く立てないことに気がついた。守護の力を引っこ抜かれたときの苦痛とは違う、耐え難い吐き気と眩暈が襲ってくる。心臓がバクバクとうるさくて、息がうまく吸えない。深呼吸しようにも、空気を吸い込むたびに眩暈はひどくなる一方だ。視界がぐるぐる回ることに耐えられず、蹲って目を閉じる。胃の中身がそっくりそのまま出てしまいそうなのを、必死で手で押さえたけれど一歩遅かった。
「ぅおぇっ……」
「!? おい!」
指の隙間からこぼれた吐瀉物が、びちゃびちゃと地面を汚していく。マルコが、「リリ! リム!」と叫んでいるが、耳の中に幕が張ったようにボーッと聞こえた。逆流したものが通ったせいで鼻が痛い。びくびくと震えているのが胃なのか全身なのかもわからない。喉が焼け付くように熱く、胃液を吐いているのだと悟るのに時間はかからなかった。
「エメリ様!?」
「えっ、どうしたの!?」
いつの間にか現れた双子が、エメリの背中を摩る。森を出立するまでなんともなかったのに、今になってどうして。そこまで考えたところでようやく気がつき、自らの鈍さを恥じた。
――守護の力を、なくしたからだ……。
黒い森は瘴気で満ちている。呼吸によって体内に入り込み、幻覚や眩暈、嘔吐等の症状を引き起こす瘴気に耐えられるのは、守護の力を宿す勇者だけ。守護の力をマルコに捧げ、勇者でなくなったエメリ。もう黒い森では、呼吸することすらままならない。耳鳴りがずいぶん酷くて、頭上で交わされる三人の会話は頭に入らない。
――ニグラス……。
薄れゆく意識の中、未だ眠ったままの想い人が脳裏に浮かぶ。早く薬を作らないといけないのに、早く助けないといけないのに。何ひとつ成し遂げられていないのに、エメリもニグラスももう二度と目覚めることはないかもしれない。唇を強く噛み締めたけれど、感覚すらない。お腹の奥が熱くなった気がしたけれど、結局そのまま意識を手放した。