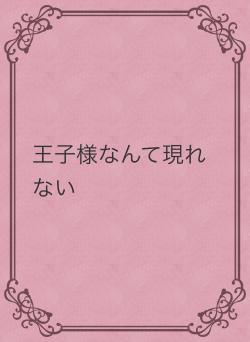「エメリ」
「あ、ニグラス。どうしたの?」
「これ」
そう言って差し出されたのは白い封筒。裏返すと、見覚えのある紋章を印璽として封蝋されている。「王国からの返事だ……」と呟くけれど、ニグラスは何も言わない。王国に向けての手紙を、ニグラスの魔法経由で送ったのは半月ほど前のことだ。無事に届いているのか心配していたけれど、問題なかったようだ。どうやってここまで届いたんだろう、と思いつつ封を破る。震える指先で広げた便箋には、簡潔な一言だけが記されていた。
『魔王を討伐せよ』
*
「ニグラス」
「あ、エメリ。どうしたの?」
「王国からの返事って、まだ来てない?」
「来てないよ」
「そっか……」
そんなに早く届くわけないということはわかっているけれど、それでもなんとなく落胆してしまう。魔王を討伐するようにとだけ書かれた手紙が届いたのは一週間ほど前の話。エメリはすぐに返事を書き、その日のうちには王国に向けて送ってもらった。
エメリが黒い森に来て以降、魔族から危害は加えられていないこと。王国に立ち込めていた暗雲は直に消えて無くなること。魔王にその気がないので、王国に瘴気が流れ出ることはないこと。魔王を討伐しなくても、王国は平和を保てること。魔王討伐の命を取り下げてほしいこと。
必死に綴った思いは、王国に無事届いただろうか。王国はエメリの懇願を聞き入れてくれるだろうか。気がつけばそのことばかり考えてしまうほどにソワソワしていた。
「……エメリには悪いけど」
ガックリと肩を落とすエメリに、ニグラスは言いにくそうに口を開く。最初に王国からの返事を持ってきてくれたときから、ニグラスはどこか気まずそうにしていた。封を破る前から、書かれてあることがわかっていたかのように。
「多分、王国からの返事は変わらないと思うよ」
「どうして?」
「王国が、魔王討伐をやめなかったことがないからだよ」
確かに、と納得する。エメリの一族に生まれた守護の力を宿すものは、ただ一人の例外もなく魔王が誕生したら討伐を命じられるのだ。それはつまり、王国が魔王誕生のたびに討伐を命じている何よりの証拠だ。魔王と結婚したから討伐しません、は通用しないのかもしれない。
「僕らは何も悪いことしてないつもりだけど、王国はできるなら魔族を根絶やしにしたいだろうからね」
ポツリと呟くニグラスの言葉に、何も言えない。大昔の魔王ならいざ知らず。少なくともニグラスは王国に対して敵意を抱いていないし、害する気もない。けれど、王国にとっては関係ないのだ。できないからしないだけで、本当なら黒い森を焼き払って魔族を殲滅したいのだろう。王国にいたときは何も思っていなかったけれど、今は。
「……でも、私にニグラスは倒せないよ」
「好きだから?」
「そ、そうじゃなくて。……私が、弱いから」
好きだから、と言うのもあながち間違いではないのだけれど。それよりも、エメリにニグラスを倒すだけの力がないことが問題だった。歴代の勇者には女性だっていたはずなのに、どうやって魔王の首を落としたのだろう。エメリは、勇者の剣をロールケーキみたいに丸められた時点で戦意の大半を喪失していた。
「今までの勇者は、どうやって魔王を倒してたんだろ……」
「うーん……いろいろかな」
ニグラスは腕を組んで考え込む。「魔王が舐めてたり、勇者が桁違いに強かったり……あ、魔法を使える勇者もいたこともあったっけ」と王国に存在する勇者関連の書物の、魔王側の話を思い出しているようだ。
「あと、エメリが思ってる以上に守護の力ってすごいんだよ」
「そうなの?」
「そもそも人間が瘴気に侵されないっていうのが大きいよね。あと、守護の力が強いほど勇者の剣での攻撃力も増すし」
「私勇者の剣はロールケーキみたいに丸められたのに?」
「……」
「なんか言ってよ!」
素質自体はあるけれどエメリが弱すぎて話にならない、ということを暗に示されてしまった。「いやでも本当にすごいんだって。僕ら魔族が取り込んだら魔力の底上げにもなるし」とフォローにならないフォローをしている。
「私がニグラスと結婚しなかったら、今頃魔力目当ての魔族に食べられてた?」
「それはもう頭からバリバリと」
「……」
薬指の指輪は思った以上にエメリを守ってくれているらしい。魔王夫人という肩書きがなければ、今頃魔力目当ての魔族に骨も残さず食べられていたのかもしれないのだ。ありえないとは言い切れない、あったかもしれない未来にゾッとする。「ちなみにどれぐらい底上げされるの?」と尋ねたところ、「マルコが玉座に座れるぐらいかな」と独特の基準で答えが返ってきた。よくわからないけれど、一人の魔族を魔王に押し上げることができるのはなかなかにすごそうだ。
「ていうか、なんで詳しいの?」
「図書室で読んだ」
「なるほど」
案内されて以降、週に二、三回のペースで図書室に通うエメリだけれど、魔王から見た勇者の話を読もうという発想はなかった。そもそもそんな本が存在しているとは。膨大な書物の中には、エメリの知らない歴史がまだ眠っているのかもしれない。今度探してみようと決めた。
「あ、あとあれだ。話し合いで解決」
「話し合い!?」
予想だにしなかった歴史である。魔王と話し合いで解決した勇者なんて聞いたことがない、と目を見開いていると、「僕の前の魔王だから、百年ぐらい前かな?」と世間話でもするような気軽さで続けている。
「そのときの勇者とどういうやりとりがあったのかは知らないけど、角をあげたらしいよ」
「角? これ?」
「あっ、そんな急に触るなんて大胆……!」
「え、ごめん」
そんなつもりじゃなかったのですぐに手を引っ込めようとすると、むんずと掴まれてそのまま触れさせられる。なんなんだ、と思っていると、角から手のひらを通して感情が伝わる。気恥ずかしいけれど嬉しい、と思っているのがよくわかって、なんだかくすぐったい。魔力は引き続き注がれているので、感情を感じ取る精度はますます高まっている。いつ触れても熱を持っている角は、言葉にして好きだの愛しているだのと言われるよりもダイレクトに伝わるかのようで、なんだか顔が熱い。エメリに角を触れさせながら、ニグラスは、「先代魔王も、角が魔力の源だったんだよ」と続ける。
「だから、角をあげたら魔法を使えなくなって、寿命も人間と同じぐらいになる」
「そう、なんだ……」
つまり、角をなくせば魔族としての力をなくし、人間に近づくということなのだろうか。先代魔王にとって、何のメリットがあって角を渡したのだろう。リリやリム、それからマルコを見ていても、魔族は基本的に人間を舐めている。ほとんど見下しているような存在に近づきたがるとは、到底考えられない。
――あれ、そういえば。
「ニグラスって何歳なの?」
ふと気になった。魔族の寿命が人間より長いことはなんとなく知っていたけれど、そういえばこの男は何歳なのだろうか。エメリとほとんど変わらないように見えるけれど、数百年は生きていたりするのだろうか。「僕? 二十一歳」だそうだ。エメリとほとんど変わらなかった。
「私と二つしか変わらないんだ」
「そうだよ。エメリの二、三倍生きるけど」
「長生きだ……」
「エメリは十九だっけ?」
「うん。言ったことあったっけ?」
「ないけど、エメリのことならなんでも知ってるから」
「へえ……」
相変わらずたまに気持ち悪いこと言うなこの人、と思ったけれどもはや慣れっこなので深くは突っ込まない。魔王パワーをもってすれば、エメリの年齢を推し量るぐらい朝飯前なのだろう。目の前の二十一歳に、「どうして先代魔王は角を渡したの?」と尋ねる。
「魔法が使えなくなって寿命が短くなるなんて、魔王に良いことがあるとは思えない」
「うーん……飽きたんじゃない?」
「飽きた?」
「僕らは数百年生きることを当たり前だと思ってるけどさ、中にはそれに飽き飽きするやつもいるんだよ」
「そう、なんだ」
飽きたから。そんな単純な理由で、魔力の源を渡して寿命を縮めたのだろうか。百年ぐらい前、と言うことはその当時の勇者は祖父の祖父だろうか。直前に魔王が現れたのが百年ぐらい前で、エメリの前に守護の力を宿していたのが祖父の祖父だったことは、祖父から聞いている話と辻褄が合う。けれど、よくよく思い返せば祖父の祖父が黒い森に向かったとは聞いたけれど、魔王討伐に成功したとは聞いていない。魔王の首ではなく角を持ち帰ったなんて例外的な話、一度聞いたなら絶対忘れないはずだ。知らないと言うことは、伝えられていないということ。エメリの父や祖父は、この話を知っているのだろうか。魔王の首ではなく、角を持ち帰った勇者を、王家は魔王討伐として見做したのだろうか。
――ううん、多分見做していないんだ。
点と点が線になる。何代か前の祖先が贅沢の限りを尽くし、ここ百年ほど魔王が現れなかったせいで勇者の一族は没落した。苦労して立て直したのは祖父だけれど、祖父の祖父が魔王討伐で得た褒美ではどうにもならなかったのだろうか。――きっと、どうにもならなかった。褒美が得られなかったからだ。
百年前の王家は、首ではなく角を持ち帰ることを魔王討伐とは見做さなかったのだろう。褒美を得られなかった祖父の祖父は、勇者として詳細を語り継がれることはなく。勇者の一族はますます没落したに違いない。一族の歴史をまさかこんなところで解き明かすことになるとは思いもしなかった。全てを理解してぞくぞくと鳥肌が立つような感覚を覚えると同時に、エメリは悟ってしまう。
――勇者が魔王を討伐しないことを、王国は許してくれない。
エメリがいくら王国に、魔王討伐の命を取り下げるように懇願したところできっと聞く耳は持ってくれない。王国からの返事は、「魔王を討伐せよ」の一言だけだろう。
「エメリ?」
黙り込んだエメリの顔を、ニグラスは心配そうに覗き込む。「大丈夫?」と尋ねる彼は、どこまでわかっているのだろう。王国には、エメリを除いて守護の力を宿すものはいない。つまり、黒い森に援軍が来ることはないのだから、王国からどれだけ魔王討伐を催促されようとも無視していればいいのだけれど。どうにもそれだけでは終わらなさそうな、胸騒ぎがした。嫌な予感と言ってもいい。
「ニグラス」
「どした、のっ!? おおっ!?」
ぎゅ、と正面から抱きつく。背中に回した腕で力の限り抱きしめていると、「え、エメリ!? そんな、日も高いのにいいの!?」とあわあわしている。全く違うけれど、もう良いやと黙っておいた。視界いっぱいに広がる黒い服に額を擦り付けていると、ニグラスの腕がエメリの背中に回る。後頭部を撫でられて、わけもなく泣きたくなった。
「例えば私が、勇者の役目を全うしたいって言ったら、どうする?」
「!」
ぴく、と体が強張るのがわかった。エメリがどれだけ懇願したところで、結果を出していない勇者の話を王国が聞いてくれるとは思わない。それなら魔王を討伐した上で交渉の権利を勝ち得るしかないだろう。けれど、それが正しいとは到底思えない。第一、交渉するとして、エメリは一体何を交渉したいのだろうか。王国に何を求めているのか、エメリは自分でもよくわからなくなっていた。
背中に回していた腕を外すニグラスに、今度はエメリが体を強張らせた。なんとなく緊張するエメリとは裏腹にニグラスの表情は柔らかい。エメリの前髪をかき分けると、額に唇を落とす。ぽかん、と口を開けていると、ニグラスは言葉を紡いだ。
「それが本当にエメリのしたいことなら、いいよ」
「え……」
「エメリの願いはなんでも叶えてあげるって言ったからね。僕の角だろうと首だろうと、欲しいならあげる」
だからいいよ、と重ねるニグラス。今角を触ったとしても、言葉通りの感情が伝わるのだろう。確かに、初めて会ったときにそう言われたけれど。けれど、本当にその通りにするつもりなのだろうか。エメリが望んだら、命さえ惜しくないとでも言うのだろうか。
「なんで、そこまで……」
「大好きだから、エメリのこと」
即答するニグラス。ニコニコと微笑む顔は初めて会った時から変わらないのに、あの時よりずっと安心感を覚えてしまうのはどうしてだろうか。答えはきっと、とっくに知っている。目の奥が熱い。胸の奥に降り積もる感情を、どう表せばいいのだろうか。
「キスしていい?」
「うん」
頷くと、嬉しそうに微笑んで後頭部に手を添える。聞かなくてもいいよ、と言っているけれど、一度を除いて毎回律儀に聞いてくれるのがエメリは好きだった。ちゅ、と唇が触れ合っては離れ、かぷりと唇を噛まれ、舌を吸われる。昨日もこんな感じで始まった気がすると思っていると、案の定。唇を離したニグラスが、「続き、してもいい?」と赤い顔で尋ねた。
「……ここじゃないのなら」
「もちろん」
そう言ってエメリを抱え上げると指を鳴らす。もう何度目かもわからない、魔法での移動にもすっかり慣れた。ベッドにそっと押し倒されて服を脱がされながら、この人を殺すことはできないと思うのと同時に、恋心を自覚した。
「あ、ニグラス。どうしたの?」
「これ」
そう言って差し出されたのは白い封筒。裏返すと、見覚えのある紋章を印璽として封蝋されている。「王国からの返事だ……」と呟くけれど、ニグラスは何も言わない。王国に向けての手紙を、ニグラスの魔法経由で送ったのは半月ほど前のことだ。無事に届いているのか心配していたけれど、問題なかったようだ。どうやってここまで届いたんだろう、と思いつつ封を破る。震える指先で広げた便箋には、簡潔な一言だけが記されていた。
『魔王を討伐せよ』
*
「ニグラス」
「あ、エメリ。どうしたの?」
「王国からの返事って、まだ来てない?」
「来てないよ」
「そっか……」
そんなに早く届くわけないということはわかっているけれど、それでもなんとなく落胆してしまう。魔王を討伐するようにとだけ書かれた手紙が届いたのは一週間ほど前の話。エメリはすぐに返事を書き、その日のうちには王国に向けて送ってもらった。
エメリが黒い森に来て以降、魔族から危害は加えられていないこと。王国に立ち込めていた暗雲は直に消えて無くなること。魔王にその気がないので、王国に瘴気が流れ出ることはないこと。魔王を討伐しなくても、王国は平和を保てること。魔王討伐の命を取り下げてほしいこと。
必死に綴った思いは、王国に無事届いただろうか。王国はエメリの懇願を聞き入れてくれるだろうか。気がつけばそのことばかり考えてしまうほどにソワソワしていた。
「……エメリには悪いけど」
ガックリと肩を落とすエメリに、ニグラスは言いにくそうに口を開く。最初に王国からの返事を持ってきてくれたときから、ニグラスはどこか気まずそうにしていた。封を破る前から、書かれてあることがわかっていたかのように。
「多分、王国からの返事は変わらないと思うよ」
「どうして?」
「王国が、魔王討伐をやめなかったことがないからだよ」
確かに、と納得する。エメリの一族に生まれた守護の力を宿すものは、ただ一人の例外もなく魔王が誕生したら討伐を命じられるのだ。それはつまり、王国が魔王誕生のたびに討伐を命じている何よりの証拠だ。魔王と結婚したから討伐しません、は通用しないのかもしれない。
「僕らは何も悪いことしてないつもりだけど、王国はできるなら魔族を根絶やしにしたいだろうからね」
ポツリと呟くニグラスの言葉に、何も言えない。大昔の魔王ならいざ知らず。少なくともニグラスは王国に対して敵意を抱いていないし、害する気もない。けれど、王国にとっては関係ないのだ。できないからしないだけで、本当なら黒い森を焼き払って魔族を殲滅したいのだろう。王国にいたときは何も思っていなかったけれど、今は。
「……でも、私にニグラスは倒せないよ」
「好きだから?」
「そ、そうじゃなくて。……私が、弱いから」
好きだから、と言うのもあながち間違いではないのだけれど。それよりも、エメリにニグラスを倒すだけの力がないことが問題だった。歴代の勇者には女性だっていたはずなのに、どうやって魔王の首を落としたのだろう。エメリは、勇者の剣をロールケーキみたいに丸められた時点で戦意の大半を喪失していた。
「今までの勇者は、どうやって魔王を倒してたんだろ……」
「うーん……いろいろかな」
ニグラスは腕を組んで考え込む。「魔王が舐めてたり、勇者が桁違いに強かったり……あ、魔法を使える勇者もいたこともあったっけ」と王国に存在する勇者関連の書物の、魔王側の話を思い出しているようだ。
「あと、エメリが思ってる以上に守護の力ってすごいんだよ」
「そうなの?」
「そもそも人間が瘴気に侵されないっていうのが大きいよね。あと、守護の力が強いほど勇者の剣での攻撃力も増すし」
「私勇者の剣はロールケーキみたいに丸められたのに?」
「……」
「なんか言ってよ!」
素質自体はあるけれどエメリが弱すぎて話にならない、ということを暗に示されてしまった。「いやでも本当にすごいんだって。僕ら魔族が取り込んだら魔力の底上げにもなるし」とフォローにならないフォローをしている。
「私がニグラスと結婚しなかったら、今頃魔力目当ての魔族に食べられてた?」
「それはもう頭からバリバリと」
「……」
薬指の指輪は思った以上にエメリを守ってくれているらしい。魔王夫人という肩書きがなければ、今頃魔力目当ての魔族に骨も残さず食べられていたのかもしれないのだ。ありえないとは言い切れない、あったかもしれない未来にゾッとする。「ちなみにどれぐらい底上げされるの?」と尋ねたところ、「マルコが玉座に座れるぐらいかな」と独特の基準で答えが返ってきた。よくわからないけれど、一人の魔族を魔王に押し上げることができるのはなかなかにすごそうだ。
「ていうか、なんで詳しいの?」
「図書室で読んだ」
「なるほど」
案内されて以降、週に二、三回のペースで図書室に通うエメリだけれど、魔王から見た勇者の話を読もうという発想はなかった。そもそもそんな本が存在しているとは。膨大な書物の中には、エメリの知らない歴史がまだ眠っているのかもしれない。今度探してみようと決めた。
「あ、あとあれだ。話し合いで解決」
「話し合い!?」
予想だにしなかった歴史である。魔王と話し合いで解決した勇者なんて聞いたことがない、と目を見開いていると、「僕の前の魔王だから、百年ぐらい前かな?」と世間話でもするような気軽さで続けている。
「そのときの勇者とどういうやりとりがあったのかは知らないけど、角をあげたらしいよ」
「角? これ?」
「あっ、そんな急に触るなんて大胆……!」
「え、ごめん」
そんなつもりじゃなかったのですぐに手を引っ込めようとすると、むんずと掴まれてそのまま触れさせられる。なんなんだ、と思っていると、角から手のひらを通して感情が伝わる。気恥ずかしいけれど嬉しい、と思っているのがよくわかって、なんだかくすぐったい。魔力は引き続き注がれているので、感情を感じ取る精度はますます高まっている。いつ触れても熱を持っている角は、言葉にして好きだの愛しているだのと言われるよりもダイレクトに伝わるかのようで、なんだか顔が熱い。エメリに角を触れさせながら、ニグラスは、「先代魔王も、角が魔力の源だったんだよ」と続ける。
「だから、角をあげたら魔法を使えなくなって、寿命も人間と同じぐらいになる」
「そう、なんだ……」
つまり、角をなくせば魔族としての力をなくし、人間に近づくということなのだろうか。先代魔王にとって、何のメリットがあって角を渡したのだろう。リリやリム、それからマルコを見ていても、魔族は基本的に人間を舐めている。ほとんど見下しているような存在に近づきたがるとは、到底考えられない。
――あれ、そういえば。
「ニグラスって何歳なの?」
ふと気になった。魔族の寿命が人間より長いことはなんとなく知っていたけれど、そういえばこの男は何歳なのだろうか。エメリとほとんど変わらないように見えるけれど、数百年は生きていたりするのだろうか。「僕? 二十一歳」だそうだ。エメリとほとんど変わらなかった。
「私と二つしか変わらないんだ」
「そうだよ。エメリの二、三倍生きるけど」
「長生きだ……」
「エメリは十九だっけ?」
「うん。言ったことあったっけ?」
「ないけど、エメリのことならなんでも知ってるから」
「へえ……」
相変わらずたまに気持ち悪いこと言うなこの人、と思ったけれどもはや慣れっこなので深くは突っ込まない。魔王パワーをもってすれば、エメリの年齢を推し量るぐらい朝飯前なのだろう。目の前の二十一歳に、「どうして先代魔王は角を渡したの?」と尋ねる。
「魔法が使えなくなって寿命が短くなるなんて、魔王に良いことがあるとは思えない」
「うーん……飽きたんじゃない?」
「飽きた?」
「僕らは数百年生きることを当たり前だと思ってるけどさ、中にはそれに飽き飽きするやつもいるんだよ」
「そう、なんだ」
飽きたから。そんな単純な理由で、魔力の源を渡して寿命を縮めたのだろうか。百年ぐらい前、と言うことはその当時の勇者は祖父の祖父だろうか。直前に魔王が現れたのが百年ぐらい前で、エメリの前に守護の力を宿していたのが祖父の祖父だったことは、祖父から聞いている話と辻褄が合う。けれど、よくよく思い返せば祖父の祖父が黒い森に向かったとは聞いたけれど、魔王討伐に成功したとは聞いていない。魔王の首ではなく角を持ち帰ったなんて例外的な話、一度聞いたなら絶対忘れないはずだ。知らないと言うことは、伝えられていないということ。エメリの父や祖父は、この話を知っているのだろうか。魔王の首ではなく、角を持ち帰った勇者を、王家は魔王討伐として見做したのだろうか。
――ううん、多分見做していないんだ。
点と点が線になる。何代か前の祖先が贅沢の限りを尽くし、ここ百年ほど魔王が現れなかったせいで勇者の一族は没落した。苦労して立て直したのは祖父だけれど、祖父の祖父が魔王討伐で得た褒美ではどうにもならなかったのだろうか。――きっと、どうにもならなかった。褒美が得られなかったからだ。
百年前の王家は、首ではなく角を持ち帰ることを魔王討伐とは見做さなかったのだろう。褒美を得られなかった祖父の祖父は、勇者として詳細を語り継がれることはなく。勇者の一族はますます没落したに違いない。一族の歴史をまさかこんなところで解き明かすことになるとは思いもしなかった。全てを理解してぞくぞくと鳥肌が立つような感覚を覚えると同時に、エメリは悟ってしまう。
――勇者が魔王を討伐しないことを、王国は許してくれない。
エメリがいくら王国に、魔王討伐の命を取り下げるように懇願したところできっと聞く耳は持ってくれない。王国からの返事は、「魔王を討伐せよ」の一言だけだろう。
「エメリ?」
黙り込んだエメリの顔を、ニグラスは心配そうに覗き込む。「大丈夫?」と尋ねる彼は、どこまでわかっているのだろう。王国には、エメリを除いて守護の力を宿すものはいない。つまり、黒い森に援軍が来ることはないのだから、王国からどれだけ魔王討伐を催促されようとも無視していればいいのだけれど。どうにもそれだけでは終わらなさそうな、胸騒ぎがした。嫌な予感と言ってもいい。
「ニグラス」
「どした、のっ!? おおっ!?」
ぎゅ、と正面から抱きつく。背中に回した腕で力の限り抱きしめていると、「え、エメリ!? そんな、日も高いのにいいの!?」とあわあわしている。全く違うけれど、もう良いやと黙っておいた。視界いっぱいに広がる黒い服に額を擦り付けていると、ニグラスの腕がエメリの背中に回る。後頭部を撫でられて、わけもなく泣きたくなった。
「例えば私が、勇者の役目を全うしたいって言ったら、どうする?」
「!」
ぴく、と体が強張るのがわかった。エメリがどれだけ懇願したところで、結果を出していない勇者の話を王国が聞いてくれるとは思わない。それなら魔王を討伐した上で交渉の権利を勝ち得るしかないだろう。けれど、それが正しいとは到底思えない。第一、交渉するとして、エメリは一体何を交渉したいのだろうか。王国に何を求めているのか、エメリは自分でもよくわからなくなっていた。
背中に回していた腕を外すニグラスに、今度はエメリが体を強張らせた。なんとなく緊張するエメリとは裏腹にニグラスの表情は柔らかい。エメリの前髪をかき分けると、額に唇を落とす。ぽかん、と口を開けていると、ニグラスは言葉を紡いだ。
「それが本当にエメリのしたいことなら、いいよ」
「え……」
「エメリの願いはなんでも叶えてあげるって言ったからね。僕の角だろうと首だろうと、欲しいならあげる」
だからいいよ、と重ねるニグラス。今角を触ったとしても、言葉通りの感情が伝わるのだろう。確かに、初めて会ったときにそう言われたけれど。けれど、本当にその通りにするつもりなのだろうか。エメリが望んだら、命さえ惜しくないとでも言うのだろうか。
「なんで、そこまで……」
「大好きだから、エメリのこと」
即答するニグラス。ニコニコと微笑む顔は初めて会った時から変わらないのに、あの時よりずっと安心感を覚えてしまうのはどうしてだろうか。答えはきっと、とっくに知っている。目の奥が熱い。胸の奥に降り積もる感情を、どう表せばいいのだろうか。
「キスしていい?」
「うん」
頷くと、嬉しそうに微笑んで後頭部に手を添える。聞かなくてもいいよ、と言っているけれど、一度を除いて毎回律儀に聞いてくれるのがエメリは好きだった。ちゅ、と唇が触れ合っては離れ、かぷりと唇を噛まれ、舌を吸われる。昨日もこんな感じで始まった気がすると思っていると、案の定。唇を離したニグラスが、「続き、してもいい?」と赤い顔で尋ねた。
「……ここじゃないのなら」
「もちろん」
そう言ってエメリを抱え上げると指を鳴らす。もう何度目かもわからない、魔法での移動にもすっかり慣れた。ベッドにそっと押し倒されて服を脱がされながら、この人を殺すことはできないと思うのと同時に、恋心を自覚した。