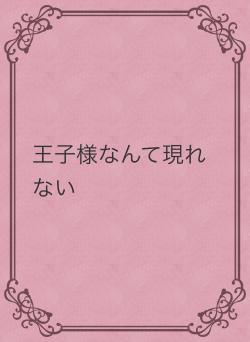「勇者よ、黒い森に住む悪しき魔王の討伐へ行け」
さすれば褒美をやらん、と玉座でふんぞり返る国王はそう命じる。右手に持つのは、王家の象徴である王笏。嵌め込まれたダイヤモンドは、玉座の背後にあるステンドグラスから差し込む光を受けてキラキラと輝く、はずだが。今日はその輝きがなんだか鈍い。
理由は明白。ここ最近王国を覆う暗雲のせいで、日の光がろくに射さないからだ。
「魔族を殲滅し、我が国に光をもたらせ」
「はい、陛下。必ずや」
跪く勇者――エメリは、決意と恐怖で震えそうになるのを必死で堪えて顔を上げる。王国に再び光と平和を取り戻すため、怖くても逃げ出したくてもやり遂げなければならない。
エメリの短い返事に満足したのだろう。鷹揚に頷く国王は、「出立せよ」とだけ告げた。目の前に置いていた剣を手に取り、エメリは立ち上がる。いつまで経っても慣れない剣の重みだけれど、今日はさらに重たい。億劫なのを気取られないよう腰に提げ直し、国王に一礼してその場を後にする。
王国の端に広がる、魔族の住む黒い森。近づけば最後、生きては戻れないと実しやかに囁かれているその森は、瘴気が満ちているせいで昼間でも薄暗い。近隣の住民は不気味がって近づかないその場所に向けて、エメリは今日出立する。
*
遡ること数百年前、魔族に侵略されていた王国は今よりも闇に包まれていた。暗雲が立ち込めるせいで、日中でも日が差さない。普段は黒い森の中で留まる瘴気が、魔族とともに近隣の村にも流れ込む。瘴気は呼吸によって体内に入り込み、幻覚や眩暈、嘔吐等の症状を引き起こすのだ。魔族と瘴気に怯える村人たちは家を出ることは愚か、安心して眠ることもできない。
このままでは王国が魔族に乗っ取られるのではないか、誰もがそう危惧したときだった。
「俺が魔王を倒してきます」
決然として立ち上がったのは、黒い森から程近い家に一人で住む青年。村唯一の鍛冶屋を営む彼は、特別腕っぷしが立つわけでも魔法を使えるわけでもない。実直で真面目な青年をむざむざ死なせたくない村人は必死になって止めたけれど、正義感と義憤に駆られた彼が聞く耳を持つことはない。村の惨状と暗雲立ち込める王国を救うため、自ら鍛えた剣を腰に提げて単身黒い森に乗り込んだ。
青年はもう二度と戻ってこないのだろうと悲嘆に暮れる村人に反し、青年はわずか数日で戻ってきた。その手に魔王の首を提げて。後から分かったことだが、青年は特異体質の持ち主だった。瘴気に侵されない、守護の力。その力を体内に宿した彼は、黒い森の瘴気のせいで倒れることも、魔獣に襲われることもなかった。澱みなく真っ直ぐに黒い森を抜けて魔王城に辿り着き、そのまま魔王に斬りかかる。まさか人間が黒い森で生き延びるとは思わなかったのだろう。油断していた魔王の首は、あっさり落とされたらしい。
魔王を討伐したことで魔族は黒い森へと帰り、王国の危機は去った。片田舎に住む青年が魔王を倒したことはすぐに国王の耳にも入り、青年は王都へと呼び寄せられる。彼の働きに、当時の国王は大層感謝したらしい。王国を救った勇者への褒美として、可愛がっていた娘を彼に嫁がせ爵位と屋敷を与えた。
これがエメリの祖先、勇者の一族の始まりの話である。
勇者によって魔王は討伐されたが、その平和が永久に続くわけではない。魔族が絶滅したわけでも、黒い森がなくなるわけでもないのだ。数十年後には新たな魔王が誕生し、王国は再び危機に瀕する。国王は再び魔王を討伐するよう命じるが、もう一度黒い森に乗り込むには勇者は歳をとり過ぎていた。そこで代わりにと勇者が推薦したのが自身の孫である。勇者の特異体質を受け継ぎ、守護の力をその身に宿した青年は祖父に代わって黒い森へ。そして祖父と同じように、魔王の首を提げて戻ってきた。
勇者は黒い森に派遣されるたび、魔王の首を手土産に王国へと戻ってくる。が、やはり平和は長く続かない。不規則ではあるが、数十年もすると再び魔王は誕生する。その度に勇者の子孫は勇者として魔王討伐を命じられるのだ。倒しても倒しても倒しても倒しても魔王は生まれ、その度に勇者は黒い森へと単身乗り込む。何度も何度も何度も何度も。
数百年の歴史の中で、黒い森を焼き払い魔族の殲滅を提唱するものもいた。勇者一人で討伐させるのではなく、軍隊を組織するべきだという声も上がった。しかし、黒い森の木々は火に焚べると瘴気を大量に発するので焼き払うことはできず、軍隊を組織しようにも瘴気に耐えうるのは勇者の一族の中でも守護の力を受け継ぐものだけ。勇者の一族であれば誰でもその力を宿すわけではない、ほんの一握りだ。たった一人では魔族を殲滅することはできず、魔王を倒して勢いを押さえ込むので精一杯。
そういうわけで、魔王誕生により王国が危機に直面するたびに、守護の力を受け継ぐものを勇者として黒い森に派遣する形に落ち着き――いつしか『勇者の一族』と呼ばれるようになったその一族は、数十年に一度の魔王討伐を家業とするようになる。
*
王城から帰ってきたエメリは、侍女にも入ってこないように言いつけて自室に引きこもった。床には荷物でいっぱいのリュックが置きっぱなしになっている。その近くに座り込み、見るともなしに外を眺める。相変わらず空には暗雲が立ち込めていて、今にも魔族が黒い森から飛び出してきそうだ。魔王の誕生を知らされてすぐに荷造りを始めたし、勇者として魔王城に討伐へと向かった祖先が書き記した文献の数々は擦り切れるほどに読み返した。今すぐにでも出立することはできるし、そうしなければならない。けれど。
「やだなあ」
誰にも聞かれていないのを良いことに一人呟く。存命する勇者の一族で唯一、守護の力をその身に宿すエメリ。十九年前、この世に生を受けた瞬間に勇者となることが決まった彼女だが、勇者になりたいと思ったことはないし向いていると思ったこともない。魔王誕生により黒い森に行くことを国王から正式に命じられたのだが、既に逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。
勇者の一族に生まれた守護の力を受け継ぐものは、漏れなく勇者となることが義務付けられていた。いつ魔王が誕生しても良いようにあらゆる武術の稽古をつけられ、魔王の誕生と共に討伐を命じられる。魔王の首と引き換えに、金銀財宝や領地を賜る。褒美の品々を元手に家業の鍛冶屋を発展させることで領地の拡大と繁栄を続け、エメリの一族は王国でも有数の有力貴族となった。が、近頃はその栄華も危うい。何代か前のエメリの祖先が贅沢三昧で散財し続けたことに加え、ここ百年ほど魔王が現れなかったからだ。
人間というものは、贅沢に慣れると貧相な生活を許容することはできない。社交界でのドレスを仕立てられなくなっても、レストランでの支払いに困るようになっても、果ては使用人に払う給金すら用意できなくなっても、借金してでも散財をやめることはできない。いよいよ初代勇者が賜った屋敷を売り払わなければならないかもしれない、というときに窮状をなんとか立て直したのがエメリの祖父だ。鍛冶屋の工房や領地をいくつか手放すことで借金を全て返済し、どうにか屋敷を守り抜いた彼こそが勇者であり英雄だとエメリは思っている。
エメリの祖父は守護の力を受け継いでいないため、勇者として魔王を討伐することはできない。けれど、祖父はそれでいいと思っていた。魔王が現れないのも祖父に守護の力が現れないのも、きっと王国が平和である証拠。屋敷は守れたのだから、細々と鍛冶屋を続けていけば食うに困ることはない。地に足のついた祖父はそう考えていたのだけれど、エメリの父親はそうではなかった。文献や村の人々から伝え聞く話から、一時期の栄華への憧れを募らせたのだろう。魔王討伐による報奨金を得て、一族の復興を遂げたい気持ちが人一倍強かった。
しかし悲劇的なのが、エメリの父親にも守護の力が備わっていなかったことだろう。まだ現れてもいない魔王討伐へのやる気に燃えていたが、肩慣らしに魔獣を倒そうと黒い森に一歩足を踏み入れたところで気絶した。共をしていた従僕が必死になって連れ戻さなければ、そのまま命を落としていただろう。その後も懲りずに何度か黒い森に踏み入ろうとしたのだが、結果はいつも同じ。そのうち、父親である祖父に立ち入りを禁じられるまでになった。一族の誰よりも魔王を倒すことを望んでいるのに、誰よりもその資格がない。それでもエメリの父は諦められなかった。武勲を上げて領地を拡大することも、絵に描いたような贅沢な暮らしも。憧れはいつか妄執となり、その皺寄せを食らったのがエメリである。
守護の力を宿して生まれたエメリは、数世代ぶりの勇者となれる子供だ。出産で体力と気力を使い果たしてしまったのだろう、エメリの母親はエメリを産み落とすと同時に息を引き取った。しかしエメリの父親が、それを気に留めることはない。これでようやく一族の復興が果たせるのだと喜ぶばかりだった。
まだ五つにも届かないうちから、剣術や弓術の稽古が始まる。遊びたい盛りに容赦なく鍛えられ、何度も泣き出して逃げ出したがその度に連れ戻された。不憫に思った祖父や侍女が止めに入ろうとしてくれたこともあったけれど、妄執に取り憑かれた父親が止まることはない。自分を助けようとする祖父や侍女にまで容赦なく手をあげる父の姿を見て、エメリは幼いながらに覚悟を決める。血反吐を吐くような厳しい稽古の日々を、耐え抜くしかないのだと。
そうして時は流れ、エメリの祖父が老衰で息を引き取って数ヶ月後。このまま魔王が誕生せず討伐に行けないのであれば自ら魔王城に乗り込み魔族の首をとってこい、それができないのであればせめて守護の力を宿す子を成せと迫られる頃。とうとう父親の待望の瞬間は訪れた。大地を裂くような雷鳴が轟、王国全土を覆うような暗雲が黒い森から立ち込める――魔王が誕生したのだ。
「逃げたら怒られる、よね」
やはり誰も聞いていないのを良いことにそんなことを呟く。父親に聞かれていたら間違いなく殴られていただろう。稽古を嫌がるエメリを脅すように、昔から父親が繰り返す言葉がある。
「私たちが何不自由なく暮らせるのはどうしてかわかるか? 魔王を倒してきた一族だからだ」
「叶うなら私がこの手で魔王を討伐したかった。魔族を根絶やしにしたかった。だが、それは叶わない」
「だからお前がやるんだ、エメリ。お前が一族の悲願を果たすのだ」
幼いエメリにはその言葉がどれだけ無茶苦茶なのかがわからなかった。わかるのは、父親が果たせなかったことをエメリが果たさなければならないということだけ。戦いたくなんてないし、そもそも戦うことに向いていないし、本当は勇者じゃなくて薬師になりたい。けれど、それでもエメリはやらなければならない。
「やだなあー……」
立てた膝に顔を埋め、肺の中の息を絞り出す。やりたくなくても、向いていなくても、やらなければならない。魔王が誕生し、国王から勅命も受けてしまった今、守護の力を宿したエメリは正真正銘の勇者となってしまったから。
王国の平和のために戦うことが、彼女の責務だから。
さすれば褒美をやらん、と玉座でふんぞり返る国王はそう命じる。右手に持つのは、王家の象徴である王笏。嵌め込まれたダイヤモンドは、玉座の背後にあるステンドグラスから差し込む光を受けてキラキラと輝く、はずだが。今日はその輝きがなんだか鈍い。
理由は明白。ここ最近王国を覆う暗雲のせいで、日の光がろくに射さないからだ。
「魔族を殲滅し、我が国に光をもたらせ」
「はい、陛下。必ずや」
跪く勇者――エメリは、決意と恐怖で震えそうになるのを必死で堪えて顔を上げる。王国に再び光と平和を取り戻すため、怖くても逃げ出したくてもやり遂げなければならない。
エメリの短い返事に満足したのだろう。鷹揚に頷く国王は、「出立せよ」とだけ告げた。目の前に置いていた剣を手に取り、エメリは立ち上がる。いつまで経っても慣れない剣の重みだけれど、今日はさらに重たい。億劫なのを気取られないよう腰に提げ直し、国王に一礼してその場を後にする。
王国の端に広がる、魔族の住む黒い森。近づけば最後、生きては戻れないと実しやかに囁かれているその森は、瘴気が満ちているせいで昼間でも薄暗い。近隣の住民は不気味がって近づかないその場所に向けて、エメリは今日出立する。
*
遡ること数百年前、魔族に侵略されていた王国は今よりも闇に包まれていた。暗雲が立ち込めるせいで、日中でも日が差さない。普段は黒い森の中で留まる瘴気が、魔族とともに近隣の村にも流れ込む。瘴気は呼吸によって体内に入り込み、幻覚や眩暈、嘔吐等の症状を引き起こすのだ。魔族と瘴気に怯える村人たちは家を出ることは愚か、安心して眠ることもできない。
このままでは王国が魔族に乗っ取られるのではないか、誰もがそう危惧したときだった。
「俺が魔王を倒してきます」
決然として立ち上がったのは、黒い森から程近い家に一人で住む青年。村唯一の鍛冶屋を営む彼は、特別腕っぷしが立つわけでも魔法を使えるわけでもない。実直で真面目な青年をむざむざ死なせたくない村人は必死になって止めたけれど、正義感と義憤に駆られた彼が聞く耳を持つことはない。村の惨状と暗雲立ち込める王国を救うため、自ら鍛えた剣を腰に提げて単身黒い森に乗り込んだ。
青年はもう二度と戻ってこないのだろうと悲嘆に暮れる村人に反し、青年はわずか数日で戻ってきた。その手に魔王の首を提げて。後から分かったことだが、青年は特異体質の持ち主だった。瘴気に侵されない、守護の力。その力を体内に宿した彼は、黒い森の瘴気のせいで倒れることも、魔獣に襲われることもなかった。澱みなく真っ直ぐに黒い森を抜けて魔王城に辿り着き、そのまま魔王に斬りかかる。まさか人間が黒い森で生き延びるとは思わなかったのだろう。油断していた魔王の首は、あっさり落とされたらしい。
魔王を討伐したことで魔族は黒い森へと帰り、王国の危機は去った。片田舎に住む青年が魔王を倒したことはすぐに国王の耳にも入り、青年は王都へと呼び寄せられる。彼の働きに、当時の国王は大層感謝したらしい。王国を救った勇者への褒美として、可愛がっていた娘を彼に嫁がせ爵位と屋敷を与えた。
これがエメリの祖先、勇者の一族の始まりの話である。
勇者によって魔王は討伐されたが、その平和が永久に続くわけではない。魔族が絶滅したわけでも、黒い森がなくなるわけでもないのだ。数十年後には新たな魔王が誕生し、王国は再び危機に瀕する。国王は再び魔王を討伐するよう命じるが、もう一度黒い森に乗り込むには勇者は歳をとり過ぎていた。そこで代わりにと勇者が推薦したのが自身の孫である。勇者の特異体質を受け継ぎ、守護の力をその身に宿した青年は祖父に代わって黒い森へ。そして祖父と同じように、魔王の首を提げて戻ってきた。
勇者は黒い森に派遣されるたび、魔王の首を手土産に王国へと戻ってくる。が、やはり平和は長く続かない。不規則ではあるが、数十年もすると再び魔王は誕生する。その度に勇者の子孫は勇者として魔王討伐を命じられるのだ。倒しても倒しても倒しても倒しても魔王は生まれ、その度に勇者は黒い森へと単身乗り込む。何度も何度も何度も何度も。
数百年の歴史の中で、黒い森を焼き払い魔族の殲滅を提唱するものもいた。勇者一人で討伐させるのではなく、軍隊を組織するべきだという声も上がった。しかし、黒い森の木々は火に焚べると瘴気を大量に発するので焼き払うことはできず、軍隊を組織しようにも瘴気に耐えうるのは勇者の一族の中でも守護の力を受け継ぐものだけ。勇者の一族であれば誰でもその力を宿すわけではない、ほんの一握りだ。たった一人では魔族を殲滅することはできず、魔王を倒して勢いを押さえ込むので精一杯。
そういうわけで、魔王誕生により王国が危機に直面するたびに、守護の力を受け継ぐものを勇者として黒い森に派遣する形に落ち着き――いつしか『勇者の一族』と呼ばれるようになったその一族は、数十年に一度の魔王討伐を家業とするようになる。
*
王城から帰ってきたエメリは、侍女にも入ってこないように言いつけて自室に引きこもった。床には荷物でいっぱいのリュックが置きっぱなしになっている。その近くに座り込み、見るともなしに外を眺める。相変わらず空には暗雲が立ち込めていて、今にも魔族が黒い森から飛び出してきそうだ。魔王の誕生を知らされてすぐに荷造りを始めたし、勇者として魔王城に討伐へと向かった祖先が書き記した文献の数々は擦り切れるほどに読み返した。今すぐにでも出立することはできるし、そうしなければならない。けれど。
「やだなあ」
誰にも聞かれていないのを良いことに一人呟く。存命する勇者の一族で唯一、守護の力をその身に宿すエメリ。十九年前、この世に生を受けた瞬間に勇者となることが決まった彼女だが、勇者になりたいと思ったことはないし向いていると思ったこともない。魔王誕生により黒い森に行くことを国王から正式に命じられたのだが、既に逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。
勇者の一族に生まれた守護の力を受け継ぐものは、漏れなく勇者となることが義務付けられていた。いつ魔王が誕生しても良いようにあらゆる武術の稽古をつけられ、魔王の誕生と共に討伐を命じられる。魔王の首と引き換えに、金銀財宝や領地を賜る。褒美の品々を元手に家業の鍛冶屋を発展させることで領地の拡大と繁栄を続け、エメリの一族は王国でも有数の有力貴族となった。が、近頃はその栄華も危うい。何代か前のエメリの祖先が贅沢三昧で散財し続けたことに加え、ここ百年ほど魔王が現れなかったからだ。
人間というものは、贅沢に慣れると貧相な生活を許容することはできない。社交界でのドレスを仕立てられなくなっても、レストランでの支払いに困るようになっても、果ては使用人に払う給金すら用意できなくなっても、借金してでも散財をやめることはできない。いよいよ初代勇者が賜った屋敷を売り払わなければならないかもしれない、というときに窮状をなんとか立て直したのがエメリの祖父だ。鍛冶屋の工房や領地をいくつか手放すことで借金を全て返済し、どうにか屋敷を守り抜いた彼こそが勇者であり英雄だとエメリは思っている。
エメリの祖父は守護の力を受け継いでいないため、勇者として魔王を討伐することはできない。けれど、祖父はそれでいいと思っていた。魔王が現れないのも祖父に守護の力が現れないのも、きっと王国が平和である証拠。屋敷は守れたのだから、細々と鍛冶屋を続けていけば食うに困ることはない。地に足のついた祖父はそう考えていたのだけれど、エメリの父親はそうではなかった。文献や村の人々から伝え聞く話から、一時期の栄華への憧れを募らせたのだろう。魔王討伐による報奨金を得て、一族の復興を遂げたい気持ちが人一倍強かった。
しかし悲劇的なのが、エメリの父親にも守護の力が備わっていなかったことだろう。まだ現れてもいない魔王討伐へのやる気に燃えていたが、肩慣らしに魔獣を倒そうと黒い森に一歩足を踏み入れたところで気絶した。共をしていた従僕が必死になって連れ戻さなければ、そのまま命を落としていただろう。その後も懲りずに何度か黒い森に踏み入ろうとしたのだが、結果はいつも同じ。そのうち、父親である祖父に立ち入りを禁じられるまでになった。一族の誰よりも魔王を倒すことを望んでいるのに、誰よりもその資格がない。それでもエメリの父は諦められなかった。武勲を上げて領地を拡大することも、絵に描いたような贅沢な暮らしも。憧れはいつか妄執となり、その皺寄せを食らったのがエメリである。
守護の力を宿して生まれたエメリは、数世代ぶりの勇者となれる子供だ。出産で体力と気力を使い果たしてしまったのだろう、エメリの母親はエメリを産み落とすと同時に息を引き取った。しかしエメリの父親が、それを気に留めることはない。これでようやく一族の復興が果たせるのだと喜ぶばかりだった。
まだ五つにも届かないうちから、剣術や弓術の稽古が始まる。遊びたい盛りに容赦なく鍛えられ、何度も泣き出して逃げ出したがその度に連れ戻された。不憫に思った祖父や侍女が止めに入ろうとしてくれたこともあったけれど、妄執に取り憑かれた父親が止まることはない。自分を助けようとする祖父や侍女にまで容赦なく手をあげる父の姿を見て、エメリは幼いながらに覚悟を決める。血反吐を吐くような厳しい稽古の日々を、耐え抜くしかないのだと。
そうして時は流れ、エメリの祖父が老衰で息を引き取って数ヶ月後。このまま魔王が誕生せず討伐に行けないのであれば自ら魔王城に乗り込み魔族の首をとってこい、それができないのであればせめて守護の力を宿す子を成せと迫られる頃。とうとう父親の待望の瞬間は訪れた。大地を裂くような雷鳴が轟、王国全土を覆うような暗雲が黒い森から立ち込める――魔王が誕生したのだ。
「逃げたら怒られる、よね」
やはり誰も聞いていないのを良いことにそんなことを呟く。父親に聞かれていたら間違いなく殴られていただろう。稽古を嫌がるエメリを脅すように、昔から父親が繰り返す言葉がある。
「私たちが何不自由なく暮らせるのはどうしてかわかるか? 魔王を倒してきた一族だからだ」
「叶うなら私がこの手で魔王を討伐したかった。魔族を根絶やしにしたかった。だが、それは叶わない」
「だからお前がやるんだ、エメリ。お前が一族の悲願を果たすのだ」
幼いエメリにはその言葉がどれだけ無茶苦茶なのかがわからなかった。わかるのは、父親が果たせなかったことをエメリが果たさなければならないということだけ。戦いたくなんてないし、そもそも戦うことに向いていないし、本当は勇者じゃなくて薬師になりたい。けれど、それでもエメリはやらなければならない。
「やだなあー……」
立てた膝に顔を埋め、肺の中の息を絞り出す。やりたくなくても、向いていなくても、やらなければならない。魔王が誕生し、国王から勅命も受けてしまった今、守護の力を宿したエメリは正真正銘の勇者となってしまったから。
王国の平和のために戦うことが、彼女の責務だから。