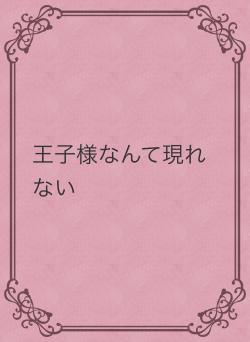エリシアの妃教育が開始したのとほぼ並行して、シルビオはキシュ王国の調査で忙しくなった。最優先は、消えた村人の行方を突き止めること。日夜、王国と帝国を往復して調査を進めているのだけれど、状況は芳しくない。
調べるにつれて、謎は深まるばかりだ。捕らえた王国兵を尋問しても、「国王夫妻に、帝国兵が侵入してきたら攻撃するよう言われた」と口を揃えて言われるだけ。国王夫妻が自害した際に衛兵が近くにいなかったことも、「命じられて席を外していた」とのこと。帝国の村で行方不明者が出ていることや、貴族が姿をくらましていることに至っては、誰も知らない。命令を下したとされる国王夫妻には事情を聞きたくとも聞けないのだから、ほとんど進展はないと言っていいだろう。
唯一進展があったとすれば、エリシア王女はよく転移魔法を使って姿を消していたという情報を得られたこと。王女が頻繁に姿を消して警備上問題はないのか、と言いたいところだけれど。稀代の魔法使いにそんな心配は杞憂だろうか。いずれにせよ、どこに姿を消していたのかは誰も知らないので結局進展はない。
「殿下」
どうしたものか、と王国から帰ってきて執務室で頭を抱えているときだった。エリシアの侍女に呼ばれたというリオンが戻ってくる。
「ああ、なんだった?」
「エリシア様から手紙が届いています」
「手紙ぃ?」
訝しむシルビオに、リオンが封筒とペーパーナイフを差し出す。どういう風の吹き回しだろうか。ご丁寧に封蝋までされているそれを開くと、中からは便箋が一枚。当たり障りのない季節の挨拶と、できれば今夜にでも話したいという内容が、丸っこい字で書かれている。
「なんて書いてあったんです?」
気づけば眉間に皺を寄せていたシルビオに、リオンが好奇心も隠さず尋ねる。無言で便箋を押し付けると、「えっ、そんな険しい顔する場所ありました?」とリオンは目を丸くした。
「いきなり俺と話したいとか言い出すか? あんな気の強い女が」
「気が強い以前に、婚約者ですから。ここ最近全く顔を合わせていないので、自然なことかと」
「どうだか。絶対なんか企んでんだろ」
「……」
シルビオが皇宮に呼び寄せられてから、十年の付き合いになるリオン。唯一の忠臣と言える彼は、シルビオの意志を尊重して口を噤む。が、口ほどにものを言う目が、非難するようにシルビオを見つめた。「なんだよ」と促すと、リオンは慎重に口を開く。
「恐れながら殿下は、エリシア様に対して悪印象を抱きすぎかと」
「はあ?」
予想外の言葉に素っ頓狂な声をあげるシルビオ。リオンはやれやれ、と言った様子で首を振る。便箋を元のように折りたたんで渡されるのを受け取りながら、「悪印象も何も。怪しすぎるんだよ、あいつ」とぶっきらぼうに返す。「怪しいとは?」と首を傾げるリオンに、正気かと疑ってしまった。
「そもそも、どう見てもエリシア王女じゃねえ」
「まだ確定していませんよ」
「ほぼ確定だろ」
王国兵の誰に聞いても、エリシア王女と言えば白金の髪をした稀代の魔法使いだと言っている。どれだけのストレスや精神的負荷がかかったとしても、魔力の消失はともかくとして、あそこまで艶やかな黒髪に染まることはまずない。
「では、エリシア王女でないとしたら、彼女は一体誰だとお考えで?」
「……」
その問いに対する答えは持ち合わせていない。他人の空似、あるいは公にはなっていない姉妹。有力なのは後者だけれど、その答えにはなんとなく辿りつきたくなかった。「赤の他人の顔を魔法で自分そっくりに似せたとか」と苦し紛れに言ってみると、「それなら髪色もそっくりにするでしょう」と返された。その通りである。
「けど、本当に王女だとして、あんなに何も知らないなんてことがあるか?」
「確かに疑問は残りますが……兵士たちは、国王から指示を受けたと言っているのですから、矛盾は一応ないかと」
今は亡き国王。その国王が娘には何も知らせずに、王国兵に指示を出した可能性は十分にある。けれど、相手は魔法を信仰するキシュ王国なのだ。稀代の魔法使いと謳われる王女がいながら、有事の際に全く頼らないなんてことがあるだろうか。それとも、貴重な魔法使いだからこそ、戦場には駆り出さなかったとでも言うのだろうか。いずれにせよ、死人に口無し。どういう意図で国王が娘を関わらせなかったのかは結局迷宮入りだ。
「エリシア様が何も知らなさそうなのは事実ですが、殿下にずっと疑われるのは少々酷かと」
「……お前はなんでそこまであいつに同情的なんだよ」
「逆にどうして殿下はそこまでエリシア様を嫌うのです?」
「嫌いってほどじゃ……」
「意図的に避けているのは事実でしょう?」
「……」
忠臣は思った以上に目敏い。ちょうど妃教育が始まった頃と並行して、シルビオが執務や調査で忙しくなったことは事実。けれど、エリシアとろくに会話も交わしていないのは、忙しいからだけではない。リオンの言う通り、シルビオがエリシアとの会話を避けているからだ。黙ったままでいると、「エリシア様の妃教育の様子は、殿下も聞き及んでいるはずです」とリオンが続ける。
「確かに、王国で十分な教育が為されたとは言い難い様子には、疑問が残ります。ですが、本人の努力と素質には目を見張るものがあると、どの教師からも評判です」
「……」
「彼女が王女であろうとそうでなかろうと、殿下の婚約者として努力していることについては認めた方がよろしいのでは?」
リオンの言葉は何も間違っていない。意思とは関係なく婚約を結ばされても、妃教育を受けさせられても。シルビオに対して強気な物言いをすることはあれど、エリシアは文句や不満の類を一切口にしなかった。特に、一国の王女に妃教育を受けろだなんて、母国での教育が足りないと馬鹿にされているようなもの。唐突に連れて来られた異国、しかも心の底から信用できる味方もいない。彼女の本心や思惑はどうあれ、状況を鑑みればよく耐えているほうだと思う。実際、兄嫁予定のセレステにも似たようなことは言われた。
エリシアと名乗る彼女の正体がどうであれ、婚約が破棄されることは恐らくない。皇帝の大陸制覇という悲願を成し遂げるためには、彼女とシルビオの結婚がどうしても欠かせないからだ。それなら婚約者としても、王国で起きたあれこれの事件を解決するためにも、彼女とは仲を深めておくに越したことはない。シルビオだって、本当はわかっている。
「……あいつと、話してると」
わかっているけれど、だ。じっと耳を傾けるリオン相手に、シルビオは重たい口を開いた。
「なんか、落ち着かねえんだよ」
「落ち着かない、とは?」
「心臓がソワソワして、胸の辺りを掻きむしりたくなる」
「は?」
「だから会いたくねえ」
思えば、聖堂で初めて会ったときからそうだった。魔法にかけられたように動悸が収まらず、心臓がうるさく脈を打つ。リオンにも宮廷魔術師にも異常はないと言われたけれど、エリシアと顔を合わせるたびに定期的にそうなるのだ。だからシルビオはエリシアと名乗る彼女をずっと怪しんでいるし、できれば長く顔を合わせたくないとも思う。表面上だけでも仲良くしたほうがいいとわかっているのに、本能がそれを拒絶しているのだ。
「それは……」
黙って聞いていたリオンが、ようやく口を開いた。その表情はどこか困惑したようにも見える。どうしてそんな顔をされるのか、と訝しむシルビオに、リオンはとんでもないことを告げた。
「それは、恋では?」
「……は?」
*
夜。湯浴みを済ませたシルビオは、隣の部屋の扉をノックしていた。
「はーい……って、殿下?」
「よお」
ネグリジェ姿の彼女はぱち、と目を瞬く。急に訪ねてきたシルビオに驚いているように見えるが、特に何も聞き返さず部屋に入るよう促した。侍女はもう下がっているから仕方がないとしても、こんな夜更けに尋ねてきた相手に警戒することもなく扉を開け、あまつさえ部屋に招き入れるとは。手紙で呼び出したのが自分自身とはいえ、シルビオが無体を働くとは思っていないのだろうか。婚約しているのだから一線を越えたとしても別に構わないとは思うが、警戒心はないのかと言いたくなった。
促されるままに、ソファに腰を下ろす。サイドテーブルの水差しから水を注ぐのを待つ間、なんとなく部屋を見渡した。シルビオが訪れなかった数日の間で、ほんの少しだけ模様替えしたらしい。新しく増えた調度品はなさそうだけれど、壁紙やカーテンの色が変わっている。
「手紙を読んでくださったの?」
シルビオに水の入ったコップを差し出しながら、エリシアは隣に腰掛ける。湯浴みを済ませているからだろう、ふわりと香る石鹸の匂いのせいでなんだか落ち着かない。胸の辺りがソワソワするのを誤魔化すようにして水をがぶ飲みし、「ああ」と短く答えた。無言ではにかむ彼女はほんの少し嬉しそうで、しっとり濡れた髪の毛をわしゃわしゃに乱してやりたい衝動に駆られる。
「で? 話したいことって?」
よくわからない衝動も、心臓が落ち着かないのも一旦無視だ。素っ気なさを取り繕って本題を切り出す。昼間にリオンに言われた言葉が頭を過ぎるせいもあって、なんだか無駄に緊張してしまう。隣でシルビオが必死に平静を保とうとしているのも知らず、エリシアは気合を入れた様子で口を開いた。
「私たち、あまりにもお互いのことを知らないでしょう?」
「まあ、そうだな」
「仮にも王国と帝国の和平が名目なら、せめてもう少し歩み寄ってお互いのことを知る必要があると思って」
エリシアの言い分は至極真っ当だ。シルビオだって、そうしたほうがいいことはわかっている。口を閉ざすシルビオに、「でも、昼間はお互いに妃教育とか執務とかで忙しいでしょう? だから、夜ならお話しできるかと思って手紙を書いたの」と理由を告げた。いつもと違う、棘のない口ぶりにほんの少し驚く。気が強く、生意気だとばかり思い込んでいたけれど、あれは虚勢を張っているだけなのだろうか。ますます、目の前の彼女の本質がよくわからない。
「あの……まず、謝らなければいけないことがあるの」
「謝る?」
どれのことだ、と首を傾げた。売り言葉に買い言葉で散々言い合いしてきたのだ、エリシアのみならずシルビオにだって謝ることはたくさんある。それとも、もしかしてエリシア王女ではないことをようやく認めて謝るつもりなのだろうか。固唾を飲んで続きの言葉を待つ。
「髪のことで、嫌な言い方をしてしまってごめんなさい」
「……髪?」
「今日、セレステ様から聞いたの」
「何を」
「あなたの生い立ちです」
「!」
目を見開くシルビオ。古傷を指を這わされ、爪を立てられたような感覚。とっくの昔に塞がって瘡蓋も剥がれたけれど、醜く引き攣った跡は残ったまま。恥じているわけではないし、隠しているわけでもない。いずれは誰かの口から聞かされていただろう。むしろ、兄の婚約者であり昔馴染みでもあるセレステが話してくれるのが、一番公平性が保たれていると言ってもいい。けれど、どうしてだろうか。
――知られたくなかった。
翡翠の瞳に、同情と憐憫が宿る。人の過去も知らずに揶揄するような態度を取ったことを、心底から反省しているのだろう。きっと何も間違っていないし、エリシアの善性の現れだろう。頭では理解しているが、納得することはできなかった。同情されるような目で見られるぐらいなら、何も知らずに煽ってくれたほうがまだよかった。
「あの、髪の色なんて別に気にすることないと思うし……」
「お互いのことを知ろうっていうんなら」
エリシアの言葉を遮る。これ以上、その話を広げたくはなかった。グッと掴んだ手首は、シルビオの手が一周して余りある。翡翠の瞳を瞬かせてシルビオを見る彼女を見ていると、腹の底から熱い何かが湧き上がるようだ。こんな感情が恋であってたまるか、そう思いながら吐き捨てるように続ける。
「手っ取り早い方法があるけど?」
「へっ……きゃっ!?」
掴んだ手首を押してソファに押し倒すと、エリシアは素っ頓狂な声を上げた。豊かで艶やかな黒髪が、ソファに散らばる。強気な態度や物言いは見る影もない。口をぱくぱくと開けては閉め、目を白黒とさせているあたり状況がなかなか飲み込めないらしい。この行為が意味するものを本当にわかっていないのだろうか、と怪訝に思う反面、胸の内がスッとする。
――泣かしてやりたい。
自分でも最低なことを思っている自覚はある。こんなことをしたところで無意味なこともわかりきっている。けれど、その目に映る同情を、翡翠が浮かべる憐憫を、どうにかして別の何かに塗り替えてやりたかった。
調べるにつれて、謎は深まるばかりだ。捕らえた王国兵を尋問しても、「国王夫妻に、帝国兵が侵入してきたら攻撃するよう言われた」と口を揃えて言われるだけ。国王夫妻が自害した際に衛兵が近くにいなかったことも、「命じられて席を外していた」とのこと。帝国の村で行方不明者が出ていることや、貴族が姿をくらましていることに至っては、誰も知らない。命令を下したとされる国王夫妻には事情を聞きたくとも聞けないのだから、ほとんど進展はないと言っていいだろう。
唯一進展があったとすれば、エリシア王女はよく転移魔法を使って姿を消していたという情報を得られたこと。王女が頻繁に姿を消して警備上問題はないのか、と言いたいところだけれど。稀代の魔法使いにそんな心配は杞憂だろうか。いずれにせよ、どこに姿を消していたのかは誰も知らないので結局進展はない。
「殿下」
どうしたものか、と王国から帰ってきて執務室で頭を抱えているときだった。エリシアの侍女に呼ばれたというリオンが戻ってくる。
「ああ、なんだった?」
「エリシア様から手紙が届いています」
「手紙ぃ?」
訝しむシルビオに、リオンが封筒とペーパーナイフを差し出す。どういう風の吹き回しだろうか。ご丁寧に封蝋までされているそれを開くと、中からは便箋が一枚。当たり障りのない季節の挨拶と、できれば今夜にでも話したいという内容が、丸っこい字で書かれている。
「なんて書いてあったんです?」
気づけば眉間に皺を寄せていたシルビオに、リオンが好奇心も隠さず尋ねる。無言で便箋を押し付けると、「えっ、そんな険しい顔する場所ありました?」とリオンは目を丸くした。
「いきなり俺と話したいとか言い出すか? あんな気の強い女が」
「気が強い以前に、婚約者ですから。ここ最近全く顔を合わせていないので、自然なことかと」
「どうだか。絶対なんか企んでんだろ」
「……」
シルビオが皇宮に呼び寄せられてから、十年の付き合いになるリオン。唯一の忠臣と言える彼は、シルビオの意志を尊重して口を噤む。が、口ほどにものを言う目が、非難するようにシルビオを見つめた。「なんだよ」と促すと、リオンは慎重に口を開く。
「恐れながら殿下は、エリシア様に対して悪印象を抱きすぎかと」
「はあ?」
予想外の言葉に素っ頓狂な声をあげるシルビオ。リオンはやれやれ、と言った様子で首を振る。便箋を元のように折りたたんで渡されるのを受け取りながら、「悪印象も何も。怪しすぎるんだよ、あいつ」とぶっきらぼうに返す。「怪しいとは?」と首を傾げるリオンに、正気かと疑ってしまった。
「そもそも、どう見てもエリシア王女じゃねえ」
「まだ確定していませんよ」
「ほぼ確定だろ」
王国兵の誰に聞いても、エリシア王女と言えば白金の髪をした稀代の魔法使いだと言っている。どれだけのストレスや精神的負荷がかかったとしても、魔力の消失はともかくとして、あそこまで艶やかな黒髪に染まることはまずない。
「では、エリシア王女でないとしたら、彼女は一体誰だとお考えで?」
「……」
その問いに対する答えは持ち合わせていない。他人の空似、あるいは公にはなっていない姉妹。有力なのは後者だけれど、その答えにはなんとなく辿りつきたくなかった。「赤の他人の顔を魔法で自分そっくりに似せたとか」と苦し紛れに言ってみると、「それなら髪色もそっくりにするでしょう」と返された。その通りである。
「けど、本当に王女だとして、あんなに何も知らないなんてことがあるか?」
「確かに疑問は残りますが……兵士たちは、国王から指示を受けたと言っているのですから、矛盾は一応ないかと」
今は亡き国王。その国王が娘には何も知らせずに、王国兵に指示を出した可能性は十分にある。けれど、相手は魔法を信仰するキシュ王国なのだ。稀代の魔法使いと謳われる王女がいながら、有事の際に全く頼らないなんてことがあるだろうか。それとも、貴重な魔法使いだからこそ、戦場には駆り出さなかったとでも言うのだろうか。いずれにせよ、死人に口無し。どういう意図で国王が娘を関わらせなかったのかは結局迷宮入りだ。
「エリシア様が何も知らなさそうなのは事実ですが、殿下にずっと疑われるのは少々酷かと」
「……お前はなんでそこまであいつに同情的なんだよ」
「逆にどうして殿下はそこまでエリシア様を嫌うのです?」
「嫌いってほどじゃ……」
「意図的に避けているのは事実でしょう?」
「……」
忠臣は思った以上に目敏い。ちょうど妃教育が始まった頃と並行して、シルビオが執務や調査で忙しくなったことは事実。けれど、エリシアとろくに会話も交わしていないのは、忙しいからだけではない。リオンの言う通り、シルビオがエリシアとの会話を避けているからだ。黙ったままでいると、「エリシア様の妃教育の様子は、殿下も聞き及んでいるはずです」とリオンが続ける。
「確かに、王国で十分な教育が為されたとは言い難い様子には、疑問が残ります。ですが、本人の努力と素質には目を見張るものがあると、どの教師からも評判です」
「……」
「彼女が王女であろうとそうでなかろうと、殿下の婚約者として努力していることについては認めた方がよろしいのでは?」
リオンの言葉は何も間違っていない。意思とは関係なく婚約を結ばされても、妃教育を受けさせられても。シルビオに対して強気な物言いをすることはあれど、エリシアは文句や不満の類を一切口にしなかった。特に、一国の王女に妃教育を受けろだなんて、母国での教育が足りないと馬鹿にされているようなもの。唐突に連れて来られた異国、しかも心の底から信用できる味方もいない。彼女の本心や思惑はどうあれ、状況を鑑みればよく耐えているほうだと思う。実際、兄嫁予定のセレステにも似たようなことは言われた。
エリシアと名乗る彼女の正体がどうであれ、婚約が破棄されることは恐らくない。皇帝の大陸制覇という悲願を成し遂げるためには、彼女とシルビオの結婚がどうしても欠かせないからだ。それなら婚約者としても、王国で起きたあれこれの事件を解決するためにも、彼女とは仲を深めておくに越したことはない。シルビオだって、本当はわかっている。
「……あいつと、話してると」
わかっているけれど、だ。じっと耳を傾けるリオン相手に、シルビオは重たい口を開いた。
「なんか、落ち着かねえんだよ」
「落ち着かない、とは?」
「心臓がソワソワして、胸の辺りを掻きむしりたくなる」
「は?」
「だから会いたくねえ」
思えば、聖堂で初めて会ったときからそうだった。魔法にかけられたように動悸が収まらず、心臓がうるさく脈を打つ。リオンにも宮廷魔術師にも異常はないと言われたけれど、エリシアと顔を合わせるたびに定期的にそうなるのだ。だからシルビオはエリシアと名乗る彼女をずっと怪しんでいるし、できれば長く顔を合わせたくないとも思う。表面上だけでも仲良くしたほうがいいとわかっているのに、本能がそれを拒絶しているのだ。
「それは……」
黙って聞いていたリオンが、ようやく口を開いた。その表情はどこか困惑したようにも見える。どうしてそんな顔をされるのか、と訝しむシルビオに、リオンはとんでもないことを告げた。
「それは、恋では?」
「……は?」
*
夜。湯浴みを済ませたシルビオは、隣の部屋の扉をノックしていた。
「はーい……って、殿下?」
「よお」
ネグリジェ姿の彼女はぱち、と目を瞬く。急に訪ねてきたシルビオに驚いているように見えるが、特に何も聞き返さず部屋に入るよう促した。侍女はもう下がっているから仕方がないとしても、こんな夜更けに尋ねてきた相手に警戒することもなく扉を開け、あまつさえ部屋に招き入れるとは。手紙で呼び出したのが自分自身とはいえ、シルビオが無体を働くとは思っていないのだろうか。婚約しているのだから一線を越えたとしても別に構わないとは思うが、警戒心はないのかと言いたくなった。
促されるままに、ソファに腰を下ろす。サイドテーブルの水差しから水を注ぐのを待つ間、なんとなく部屋を見渡した。シルビオが訪れなかった数日の間で、ほんの少しだけ模様替えしたらしい。新しく増えた調度品はなさそうだけれど、壁紙やカーテンの色が変わっている。
「手紙を読んでくださったの?」
シルビオに水の入ったコップを差し出しながら、エリシアは隣に腰掛ける。湯浴みを済ませているからだろう、ふわりと香る石鹸の匂いのせいでなんだか落ち着かない。胸の辺りがソワソワするのを誤魔化すようにして水をがぶ飲みし、「ああ」と短く答えた。無言ではにかむ彼女はほんの少し嬉しそうで、しっとり濡れた髪の毛をわしゃわしゃに乱してやりたい衝動に駆られる。
「で? 話したいことって?」
よくわからない衝動も、心臓が落ち着かないのも一旦無視だ。素っ気なさを取り繕って本題を切り出す。昼間にリオンに言われた言葉が頭を過ぎるせいもあって、なんだか無駄に緊張してしまう。隣でシルビオが必死に平静を保とうとしているのも知らず、エリシアは気合を入れた様子で口を開いた。
「私たち、あまりにもお互いのことを知らないでしょう?」
「まあ、そうだな」
「仮にも王国と帝国の和平が名目なら、せめてもう少し歩み寄ってお互いのことを知る必要があると思って」
エリシアの言い分は至極真っ当だ。シルビオだって、そうしたほうがいいことはわかっている。口を閉ざすシルビオに、「でも、昼間はお互いに妃教育とか執務とかで忙しいでしょう? だから、夜ならお話しできるかと思って手紙を書いたの」と理由を告げた。いつもと違う、棘のない口ぶりにほんの少し驚く。気が強く、生意気だとばかり思い込んでいたけれど、あれは虚勢を張っているだけなのだろうか。ますます、目の前の彼女の本質がよくわからない。
「あの……まず、謝らなければいけないことがあるの」
「謝る?」
どれのことだ、と首を傾げた。売り言葉に買い言葉で散々言い合いしてきたのだ、エリシアのみならずシルビオにだって謝ることはたくさんある。それとも、もしかしてエリシア王女ではないことをようやく認めて謝るつもりなのだろうか。固唾を飲んで続きの言葉を待つ。
「髪のことで、嫌な言い方をしてしまってごめんなさい」
「……髪?」
「今日、セレステ様から聞いたの」
「何を」
「あなたの生い立ちです」
「!」
目を見開くシルビオ。古傷を指を這わされ、爪を立てられたような感覚。とっくの昔に塞がって瘡蓋も剥がれたけれど、醜く引き攣った跡は残ったまま。恥じているわけではないし、隠しているわけでもない。いずれは誰かの口から聞かされていただろう。むしろ、兄の婚約者であり昔馴染みでもあるセレステが話してくれるのが、一番公平性が保たれていると言ってもいい。けれど、どうしてだろうか。
――知られたくなかった。
翡翠の瞳に、同情と憐憫が宿る。人の過去も知らずに揶揄するような態度を取ったことを、心底から反省しているのだろう。きっと何も間違っていないし、エリシアの善性の現れだろう。頭では理解しているが、納得することはできなかった。同情されるような目で見られるぐらいなら、何も知らずに煽ってくれたほうがまだよかった。
「あの、髪の色なんて別に気にすることないと思うし……」
「お互いのことを知ろうっていうんなら」
エリシアの言葉を遮る。これ以上、その話を広げたくはなかった。グッと掴んだ手首は、シルビオの手が一周して余りある。翡翠の瞳を瞬かせてシルビオを見る彼女を見ていると、腹の底から熱い何かが湧き上がるようだ。こんな感情が恋であってたまるか、そう思いながら吐き捨てるように続ける。
「手っ取り早い方法があるけど?」
「へっ……きゃっ!?」
掴んだ手首を押してソファに押し倒すと、エリシアは素っ頓狂な声を上げた。豊かで艶やかな黒髪が、ソファに散らばる。強気な態度や物言いは見る影もない。口をぱくぱくと開けては閉め、目を白黒とさせているあたり状況がなかなか飲み込めないらしい。この行為が意味するものを本当にわかっていないのだろうか、と怪訝に思う反面、胸の内がスッとする。
――泣かしてやりたい。
自分でも最低なことを思っている自覚はある。こんなことをしたところで無意味なこともわかりきっている。けれど、その目に映る同情を、翡翠が浮かべる憐憫を、どうにかして別の何かに塗り替えてやりたかった。