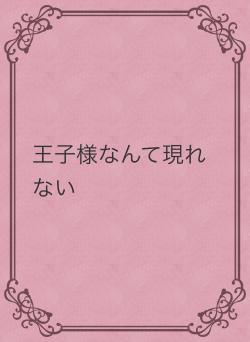晩餐会は、思っていた以上に和やかだったと思う。皇帝はシルビオ同様、エリシアのことを疑っているようだったけれど基本的には善人らしい。食事中にまで、探りを入れてくるようなことはなかった。それでも気を張っていたせいか、シルビオに送られて部屋に戻る頃には疲労困憊。侍女に浴を手伝ってもらって下がらせた後は、朝まで一度も目覚めることなく泥のように眠った。塔の簡素な寝台とも地下牢の硬いベッドとも違う、フカフカのベッドは雲のように柔らかい。もう二度と目覚めなくてもいいとすら思ったけれど、そういうわけにもいかない。
一瞬にも思える至福の時間を過ごした翌朝。やってきた侍女たちに着替えを手伝われ、朝食を取るために広間まで赴く。シルビオは昨日と変わらない様子でテーブルに着いていて、ネリアを見ても仏頂面のままだ。「おはようございます」と挨拶すると、「……ああ」とだけ返ってきた。使用人たちの間で不仲が広まったらどうするのだろう、婚約破棄になったりしないだろうか、と期待を込めながら席に着く。逆らえないから従うけれど、できれば好いてくれる人と結婚したいのだ。間違っても、自分を嫌っている人とは結婚したくない。
侍女が取り分けてくれる朝食を、塔では朝からこんなに食べたことないなと思いながら手をつける。帝国は領土が広いだけあって、食糧の量も種類も豊富らしい。王国では見たことのない食べ物がたくさん並んでいる。パンを手に取りちぎっていると、コーヒーを手にしたシルビオが不意に口を開いた。
「今日から妃教育を受けてもらおうと思っている」
「妃教育、ですか」
聞き返すネリアに、「王国で教育を受けてきたお前に今更教えることなんてないだろうけど、念のためにな」と無愛想に続ける。めんどくさそうな口調だけれど、正直ネリアとしてはありがたい申し出だ。必要最低限の教養をマリーから教わった程度で、王女としての教育は不十分。エリシアのふりをしているけれど、いつボロが出てもおかしくない。帝国がわざわざ教えてくれるのなら、申し出を受けない理由はなかった。
「ありがとうございます。ぜひ、お願いしたいですわ」
素直にお礼を告げるネリアに、シルビオは怪訝そうな目を向ける。自国をほとんど乗っ取られているような状況なのに呑気かよ、とでも言いたげだけれどそうではない。放っておけば、キシュ王国が消滅しかねないからこそだ。エリシアが、ネリアに対してどこまでの身代わりを求めたのかはわからないけれど、ここでじっとしていればそれこそキシュ王国の王女としての名折れ。ネリアが今すべきことは、状況を判断して行動するための情報を集めることだ。
――エリシアの身代わりを務めるためにも、王国を救うためにも、私が頑張るしかない。
ネリアは王女としての責任感に燃えていた。
*
シルビオに宣言された通り、その日のうちから妃教育は始まった。
礼儀作法から、帝国の歴史や文化、果ては舞踏会でのダンスの練習まで。朝から晩までみっちりと入れられたスケジュールと、基礎的な内容から鑑みるに、ネリアが王国でろくな教育を受けていないと決めつけているようだ。シルビオの、「王国で教育を受けてきたお前に今更教えることなんてないだろうけど」という言葉は正しく社交辞令でしかなかったのだと痛感する。教育を受けていないことは事実なので別に構わないけれど、王女ではないと疑われているのはやはり心外だ。ネリアはネリアなりに、王女としての務めを果たしてきたつもりだったのに。
――王国は、今どうなっているんだろう。
王国を救うため、情報収集に勤しむネリアだけれど、学べば学ぶほど理解する。キシュ王国は、コーア帝国に国力で劣っているという事実を。国土は王国の約四倍、人口は約三倍。魔法を使える人口は全体の三分の一程度だけれど、その分科学というものが発展しているので生活に不便はない。おまけに魔力封じの腕輪を発明するぐらいには、魔法自体もそれなりに発展している。国民のほぼ全員が魔法を使えるとはいえ、どう抗ったところで王国は帝国に対して勝ち目などないのだ。
国王も貴族もいないキシュ王国は現在、コーア帝国が統治している。それがいつまでになるかを皇帝は明言しなかった。きっと一時的ではないことには、さすがに気がついている。王女エリシアと皇弟シルビオで婚約を結ばされたことが何よりの証拠だ。長期的にキシュ王国を王位継承者不在の状態にして、しれっと国を吸収するつもりなのだろう。キシュ王国はやはり消滅または乗っ取りの危機に瀕している、けれど。
――国民にとって、幸せなのはどちらなんだろう。
キシュ王国の様子を、民衆の暮らしを、間近で見たことがあるわけではない。塔の上から眺める国民の姿は、幸せそうに見えた。けれど、それはネリアの願望込みの姿だったのかもしれない。物心がつく前から、ネリアは誰にも知られずひっそりと塔に閉じ込められて生きてきた。「みんなが幸せなら、文句も不満も言わないで耐えられる」という尊い自己犠牲精神は、「文句も不満も言わないで耐えるから、せめてみんなが幸せであってほしい」という願望の裏返しだと言ってもいい。そうやって今までの十八年間を、エリシアとマリー以外の誰にも知られずひっそりと生きてきた。
けれど、結果としてネリアは外に出てしまい、王国はとてもじゃないけれど幸せとは言えない状態に陥っている。どうにかするのがネリアの王女としての務めで、だからこそ妃教育を利用して情報を集めたのだけれど。結果として知り得たのは、キシュ王国があまりにもコーア帝国に比べて弱い立場にあるということ。それならばいっそのこと、帝国の一部として生きる道を選んだ方が民衆にとって幸せなのではないかということ。
そんなことが頭を過ぎったときだった。
「精が出るのね?」
「! セレステ様!?」
書庫で真剣に調べ物をしていたせいか、すぐ後ろにセレステが来ていることにも気づかなかった。慌てて立ちあがろうとすると、「そのままで大丈夫よ」と笑顔で制される。迷ったけれど、厚意を固辞するのも失礼にあたるだろう。浮かせた腰を再び下ろすと、セレステはその隣に腰を下ろす。
「この間は、お手紙と花束をありがとう。とっても素敵だから、お花は部屋に飾ってあるの」
「とんでもございません。こちらこそ、あのときはありがとうございました」
彼女と話すのは晩餐会以来のこと。その翌日にドレスを頂いたお礼として、手紙と小さな花束を贈ったけれど、喜んでもらえてよかったと心の底から安心した。誰かに贈り物を贈るなんて、エリシアとマリーにしか経験がない。息を吐いていると、「書庫に用事があって来てみたら、姿を見かけたものだから。思わず話しかけてしまったのだけれど、お邪魔だったかしら?」と尋ねられる。
「いいえ、全然! 嬉しいです」
「それならよかったわ」
ニコニコと微笑むセレステは、第一印象と変わらず綺麗で優しい。王国からやって来た訳ありの王女なんて、きっと接しにくくて仕方ないだろうに。婚約者であるシルビオには終始冷たくされているので、セレステの優しさが余計に沁みた。
「これは、妃教育の?」
「はい。先生から宿題を出されたので、文化や歴史を調べていたところです」
「そう……毎日、よく頑張っているのね」
「! い、え……」
頑張っている、だなんて褒められると思っていなかったので、エリシアを取り繕うこともできなかった。「全然、本当に全然、そんなことは……」と吃ったように返すことしかできない。こうやって真正面から褒められたことは、今までの人生でなかったのだ。労わるような口調はまるで本当の姉のようで、甘えてしまいたくなる。ドキドキしていると、「王国から嫁ぐことになって、大変なことがたくさんあると思うわ」とセレステはネリアをまっすぐ見つめて口を開いた。
「困ったことがあったらいつでも仰ってね。私でよければ、力になるから」
「あ、りがとうございます……」
思わず泣きそうになったのを一生懸命に堪える。こんな簡単なことで絆されてちょろいな、と自分でも思ったけれど仕方がない。帝国に来てからずっと、頼れる人も優しくしてくれる人もいなかったのだ。真正面からこうやって甘やかされて、心を開かないわけがない。もしかしたら皇帝に言われて様子を見に来たのかもしれないし、セレステ自身に何か思惑があるのかもしれない。けれど、それでもいい。一時でも優しくしてくれるのだから、利用されたって構わないとさえ思った。
ふとそこで、ネリアは閃いた。そう、利用されたって構わない。その代わり、ネリアも頼らせてもらいたい。
「セレステ様、一つご相談しても良いですか?」
「ええ、もちろん」
*
翌日、ネリアは机に向かっていた。理由はただ一つ、シルビオに手紙を書くためだ。
「これで大丈夫かしら」
出来上がった文面に問題がないか、正直不安でたまらない。何度も書き直したせいで、机の隅には書き損じた便箋がいくつも重なっている。侍女たちに用意してもらったのに、無駄にしているようで申し訳ない。けれど、下手な手紙を送ってまともに取り合ってくれない事態は避けたかった。
「サラ。この手紙、殿下に届けてくれる?」
「かしこまりました」
ようやく書き上げた手紙を丁寧に封蝋し、侍女に託す。サラが部屋から出ていくのを見届けていると、ケイトが弾んだように話しかけてきた。
「殿下もきっとお喜びになりますよ」
「そうだと良いけれど」
きっと喜ぶことはないと思ったけれど、曖昧に笑って誤魔化す。シルビオに手紙を書いてはどうか、と提案してくれたのはセレステ。昨日、「殿下ともっと話したいけれど、どうきっかけを作ったら良いかわからない」と相談したのがきっかけだった。
王国と帝国の国力の差を痛感したネリア。国の今後を決めるためにも、まずこの目で王国の様子を見ることが先決だと考えた。けれど、今のネリアが頼んだところでシルビオが素直に帰してくれないことは火を見るより明らか。一体何を企んでいるんだ、と疑われるのが関の山だろう。
本当はネリアのことを好きな人と結婚したいし、嫌われたまま結婚するぐらいなら、いっそのこと婚約破棄にならないかなと望んでもいた。けれど、国のことを思うのならそんなわがままは言っていられない。シルビオと結婚することが、王国にとって最善の選択ならば、シルビオに歩み寄るための努力は厭うべきではない。
平和に王国へ帰してもらうには、まずシルビオからの信頼を得る必要がある。そのためにはシルビオのことをよく知ることから始めなければならないけれど、彼と話す機会は滅多にない。朝食のときに少し顔を合わせるだけで、昼間はお互いに妃教育や皇弟としての執務で忙しく、夜は別々に眠る。だから、手紙を書いたのだ。
――読んでくれるといいな。
生まれて初めて異性に宛てた手紙だ。返事が来るかはわからないけれど、せめて読んでもらえればいい。そんなことを考えながら、今日の妃教育の準備を進めた。
一瞬にも思える至福の時間を過ごした翌朝。やってきた侍女たちに着替えを手伝われ、朝食を取るために広間まで赴く。シルビオは昨日と変わらない様子でテーブルに着いていて、ネリアを見ても仏頂面のままだ。「おはようございます」と挨拶すると、「……ああ」とだけ返ってきた。使用人たちの間で不仲が広まったらどうするのだろう、婚約破棄になったりしないだろうか、と期待を込めながら席に着く。逆らえないから従うけれど、できれば好いてくれる人と結婚したいのだ。間違っても、自分を嫌っている人とは結婚したくない。
侍女が取り分けてくれる朝食を、塔では朝からこんなに食べたことないなと思いながら手をつける。帝国は領土が広いだけあって、食糧の量も種類も豊富らしい。王国では見たことのない食べ物がたくさん並んでいる。パンを手に取りちぎっていると、コーヒーを手にしたシルビオが不意に口を開いた。
「今日から妃教育を受けてもらおうと思っている」
「妃教育、ですか」
聞き返すネリアに、「王国で教育を受けてきたお前に今更教えることなんてないだろうけど、念のためにな」と無愛想に続ける。めんどくさそうな口調だけれど、正直ネリアとしてはありがたい申し出だ。必要最低限の教養をマリーから教わった程度で、王女としての教育は不十分。エリシアのふりをしているけれど、いつボロが出てもおかしくない。帝国がわざわざ教えてくれるのなら、申し出を受けない理由はなかった。
「ありがとうございます。ぜひ、お願いしたいですわ」
素直にお礼を告げるネリアに、シルビオは怪訝そうな目を向ける。自国をほとんど乗っ取られているような状況なのに呑気かよ、とでも言いたげだけれどそうではない。放っておけば、キシュ王国が消滅しかねないからこそだ。エリシアが、ネリアに対してどこまでの身代わりを求めたのかはわからないけれど、ここでじっとしていればそれこそキシュ王国の王女としての名折れ。ネリアが今すべきことは、状況を判断して行動するための情報を集めることだ。
――エリシアの身代わりを務めるためにも、王国を救うためにも、私が頑張るしかない。
ネリアは王女としての責任感に燃えていた。
*
シルビオに宣言された通り、その日のうちから妃教育は始まった。
礼儀作法から、帝国の歴史や文化、果ては舞踏会でのダンスの練習まで。朝から晩までみっちりと入れられたスケジュールと、基礎的な内容から鑑みるに、ネリアが王国でろくな教育を受けていないと決めつけているようだ。シルビオの、「王国で教育を受けてきたお前に今更教えることなんてないだろうけど」という言葉は正しく社交辞令でしかなかったのだと痛感する。教育を受けていないことは事実なので別に構わないけれど、王女ではないと疑われているのはやはり心外だ。ネリアはネリアなりに、王女としての務めを果たしてきたつもりだったのに。
――王国は、今どうなっているんだろう。
王国を救うため、情報収集に勤しむネリアだけれど、学べば学ぶほど理解する。キシュ王国は、コーア帝国に国力で劣っているという事実を。国土は王国の約四倍、人口は約三倍。魔法を使える人口は全体の三分の一程度だけれど、その分科学というものが発展しているので生活に不便はない。おまけに魔力封じの腕輪を発明するぐらいには、魔法自体もそれなりに発展している。国民のほぼ全員が魔法を使えるとはいえ、どう抗ったところで王国は帝国に対して勝ち目などないのだ。
国王も貴族もいないキシュ王国は現在、コーア帝国が統治している。それがいつまでになるかを皇帝は明言しなかった。きっと一時的ではないことには、さすがに気がついている。王女エリシアと皇弟シルビオで婚約を結ばされたことが何よりの証拠だ。長期的にキシュ王国を王位継承者不在の状態にして、しれっと国を吸収するつもりなのだろう。キシュ王国はやはり消滅または乗っ取りの危機に瀕している、けれど。
――国民にとって、幸せなのはどちらなんだろう。
キシュ王国の様子を、民衆の暮らしを、間近で見たことがあるわけではない。塔の上から眺める国民の姿は、幸せそうに見えた。けれど、それはネリアの願望込みの姿だったのかもしれない。物心がつく前から、ネリアは誰にも知られずひっそりと塔に閉じ込められて生きてきた。「みんなが幸せなら、文句も不満も言わないで耐えられる」という尊い自己犠牲精神は、「文句も不満も言わないで耐えるから、せめてみんなが幸せであってほしい」という願望の裏返しだと言ってもいい。そうやって今までの十八年間を、エリシアとマリー以外の誰にも知られずひっそりと生きてきた。
けれど、結果としてネリアは外に出てしまい、王国はとてもじゃないけれど幸せとは言えない状態に陥っている。どうにかするのがネリアの王女としての務めで、だからこそ妃教育を利用して情報を集めたのだけれど。結果として知り得たのは、キシュ王国があまりにもコーア帝国に比べて弱い立場にあるということ。それならばいっそのこと、帝国の一部として生きる道を選んだ方が民衆にとって幸せなのではないかということ。
そんなことが頭を過ぎったときだった。
「精が出るのね?」
「! セレステ様!?」
書庫で真剣に調べ物をしていたせいか、すぐ後ろにセレステが来ていることにも気づかなかった。慌てて立ちあがろうとすると、「そのままで大丈夫よ」と笑顔で制される。迷ったけれど、厚意を固辞するのも失礼にあたるだろう。浮かせた腰を再び下ろすと、セレステはその隣に腰を下ろす。
「この間は、お手紙と花束をありがとう。とっても素敵だから、お花は部屋に飾ってあるの」
「とんでもございません。こちらこそ、あのときはありがとうございました」
彼女と話すのは晩餐会以来のこと。その翌日にドレスを頂いたお礼として、手紙と小さな花束を贈ったけれど、喜んでもらえてよかったと心の底から安心した。誰かに贈り物を贈るなんて、エリシアとマリーにしか経験がない。息を吐いていると、「書庫に用事があって来てみたら、姿を見かけたものだから。思わず話しかけてしまったのだけれど、お邪魔だったかしら?」と尋ねられる。
「いいえ、全然! 嬉しいです」
「それならよかったわ」
ニコニコと微笑むセレステは、第一印象と変わらず綺麗で優しい。王国からやって来た訳ありの王女なんて、きっと接しにくくて仕方ないだろうに。婚約者であるシルビオには終始冷たくされているので、セレステの優しさが余計に沁みた。
「これは、妃教育の?」
「はい。先生から宿題を出されたので、文化や歴史を調べていたところです」
「そう……毎日、よく頑張っているのね」
「! い、え……」
頑張っている、だなんて褒められると思っていなかったので、エリシアを取り繕うこともできなかった。「全然、本当に全然、そんなことは……」と吃ったように返すことしかできない。こうやって真正面から褒められたことは、今までの人生でなかったのだ。労わるような口調はまるで本当の姉のようで、甘えてしまいたくなる。ドキドキしていると、「王国から嫁ぐことになって、大変なことがたくさんあると思うわ」とセレステはネリアをまっすぐ見つめて口を開いた。
「困ったことがあったらいつでも仰ってね。私でよければ、力になるから」
「あ、りがとうございます……」
思わず泣きそうになったのを一生懸命に堪える。こんな簡単なことで絆されてちょろいな、と自分でも思ったけれど仕方がない。帝国に来てからずっと、頼れる人も優しくしてくれる人もいなかったのだ。真正面からこうやって甘やかされて、心を開かないわけがない。もしかしたら皇帝に言われて様子を見に来たのかもしれないし、セレステ自身に何か思惑があるのかもしれない。けれど、それでもいい。一時でも優しくしてくれるのだから、利用されたって構わないとさえ思った。
ふとそこで、ネリアは閃いた。そう、利用されたって構わない。その代わり、ネリアも頼らせてもらいたい。
「セレステ様、一つご相談しても良いですか?」
「ええ、もちろん」
*
翌日、ネリアは机に向かっていた。理由はただ一つ、シルビオに手紙を書くためだ。
「これで大丈夫かしら」
出来上がった文面に問題がないか、正直不安でたまらない。何度も書き直したせいで、机の隅には書き損じた便箋がいくつも重なっている。侍女たちに用意してもらったのに、無駄にしているようで申し訳ない。けれど、下手な手紙を送ってまともに取り合ってくれない事態は避けたかった。
「サラ。この手紙、殿下に届けてくれる?」
「かしこまりました」
ようやく書き上げた手紙を丁寧に封蝋し、侍女に託す。サラが部屋から出ていくのを見届けていると、ケイトが弾んだように話しかけてきた。
「殿下もきっとお喜びになりますよ」
「そうだと良いけれど」
きっと喜ぶことはないと思ったけれど、曖昧に笑って誤魔化す。シルビオに手紙を書いてはどうか、と提案してくれたのはセレステ。昨日、「殿下ともっと話したいけれど、どうきっかけを作ったら良いかわからない」と相談したのがきっかけだった。
王国と帝国の国力の差を痛感したネリア。国の今後を決めるためにも、まずこの目で王国の様子を見ることが先決だと考えた。けれど、今のネリアが頼んだところでシルビオが素直に帰してくれないことは火を見るより明らか。一体何を企んでいるんだ、と疑われるのが関の山だろう。
本当はネリアのことを好きな人と結婚したいし、嫌われたまま結婚するぐらいなら、いっそのこと婚約破棄にならないかなと望んでもいた。けれど、国のことを思うのならそんなわがままは言っていられない。シルビオと結婚することが、王国にとって最善の選択ならば、シルビオに歩み寄るための努力は厭うべきではない。
平和に王国へ帰してもらうには、まずシルビオからの信頼を得る必要がある。そのためにはシルビオのことをよく知ることから始めなければならないけれど、彼と話す機会は滅多にない。朝食のときに少し顔を合わせるだけで、昼間はお互いに妃教育や皇弟としての執務で忙しく、夜は別々に眠る。だから、手紙を書いたのだ。
――読んでくれるといいな。
生まれて初めて異性に宛てた手紙だ。返事が来るかはわからないけれど、せめて読んでもらえればいい。そんなことを考えながら、今日の妃教育の準備を進めた。