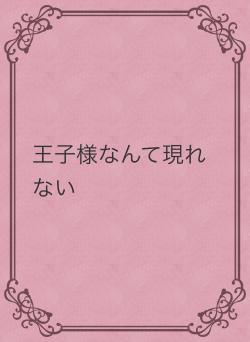「広いのね、この部屋……」
ぽつ、と呟く声の響き方すら違うような気がする。石造りの狭い部屋は、やけに声が響いたのに。耳鳴りがしそうなほどの静けさは、ネリアを物思いに耽らせるには十分だった。
――やっていけるのかしら……。
カウチの端っこにちょこんと腰掛け、深く息を吐く。足をぷらぷらとパタつかせながら、ここ数日のことを思い返す。
キシュ王国からコーア帝国に連れてこられたのは、数日前のこと。エリシアの身代わりとしての人生は、幕を開けた瞬間に閉じるものとばかり思っていたがそうではないらしい。聖堂で出会い頭に剣を突き付けた男――コーア帝国皇弟のシルビオは、エリシアと名乗るネリアのことをかなり疑っていた。ネリアはエリシアのように魔法を使えないし、輝く白金の髪も持っていないのだから無理もない。散々疑っている様子のシルビオだけれど、結局その場でネリアを切り捨てることはしなかった。代わりに、コーア帝国へと連れ帰られた。
*
コーア帝国に着いて早々、連れて行かれたのは皇宮の地下牢。薄暗くて寒くてお世辞にも快適とは言えなかったけれど、似たようなところで暮らしていたのが功を奏した。ネリアが生まれ育った塔も、大体こんなものだ。窓がないのが残念、と思うだけで特に辛くはない。尋問という名の事情聴取も同じ。もっと手酷い拷問でも加えられるのかと思ったけれど、淡々と事実確認をされるのみで拍子抜けしたほどだ。念の為の拘束として魔力封じの腕輪を付けられたけれど、魔法の使えないエリシアにとっては何の意味もない。
地下牢にて尋ねられた内容は、ネリアに衝撃を与えた。キシュ王国の国王夫妻の死、有力貴族の失踪、キシュ王国との国境沿いに住む村人の行方不明……。ネリアが知っていることは両親が亡くなったことだけで、他のことは寝耳に水。何か知っているか、という問いには首を振ることしかできなかった。隠し立てしているわけではなく、本当に何も知らないのだ。
エリシアはどこに行ったのか、マリーは無事でいるのか、王国の人たちはどうなったのか。ネリアの方こそ聞きたいことがたくさんあるのに、地下牢の衛兵たちは何も返してくれない。話しかけられても答えるな、とでも言われているのだろうか。話し相手も娯楽もない地下牢は静かで、日がな一日何もやることがない。両親の死をうっすら思い、姉の行方を考え、侍女のマリーを心配して、一日はなんとなく過ぎていく。
エリシアとして殺されるのか、それともここに閉じ込められて一生を終えるのか。皇弟がやってきたのは、そんなことをぼんやりと考えていたときだった。金髪碧眼で中性的な整った顔立ちの彼は、絵本に出てくる王子様そっくりだ。聖堂で会ったときはそんなことを考える余裕もなかったけれど、時間だけが有り余るこの状況では顔の良さに嫌でも注目してしまう。が、見惚れるのも一瞬。シルビオはびっくりするほど口が悪かった。
既に他の兵士からも聞かれたことを、高圧的に尋ねてくるシルビオ。どうしてこんなに突っかかるような言い方ばかりするのだろう、と思いつつやられっぱなしのネリアではない。なんてったって今のネリアはネリアではない、エリシアなのだ。記憶の中のエリシアはいつでも清く正しく、そして勝気だった。パーティーでの出来事を聞くにつけ、エリシアが優雅な口調の裏に毒を潜めていたことはよくわかる。酔った勢いで口説いてきた伯爵令息を口八丁でやり込めた話なんかは聞き応えがあり、手に汗握ったものだ。
そういうわけで、自分を捕まえた皇弟相手に一歩も退く気はないネリア。他人と口喧嘩だなんて初めてなのだ、心臓はバクバクだけれど悟られるわけにはいかない。高圧的に見えるよう顎を逸らし、売り言葉に買い言葉。どう考えてもシルビオは、ネリアのことをエリシアだとは信じていない。エリシアはどんな感じだっけ、と必死に思い出しているうちにシルビオは盛大な舌打ちを残してその場を後にする。
結局何だったんだ、と首を傾げていると数時間後。再び現れたシルビオは、ネリアとの婚約が決まったことを苦虫を噛み潰したような顔で告げた。
*
そうして地下牢から連れ出され、案内された先がこの部屋だ。王城のエリシアの部屋ほどではないけれど、ネリアの住処であった塔とは比べるべくもない。「必要なものがあれば言え」と言われたけれど、これ以上何を望めばいいのだろう。フカフカのベッドもピカピカのカウチも、ネリアの人生において初めて与えられたものだ。エリシアを装っているのだから、エリシアの部屋にあったものを頼むべきだろうか。ぼんやりしているうちに皇宮を案内され、途中で出会った老侯爵に失礼なことを言われ、エリシアを思い出しながらシルビオと喧嘩し、金色の髪にやはり強烈な羨ましさを覚えて今に至るわけだが。
――疲れたわ。
カウチに腰掛けたまま、今日という日を振り返る。こんなに疲れた日はない、と断言できるぐらいには疲労困憊だった。今までの人生で出会った人間の総数を今日だけで超えてしまったのだから、それも仕方のないことだろう。人と会うことも、話すことも、エリシアの振りをすることも。全てに疲れてしまった。
エリシアは、一体いつまでネリアに自分の振りをさせたいのだろう。王国の様子が一向にわからないのも不安だ。マリーの安否は、聞けば教えてもらえるのだろうか。いっそのこと、どうにかして皇宮を抜け出して王国に帰ってしまおうか。そんな、あまり現実的とは言えないことを考えていたときだった。
コンコン、と軽快なノックの音が響く。慌てて姿勢を正して返事をすると、入ってきたのはシルビオだった。先ほども連れていた侍従――確かリオンと呼ばれていた――と、お仕着せを着た侍女を二人連れている。そういえば皇宮を案内してもらうために部屋を出るとき、侍女を手配するよう言いつけていた。ネリアのことを偽王女だと思っていても、きちんとした侍女をつけてくれるらしい。控えめに微笑む二人は、穏やかに業務をこなしてくれそうだ。
「足りない調度品や服飾品は二人に言いつけろ。すぐに手配する」
「お気遣いに感謝いたしますわ」
微笑んでみせたけれど、内心焦るネリア。この二人はどれぐらい一緒にいるのだろう。塔でネリアの世話を焼いてくれたマリーは、ほとんど四六時中と言っていいほど一緒にいた。もしマリーと同じぐらい一緒にいるのであれば、二人の前でも常にエリシアを装う必要がある。一応は王女として生まれたとはいえ、生まれてからずっと塔に閉じ込められていたのだ。最低限の礼儀作法はともかくとして。王女としての教養や相応しい振る舞いは、ネリアにはほとんど備わっていない。
「ああ、それから。陛下と陛下の婚約者であるセレステ殿と四人で晩餐会を開くことになっている」
「えっ?」
「二人はそれまでに準備を頼む」
それだけ言うと、ネリアの返事を聞くこともなくリオンを伴って部屋を後にするシルビオ。要件だけ伝えてさっさと帰っていくあたり、ネリアを細やかに気遣うつもりはないらしい。別にいいけれど、もう少し歩み寄りの姿勢はないのかと文句をつけたくなった。部屋に残されたのは、ネリアを見て控えめに微笑む侍女たち。自分よりもよっぽど教養に溢れているであろう二人に、今のうちにテーブルマナーだけでも聞いておくべきだろうか。王女といえど、胸を張って皇帝一家と食事できるだけのマナーが身についているとはとても言えない。マリーが一応教えてくれたけれど、それを披露する機会は一度もなかった。
――どうしよう。
エリシアならこんなときどうしただろうか。記憶を辿ったものの、厨房からこっそり頂戴してきた料理やデザートを、ネリアのベッドに腰掛けて手づかみで食べる姿しか思い出せない。死ぬ覚悟をして王国を出たけれど、皇帝との会食中に粗相をしでかして処刑されるのはあまりにあんまりだろう。どうか皇帝とその婚約者様が寛大な方達でありますように、と祈るしかなかった。
ぽつ、と呟く声の響き方すら違うような気がする。石造りの狭い部屋は、やけに声が響いたのに。耳鳴りがしそうなほどの静けさは、ネリアを物思いに耽らせるには十分だった。
――やっていけるのかしら……。
カウチの端っこにちょこんと腰掛け、深く息を吐く。足をぷらぷらとパタつかせながら、ここ数日のことを思い返す。
キシュ王国からコーア帝国に連れてこられたのは、数日前のこと。エリシアの身代わりとしての人生は、幕を開けた瞬間に閉じるものとばかり思っていたがそうではないらしい。聖堂で出会い頭に剣を突き付けた男――コーア帝国皇弟のシルビオは、エリシアと名乗るネリアのことをかなり疑っていた。ネリアはエリシアのように魔法を使えないし、輝く白金の髪も持っていないのだから無理もない。散々疑っている様子のシルビオだけれど、結局その場でネリアを切り捨てることはしなかった。代わりに、コーア帝国へと連れ帰られた。
*
コーア帝国に着いて早々、連れて行かれたのは皇宮の地下牢。薄暗くて寒くてお世辞にも快適とは言えなかったけれど、似たようなところで暮らしていたのが功を奏した。ネリアが生まれ育った塔も、大体こんなものだ。窓がないのが残念、と思うだけで特に辛くはない。尋問という名の事情聴取も同じ。もっと手酷い拷問でも加えられるのかと思ったけれど、淡々と事実確認をされるのみで拍子抜けしたほどだ。念の為の拘束として魔力封じの腕輪を付けられたけれど、魔法の使えないエリシアにとっては何の意味もない。
地下牢にて尋ねられた内容は、ネリアに衝撃を与えた。キシュ王国の国王夫妻の死、有力貴族の失踪、キシュ王国との国境沿いに住む村人の行方不明……。ネリアが知っていることは両親が亡くなったことだけで、他のことは寝耳に水。何か知っているか、という問いには首を振ることしかできなかった。隠し立てしているわけではなく、本当に何も知らないのだ。
エリシアはどこに行ったのか、マリーは無事でいるのか、王国の人たちはどうなったのか。ネリアの方こそ聞きたいことがたくさんあるのに、地下牢の衛兵たちは何も返してくれない。話しかけられても答えるな、とでも言われているのだろうか。話し相手も娯楽もない地下牢は静かで、日がな一日何もやることがない。両親の死をうっすら思い、姉の行方を考え、侍女のマリーを心配して、一日はなんとなく過ぎていく。
エリシアとして殺されるのか、それともここに閉じ込められて一生を終えるのか。皇弟がやってきたのは、そんなことをぼんやりと考えていたときだった。金髪碧眼で中性的な整った顔立ちの彼は、絵本に出てくる王子様そっくりだ。聖堂で会ったときはそんなことを考える余裕もなかったけれど、時間だけが有り余るこの状況では顔の良さに嫌でも注目してしまう。が、見惚れるのも一瞬。シルビオはびっくりするほど口が悪かった。
既に他の兵士からも聞かれたことを、高圧的に尋ねてくるシルビオ。どうしてこんなに突っかかるような言い方ばかりするのだろう、と思いつつやられっぱなしのネリアではない。なんてったって今のネリアはネリアではない、エリシアなのだ。記憶の中のエリシアはいつでも清く正しく、そして勝気だった。パーティーでの出来事を聞くにつけ、エリシアが優雅な口調の裏に毒を潜めていたことはよくわかる。酔った勢いで口説いてきた伯爵令息を口八丁でやり込めた話なんかは聞き応えがあり、手に汗握ったものだ。
そういうわけで、自分を捕まえた皇弟相手に一歩も退く気はないネリア。他人と口喧嘩だなんて初めてなのだ、心臓はバクバクだけれど悟られるわけにはいかない。高圧的に見えるよう顎を逸らし、売り言葉に買い言葉。どう考えてもシルビオは、ネリアのことをエリシアだとは信じていない。エリシアはどんな感じだっけ、と必死に思い出しているうちにシルビオは盛大な舌打ちを残してその場を後にする。
結局何だったんだ、と首を傾げていると数時間後。再び現れたシルビオは、ネリアとの婚約が決まったことを苦虫を噛み潰したような顔で告げた。
*
そうして地下牢から連れ出され、案内された先がこの部屋だ。王城のエリシアの部屋ほどではないけれど、ネリアの住処であった塔とは比べるべくもない。「必要なものがあれば言え」と言われたけれど、これ以上何を望めばいいのだろう。フカフカのベッドもピカピカのカウチも、ネリアの人生において初めて与えられたものだ。エリシアを装っているのだから、エリシアの部屋にあったものを頼むべきだろうか。ぼんやりしているうちに皇宮を案内され、途中で出会った老侯爵に失礼なことを言われ、エリシアを思い出しながらシルビオと喧嘩し、金色の髪にやはり強烈な羨ましさを覚えて今に至るわけだが。
――疲れたわ。
カウチに腰掛けたまま、今日という日を振り返る。こんなに疲れた日はない、と断言できるぐらいには疲労困憊だった。今までの人生で出会った人間の総数を今日だけで超えてしまったのだから、それも仕方のないことだろう。人と会うことも、話すことも、エリシアの振りをすることも。全てに疲れてしまった。
エリシアは、一体いつまでネリアに自分の振りをさせたいのだろう。王国の様子が一向にわからないのも不安だ。マリーの安否は、聞けば教えてもらえるのだろうか。いっそのこと、どうにかして皇宮を抜け出して王国に帰ってしまおうか。そんな、あまり現実的とは言えないことを考えていたときだった。
コンコン、と軽快なノックの音が響く。慌てて姿勢を正して返事をすると、入ってきたのはシルビオだった。先ほども連れていた侍従――確かリオンと呼ばれていた――と、お仕着せを着た侍女を二人連れている。そういえば皇宮を案内してもらうために部屋を出るとき、侍女を手配するよう言いつけていた。ネリアのことを偽王女だと思っていても、きちんとした侍女をつけてくれるらしい。控えめに微笑む二人は、穏やかに業務をこなしてくれそうだ。
「足りない調度品や服飾品は二人に言いつけろ。すぐに手配する」
「お気遣いに感謝いたしますわ」
微笑んでみせたけれど、内心焦るネリア。この二人はどれぐらい一緒にいるのだろう。塔でネリアの世話を焼いてくれたマリーは、ほとんど四六時中と言っていいほど一緒にいた。もしマリーと同じぐらい一緒にいるのであれば、二人の前でも常にエリシアを装う必要がある。一応は王女として生まれたとはいえ、生まれてからずっと塔に閉じ込められていたのだ。最低限の礼儀作法はともかくとして。王女としての教養や相応しい振る舞いは、ネリアにはほとんど備わっていない。
「ああ、それから。陛下と陛下の婚約者であるセレステ殿と四人で晩餐会を開くことになっている」
「えっ?」
「二人はそれまでに準備を頼む」
それだけ言うと、ネリアの返事を聞くこともなくリオンを伴って部屋を後にするシルビオ。要件だけ伝えてさっさと帰っていくあたり、ネリアを細やかに気遣うつもりはないらしい。別にいいけれど、もう少し歩み寄りの姿勢はないのかと文句をつけたくなった。部屋に残されたのは、ネリアを見て控えめに微笑む侍女たち。自分よりもよっぽど教養に溢れているであろう二人に、今のうちにテーブルマナーだけでも聞いておくべきだろうか。王女といえど、胸を張って皇帝一家と食事できるだけのマナーが身についているとはとても言えない。マリーが一応教えてくれたけれど、それを披露する機会は一度もなかった。
――どうしよう。
エリシアならこんなときどうしただろうか。記憶を辿ったものの、厨房からこっそり頂戴してきた料理やデザートを、ネリアのベッドに腰掛けて手づかみで食べる姿しか思い出せない。死ぬ覚悟をして王国を出たけれど、皇帝との会食中に粗相をしでかして処刑されるのはあまりにあんまりだろう。どうか皇帝とその婚約者様が寛大な方達でありますように、と祈るしかなかった。