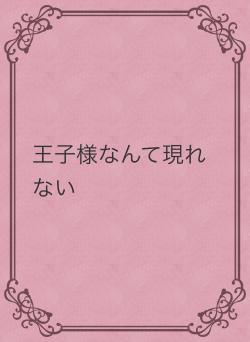――長かったな。
結婚式も無事に終わり、初夜でのこと。ここに辿り着くまでがあまりにも長すぎたので、一生結婚できないんじゃないかと不安に駆られたこともあったけれど。いざその日を迎えてみれば随分と呆気ない。結婚式でのネリアを思い出すと、緩んだ頬が戻らなくなりそうだ。きっと死ぬ間際にも思い出すのだろう。それぐらい、シルビオの記憶に鮮明に焼き付いている。
純白のドレスに身を包むネリアの、月の色をした髪を彩るのは同じ色のティアラ。胸元には、出会ったばかりの頃に贈ったブラックサファイアのネックレスが輝いている。せっかくの結婚式なのにそれでいいのかと尋ねると、これがいいのだと強目に返された。あまりに可愛いので、そのまま抱きしめてどこかに攫ってしまおうかと考えたほどだ。
「シルビオ? ぼーっとしてどうしたの?」
ベッドにちょこんと腰掛け、シルビオの顔を覗き込むネリア。「……どっかの誰かさんが可愛かったなって」と素直に答えると、「私?」と嬉しそうに破顔した。こいつこの数年で自分の可愛さに自信を持ちやがった、と呆れるのと同時に、ずっとそのままでいてほしいとも願う。「そうだよ」と返すとこの上なくニコニコするので、画家にこの笑顔を描かせて部屋に飾りたいと思った。
「結婚式、楽しかったわね。セレステ様たちのときにも思ったけれど、なんだかお祭りみたいだったわ」
結婚式が余程楽しかったのだろうか。疲れた様子も見せず、ご機嫌に足をパタつかせている。彼女が意外と子供っぽい仕草をすると知ったのは、この二年の間でのことだ。十八年も閉じ込められていたせいなのだろう。本人も自覚しているのか、人前では出さないようにしているけれど。シルビオの前でだけ、そういう無防備なところを出してくれると気づいたのはいつだったか。気づいた瞬間、無意識に丸い頭を撫でくり回したので困惑されたものだ。
いつまでも見ていられる、なんて思いながらご機嫌なネリアを見つつ、膝に置かれた手を握る。肩にかけられているブランケットは、寒くないか心配したシルビオがかけたものだ。ペラペラで頼りない夜着に煽られないはずはなかったけれど、それよりも心配が勝った。この二年でびっくりするほど過保護になったな、とはネリアを含め皇宮内の全員が思っていることだ。しっとりと柔らかい手をにぎにぎと握りながら、これからどうしようかとシルビオは思案する。この二年の間も、夜の雑談という日課は続いていた。手を握ることにも、抱きしめ合うことにも、キスすることだってあったけれど。結局、一線を越えることは一度もなかった。
よっぽど婚前交渉に踏み切ってやろうかと葛藤したことはあれど、それでも、亡国の王女として努力する彼女にそんな無体は働けない。いくら婚約者といえど、「結婚前に傷物にされた」と思わせたくなかったし、そもそも押し倒して泣かせたことが二度もある上、初対面では剣を向けているのだ。これ以上、罪は重ねられない。それに、二年も我慢したのだから、今更初夜が先延ばしになってもどうということはない。このまま朝まで喋り倒すのも楽しそうだ、と思うシルビオだけれど。ネリアはどうやら、そうではないらしい。話したいことを一通り話し終えたのか、「抱きついてもいい?」と唐突に尋ねられた。
「えっ、急に?」
「だめかしら?」
「だめではない」
即答して抱きしめる。その拍子にブランケットが肩から落ちたけれど、拾うのは一旦諦めた。少しだけ体を離して、「キスしていい?」と尋ねると、こくりと無言で頷かれる。頬に手のひらを添え、もう何度口付けたかわからない唇に、自身のそれを重ねた。角度を変えて啄み、舌を潜り込ませる。されるがままのネリアは、縋るようにしてシルビオの夜着に手を伸ばした。一人でどこまでも頑張れる彼女が甘えるのは、シルビオにだけ。特権のような優越感に、ゾクゾクした。
唇を離し、抱きしめたまま寝台に倒れる。腰をさらに抱き寄せ、「最後までしてもいい?」と尋ねると、またも無言で頷かれた。「意味わかってる?」と確認すると、「妃教育で習ったから大丈夫」と胸を張って返される。根拠があるようでない自信に満ち溢れた様子に、いつぞやの婚約お披露目パーティーでのことが思い出された。
「……」
少し逡巡し、ネリアの腕から魔力封じの腕輪を取る。無骨に輝くそれは、見た目よりは重たい。枕元に置くのをネリアはきょとんと見ているので、シルビオは真剣に告げた。
「無理だと思ったらこれで俺を殴れ」
「ど、どうして!?」
「最悪、魔法を使ってもいい」
「そこまでしないわ!」
ギョッとしているけれど、シルビオはいたって真面目だ。初夜を完遂したくないといえば嘘になるけれど、万が一にも傷つけるようなことがあってはならない。ネリアの数倍は頑丈にできているのだから、腕輪で殴られるぐらいどうということもない。「わかったな?」と念押しすると困惑気味に頷いた。あんまりわかっていないけどとりあえず頷いておこう、と思ったのだよくわかる。
まあ今はそれでいいか、と思いつつ口付けを再開した。薄い夜着越しに胸に触れると、びくりと体が震える。怖いのだろうか、と体を離しかけたけれど、首に腕を回して止められた。ちゅ、ちゅ、と緩い水音が鼓膜に響く。初めて触れた胸は形容し難い柔らかさで、一生触ってられるなと邪なことを思った。胸元の布をずり下げ、直接触れる。手のひらに当たる突起を軽く引っ掻くと、「んっ……」と声に艶が混じった。
「かわい」
唇を離して譫言のようにぽつりと呟き、ふるふると震えるそこに吸い付く。唇を塞いでいないせいで、「あっ、んっ」と嬌声がよく聞こえる。が、あられもない声が出てしまうのが恥ずかしいのか、手でぱちんと口を覆ってしまった。胸から顔を上げて抗議する。
「声、聞かしてよ」
「や、は、はずかしい」
別に恥ずかしがることないだろ、と思ったけれど無理強いはしない。ついでとばかりに体を起こし、自身の夜着を脱ぎ去る。興奮しているせいか、先ほどから体が火照って仕方がない。心臓もうるさいぐらいに脈打っている。ふと見下ろすと、顔を真っ赤にしたネリアがまん丸い瞳で見上げていることに気がついた。
「なんだよ」
「筋肉がすごい……」
「そりゃどうも。触るか?」
「えっ」
さっきまで散々触らしてもらったしな、とお返しにもならないことを思いつつ、彼女の右手を自身の左胸に触れさせる。小さな手は熱を帯びていて、触れられると無性にドキドキした。勢いで触るかと尋ねてしまったけれど、どう思われているのだろう。見下ろすと、ネリアはどうしてか顔を赤くしている。なんで、と口にする前に、「心臓が……」と惚けたように呟いた。
「心臓の音が、すごい」
「……」
「緊張してるの?」
なぜかキラキラと眩しいぐらいの輝きを放つ瞳で見つめられ、軽々に触れさせたことを後悔した。格好がつかないにも程があるけれど、初めてなのだから仕方がない。ネリアは、「ね、緊張してるの? 私とお揃い?」とニヤニヤしている。「お前まじで可愛いからって調子に乗んなよ」と悪態を吐くと、「? ありがとう」と返された。相変わらずよくわかっていなさそうな様子に、心臓が大きく脈打った。今触れられていたら、間違いなくさらにニヤつかれただろう。
首の下に腕を入れて抱き起こし、再び口付ける。舌を入れると一生懸命応えようとするのが、可愛くて仕方がない。ネリアキスに夢中になっている間に夜着を下からたくし上げ、茂みに指を差し入れる。「んっ!?」と驚いたような声を上げたけれど、全て飲み込んでしまった。反射的にか足を閉じようとするけれど、鍛えているシルビオに敵うはずもない。あっさりと手で押さえ込みながら、陰核を指で引っ掻いた。
「んっ、あっ、ああっ」
「ここ? 気持ちいい?」
「あっ、んっ、ぅあ」
唇を離して尋ねると、こくこくと一生懸命に頷いて答えてくれた。ちゅぷ、と指を抜き差しするたびに生まれる水音が部屋を満たす。手で口を覆う余裕はなくなったのか、可愛い声は何にも邪魔されることなくシルビオの耳にとどく。瞼が硬くつむられているのを良いことに、真っ赤な顔をこれでもかとガン見する。どこに触れても反応を返すのが愛おしくて、頭がどうにかなりそうだ。中に差し込む指を増やし、ちゅ、ちゅ、と顔中に唇を落とす。
「ひぁ、あ、だ、だめっ」
「痛い?」
「ち、がっ、な、なんだか、へん、でっ」
「ん、変になっていいよ」
「ひゃ、あっ、あああっ……」
シルビオの腕を、細い指が掴むけれど大した抵抗にもならない。一際声が高くなるところを押してやると、指がぎゅうぎゅうと締め付けられる。つま先が丸くなり、体がこわばったかと思うと、くったりと力が抜けた。イったんだ、と思うと仄暗い興奮が胸を満たす。はあ、はあ、と肩で息をするネリアを寝台に横たえ、その上から覆い被さった。寝台に散らばる銀色の髪は煌めいていて、神聖なものを穢すような背徳感でゾクゾクする。
「挿れていい?」
ネリアを可愛がる最中から、自身は痛いぐらいに張り詰めている。正直待っている余裕はないけれど、そこは二年も我慢した男。強靭な理性と忍耐力で、ネリアの返事を待つ。
「う、ん」
ゆっくりと瞼を開けたネリアが、蕩けた瞳でシルビオを見つめる。こくり、と頷くのを見て、言いようのない感情で満たされていくのを感じた。「無理だったら言えよ。ていうか、ちゃんとこれで殴れよ」と枕元の腕輪を示すと、ふにゃりと微笑んで口を開く。
「殴らなくても、シルビオは止まってくれるでしょ?」
「……信頼されてんな」
「だって、私に甘いんだもの。私がやめてって言ったらやめてくれるわ」
「……」
得意気に微笑むネリア。大事にされていることを微塵も疑っていない無防備さが、あまりにも可愛くてどうにかなりそうだ。本当の名前すら明かしてもらえない、ともどかしさを覚えていた頃の自分が聞いたらどう思うだろうか。無条件に寄せられる信頼があまりにくすぐったくて、心地いい。途中でやっぱりやめて、とお預けをくらったとしても満足して眠りにつく自信がある。
「力、抜いてろよ」
切先を宛てがい、腰を進めていく。ひゅっ、と緊張からか息を呑むので、「痛くしないから」と慰めるように呟きながら頭を撫でる。それだけで力が抜けるのだから、愛おしくて仕方がない。寝台で所在なげに握り込まれた手に触れると、しがみつくように握られる。力の限り握られているようだけれど、子猫に戯れつかれているぐらいの力だ。ずぷずぷとできるだけゆっくり埋め込み、時間をかけて最奥まで辿り着く。
「痛い?」
「んっ、お腹いっぱいな感じがする……」
「……痛くないなら良かった」
少しの刺激でも出してしまいそうなので、煽るようなことを言わないでほしい。どうにか耐えて、ネリアの顔にかかった髪を払う。銀色に変わった当初は、鏡を見るたびしょんぼりしていたけれど、最近ではそれも無くなったような気がする。黒でも銀でも、似合っているし可愛いことには変わりないのだ。できれば気にしないで、いつまでも笑っていてほしい。
「動いていい?」
「ん、うん」
許しを得たので、ゆっくりと腰を揺する。とちゅ、とちゅ、と打ち付ける音の合間に、ネリアの嬌声が混じる。どうにかなりそうなぐらい気持ちが良い。お預けにされても我慢できたけれど、されなくてよかったと心から思ってしまった。「ネリア、好き。好きだよ」と譫言のように口走ると、「んっ、あっ、う、んっ」と一生懸命に頷いてくれる。余裕がないだろうに、それでも返事をしてくれる律儀さが愛おしい。震える唇に吸い寄せられるようにしてキスすると、怖いぐらいの幸福を感じた。
*
汚れた体を清め、再び夜着を着せてネリアを抱きしめて横たわるシルビオ。
すげーよかった……と余韻に浸っていると、「そういえば」と、不意にネリアが振り向く。最中はあんなに乱れて訳が分からなさそうにしていたのに、終わってみれば随分ケロッとしたものである。爛々と輝く瞳に見つめられ、なんなんだと首を傾げていると、「結局シルビオの初恋の人って誰なの?」と尋ねられた。ピロートークに相応しいようで似つかわしくない話題に、拍子抜けする。思えば、まだ彼女がシルビオを「殿下」と読んでいた頃の話題だ。
「何年前の話だよ、それ」
「だって結局教えてもらってないもの。セレステ様じゃないの?」
「ちげーわ」
何が楽しくて、初対面時から兄の婚約者だった人に横恋慕などという茨の道を歩むのか。「でも、皇宮に来たときセレステ様には優しくされたでしょう?」と不思議がっているけれど、その優しさを恋愛感情に結びつけるほど初心だったわけでもない。隙あらば俺と恋バナしたがるのはなんなんだよ、と呆れつつ柔らかい頬に手を伸ばす。むに、と摘みながら、「そう言うそっちはどうなんだよ」と尋ねた。数年前は、王女だからそんな暇はなかっただのなんだのとはぐらかされたけれど。きょとんと目を丸くする様子に、今回もどうせ適当に流されるのだろう、と予想するシルビオ。
「私はシルビオよ」
「……は」
胸を張って答えるネリアに一瞬、時が止まる。頬を摘んだまま固まるシルビオにネリアは、「私ね、シルビオのことが好き。大好きよ」と赤い顔で告げ、そのまま胸元に顔を埋めた。初恋相手が自分だということに未だ衝撃を受けているシルビオは、「は、待って、一旦待って」としか言えない。衝撃を与えた本人はと言えば、言いたいことは一通り言えたとばかりに満足気だ。シルビオだけが置いて行かれている。
「ネリア、顔上げて」
「心臓の音が、本当にすごいわ」
「おいネリア、顔上げろ」
両手で頬を挟み、ぐいっと強引に顔を上げさせる。耳まで真っ赤にしたネリアがふにゃふにゃと緩んだ顔でシルビオを見上げていて、考える間もなくキスしていた。何度も口付けているうちに息が苦しくなったのか、胸をとんとんと控えめに叩かれる。仕方なく離してやると、「照れた? 照れたの?」とニヤニヤしている。この期に及んで、いい度胸をしているものだ。
「お前ほんと、まじで可愛いからって調子乗りやがって」
「ふふ、ありがとう」
「褒めてねえよ可愛いなちくしょう」
ヤケクソのようにそう呟いて細い肩に顔を埋めると、頭から抱きしめられる。柔らかい檻に閉じ込められるような感覚に、気を抜いたら病みつきになってしまいそうだ。よしよしと小さな手に撫でられる感触を享受していると、「ねえ、私のこといつから好きだった?」と弾んだような声で尋ねられる。シルビオに好かれていることを微塵も疑っていない、そんなところも可愛くてたまらない。
「……さあ、どうだっけな」
「はぐらかした!」
むくれたような声を聞きながら、初めて会ったときのことを思い出す。あの日、王国の聖堂で身代わりの王女を捕まえたのはシルビオだけれど。一目見て囚われたのは、きっとシルビオの方だった。
結婚式も無事に終わり、初夜でのこと。ここに辿り着くまでがあまりにも長すぎたので、一生結婚できないんじゃないかと不安に駆られたこともあったけれど。いざその日を迎えてみれば随分と呆気ない。結婚式でのネリアを思い出すと、緩んだ頬が戻らなくなりそうだ。きっと死ぬ間際にも思い出すのだろう。それぐらい、シルビオの記憶に鮮明に焼き付いている。
純白のドレスに身を包むネリアの、月の色をした髪を彩るのは同じ色のティアラ。胸元には、出会ったばかりの頃に贈ったブラックサファイアのネックレスが輝いている。せっかくの結婚式なのにそれでいいのかと尋ねると、これがいいのだと強目に返された。あまりに可愛いので、そのまま抱きしめてどこかに攫ってしまおうかと考えたほどだ。
「シルビオ? ぼーっとしてどうしたの?」
ベッドにちょこんと腰掛け、シルビオの顔を覗き込むネリア。「……どっかの誰かさんが可愛かったなって」と素直に答えると、「私?」と嬉しそうに破顔した。こいつこの数年で自分の可愛さに自信を持ちやがった、と呆れるのと同時に、ずっとそのままでいてほしいとも願う。「そうだよ」と返すとこの上なくニコニコするので、画家にこの笑顔を描かせて部屋に飾りたいと思った。
「結婚式、楽しかったわね。セレステ様たちのときにも思ったけれど、なんだかお祭りみたいだったわ」
結婚式が余程楽しかったのだろうか。疲れた様子も見せず、ご機嫌に足をパタつかせている。彼女が意外と子供っぽい仕草をすると知ったのは、この二年の間でのことだ。十八年も閉じ込められていたせいなのだろう。本人も自覚しているのか、人前では出さないようにしているけれど。シルビオの前でだけ、そういう無防備なところを出してくれると気づいたのはいつだったか。気づいた瞬間、無意識に丸い頭を撫でくり回したので困惑されたものだ。
いつまでも見ていられる、なんて思いながらご機嫌なネリアを見つつ、膝に置かれた手を握る。肩にかけられているブランケットは、寒くないか心配したシルビオがかけたものだ。ペラペラで頼りない夜着に煽られないはずはなかったけれど、それよりも心配が勝った。この二年でびっくりするほど過保護になったな、とはネリアを含め皇宮内の全員が思っていることだ。しっとりと柔らかい手をにぎにぎと握りながら、これからどうしようかとシルビオは思案する。この二年の間も、夜の雑談という日課は続いていた。手を握ることにも、抱きしめ合うことにも、キスすることだってあったけれど。結局、一線を越えることは一度もなかった。
よっぽど婚前交渉に踏み切ってやろうかと葛藤したことはあれど、それでも、亡国の王女として努力する彼女にそんな無体は働けない。いくら婚約者といえど、「結婚前に傷物にされた」と思わせたくなかったし、そもそも押し倒して泣かせたことが二度もある上、初対面では剣を向けているのだ。これ以上、罪は重ねられない。それに、二年も我慢したのだから、今更初夜が先延ばしになってもどうということはない。このまま朝まで喋り倒すのも楽しそうだ、と思うシルビオだけれど。ネリアはどうやら、そうではないらしい。話したいことを一通り話し終えたのか、「抱きついてもいい?」と唐突に尋ねられた。
「えっ、急に?」
「だめかしら?」
「だめではない」
即答して抱きしめる。その拍子にブランケットが肩から落ちたけれど、拾うのは一旦諦めた。少しだけ体を離して、「キスしていい?」と尋ねると、こくりと無言で頷かれる。頬に手のひらを添え、もう何度口付けたかわからない唇に、自身のそれを重ねた。角度を変えて啄み、舌を潜り込ませる。されるがままのネリアは、縋るようにしてシルビオの夜着に手を伸ばした。一人でどこまでも頑張れる彼女が甘えるのは、シルビオにだけ。特権のような優越感に、ゾクゾクした。
唇を離し、抱きしめたまま寝台に倒れる。腰をさらに抱き寄せ、「最後までしてもいい?」と尋ねると、またも無言で頷かれた。「意味わかってる?」と確認すると、「妃教育で習ったから大丈夫」と胸を張って返される。根拠があるようでない自信に満ち溢れた様子に、いつぞやの婚約お披露目パーティーでのことが思い出された。
「……」
少し逡巡し、ネリアの腕から魔力封じの腕輪を取る。無骨に輝くそれは、見た目よりは重たい。枕元に置くのをネリアはきょとんと見ているので、シルビオは真剣に告げた。
「無理だと思ったらこれで俺を殴れ」
「ど、どうして!?」
「最悪、魔法を使ってもいい」
「そこまでしないわ!」
ギョッとしているけれど、シルビオはいたって真面目だ。初夜を完遂したくないといえば嘘になるけれど、万が一にも傷つけるようなことがあってはならない。ネリアの数倍は頑丈にできているのだから、腕輪で殴られるぐらいどうということもない。「わかったな?」と念押しすると困惑気味に頷いた。あんまりわかっていないけどとりあえず頷いておこう、と思ったのだよくわかる。
まあ今はそれでいいか、と思いつつ口付けを再開した。薄い夜着越しに胸に触れると、びくりと体が震える。怖いのだろうか、と体を離しかけたけれど、首に腕を回して止められた。ちゅ、ちゅ、と緩い水音が鼓膜に響く。初めて触れた胸は形容し難い柔らかさで、一生触ってられるなと邪なことを思った。胸元の布をずり下げ、直接触れる。手のひらに当たる突起を軽く引っ掻くと、「んっ……」と声に艶が混じった。
「かわい」
唇を離して譫言のようにぽつりと呟き、ふるふると震えるそこに吸い付く。唇を塞いでいないせいで、「あっ、んっ」と嬌声がよく聞こえる。が、あられもない声が出てしまうのが恥ずかしいのか、手でぱちんと口を覆ってしまった。胸から顔を上げて抗議する。
「声、聞かしてよ」
「や、は、はずかしい」
別に恥ずかしがることないだろ、と思ったけれど無理強いはしない。ついでとばかりに体を起こし、自身の夜着を脱ぎ去る。興奮しているせいか、先ほどから体が火照って仕方がない。心臓もうるさいぐらいに脈打っている。ふと見下ろすと、顔を真っ赤にしたネリアがまん丸い瞳で見上げていることに気がついた。
「なんだよ」
「筋肉がすごい……」
「そりゃどうも。触るか?」
「えっ」
さっきまで散々触らしてもらったしな、とお返しにもならないことを思いつつ、彼女の右手を自身の左胸に触れさせる。小さな手は熱を帯びていて、触れられると無性にドキドキした。勢いで触るかと尋ねてしまったけれど、どう思われているのだろう。見下ろすと、ネリアはどうしてか顔を赤くしている。なんで、と口にする前に、「心臓が……」と惚けたように呟いた。
「心臓の音が、すごい」
「……」
「緊張してるの?」
なぜかキラキラと眩しいぐらいの輝きを放つ瞳で見つめられ、軽々に触れさせたことを後悔した。格好がつかないにも程があるけれど、初めてなのだから仕方がない。ネリアは、「ね、緊張してるの? 私とお揃い?」とニヤニヤしている。「お前まじで可愛いからって調子に乗んなよ」と悪態を吐くと、「? ありがとう」と返された。相変わらずよくわかっていなさそうな様子に、心臓が大きく脈打った。今触れられていたら、間違いなくさらにニヤつかれただろう。
首の下に腕を入れて抱き起こし、再び口付ける。舌を入れると一生懸命応えようとするのが、可愛くて仕方がない。ネリアキスに夢中になっている間に夜着を下からたくし上げ、茂みに指を差し入れる。「んっ!?」と驚いたような声を上げたけれど、全て飲み込んでしまった。反射的にか足を閉じようとするけれど、鍛えているシルビオに敵うはずもない。あっさりと手で押さえ込みながら、陰核を指で引っ掻いた。
「んっ、あっ、ああっ」
「ここ? 気持ちいい?」
「あっ、んっ、ぅあ」
唇を離して尋ねると、こくこくと一生懸命に頷いて答えてくれた。ちゅぷ、と指を抜き差しするたびに生まれる水音が部屋を満たす。手で口を覆う余裕はなくなったのか、可愛い声は何にも邪魔されることなくシルビオの耳にとどく。瞼が硬くつむられているのを良いことに、真っ赤な顔をこれでもかとガン見する。どこに触れても反応を返すのが愛おしくて、頭がどうにかなりそうだ。中に差し込む指を増やし、ちゅ、ちゅ、と顔中に唇を落とす。
「ひぁ、あ、だ、だめっ」
「痛い?」
「ち、がっ、な、なんだか、へん、でっ」
「ん、変になっていいよ」
「ひゃ、あっ、あああっ……」
シルビオの腕を、細い指が掴むけれど大した抵抗にもならない。一際声が高くなるところを押してやると、指がぎゅうぎゅうと締め付けられる。つま先が丸くなり、体がこわばったかと思うと、くったりと力が抜けた。イったんだ、と思うと仄暗い興奮が胸を満たす。はあ、はあ、と肩で息をするネリアを寝台に横たえ、その上から覆い被さった。寝台に散らばる銀色の髪は煌めいていて、神聖なものを穢すような背徳感でゾクゾクする。
「挿れていい?」
ネリアを可愛がる最中から、自身は痛いぐらいに張り詰めている。正直待っている余裕はないけれど、そこは二年も我慢した男。強靭な理性と忍耐力で、ネリアの返事を待つ。
「う、ん」
ゆっくりと瞼を開けたネリアが、蕩けた瞳でシルビオを見つめる。こくり、と頷くのを見て、言いようのない感情で満たされていくのを感じた。「無理だったら言えよ。ていうか、ちゃんとこれで殴れよ」と枕元の腕輪を示すと、ふにゃりと微笑んで口を開く。
「殴らなくても、シルビオは止まってくれるでしょ?」
「……信頼されてんな」
「だって、私に甘いんだもの。私がやめてって言ったらやめてくれるわ」
「……」
得意気に微笑むネリア。大事にされていることを微塵も疑っていない無防備さが、あまりにも可愛くてどうにかなりそうだ。本当の名前すら明かしてもらえない、ともどかしさを覚えていた頃の自分が聞いたらどう思うだろうか。無条件に寄せられる信頼があまりにくすぐったくて、心地いい。途中でやっぱりやめて、とお預けをくらったとしても満足して眠りにつく自信がある。
「力、抜いてろよ」
切先を宛てがい、腰を進めていく。ひゅっ、と緊張からか息を呑むので、「痛くしないから」と慰めるように呟きながら頭を撫でる。それだけで力が抜けるのだから、愛おしくて仕方がない。寝台で所在なげに握り込まれた手に触れると、しがみつくように握られる。力の限り握られているようだけれど、子猫に戯れつかれているぐらいの力だ。ずぷずぷとできるだけゆっくり埋め込み、時間をかけて最奥まで辿り着く。
「痛い?」
「んっ、お腹いっぱいな感じがする……」
「……痛くないなら良かった」
少しの刺激でも出してしまいそうなので、煽るようなことを言わないでほしい。どうにか耐えて、ネリアの顔にかかった髪を払う。銀色に変わった当初は、鏡を見るたびしょんぼりしていたけれど、最近ではそれも無くなったような気がする。黒でも銀でも、似合っているし可愛いことには変わりないのだ。できれば気にしないで、いつまでも笑っていてほしい。
「動いていい?」
「ん、うん」
許しを得たので、ゆっくりと腰を揺する。とちゅ、とちゅ、と打ち付ける音の合間に、ネリアの嬌声が混じる。どうにかなりそうなぐらい気持ちが良い。お預けにされても我慢できたけれど、されなくてよかったと心から思ってしまった。「ネリア、好き。好きだよ」と譫言のように口走ると、「んっ、あっ、う、んっ」と一生懸命に頷いてくれる。余裕がないだろうに、それでも返事をしてくれる律儀さが愛おしい。震える唇に吸い寄せられるようにしてキスすると、怖いぐらいの幸福を感じた。
*
汚れた体を清め、再び夜着を着せてネリアを抱きしめて横たわるシルビオ。
すげーよかった……と余韻に浸っていると、「そういえば」と、不意にネリアが振り向く。最中はあんなに乱れて訳が分からなさそうにしていたのに、終わってみれば随分ケロッとしたものである。爛々と輝く瞳に見つめられ、なんなんだと首を傾げていると、「結局シルビオの初恋の人って誰なの?」と尋ねられた。ピロートークに相応しいようで似つかわしくない話題に、拍子抜けする。思えば、まだ彼女がシルビオを「殿下」と読んでいた頃の話題だ。
「何年前の話だよ、それ」
「だって結局教えてもらってないもの。セレステ様じゃないの?」
「ちげーわ」
何が楽しくて、初対面時から兄の婚約者だった人に横恋慕などという茨の道を歩むのか。「でも、皇宮に来たときセレステ様には優しくされたでしょう?」と不思議がっているけれど、その優しさを恋愛感情に結びつけるほど初心だったわけでもない。隙あらば俺と恋バナしたがるのはなんなんだよ、と呆れつつ柔らかい頬に手を伸ばす。むに、と摘みながら、「そう言うそっちはどうなんだよ」と尋ねた。数年前は、王女だからそんな暇はなかっただのなんだのとはぐらかされたけれど。きょとんと目を丸くする様子に、今回もどうせ適当に流されるのだろう、と予想するシルビオ。
「私はシルビオよ」
「……は」
胸を張って答えるネリアに一瞬、時が止まる。頬を摘んだまま固まるシルビオにネリアは、「私ね、シルビオのことが好き。大好きよ」と赤い顔で告げ、そのまま胸元に顔を埋めた。初恋相手が自分だということに未だ衝撃を受けているシルビオは、「は、待って、一旦待って」としか言えない。衝撃を与えた本人はと言えば、言いたいことは一通り言えたとばかりに満足気だ。シルビオだけが置いて行かれている。
「ネリア、顔上げて」
「心臓の音が、本当にすごいわ」
「おいネリア、顔上げろ」
両手で頬を挟み、ぐいっと強引に顔を上げさせる。耳まで真っ赤にしたネリアがふにゃふにゃと緩んだ顔でシルビオを見上げていて、考える間もなくキスしていた。何度も口付けているうちに息が苦しくなったのか、胸をとんとんと控えめに叩かれる。仕方なく離してやると、「照れた? 照れたの?」とニヤニヤしている。この期に及んで、いい度胸をしているものだ。
「お前ほんと、まじで可愛いからって調子乗りやがって」
「ふふ、ありがとう」
「褒めてねえよ可愛いなちくしょう」
ヤケクソのようにそう呟いて細い肩に顔を埋めると、頭から抱きしめられる。柔らかい檻に閉じ込められるような感覚に、気を抜いたら病みつきになってしまいそうだ。よしよしと小さな手に撫でられる感触を享受していると、「ねえ、私のこといつから好きだった?」と弾んだような声で尋ねられる。シルビオに好かれていることを微塵も疑っていない、そんなところも可愛くてたまらない。
「……さあ、どうだっけな」
「はぐらかした!」
むくれたような声を聞きながら、初めて会ったときのことを思い出す。あの日、王国の聖堂で身代わりの王女を捕まえたのはシルビオだけれど。一目見て囚われたのは、きっとシルビオの方だった。