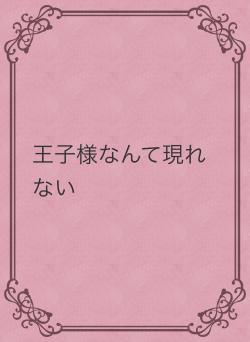一連の事件の顛末を話そう。
シルビオは無事にネリアを連れ帰ると共に、本物のエリシアを捕まえることにも成功。髪の色が黒から銀に変わった一人目の「エリシア」と、突然現れた二人目の「エリシア」に、皇宮のみならず国民までもが騒然とする。今まで「エリシア」だと名乗っていた彼女は、王国で出生すら秘匿されていたネリア王女であること、一連の事件の首謀者は、稀代の魔法使いだと持て囃されていたエリシア王女であることを説明すると、帝国と王国中に動揺は広がった。
当然、ネリアがエリシアと共謀し、帝国を乗っ取ろうとしていたのでは、ということが疑われた。長い間エリシアを名乗り、正体を隠していた上、髪の色が銀色に変わっているのだ。「魔力を持たないせいで閉じ込められていた王女がコンプレックスを抱き、姉と共謀して魔力を奪う魔法を編み出した」と疑われるのは、仕方がないと言えば仕方がない。
ただ、ネリアに対する同情的な声も少なくはなかった。魔力がない、それだけの理由で王女の誕生すら闇に葬る王国の異常性と、生まれてこの方エリシアとマリーとしか関わったことがないのを鑑みると、言われるがままにエリシアの身代わりを務めたとしてもおかしくはない。そもそも、正体を偽っていたとはいえ、ネリアが王国と連絡を取り合っている様子はマリーからの接触があるまで一度としてないのだ。
「ネリア王女は巻き込まれただけであり、全てはエリシア王女が一人で実行に移したことだ」
そう主張したのはシルビオだった。ネリアが処罰を受けることがないよう、彼は必死に弁護した。とはいえ、シルビオも皇宮内で特別信用されているわけではない。庶民の血を引く皇弟の言うことにはやはり説得力がないらしい。もはや何を言っても聞き入れてはもらえないかと思ったけれど。意外なことに、ユルゲン侯爵がシルビオの意見を支持した。
「稀代の魔法使いを制圧した皇子のご意志を、尊重しないわけにはいかないでしょう」
ネリアもエリシアと同罪だと騒ぎ立てる貴族たちに対し、毅然として言い放ったユルゲン侯爵。気づかぬ間に別人にでも入れ替わったのだろうか、と思わず疑ってしまったほどだ。けれど、疑いの余地もなくユルゲン侯爵である彼の発言は、シルビオの大きな助けとなる。結果として、ネリアには情状酌量の余地があるとして処罰は免れた。
「それでも、婚約は破棄にするべきだわ」
けれど、強い意志でそう告げたのは誰あろう、ネリア本人だ。彼女の自責の念は深い。何も知らなかったとはいえ、双子の姉が二つの国に甚大な被害を及ぼしたのだ。姉同様、自分も罪を償うべきだとして、ネリアは譲らない。「……お前は悪くない、って言っても納得しないんだろうな」そう呟くシルビオの目を、ネリアは真っ直ぐに見据える。力強い意思を宿す翡翠の瞳を見ながら、シルビオは腹を括った。
「どうしても気が済まないのなら、王女として責任を取ってほしい」
「え?」
「キシュ王国最後の王女、ネリア・キシュ。コーア帝国とキシュ王国の統合の証として、俺と結婚してくれ」
目を丸くするネリア。正直、一連の事件の犯人がエリシアだとわかった時点で、彼女が婚約破棄を言い出すことは薄々予想できていた。一度も外に出たことがなくとも、「自分は王国の王女である」という誇りのみで生きてきたのだ。責任感からそう言い出すことは、想像に難くない。
その上で、シルビオは帝国に帰ってすぐ皇帝に対して進言した。彼女が無罪であることを証明し、キシュ王国の王女として認めた上で、王国が帝国の支配下に入ることに同意させることを。そして、両国の統合の証として、ネリアを娶りたいということを。皇帝であるライナスは、シルビオの意思を尊重してくれた。そもそも、王国での事件に対する疑念があった上で、エリシアと名乗る彼女をシルビオと婚約させたのはライナスだ。キシュ王国の統治権を掌握し、大陸制覇の足掛かりになればそれでいい、という姿勢は変わらない。
「王国と、帝国の統合の証……」
呆然と繰り返すネリア。事実上、キシュ王国の消滅に同意しろと迫られているようなものだ。王女として思うところはあったのだろう。重い選択を課していることに罪悪感を覚えたけれど、結局ネリアは首を縦に振る。ネリアとしても正直、帝国の支配下に入った方が王国民は幸せになれるのではないか、と考えていたそうだ。王国が帝国の支配下に入ることと、シルビオとの婚約に同意した。
一連の首謀者であるエリシアはと言えば、魔力を封じられた上で一生涯幽閉されることになった。幽閉場所は、ネリアを十八年間閉じ込めていた王国の塔。元々罪人を閉じ込めるために建てられた塔だというのだから、使い道としては正しいのだろう。魔力封じの腕輪が稀代の魔法使いに効くのだろうか、と思ったけれど。ネリアに魔力を与えたことでエリシアの魔力は半減していたこともあり、腕輪は十全に効果を発揮した。裁判の間、ずっと無表情だった彼女が、これからの人生を閉じ込められて過ごすことにどう思っていたのかはわからない。
ちなみに、ネリアにつけられていた魔力封じの腕輪は、そのままつけられることになった。魔力を与えられたとはいえ、魔力の制御は一朝一夕に身につくものではない。生まれながらの魔力持ちではないネリアには、魔法を使いこなすことは難しかったようだ。その制御も兼ねて腕輪をつけるように言ったのだけれど、ネリアとしても特に文句はないらしい。エリシアの開発した魔法は闇に葬られ、彼女が魔法を編み出した意味もなくなる。けれど、それを伝えたところでエリシアは、「そうなのね」と何の感慨もなさそうに呟くだけだった。
「王国は帝国の支配下に入った。平たく言えば、キシュ王国は消滅したようなものだな」
「そう。あんな国、なくなって当然だわ」
興味なさそうに、白金の髪を指に巻き付けるエリシア。双子の妹に魔力を分け与えたものの、彼女の髪の色は変わらないらしい。そのあたりの仕組みはよくわからないけれど、稀代の魔法使いはやはり規格外だということなのだろうか。
ネリアの侍女であったマリーは、帝国の辺境にある修道院に身を寄せることとなった。王国に良い思い出もなく、ネリアの侍女として雇われることも拒否したマリー。「静かに暮らしたい」と項垂れる彼女の願いを、ネリアは聞き入れた。
王宮でエリシアに仕えていた侍女を、塔に連れてくることもしなかったため、彼女の身の回りの世話をする者は誰もいない。心なしか最後に顔を合わせたときよりも身なりは乱れている気がするけれど、それでも不遜さは失われなかったようだ。
あんまりな物言いに、「お前は、ネリアとは違うんだな」と思わず口にする。エリシアを取り繕っていたときのネリアは、暇さえあればシルビオに王国の様子を尋ねるほど心配していた。真似をされた張本人は、王国のことなんてどうでもよさそうだというのに。皮肉を込めた言葉に、エリシアは鼻で笑う。
「あの子は王国を見たことがないから」
「……」
「私が、見せないようにしたんだから当然よ」
そう呟くエリシアに、シルビオは何も言えなかった。双子の接触は禁じているので、今後ネリアがエリシアに会うことはない。二人ともそうなるだろうとは予想していたのか、特に何も言わなかった。二人が最後に交わした会話の内容は、双子のみぞ知ることだ。
これが、稀代の魔法使いが起こした事件の顛末。一人の王女が二つの国を揺るがせた結果。支配者を失い、信仰までも否定されたキシュ王国は最初こそ荒れたものの。ネリアとシルビオの尽力により、徐々に沈静化していく。帝国内での反発の声も、次第に鳴りを潜めていった。
そうして、シルビオとネリアが結婚するまでに、二年の月日が流れた。
シルビオは無事にネリアを連れ帰ると共に、本物のエリシアを捕まえることにも成功。髪の色が黒から銀に変わった一人目の「エリシア」と、突然現れた二人目の「エリシア」に、皇宮のみならず国民までもが騒然とする。今まで「エリシア」だと名乗っていた彼女は、王国で出生すら秘匿されていたネリア王女であること、一連の事件の首謀者は、稀代の魔法使いだと持て囃されていたエリシア王女であることを説明すると、帝国と王国中に動揺は広がった。
当然、ネリアがエリシアと共謀し、帝国を乗っ取ろうとしていたのでは、ということが疑われた。長い間エリシアを名乗り、正体を隠していた上、髪の色が銀色に変わっているのだ。「魔力を持たないせいで閉じ込められていた王女がコンプレックスを抱き、姉と共謀して魔力を奪う魔法を編み出した」と疑われるのは、仕方がないと言えば仕方がない。
ただ、ネリアに対する同情的な声も少なくはなかった。魔力がない、それだけの理由で王女の誕生すら闇に葬る王国の異常性と、生まれてこの方エリシアとマリーとしか関わったことがないのを鑑みると、言われるがままにエリシアの身代わりを務めたとしてもおかしくはない。そもそも、正体を偽っていたとはいえ、ネリアが王国と連絡を取り合っている様子はマリーからの接触があるまで一度としてないのだ。
「ネリア王女は巻き込まれただけであり、全てはエリシア王女が一人で実行に移したことだ」
そう主張したのはシルビオだった。ネリアが処罰を受けることがないよう、彼は必死に弁護した。とはいえ、シルビオも皇宮内で特別信用されているわけではない。庶民の血を引く皇弟の言うことにはやはり説得力がないらしい。もはや何を言っても聞き入れてはもらえないかと思ったけれど。意外なことに、ユルゲン侯爵がシルビオの意見を支持した。
「稀代の魔法使いを制圧した皇子のご意志を、尊重しないわけにはいかないでしょう」
ネリアもエリシアと同罪だと騒ぎ立てる貴族たちに対し、毅然として言い放ったユルゲン侯爵。気づかぬ間に別人にでも入れ替わったのだろうか、と思わず疑ってしまったほどだ。けれど、疑いの余地もなくユルゲン侯爵である彼の発言は、シルビオの大きな助けとなる。結果として、ネリアには情状酌量の余地があるとして処罰は免れた。
「それでも、婚約は破棄にするべきだわ」
けれど、強い意志でそう告げたのは誰あろう、ネリア本人だ。彼女の自責の念は深い。何も知らなかったとはいえ、双子の姉が二つの国に甚大な被害を及ぼしたのだ。姉同様、自分も罪を償うべきだとして、ネリアは譲らない。「……お前は悪くない、って言っても納得しないんだろうな」そう呟くシルビオの目を、ネリアは真っ直ぐに見据える。力強い意思を宿す翡翠の瞳を見ながら、シルビオは腹を括った。
「どうしても気が済まないのなら、王女として責任を取ってほしい」
「え?」
「キシュ王国最後の王女、ネリア・キシュ。コーア帝国とキシュ王国の統合の証として、俺と結婚してくれ」
目を丸くするネリア。正直、一連の事件の犯人がエリシアだとわかった時点で、彼女が婚約破棄を言い出すことは薄々予想できていた。一度も外に出たことがなくとも、「自分は王国の王女である」という誇りのみで生きてきたのだ。責任感からそう言い出すことは、想像に難くない。
その上で、シルビオは帝国に帰ってすぐ皇帝に対して進言した。彼女が無罪であることを証明し、キシュ王国の王女として認めた上で、王国が帝国の支配下に入ることに同意させることを。そして、両国の統合の証として、ネリアを娶りたいということを。皇帝であるライナスは、シルビオの意思を尊重してくれた。そもそも、王国での事件に対する疑念があった上で、エリシアと名乗る彼女をシルビオと婚約させたのはライナスだ。キシュ王国の統治権を掌握し、大陸制覇の足掛かりになればそれでいい、という姿勢は変わらない。
「王国と、帝国の統合の証……」
呆然と繰り返すネリア。事実上、キシュ王国の消滅に同意しろと迫られているようなものだ。王女として思うところはあったのだろう。重い選択を課していることに罪悪感を覚えたけれど、結局ネリアは首を縦に振る。ネリアとしても正直、帝国の支配下に入った方が王国民は幸せになれるのではないか、と考えていたそうだ。王国が帝国の支配下に入ることと、シルビオとの婚約に同意した。
一連の首謀者であるエリシアはと言えば、魔力を封じられた上で一生涯幽閉されることになった。幽閉場所は、ネリアを十八年間閉じ込めていた王国の塔。元々罪人を閉じ込めるために建てられた塔だというのだから、使い道としては正しいのだろう。魔力封じの腕輪が稀代の魔法使いに効くのだろうか、と思ったけれど。ネリアに魔力を与えたことでエリシアの魔力は半減していたこともあり、腕輪は十全に効果を発揮した。裁判の間、ずっと無表情だった彼女が、これからの人生を閉じ込められて過ごすことにどう思っていたのかはわからない。
ちなみに、ネリアにつけられていた魔力封じの腕輪は、そのままつけられることになった。魔力を与えられたとはいえ、魔力の制御は一朝一夕に身につくものではない。生まれながらの魔力持ちではないネリアには、魔法を使いこなすことは難しかったようだ。その制御も兼ねて腕輪をつけるように言ったのだけれど、ネリアとしても特に文句はないらしい。エリシアの開発した魔法は闇に葬られ、彼女が魔法を編み出した意味もなくなる。けれど、それを伝えたところでエリシアは、「そうなのね」と何の感慨もなさそうに呟くだけだった。
「王国は帝国の支配下に入った。平たく言えば、キシュ王国は消滅したようなものだな」
「そう。あんな国、なくなって当然だわ」
興味なさそうに、白金の髪を指に巻き付けるエリシア。双子の妹に魔力を分け与えたものの、彼女の髪の色は変わらないらしい。そのあたりの仕組みはよくわからないけれど、稀代の魔法使いはやはり規格外だということなのだろうか。
ネリアの侍女であったマリーは、帝国の辺境にある修道院に身を寄せることとなった。王国に良い思い出もなく、ネリアの侍女として雇われることも拒否したマリー。「静かに暮らしたい」と項垂れる彼女の願いを、ネリアは聞き入れた。
王宮でエリシアに仕えていた侍女を、塔に連れてくることもしなかったため、彼女の身の回りの世話をする者は誰もいない。心なしか最後に顔を合わせたときよりも身なりは乱れている気がするけれど、それでも不遜さは失われなかったようだ。
あんまりな物言いに、「お前は、ネリアとは違うんだな」と思わず口にする。エリシアを取り繕っていたときのネリアは、暇さえあればシルビオに王国の様子を尋ねるほど心配していた。真似をされた張本人は、王国のことなんてどうでもよさそうだというのに。皮肉を込めた言葉に、エリシアは鼻で笑う。
「あの子は王国を見たことがないから」
「……」
「私が、見せないようにしたんだから当然よ」
そう呟くエリシアに、シルビオは何も言えなかった。双子の接触は禁じているので、今後ネリアがエリシアに会うことはない。二人ともそうなるだろうとは予想していたのか、特に何も言わなかった。二人が最後に交わした会話の内容は、双子のみぞ知ることだ。
これが、稀代の魔法使いが起こした事件の顛末。一人の王女が二つの国を揺るがせた結果。支配者を失い、信仰までも否定されたキシュ王国は最初こそ荒れたものの。ネリアとシルビオの尽力により、徐々に沈静化していく。帝国内での反発の声も、次第に鳴りを潜めていった。
そうして、シルビオとネリアが結婚するまでに、二年の月日が流れた。