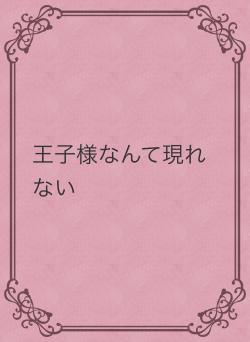――疲れたな。
夜も更け、招待客を見送りながらシルビオはぼんやりと思う。シルビオとエリシアの婚約を披露し、帝国と王国の和平を広く知らしめる名目のパーティー。事情により王国側の参列者は不在のままだったけれど、帝国や他国には知らしめられたのだろうか。目的を果たせたのかどうか、疲れた頭ではよくわからない。
ちらりとエリシアのほうを見遣ると、セレステと談笑している。丸い頬を赤く染めてニコニコしているが、何がそんなに楽しいのだろうか。俺がネックレスあげたときより嬉しそうじゃねえか、となんとなくムッとしていると、片手に握られたワイングラスに気がついた。どうやら、酔っ払ってテンションが上がっているらしい。あいつ酒飲めたのか、と意外に思っているときだった。
「シルビオ」
「! 陛下」
シルビオを呼んだのは、皇帝であるライナス。シルビオの視線の先を辿り、「エリシア殿は酔っているのか?」と尋ねられた。誰が見ても酔っ払っている婚約者を眺めつつ、「そのようです」と返すと、「彼女を連れて下がるといい」と言われた。侍従であるリオンにも、侍女であるサラとケイトにも、もう遅いからと下がらせている。ライナスたちが場を辞してから帰ろうと思っていたのだけれど。
「ですが、まだ賓客の見送りが……」
「私とセレステがいれば問題ないだろう」
それはそうだけれど、皇帝がまだ辞していないのに先に帰ってもいいものなのか。少しの間逡巡したけれど、「では、そのように」と従った。あまり固辞し続けるのも無礼に当たるだろう。あいつちゃんと歩けんのか、と懸念しつつエリシアの方に足を向けると、「シルビオ」ともう一度呼び止められた。
「お前とエリシア殿の婚約は、帝国の利益のためのものだ。それ以上の意図はない」
「はい」
エリシアとの婚約も、このパーティーも、政略的な意味しかないことはわかっている。仲良くするに越したことはないけれど、恋愛感情を持つ必要はない。帝国が大陸制覇を進めるための足がかりにさえなればいい。十全に果たせたかには疑問が残るけれど、役割自体を忘れたつもりはない。改まってなんだろう、と首を傾げていると、「だが」とライナスが続ける。
「できれば仲良くやっていって欲しいと、兄として願っているよ」
「へ」
「それだけだ」
そう言ってはにかむライナスは、「皇帝」ではなく「兄」の顔をしていた。呆然と立ち尽くすシルビオの肩を叩くと、賓客の見送りに出向く。数秒して、ようやく兄の言葉を飲み込めたシルビオ。パッと勢いよくエリシアの方を向くと、未だワイングラスを傾けようとしているので、そろそろ取り上げようと足を向けた。
*
「酒、飲めるんだな?」
「初めて飲みました!」
「飲めないってことね」
呆れるシルビオとは対照的に、エリシアはニコニコとご機嫌だ。いつもならお目にかかることのできない緩み切った表情に、頬をもちもちと撫でくりまわしたくなる。面倒を見てくれていたセレステにお礼を言って帰ることを促したけれど、足取りはどうにも覚束ない。二の腕をしっかり掴み、ホールを後にするけれど、ヘロヘロなので抱き抱えた方が早いかもしれないと思った。
――転移魔法が使えりゃよかったけど。
シルビオは魔法が使えるけれど、決して魔力が高い方ではない。転移魔法、それも他人を伴って移動するなんて芸当は、とてもじゃないができそうにない。ふと、つい最近得られた、「エリシア王女はよく転移魔法を使って姿を消していた」という情報を思い出す。常時嵌められている魔力封じの腕輪を外したら、彼女は魔法を使えるようになるのだろうか。どう考えても稀代の魔法使いではない彼女に、稀代の魔法使いらしく転移魔法を使ってみせろと吹っかけてやろうかと思ったけれど、やめておいた。酔いどれ魔法使いでは、どこに転移させられるかわかったものではない。
「ふふ、パーティー楽しかったですね」
そんなシルビオの内心など知る由もなく、エリシアは呑気にヘラヘラと笑っている。あまりの無防備さに、こいつ危機感とかねえのかと謎の心配を覚えてしまったほどだ。自国を乗っ取られようというときに、貴族連中から品定めするようなネチネチとした視線を受けながらも、ベロベロになるまで酒を飲める神経がよくわからない。シルビオの婚約者は、思った以上に図太いらしい。
「ねえ、散歩しません?」
パッとシルビオを見上げるエリシア。翡翠の瞳が月明かりに反射して、キラキラと眩しい。ドギマギするのを必死に隠しつつ、呑気な提案に、「はあ? 散歩?」と怪訝そうに見えるよう装った。酔っ払ったエリシアは特に何を気にした様子もなく、「お昼の庭園は見たことがあっても、夜の庭園は見たことがないもの」と、ふわふわと零している。
「あっ、おい」
二の腕を掴むシルビオを引きずるようにして、庭園へと足を向けるエリシア。リードに繋がれた狩猟犬が全く言うことを聞いてくれないときのことが脳裏によぎった。こんなに酔っ払ってんのにふらふら歩いて大丈夫かよ、と思わず心配したけれど、エリシアが止まりそうな様子はない。シルビオが本気を出せば、立ち止まることもエリシアを無理やり抱えて部屋に連れて行くことも容易い。けれど、なんとなくそうする気分にはなれなかった。
「帝国のお庭、夜に見ても綺麗ですね」
エリシアの行きたい方向に着いていくと、感嘆したように息を漏らしている。「そうだな」と答えたけれど、美的な感性に乏しいシルビオとしては、昼でも夜でもさして変化は感じない。庭師が聞いたら落ち込みそうなことを考えながら、エリシアの方を見遣る。彼女の翡翠の目には、この庭園がどう映っているのだろうか。
「ふう、疲れたわ。座りましょう、殿下」
「自由だな……」
別に普段から従順というわけではないけれど。いつもと違ってなんとなく幼さを感じるのは気のせいだろうか。ベンチに腰掛けようとするエリシアにチーフを敷いてやると、ぱちぱちと瞬きを繰り返す。やがて緩んだ顔で、「王子様みたいですね」と微笑んだ。きゅう、と締め付けられるような音が心臓からした気がする、と思いながら、「皇子様なんだよ」と返した。
「ふふ、そうでした。ありがとうございます」
「別に」
シルビオのつっけんどんな返事も、酔っ払ってご機嫌なエリシアは気にならないらしい。「あの鶏肉のお料理、なんて名前ですか?」「トライフルをサラとケイトは食べたのかな」「お酒ってこんなにふわふわするのね」と、ペラペラと益体もないことを話している。食事しかパーティーの記憶ないのかよ、と思わず呆れてしまった。膝に頬杖をついて顔を覗き込むと、真っ赤な顔が月明かりに照らされている。ぷらぷらと足をぱたつかせるエリシアは、やはりいつもとは違って見えた。
――こいつ、こんな感じだったか?
表情も口調も仕草も、いつもよりずっと幼い。わかりやすく虚勢を張っているときとも、一国の王女たろうとしているときとも違う。まるで、体だけ成長した子供が無邪気に話しているかのようだ。ろくな返事も返さないシルビオに、一秒後には忘れてしまいそうなことをふわふわと喋り続けている。この調子だと、本当に明日にはすべて忘れているかもしれない。
「……あのさ」
「? なあに?」
唐突に話を遮ったシルビオを、怒りもせず見上げるエリシア。きょとんとしている顔はやっぱりどこかあどけない。ふと、前髪がほんの少し乱れているのが目についた。塗り込めた夜空のような黒髪は、真夜中でも艶やかさを失わない。なんとなく手を伸ばすと、眩しく輝く翡翠がシルビオの指の動きを追う。警戒心のかけらも見えないのは、酔っているからなのか。それともシルビオだからなのか。そんなどうしようもないことを考えながら、前髪を直してやる。滑らかそうだと思っていた黒髪は思っていた通りの感触で、ずっと触れていたいと思ってしまった。
「あー……俺のこと、庇ってくれてありがとう」
ぽろ、と言葉が溢れる。明日、彼女は今日のことをどれぐらい覚えているのだろう。きっと覚えていないのだろう。そう思っているのに、こんな大事なことを告げるのはずるいなんて、自分でもわかっている。けれど、胸の内の脆いところを曝け出すような真似を、素面の彼女にできる気がしなかった。
「ああいうことには、なんていうか……まあ、慣れてるんだけどさ」
どれだけ皇弟としての務めを果たそうと、良く思わない人はいる。シルビオの意思に関わらず、生まれは足を引っ張る。ライナスとセレステがどれだけ庇おうと、意味をなさない。いつしか、わざわざ二人に反論させること自体に罪悪感を覚えるようにまでなっていた。投げられる言葉にいちいち反論してもらっていてはキリがない、自身の行動で見返すから何も言わなくていい。そう進言したシルビオに、ライナスもセレステも納得していなさそうだったけれど、それでもシルビオの意思を汲んでくれた。
皇弟として、恥じない行いを。市井生まれだからと、侮られないような行動を。尊敬する兄と義姉のため、努力することは決して苦ではない。リオンのように、慕ってくれる臣下だっている。けれど、それでも向けられる悪意に痛みを感じないほど、麻痺しきっているわけでもないのだ。今日もまた耐えるしかないのか、と半ば諦めながら拳を握りしめていたシルビオ。
エリシアが庇ってくれたことは、青天の霹靂とも言えるほどの衝撃を与えた。「俺のことあんなふうに見てくれてるの、知らなかった」と溢すシルビオ。前髪に触れていた指先が滑り、丸い頬に触れる。酔っているからだろう、見た目通り熱を持つ頬は、摘むと柔らかい。唐突に触れられることに抵抗もせず、ぽつぽつと語られる言葉にじっと耳を傾ける。異国の王女は今、何を考えているのだろう。
「……お前さあ、本当はなんて名前なの?」
ぱち、と目を瞬くエリシア。唐突に転換した話題に面食らっているようだけれど、実のところ何を考えているのかはよくわからない。目の前の彼女が、キシュ王国のエリシア王女でないことも、稀代の魔法使いでないこともわかっている。その正体が何であれ、いつかは暴かなければならないだろう。
けれど、今シルビオの中に沸いたのは、目の前の彼女に対する純粋な興味だった。平民出身の皇弟ではなく、単なる「シルビオ」として見てくれる彼女の、本当の名前は何なのか。名前を呼んだら、一体どんな顔をするのか。気づけば、心臓は早鐘を打っている。きょとんとしていた彼女だけれど、瞬きの間に顎を逸らして微笑んだ。いつも見る、「エリシア王女」としての微笑みだ。
「エリシア、ですわ」
「はあー……こんだけ酔ってんのに口固えのな」
思わず仰け反って天を仰ぐ。何が彼女に、そこまでさせるのだろう。ヘロヘロに酔っ払ってなお、ガードは驚くほどに固い。じっとりと見つめると、相変わらずニコニコと微笑んでいる。酔っ払っているのか、若干酔いが覚めてきたのか、判断に迷う顔だ。
「お前ほんと、ちょっと可愛いからって調子乗んなよ」
「? ありがとうございます」
「褒めてねえよ」
どちらかといえば罵っているはずなのに、毎回お礼を言われることにシルビオは納得していない。やはり、ちょっと可愛いからと言って調子に乗っているのだろう。むにむにと指先で頬を摘むけれど、だんだんそれでも物足りなくなってきた。手を開き、頬に添えて上を向かせる。
「……綺麗な目、してんな」
「殿下も綺麗ですよ」
「それはどうも」
どういう会話だよ、と自らつっこんでしまうほど、気の抜けるやり取りをかわす。目に見えない引力に吸い寄せられるかのように、顔が徐々に近づく。キラキラと宝石のように輝く瞳に、シルビオが映るのがよく見えた。瞬きもしないでシルビオを見つめるエリシア。心臓の音が、聞こえてしまいそうなほどにうるさい。唇が触れるまであと少し、と言ったところでぴたりと動きを止めた。頭をよぎったのは、泣きながら啖呵を切るエリシアの姿。
「抵抗、しろよ」
「抵抗?」
「なんでもねえ」
ぽやっとしているエリシアの頬から手を離す。ぷらぷらと足をパタつかせるエリシアが何を考えているのか、相変わらず真意は読めない。明らかにキスされそうだったことを、彼女はわかっているのだろうか。押し倒したときはあれほど泣いて怒っていたのに、よくわからない。が、酔ってふわふわしているエリシアに口付けたところで、シルビオの胸を占めるのは罪悪感だけだ。
「帰るぞ」
「はあい」
立ち上がり、差し出した手をエリシアは素直に取る。足取りがおぼつかなかったらまた二の腕を掴もうと考えたけれど、思いの外足取りはしっかりしている。このままでいいか、と手を繋いだまま皇宮へ向かって歩き始めた。
「ふふ」
「なんだよ」
「殿下の手、あったかい」
「……そうかよ」
にぎにぎと小さな手が、感触を確かめるようにシルビオの手を握る。やっぱさっきキスしときゃよかった、と若干後悔した。
夜も更け、招待客を見送りながらシルビオはぼんやりと思う。シルビオとエリシアの婚約を披露し、帝国と王国の和平を広く知らしめる名目のパーティー。事情により王国側の参列者は不在のままだったけれど、帝国や他国には知らしめられたのだろうか。目的を果たせたのかどうか、疲れた頭ではよくわからない。
ちらりとエリシアのほうを見遣ると、セレステと談笑している。丸い頬を赤く染めてニコニコしているが、何がそんなに楽しいのだろうか。俺がネックレスあげたときより嬉しそうじゃねえか、となんとなくムッとしていると、片手に握られたワイングラスに気がついた。どうやら、酔っ払ってテンションが上がっているらしい。あいつ酒飲めたのか、と意外に思っているときだった。
「シルビオ」
「! 陛下」
シルビオを呼んだのは、皇帝であるライナス。シルビオの視線の先を辿り、「エリシア殿は酔っているのか?」と尋ねられた。誰が見ても酔っ払っている婚約者を眺めつつ、「そのようです」と返すと、「彼女を連れて下がるといい」と言われた。侍従であるリオンにも、侍女であるサラとケイトにも、もう遅いからと下がらせている。ライナスたちが場を辞してから帰ろうと思っていたのだけれど。
「ですが、まだ賓客の見送りが……」
「私とセレステがいれば問題ないだろう」
それはそうだけれど、皇帝がまだ辞していないのに先に帰ってもいいものなのか。少しの間逡巡したけれど、「では、そのように」と従った。あまり固辞し続けるのも無礼に当たるだろう。あいつちゃんと歩けんのか、と懸念しつつエリシアの方に足を向けると、「シルビオ」ともう一度呼び止められた。
「お前とエリシア殿の婚約は、帝国の利益のためのものだ。それ以上の意図はない」
「はい」
エリシアとの婚約も、このパーティーも、政略的な意味しかないことはわかっている。仲良くするに越したことはないけれど、恋愛感情を持つ必要はない。帝国が大陸制覇を進めるための足がかりにさえなればいい。十全に果たせたかには疑問が残るけれど、役割自体を忘れたつもりはない。改まってなんだろう、と首を傾げていると、「だが」とライナスが続ける。
「できれば仲良くやっていって欲しいと、兄として願っているよ」
「へ」
「それだけだ」
そう言ってはにかむライナスは、「皇帝」ではなく「兄」の顔をしていた。呆然と立ち尽くすシルビオの肩を叩くと、賓客の見送りに出向く。数秒して、ようやく兄の言葉を飲み込めたシルビオ。パッと勢いよくエリシアの方を向くと、未だワイングラスを傾けようとしているので、そろそろ取り上げようと足を向けた。
*
「酒、飲めるんだな?」
「初めて飲みました!」
「飲めないってことね」
呆れるシルビオとは対照的に、エリシアはニコニコとご機嫌だ。いつもならお目にかかることのできない緩み切った表情に、頬をもちもちと撫でくりまわしたくなる。面倒を見てくれていたセレステにお礼を言って帰ることを促したけれど、足取りはどうにも覚束ない。二の腕をしっかり掴み、ホールを後にするけれど、ヘロヘロなので抱き抱えた方が早いかもしれないと思った。
――転移魔法が使えりゃよかったけど。
シルビオは魔法が使えるけれど、決して魔力が高い方ではない。転移魔法、それも他人を伴って移動するなんて芸当は、とてもじゃないができそうにない。ふと、つい最近得られた、「エリシア王女はよく転移魔法を使って姿を消していた」という情報を思い出す。常時嵌められている魔力封じの腕輪を外したら、彼女は魔法を使えるようになるのだろうか。どう考えても稀代の魔法使いではない彼女に、稀代の魔法使いらしく転移魔法を使ってみせろと吹っかけてやろうかと思ったけれど、やめておいた。酔いどれ魔法使いでは、どこに転移させられるかわかったものではない。
「ふふ、パーティー楽しかったですね」
そんなシルビオの内心など知る由もなく、エリシアは呑気にヘラヘラと笑っている。あまりの無防備さに、こいつ危機感とかねえのかと謎の心配を覚えてしまったほどだ。自国を乗っ取られようというときに、貴族連中から品定めするようなネチネチとした視線を受けながらも、ベロベロになるまで酒を飲める神経がよくわからない。シルビオの婚約者は、思った以上に図太いらしい。
「ねえ、散歩しません?」
パッとシルビオを見上げるエリシア。翡翠の瞳が月明かりに反射して、キラキラと眩しい。ドギマギするのを必死に隠しつつ、呑気な提案に、「はあ? 散歩?」と怪訝そうに見えるよう装った。酔っ払ったエリシアは特に何を気にした様子もなく、「お昼の庭園は見たことがあっても、夜の庭園は見たことがないもの」と、ふわふわと零している。
「あっ、おい」
二の腕を掴むシルビオを引きずるようにして、庭園へと足を向けるエリシア。リードに繋がれた狩猟犬が全く言うことを聞いてくれないときのことが脳裏によぎった。こんなに酔っ払ってんのにふらふら歩いて大丈夫かよ、と思わず心配したけれど、エリシアが止まりそうな様子はない。シルビオが本気を出せば、立ち止まることもエリシアを無理やり抱えて部屋に連れて行くことも容易い。けれど、なんとなくそうする気分にはなれなかった。
「帝国のお庭、夜に見ても綺麗ですね」
エリシアの行きたい方向に着いていくと、感嘆したように息を漏らしている。「そうだな」と答えたけれど、美的な感性に乏しいシルビオとしては、昼でも夜でもさして変化は感じない。庭師が聞いたら落ち込みそうなことを考えながら、エリシアの方を見遣る。彼女の翡翠の目には、この庭園がどう映っているのだろうか。
「ふう、疲れたわ。座りましょう、殿下」
「自由だな……」
別に普段から従順というわけではないけれど。いつもと違ってなんとなく幼さを感じるのは気のせいだろうか。ベンチに腰掛けようとするエリシアにチーフを敷いてやると、ぱちぱちと瞬きを繰り返す。やがて緩んだ顔で、「王子様みたいですね」と微笑んだ。きゅう、と締め付けられるような音が心臓からした気がする、と思いながら、「皇子様なんだよ」と返した。
「ふふ、そうでした。ありがとうございます」
「別に」
シルビオのつっけんどんな返事も、酔っ払ってご機嫌なエリシアは気にならないらしい。「あの鶏肉のお料理、なんて名前ですか?」「トライフルをサラとケイトは食べたのかな」「お酒ってこんなにふわふわするのね」と、ペラペラと益体もないことを話している。食事しかパーティーの記憶ないのかよ、と思わず呆れてしまった。膝に頬杖をついて顔を覗き込むと、真っ赤な顔が月明かりに照らされている。ぷらぷらと足をぱたつかせるエリシアは、やはりいつもとは違って見えた。
――こいつ、こんな感じだったか?
表情も口調も仕草も、いつもよりずっと幼い。わかりやすく虚勢を張っているときとも、一国の王女たろうとしているときとも違う。まるで、体だけ成長した子供が無邪気に話しているかのようだ。ろくな返事も返さないシルビオに、一秒後には忘れてしまいそうなことをふわふわと喋り続けている。この調子だと、本当に明日にはすべて忘れているかもしれない。
「……あのさ」
「? なあに?」
唐突に話を遮ったシルビオを、怒りもせず見上げるエリシア。きょとんとしている顔はやっぱりどこかあどけない。ふと、前髪がほんの少し乱れているのが目についた。塗り込めた夜空のような黒髪は、真夜中でも艶やかさを失わない。なんとなく手を伸ばすと、眩しく輝く翡翠がシルビオの指の動きを追う。警戒心のかけらも見えないのは、酔っているからなのか。それともシルビオだからなのか。そんなどうしようもないことを考えながら、前髪を直してやる。滑らかそうだと思っていた黒髪は思っていた通りの感触で、ずっと触れていたいと思ってしまった。
「あー……俺のこと、庇ってくれてありがとう」
ぽろ、と言葉が溢れる。明日、彼女は今日のことをどれぐらい覚えているのだろう。きっと覚えていないのだろう。そう思っているのに、こんな大事なことを告げるのはずるいなんて、自分でもわかっている。けれど、胸の内の脆いところを曝け出すような真似を、素面の彼女にできる気がしなかった。
「ああいうことには、なんていうか……まあ、慣れてるんだけどさ」
どれだけ皇弟としての務めを果たそうと、良く思わない人はいる。シルビオの意思に関わらず、生まれは足を引っ張る。ライナスとセレステがどれだけ庇おうと、意味をなさない。いつしか、わざわざ二人に反論させること自体に罪悪感を覚えるようにまでなっていた。投げられる言葉にいちいち反論してもらっていてはキリがない、自身の行動で見返すから何も言わなくていい。そう進言したシルビオに、ライナスもセレステも納得していなさそうだったけれど、それでもシルビオの意思を汲んでくれた。
皇弟として、恥じない行いを。市井生まれだからと、侮られないような行動を。尊敬する兄と義姉のため、努力することは決して苦ではない。リオンのように、慕ってくれる臣下だっている。けれど、それでも向けられる悪意に痛みを感じないほど、麻痺しきっているわけでもないのだ。今日もまた耐えるしかないのか、と半ば諦めながら拳を握りしめていたシルビオ。
エリシアが庇ってくれたことは、青天の霹靂とも言えるほどの衝撃を与えた。「俺のことあんなふうに見てくれてるの、知らなかった」と溢すシルビオ。前髪に触れていた指先が滑り、丸い頬に触れる。酔っているからだろう、見た目通り熱を持つ頬は、摘むと柔らかい。唐突に触れられることに抵抗もせず、ぽつぽつと語られる言葉にじっと耳を傾ける。異国の王女は今、何を考えているのだろう。
「……お前さあ、本当はなんて名前なの?」
ぱち、と目を瞬くエリシア。唐突に転換した話題に面食らっているようだけれど、実のところ何を考えているのかはよくわからない。目の前の彼女が、キシュ王国のエリシア王女でないことも、稀代の魔法使いでないこともわかっている。その正体が何であれ、いつかは暴かなければならないだろう。
けれど、今シルビオの中に沸いたのは、目の前の彼女に対する純粋な興味だった。平民出身の皇弟ではなく、単なる「シルビオ」として見てくれる彼女の、本当の名前は何なのか。名前を呼んだら、一体どんな顔をするのか。気づけば、心臓は早鐘を打っている。きょとんとしていた彼女だけれど、瞬きの間に顎を逸らして微笑んだ。いつも見る、「エリシア王女」としての微笑みだ。
「エリシア、ですわ」
「はあー……こんだけ酔ってんのに口固えのな」
思わず仰け反って天を仰ぐ。何が彼女に、そこまでさせるのだろう。ヘロヘロに酔っ払ってなお、ガードは驚くほどに固い。じっとりと見つめると、相変わらずニコニコと微笑んでいる。酔っ払っているのか、若干酔いが覚めてきたのか、判断に迷う顔だ。
「お前ほんと、ちょっと可愛いからって調子乗んなよ」
「? ありがとうございます」
「褒めてねえよ」
どちらかといえば罵っているはずなのに、毎回お礼を言われることにシルビオは納得していない。やはり、ちょっと可愛いからと言って調子に乗っているのだろう。むにむにと指先で頬を摘むけれど、だんだんそれでも物足りなくなってきた。手を開き、頬に添えて上を向かせる。
「……綺麗な目、してんな」
「殿下も綺麗ですよ」
「それはどうも」
どういう会話だよ、と自らつっこんでしまうほど、気の抜けるやり取りをかわす。目に見えない引力に吸い寄せられるかのように、顔が徐々に近づく。キラキラと宝石のように輝く瞳に、シルビオが映るのがよく見えた。瞬きもしないでシルビオを見つめるエリシア。心臓の音が、聞こえてしまいそうなほどにうるさい。唇が触れるまであと少し、と言ったところでぴたりと動きを止めた。頭をよぎったのは、泣きながら啖呵を切るエリシアの姿。
「抵抗、しろよ」
「抵抗?」
「なんでもねえ」
ぽやっとしているエリシアの頬から手を離す。ぷらぷらと足をパタつかせるエリシアが何を考えているのか、相変わらず真意は読めない。明らかにキスされそうだったことを、彼女はわかっているのだろうか。押し倒したときはあれほど泣いて怒っていたのに、よくわからない。が、酔ってふわふわしているエリシアに口付けたところで、シルビオの胸を占めるのは罪悪感だけだ。
「帰るぞ」
「はあい」
立ち上がり、差し出した手をエリシアは素直に取る。足取りがおぼつかなかったらまた二の腕を掴もうと考えたけれど、思いの外足取りはしっかりしている。このままでいいか、と手を繋いだまま皇宮へ向かって歩き始めた。
「ふふ」
「なんだよ」
「殿下の手、あったかい」
「……そうかよ」
にぎにぎと小さな手が、感触を確かめるようにシルビオの手を握る。やっぱさっきキスしときゃよかった、と若干後悔した。