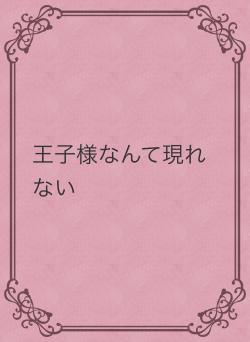「その……なんだ。どうなんだ、エリシア王女とは」
なんでそんな思春期の息子に対して距離感掴みかねてる父親みたいな感じなんですか、と突っ込みそうになった。玉座の間でなければ、口走っていただろう。腹違いの兄はシルビオに優しいけれど、紛うことなき皇帝陛下。皇弟とはいえ、流石に他の臣下の前でそんな気安い口は聞けない。
「時間を作って会話をし、交流を深めるように心がけています」
押し倒して泣かせてしまった日以降、毎晩雑談するようになったことを思い出しつつ、正直に答える。朝の挨拶すら無視するほどには警戒していたシルビオだが、今では時間が合えば朝食時にも話しかけるほどには絆されている。エリシアの方も穏やかにそれに応じるぐらいには、強気かつ生意気な口調も鳴りを潜めていた。相変わらず正体も本名もわからないままだけれど、それでも出会ったばかりの頃に比べれば打ち解けたと言ってもいいだろう。就寝前のほんのわずかな時間は、エリシアが言うところの「歩み寄ってお互いのことを知る」のに効果的だったらしい。
「そうか、上手くやっているようか」
安堵したように陛下は頷くので、シルビオはほんの少し目を見開く。エリシアともう少し仲良くしたほうがいいのでは、とセレステやリオンに諫言されたことはあれど、陛下に何かを言われたことはない。意外にも気にかけてくれていたらしいことを、シルビオは初めて知った。面映さを隠すように俯いていると、陛下の咳払いの音が聞こえる。
「今度、お前たちの婚約を披露するパーティーを開く」
「パーティー、ですか」
顔を上げると、今度は重々しく頷く陛下が見える。おそらく、単に婚約したことを知らしめるためだけのパーティーではないのだろう。帝国と王国の和平を広く見せつけ、大陸制覇の足がかりにするための準備。キシュ王国の国王夫妻どころか、貴族すらいない状況で披露するのは如何なものか、と思ったけれど。そもそも婚約自体が帝国の独断で進んでいるようなものなのだ、今更だろう。
「わかっていると思うが、くれぐれも王女とは仲睦まじくいるように」
「……善処します」
打ち解けているとはいえ、仲睦まじい様子を見せつけるまでになるのは難しいのでは。そう思ったものの顔には出さない。皇弟としてのシルビオの務めは、皇帝を支えること。無理そうな命令にも、黙して従うのみだ。
*
その日の夜。いつも通り、シルビオはエリシアの部屋を訪れていた。婚約の披露目パーティーがある、と告げるとエリシアはぽかんと口を開ける。「パーティー……」とまるで聞き馴染みのない単語を復唱するかのように呟くと、「帝国のパーティーはどういう感じなの?」と首を傾げた。自分たちが主役のパーティーである認識が薄そうな反応に、なんとなく拍子抜けする。傾いた首をそのまま胸元に引き寄せたい衝動に駆られながら、帝国でのパーティーを思い浮かべる。記憶を辿るうち、自然と眉間に皺が寄った。
「めんどい」
「他には?」
「喧しい」
「ええ……」
ご令嬢方からうんざりするほどの秋波を送られたり、生まれのことを貴族連中からチクチク言われたりすることが主に脳裏に浮かんだシルビオ。淡々と挙げられるネガティブな印象に、エリシアが引くのも無理はない。良くも悪くも注目を浴びやすいシルビオにとって、大勢の人が集まるパーティーに大した思い入れはないのだ。いっそのことセレステ殿に聞いてくれ、と義兄嫁に思いを馳せる。その思考を読み取ったかのように、「ろくな思い出がないのね」とエリシアは苦笑した。同情も憐憫も歓迎できるものではないけれど、労わるように穏やかな笑い方は嫌いではない。
きゅう、と心臓のあたりで音が鳴った気がするのをごまかすようにして、紅茶に口をつける。侍女から紅茶の淹れ方を教わったらしく、いつからか雑談のお供に淹れてくれるようになった。生まれてこの方紅茶を淹れたことがないのか、味は定まらないが毎回飲み干すようにはしている。白湯に風味がついた程度のときもあれば、眠気が覚めるほどに渋いときもあるが、今日は後者だったようだ。
「あっ、だから今日はダンスのレッスンが多かったのかしら」
納得したように呟くエリシア。こうして夜な夜な駄弁るようになってから早数日。意外と話題は尽きないのだけれど、彼女の話題の半分ぐらいは妃教育の内容だ。カーテシーなど、最低限の所作は身につけているエリシアだけれど、知らないこともできないことも多い。紅茶の淹れ方が定まらないのも、その一つ。王女でないからこそろくな教育を受けてこなかったのか、王女だからこそ世間知らずなのか。シルビオにその判断はつかない。偽王女だと決めてかかり、基礎から教育を施すよう教師たちに告げたのが英断だったらしいことはわかった。
「お披露目パーティーってことは、踊るのよね?」
お前絶対パーティーに参加したことないだろ、と言いたくなるような質問に対して、「ああ」と答える。王国のパーティーはどうだったのか、彼女に尋ねれば一体どう返すのだろう。さも参加したことがあるように、小さな顎を逸らして語り始めるのだろうか。聞いてみる前に、「あなたの足を踏まないよう、パーティーまでには上達しておくわね」と意気込み始めたので、質問は後回しにした。拳を握って気合いを入れる様子からは、初対面のときのような口の悪さや不遜さは伺えない。良くも悪くも、幼くあどけなく一生懸命なのが彼女の本質なのだろうか。
「……せいぜい頑張れよ」
「もう。またそういう言い方する」
ぷん、と怒ったように膨らんだ頬を、片手で掴んで空気を抜いてやりたいと思いながら目を逸らす。シルビオが辟易としているのとは対照的に、彼女はパーティーを楽しみにしているらしい。すまし顔を取り繕ってはいるけれど、口元の緩みを必死に隠そうとしているのがバレバレだ。とりあえず、長らく踊っていないダンスの練習をしておくことと、それから靴には硬化魔法を掛けることに決めた。
*
そうして数日が経ち、あっという間にパーティー当日。
普段は無造作におろしたままの前髪を後ろに撫で付け、堅苦しい正装に身を包む。正直行きたくない気持ちでいっぱいなので、今からでも仮病を使って欠席したい。が、そんなことができるはずもないことは、重々承知している。中座するぐらいは許されっかな、と不真面目なことを考えながら、ベルベットの小さな箱を手に隣の部屋をノックした。
「おい、準備できたか?」
「あっ、殿下」
「ちょうどできたところですよ!」
すぐに扉が開いて、興奮した様子の侍女二人が出迎える。早く早くと急かされるので、なんだよと顔を顰めつつ部屋に足を踏み入れ――目を見開いて固まった。
「殿下。もう時間ですか?」
シルビオが入ってきたことに気がつき、振り向くエリシア。いつもはゆるく纏めている黒髪は綺麗に結い上げられ、しゃらしゃらと花の髪飾りが揺れている。胸元が大きく開いた光沢のある深紅のドレスは、華奢なエリシアの魅力を惹き立たせていた。瞼や唇を彩る色はいつもより鮮やかで、華やかさが際立つ。辺りに星が舞っているかのように眩く輝くエリシアから、どうしてだか目が離せない。初めて会ったときのように、動悸が治まらない。シルビオが見惚れているのにも気づかず、「殿下って、正装なさったら本物の王子様みたいですわね」と呑気なことを言っている。
「……本物の皇子なんだよ」
「あら、そうでしたわね」
絞り出すように言葉を返すシルビオとは対照的に、エリシアはどこまでも楽しそうにケラケラと笑う。余程パーティーに浮かれているのか、いつもよりご機嫌だ。ほとんど敵国のような隣国のパーティーに参加させられるというのに、随分と肝が座っているらしい。「それで口の悪さがなければ完璧ですわね」と小生意気なことを言っているけれど、そっくりそのまま返したい。
「お前、まじで可愛いからって調子に乗んなよ」
「? ありがとうございます」
「褒めてねえよ」
背後でひゃあひゃあと騒ぐ侍女とは対照的に、ぽかんとシルビオを見つめるエリシア。柔らかそうな頬を摘んでやりたくなったが、化粧が崩れてはいけないので我慢した。眉間に皺を寄せて耐えるシルビオを他所にエリシアは、「変じゃないかしら」と侍女の二人に確認している。
「変だなんてそんな!」
「お美しいですわ」
口を揃えて主君を褒め称える二人。背中に「お前もとっとと褒めろ」と言いたげな視線が突き刺さっているのは、きっと気のせいではない。仮にも婚約者が着飾っているのだ、褒め言葉の一つや二つ掛けなければならないことは、シルビオだってわかっている。あの無口で堅物に見える兄でさえ、婚約者のセレステが着飾れば歯の浮くような台詞で褒めちぎっているのだ。シルビオが同じことをしないわけにはいかない。
「……悪いが、席を外してくれるか?」
振り向いて、侍女たちにそう告げる。二人は顔を見合わせて目を丸くしたが、やがて無言でお辞儀をして部屋を出ていった。揶揄うような言葉もかけず、職務と主君に忠実な侍女たちでよかったとこっそり息を吐く。後に残されたのはシルビオとエリシアだけ。二人きりには慣れているはずなのに、緊張してしまうのはどうしてだろう。せっかく侍女を下がらせたのに、口が乾いてうまく言葉が出てこない。気まずい沈黙に包まれかけたとき、口火を切ったのはエリシアだった。
「何か、ご用でした?」
先ほどまでのご機嫌な様子から一転。遠慮がちに問いかける声には、戸惑いが含まれている。それはそうだろう。婚約者が侍女を下がらせたきり口を開こうとしないのだから、困惑しても仕方がない。似合っている、綺麗だ、美しい。ありふれた褒め言葉を口にするだけ、たったそれだけのことなのに。どうしてここまで緊張するのだろうか。
「……これ」
逡巡した末に、どうにか絞り出したのはたった一言だった。満足に褒めることもできないまま、ずっと握りしめていたベルベットの小さな箱を差し出す。突き出した腕は鉛のように重たい。ぱち、と目を瞬くエリシアはシルビオを見上げ、「くださるの?」と尋ねた。そうでないなら誰に渡すって言うんだよ、と八つ当たりにも似た悪態を飲み込んで頷くと、腕から重みが消える。小さな箱を手に乗せ、恐る恐ると言った様子で開けるエリシア。箱の中身を認めると、エリシアは息を呑んだ。
「これ……私に?」
「ああ」
細い指がそっと摘んでいるのは、小ぶりなブラックサファイアが輝くネックレス。翡翠の瞳を輝かせて、僅かに頬を紅潮させたエリシアは食い入るようにそれを見つめる。
「本当は目の色の宝石を渡すべきなのはわかってんだけど、なんていうかそっちの方が似合いそうっていうか……」
贈り物をするときに早口で言い訳を捲し立てるだなんて、格好がつかないにも程がある。数日前、皇室御用達の宝石商を呼びつけ、小一時間ほど悩んだ挙句に選んだのはエリシアの髪の色の宝石だった。「エメラルドじゃなくていいんですか? 目じゃなくて? 目の色じゃなくて?」とリオンがドン引きしていたし、正直翡翠のネックレスを渡すのが自然だとは思う。けれど、シルビオがエリシアのことを考えるとき、真っ先に思い浮かべるのは夜空を閉じ込めたような黒髪だったのだ。
「着けても構わない?」
「ああ」
というか、着けてもらえなければ悲しい。シルビオの言い訳を気にした様子もないエリシアは、手を首の後ろに回す。ネックレスを自分で着けることになれていないのか、なかなか苦戦しているようだ。素直に助けを求めりゃいいのに、と息を吐きながら彼女の背後に回った。
「一人で何やってんだよ」
「あっ」
ネックレスをエリシアの手から攫う。「一人でもできたのに」とかなんとか言っているのは無視だ。後ろに立つと、隣に並んだときよりも体格差を感じる。顕になったうなじは、日の光を浴びたことがないかのように真っ白い。華奢な首筋に吸い付いたら、あっさり跡が残ることだろう。こんな弱くて頼りない女が稀代の魔法使いなわけあるかよ、と偏見にも程があることを決めつけながら細いチェーンをかけた。金具を留めて手を離すと、エリシアはくるりと振り向く。「似合う?」と期待するように微笑むエリシアの首には、シルビオの選んだ宝石が輝く。何にも代え難い眩しさを放っていて、見惚れるには十分だった。
「綺麗だ」
「へっ」
「……あっ」
ぱち、と口を押さえたが、思わず漏れ出てしまった本音を抑えるのには一歩遅い。ぱちくりと目を瞬いたエリシアは、褒められた子供のように満面の笑みを浮かべる。心臓に弓矢か何かを刺されたかのような衝撃を受けるシルビオ。そんなことは露と知らないエリシアは、ずいっと一歩踏み出し、キラキラと翡翠の瞳を煌めかせた。次はエメラルドのブローチを贈ろう、だなんて頭に過ったことが悟られでもしたら、その瞬間にそこのバルコニーから身を投げ出す。物騒な決意を固めつつ、一歩後ずさった。
「今、なんて仰いました? もう一度言ってくださる?」
「さあ、知らね。なんか言ったか?」
「もう、意地悪! 綺麗だって言ってくださったのに」
「聞こえてんなら言わそうとすんじゃねえよ」
ちょっと可愛いからって調子に乗りやがって、と眉間に皺を寄せて睨みつけるけれど、そわそわと嬉しそうなエリシアには今ひとつ効果がない。くるりと踵を返した彼女は、ウキウキと弾んだ様子で姿見の前へ。指先で宝石を弄び、綺麗だと嘆息する様子があんまりにもいじらしくて、後ろから抱きしめてしまおうかと思った。
「殿下は、私の髪の色が素敵だと思ってくださっているのね?」
「……」
「嬉しいわ。私は殿下の髪の色が羨ましいから」
「……そりゃどうも」
どうでもいい、と素っ気ない様子を取り繕ったけれど、うまくできたかわからない。容姿を褒められることは数あれど、ここまで心臓が忙しなく脈打つことはかつてあっただろうか。嬉しそうなエリシアは、相変わらず緩み切った笑顔でシルビオを振り向いた。
「ありがとうございます。一生大事にしますね」
「……別に、たいしたものでもねえし」
モニョモニョと呟くシルビオを、ニコニコとエリシアは見つめる。「もう時間だから行くぞ」と差し出した腕を、過去一番と言っていいぐらい安心し切った様子で掴んだ。いつもの警戒心はどうした、と思ったけれど結局何も尋ねられない。楽しそうな婚約者に水を差すのは野暮というものである。
とりあえず、侍女二人を下がらせたのは英断だったなと心の底から思った。
なんでそんな思春期の息子に対して距離感掴みかねてる父親みたいな感じなんですか、と突っ込みそうになった。玉座の間でなければ、口走っていただろう。腹違いの兄はシルビオに優しいけれど、紛うことなき皇帝陛下。皇弟とはいえ、流石に他の臣下の前でそんな気安い口は聞けない。
「時間を作って会話をし、交流を深めるように心がけています」
押し倒して泣かせてしまった日以降、毎晩雑談するようになったことを思い出しつつ、正直に答える。朝の挨拶すら無視するほどには警戒していたシルビオだが、今では時間が合えば朝食時にも話しかけるほどには絆されている。エリシアの方も穏やかにそれに応じるぐらいには、強気かつ生意気な口調も鳴りを潜めていた。相変わらず正体も本名もわからないままだけれど、それでも出会ったばかりの頃に比べれば打ち解けたと言ってもいいだろう。就寝前のほんのわずかな時間は、エリシアが言うところの「歩み寄ってお互いのことを知る」のに効果的だったらしい。
「そうか、上手くやっているようか」
安堵したように陛下は頷くので、シルビオはほんの少し目を見開く。エリシアともう少し仲良くしたほうがいいのでは、とセレステやリオンに諫言されたことはあれど、陛下に何かを言われたことはない。意外にも気にかけてくれていたらしいことを、シルビオは初めて知った。面映さを隠すように俯いていると、陛下の咳払いの音が聞こえる。
「今度、お前たちの婚約を披露するパーティーを開く」
「パーティー、ですか」
顔を上げると、今度は重々しく頷く陛下が見える。おそらく、単に婚約したことを知らしめるためだけのパーティーではないのだろう。帝国と王国の和平を広く見せつけ、大陸制覇の足がかりにするための準備。キシュ王国の国王夫妻どころか、貴族すらいない状況で披露するのは如何なものか、と思ったけれど。そもそも婚約自体が帝国の独断で進んでいるようなものなのだ、今更だろう。
「わかっていると思うが、くれぐれも王女とは仲睦まじくいるように」
「……善処します」
打ち解けているとはいえ、仲睦まじい様子を見せつけるまでになるのは難しいのでは。そう思ったものの顔には出さない。皇弟としてのシルビオの務めは、皇帝を支えること。無理そうな命令にも、黙して従うのみだ。
*
その日の夜。いつも通り、シルビオはエリシアの部屋を訪れていた。婚約の披露目パーティーがある、と告げるとエリシアはぽかんと口を開ける。「パーティー……」とまるで聞き馴染みのない単語を復唱するかのように呟くと、「帝国のパーティーはどういう感じなの?」と首を傾げた。自分たちが主役のパーティーである認識が薄そうな反応に、なんとなく拍子抜けする。傾いた首をそのまま胸元に引き寄せたい衝動に駆られながら、帝国でのパーティーを思い浮かべる。記憶を辿るうち、自然と眉間に皺が寄った。
「めんどい」
「他には?」
「喧しい」
「ええ……」
ご令嬢方からうんざりするほどの秋波を送られたり、生まれのことを貴族連中からチクチク言われたりすることが主に脳裏に浮かんだシルビオ。淡々と挙げられるネガティブな印象に、エリシアが引くのも無理はない。良くも悪くも注目を浴びやすいシルビオにとって、大勢の人が集まるパーティーに大した思い入れはないのだ。いっそのことセレステ殿に聞いてくれ、と義兄嫁に思いを馳せる。その思考を読み取ったかのように、「ろくな思い出がないのね」とエリシアは苦笑した。同情も憐憫も歓迎できるものではないけれど、労わるように穏やかな笑い方は嫌いではない。
きゅう、と心臓のあたりで音が鳴った気がするのをごまかすようにして、紅茶に口をつける。侍女から紅茶の淹れ方を教わったらしく、いつからか雑談のお供に淹れてくれるようになった。生まれてこの方紅茶を淹れたことがないのか、味は定まらないが毎回飲み干すようにはしている。白湯に風味がついた程度のときもあれば、眠気が覚めるほどに渋いときもあるが、今日は後者だったようだ。
「あっ、だから今日はダンスのレッスンが多かったのかしら」
納得したように呟くエリシア。こうして夜な夜な駄弁るようになってから早数日。意外と話題は尽きないのだけれど、彼女の話題の半分ぐらいは妃教育の内容だ。カーテシーなど、最低限の所作は身につけているエリシアだけれど、知らないこともできないことも多い。紅茶の淹れ方が定まらないのも、その一つ。王女でないからこそろくな教育を受けてこなかったのか、王女だからこそ世間知らずなのか。シルビオにその判断はつかない。偽王女だと決めてかかり、基礎から教育を施すよう教師たちに告げたのが英断だったらしいことはわかった。
「お披露目パーティーってことは、踊るのよね?」
お前絶対パーティーに参加したことないだろ、と言いたくなるような質問に対して、「ああ」と答える。王国のパーティーはどうだったのか、彼女に尋ねれば一体どう返すのだろう。さも参加したことがあるように、小さな顎を逸らして語り始めるのだろうか。聞いてみる前に、「あなたの足を踏まないよう、パーティーまでには上達しておくわね」と意気込み始めたので、質問は後回しにした。拳を握って気合いを入れる様子からは、初対面のときのような口の悪さや不遜さは伺えない。良くも悪くも、幼くあどけなく一生懸命なのが彼女の本質なのだろうか。
「……せいぜい頑張れよ」
「もう。またそういう言い方する」
ぷん、と怒ったように膨らんだ頬を、片手で掴んで空気を抜いてやりたいと思いながら目を逸らす。シルビオが辟易としているのとは対照的に、彼女はパーティーを楽しみにしているらしい。すまし顔を取り繕ってはいるけれど、口元の緩みを必死に隠そうとしているのがバレバレだ。とりあえず、長らく踊っていないダンスの練習をしておくことと、それから靴には硬化魔法を掛けることに決めた。
*
そうして数日が経ち、あっという間にパーティー当日。
普段は無造作におろしたままの前髪を後ろに撫で付け、堅苦しい正装に身を包む。正直行きたくない気持ちでいっぱいなので、今からでも仮病を使って欠席したい。が、そんなことができるはずもないことは、重々承知している。中座するぐらいは許されっかな、と不真面目なことを考えながら、ベルベットの小さな箱を手に隣の部屋をノックした。
「おい、準備できたか?」
「あっ、殿下」
「ちょうどできたところですよ!」
すぐに扉が開いて、興奮した様子の侍女二人が出迎える。早く早くと急かされるので、なんだよと顔を顰めつつ部屋に足を踏み入れ――目を見開いて固まった。
「殿下。もう時間ですか?」
シルビオが入ってきたことに気がつき、振り向くエリシア。いつもはゆるく纏めている黒髪は綺麗に結い上げられ、しゃらしゃらと花の髪飾りが揺れている。胸元が大きく開いた光沢のある深紅のドレスは、華奢なエリシアの魅力を惹き立たせていた。瞼や唇を彩る色はいつもより鮮やかで、華やかさが際立つ。辺りに星が舞っているかのように眩く輝くエリシアから、どうしてだか目が離せない。初めて会ったときのように、動悸が治まらない。シルビオが見惚れているのにも気づかず、「殿下って、正装なさったら本物の王子様みたいですわね」と呑気なことを言っている。
「……本物の皇子なんだよ」
「あら、そうでしたわね」
絞り出すように言葉を返すシルビオとは対照的に、エリシアはどこまでも楽しそうにケラケラと笑う。余程パーティーに浮かれているのか、いつもよりご機嫌だ。ほとんど敵国のような隣国のパーティーに参加させられるというのに、随分と肝が座っているらしい。「それで口の悪さがなければ完璧ですわね」と小生意気なことを言っているけれど、そっくりそのまま返したい。
「お前、まじで可愛いからって調子に乗んなよ」
「? ありがとうございます」
「褒めてねえよ」
背後でひゃあひゃあと騒ぐ侍女とは対照的に、ぽかんとシルビオを見つめるエリシア。柔らかそうな頬を摘んでやりたくなったが、化粧が崩れてはいけないので我慢した。眉間に皺を寄せて耐えるシルビオを他所にエリシアは、「変じゃないかしら」と侍女の二人に確認している。
「変だなんてそんな!」
「お美しいですわ」
口を揃えて主君を褒め称える二人。背中に「お前もとっとと褒めろ」と言いたげな視線が突き刺さっているのは、きっと気のせいではない。仮にも婚約者が着飾っているのだ、褒め言葉の一つや二つ掛けなければならないことは、シルビオだってわかっている。あの無口で堅物に見える兄でさえ、婚約者のセレステが着飾れば歯の浮くような台詞で褒めちぎっているのだ。シルビオが同じことをしないわけにはいかない。
「……悪いが、席を外してくれるか?」
振り向いて、侍女たちにそう告げる。二人は顔を見合わせて目を丸くしたが、やがて無言でお辞儀をして部屋を出ていった。揶揄うような言葉もかけず、職務と主君に忠実な侍女たちでよかったとこっそり息を吐く。後に残されたのはシルビオとエリシアだけ。二人きりには慣れているはずなのに、緊張してしまうのはどうしてだろう。せっかく侍女を下がらせたのに、口が乾いてうまく言葉が出てこない。気まずい沈黙に包まれかけたとき、口火を切ったのはエリシアだった。
「何か、ご用でした?」
先ほどまでのご機嫌な様子から一転。遠慮がちに問いかける声には、戸惑いが含まれている。それはそうだろう。婚約者が侍女を下がらせたきり口を開こうとしないのだから、困惑しても仕方がない。似合っている、綺麗だ、美しい。ありふれた褒め言葉を口にするだけ、たったそれだけのことなのに。どうしてここまで緊張するのだろうか。
「……これ」
逡巡した末に、どうにか絞り出したのはたった一言だった。満足に褒めることもできないまま、ずっと握りしめていたベルベットの小さな箱を差し出す。突き出した腕は鉛のように重たい。ぱち、と目を瞬くエリシアはシルビオを見上げ、「くださるの?」と尋ねた。そうでないなら誰に渡すって言うんだよ、と八つ当たりにも似た悪態を飲み込んで頷くと、腕から重みが消える。小さな箱を手に乗せ、恐る恐ると言った様子で開けるエリシア。箱の中身を認めると、エリシアは息を呑んだ。
「これ……私に?」
「ああ」
細い指がそっと摘んでいるのは、小ぶりなブラックサファイアが輝くネックレス。翡翠の瞳を輝かせて、僅かに頬を紅潮させたエリシアは食い入るようにそれを見つめる。
「本当は目の色の宝石を渡すべきなのはわかってんだけど、なんていうかそっちの方が似合いそうっていうか……」
贈り物をするときに早口で言い訳を捲し立てるだなんて、格好がつかないにも程がある。数日前、皇室御用達の宝石商を呼びつけ、小一時間ほど悩んだ挙句に選んだのはエリシアの髪の色の宝石だった。「エメラルドじゃなくていいんですか? 目じゃなくて? 目の色じゃなくて?」とリオンがドン引きしていたし、正直翡翠のネックレスを渡すのが自然だとは思う。けれど、シルビオがエリシアのことを考えるとき、真っ先に思い浮かべるのは夜空を閉じ込めたような黒髪だったのだ。
「着けても構わない?」
「ああ」
というか、着けてもらえなければ悲しい。シルビオの言い訳を気にした様子もないエリシアは、手を首の後ろに回す。ネックレスを自分で着けることになれていないのか、なかなか苦戦しているようだ。素直に助けを求めりゃいいのに、と息を吐きながら彼女の背後に回った。
「一人で何やってんだよ」
「あっ」
ネックレスをエリシアの手から攫う。「一人でもできたのに」とかなんとか言っているのは無視だ。後ろに立つと、隣に並んだときよりも体格差を感じる。顕になったうなじは、日の光を浴びたことがないかのように真っ白い。華奢な首筋に吸い付いたら、あっさり跡が残ることだろう。こんな弱くて頼りない女が稀代の魔法使いなわけあるかよ、と偏見にも程があることを決めつけながら細いチェーンをかけた。金具を留めて手を離すと、エリシアはくるりと振り向く。「似合う?」と期待するように微笑むエリシアの首には、シルビオの選んだ宝石が輝く。何にも代え難い眩しさを放っていて、見惚れるには十分だった。
「綺麗だ」
「へっ」
「……あっ」
ぱち、と口を押さえたが、思わず漏れ出てしまった本音を抑えるのには一歩遅い。ぱちくりと目を瞬いたエリシアは、褒められた子供のように満面の笑みを浮かべる。心臓に弓矢か何かを刺されたかのような衝撃を受けるシルビオ。そんなことは露と知らないエリシアは、ずいっと一歩踏み出し、キラキラと翡翠の瞳を煌めかせた。次はエメラルドのブローチを贈ろう、だなんて頭に過ったことが悟られでもしたら、その瞬間にそこのバルコニーから身を投げ出す。物騒な決意を固めつつ、一歩後ずさった。
「今、なんて仰いました? もう一度言ってくださる?」
「さあ、知らね。なんか言ったか?」
「もう、意地悪! 綺麗だって言ってくださったのに」
「聞こえてんなら言わそうとすんじゃねえよ」
ちょっと可愛いからって調子に乗りやがって、と眉間に皺を寄せて睨みつけるけれど、そわそわと嬉しそうなエリシアには今ひとつ効果がない。くるりと踵を返した彼女は、ウキウキと弾んだ様子で姿見の前へ。指先で宝石を弄び、綺麗だと嘆息する様子があんまりにもいじらしくて、後ろから抱きしめてしまおうかと思った。
「殿下は、私の髪の色が素敵だと思ってくださっているのね?」
「……」
「嬉しいわ。私は殿下の髪の色が羨ましいから」
「……そりゃどうも」
どうでもいい、と素っ気ない様子を取り繕ったけれど、うまくできたかわからない。容姿を褒められることは数あれど、ここまで心臓が忙しなく脈打つことはかつてあっただろうか。嬉しそうなエリシアは、相変わらず緩み切った笑顔でシルビオを振り向いた。
「ありがとうございます。一生大事にしますね」
「……別に、たいしたものでもねえし」
モニョモニョと呟くシルビオを、ニコニコとエリシアは見つめる。「もう時間だから行くぞ」と差し出した腕を、過去一番と言っていいぐらい安心し切った様子で掴んだ。いつもの警戒心はどうした、と思ったけれど結局何も尋ねられない。楽しそうな婚約者に水を差すのは野暮というものである。
とりあえず、侍女二人を下がらせたのは英断だったなと心の底から思った。