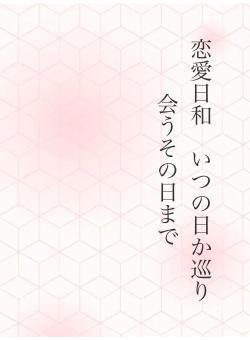「‥‥この子は‥ッ‥あの時の
子猫ですか?」
『ああ、そうだよ。弱ってたが、
病気もなく元気に育ってる。』
捨てられてしまったと思っていた
小さかった猫の姿に、目に涙が浮かび、
体を起こした私の膝の上に乗ってきた
子猫がその場で背中を丸めたので
そっと抱きしめた。
「‥ッ‥良かっ‥た。良かったね‥。」
もしかしたら旦那様は外に捨ててしまったのかもしれないと思ったけれど、使用人を気にかけてくれる優しさに、そんな事を疑ってしまっていた自分を責めたい。
『お前は心が優しい子だな‥‥。
お金など必要ない。勿論ここを
辞めずともずっと居てくれたら
いいんだよ。スズも喜ぶだろう。』
スズ?
涙が流れる私の頬に旦那様の指が触れると、緊張から体が固まってしまい、
胸が締め付けられた。
「‥旦那様‥‥」
『フッ‥‥‥鈴子が見つけたからスズ
と名付けた。お前のように心が白く
綺麗でそっくりだろう?』
ドクン
子猫ですか?」
『ああ、そうだよ。弱ってたが、
病気もなく元気に育ってる。』
捨てられてしまったと思っていた
小さかった猫の姿に、目に涙が浮かび、
体を起こした私の膝の上に乗ってきた
子猫がその場で背中を丸めたので
そっと抱きしめた。
「‥ッ‥良かっ‥た。良かったね‥。」
もしかしたら旦那様は外に捨ててしまったのかもしれないと思ったけれど、使用人を気にかけてくれる優しさに、そんな事を疑ってしまっていた自分を責めたい。
『お前は心が優しい子だな‥‥。
お金など必要ない。勿論ここを
辞めずともずっと居てくれたら
いいんだよ。スズも喜ぶだろう。』
スズ?
涙が流れる私の頬に旦那様の指が触れると、緊張から体が固まってしまい、
胸が締め付けられた。
「‥旦那様‥‥」
『フッ‥‥‥鈴子が見つけたからスズ
と名付けた。お前のように心が白く
綺麗でそっくりだろう?』
ドクン