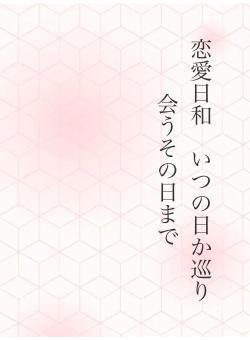そこで仲良くなったのが、同じ使用人
として働いていた1つ歳上のハルさん
だった。
誠実に主人のお役に立とうという彼女の姿はすぐに私の憧れになり、ツラい
事があっても何とか頑張れていた。
伽耶は身体が治らず、お屋敷に置いて貰えるわけもなく療養所に行く事になり、
働いたお金の殆どは伽耶の為に仕送り
していたが、私にとってただ1人の大切な家族の為だから頑張れたのだ。
そんなある日、いつものように庭掃除をしていたら、茂みの中から子猫の鳴き声が聞こえ、仕事中だったとはいえ気になり茂みを掻き分けた。
「‥‥あんたこんな所で寒いだろうに。
母猫はいないの?小さいのに
可哀想に‥‥。
」
ミーミーと鳴く真っ白な小さな子猫の
頬を指で撫でようとすると、いきなり
私の手を背後から掴まれた。
『‥‥情が湧く。飼えないのなら
手を出すのはやめなさい。』
えっ?
それが、私が旦那様である圭吾さん
と初めて出会った日だった‥‥
として働いていた1つ歳上のハルさん
だった。
誠実に主人のお役に立とうという彼女の姿はすぐに私の憧れになり、ツラい
事があっても何とか頑張れていた。
伽耶は身体が治らず、お屋敷に置いて貰えるわけもなく療養所に行く事になり、
働いたお金の殆どは伽耶の為に仕送り
していたが、私にとってただ1人の大切な家族の為だから頑張れたのだ。
そんなある日、いつものように庭掃除をしていたら、茂みの中から子猫の鳴き声が聞こえ、仕事中だったとはいえ気になり茂みを掻き分けた。
「‥‥あんたこんな所で寒いだろうに。
母猫はいないの?小さいのに
可哀想に‥‥。
」
ミーミーと鳴く真っ白な小さな子猫の
頬を指で撫でようとすると、いきなり
私の手を背後から掴まれた。
『‥‥情が湧く。飼えないのなら
手を出すのはやめなさい。』
えっ?
それが、私が旦那様である圭吾さん
と初めて出会った日だった‥‥