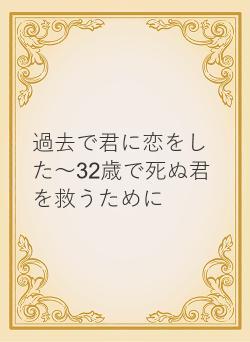リディアは、部屋中を見回した。
本当に、3年前に戻ったのか。
確かめなければ。
リディアは、机の引き出しを開けた。
中には、羊皮紙の束がある。
リディアは、その中から一枚を取り出した。
手紙だ。
アルヴィンからの、婚約通知の手紙。
リディアは、日付を見た。
「王暦1215年、3月15日」
リディアは、息を呑んだ。
3年前だ。
本当に、3年前に戻っている。
リディアは、手紙を机に戻した。
そして、壁を見た。
壁には、小さな暦がかけられている。
リディアは、それを見た。
「王暦1215年、3月15日」
今日の日付が、印をつけられている。
リディアは、震えた。
今日は、婚約発表式典の日だ。
アルヴィンとの、婚約が正式に発表される日。
リディアは、全てを思い出した。
この日から、全てが始まった。
セレナとの、出会い。
アルヴィンの、冷淡な態度。
国王の、病。
そして、追放。
リディアは、拳を握った。
手が、震えている。
前世の記憶。
製薬会社での、孤独。
薬害事件の、告発。
誰も信じてくれなかった、絶望。
そして、今世の記憶。
3年後の、記憶。
セレナの、陰謀。
国王の、毒殺。
追放され、毒を飲まされ、荒野で死んだ記憶。
全て、鮮明に残っている。
リディアは、頭を抱えた。
二つの人生の記憶が、頭の中で混在している。
だが、リディアは混乱していなかった。
むしろ、冷静だった。
これは、チャンスだ。
リディアは、全てを知っている。
何が起こるのか。
誰が敵なのか。
どうすれば、勝てるのか。
リディアは、深呼吸をした。
落ち着け。
今度こそ、変える。
全てを。
その時。
ノックの音が、聞こえた。
リディアは、扉の方を見た。
「リディア様、起きていらっしゃいますか?」
侍女の声だ。
リディアは、扉に近づいた。
「はい、起きています」
「式典の準備を、始めなければなりません。お支度を手伝わせてください」
リディアは、扉を見つめた。
式典。
婚約発表式典。
リディアは、唇を噛んだ。
あの式典で、リディアはセレナと初めて会った。
そして、カイル侯爵とも。
リディアは、決意した。
今度は、違う。
今度は、リディアが主導権を握る。
リディアは、扉を開けた。
侍女が、にこやかに立っている。
「おはようございます、リディア様」
「おはようございます」
リディアは、微笑んだ。
侍女は、部屋に入ってきた。
「さあ、お支度を。今日は大事な日ですから」
侍女は、クローゼットを開けた。
中には、ドレスがかけられている。
淡い緑色の、地味なドレス。
リディアは、それを見た。
あのドレスだ。
リディアが、式典で着たドレス。
地味で、目立たない。
まるで、リディアの存在そのものを象徴しているかのような。
侍女が、ドレスを取り出した。
「さあ、リディア様、こちらへ」
リディアは、侍女の方へ歩いた。
だが、心の中で、リディアは戦略を練っていた。
今度は、この地味さを武器にする。
リディアは、目立たないことで、セレナの警戒を解く。
そして、裏で動く。
証拠を集める。
味方を作る。
リディアは、鏡の前に立った。
侍女が、ドレスを着せてくれる。
リディアは、鏡の中の自分を見た。
地味なドレス。
栗色の、艶のない髪。
灰色の、疲れた瞳。
だが、リディアは微笑んだ。
この弱々しい姿も、今回は武器にする。
誰も、リディアを警戒しない。
誰も、リディアを脅威とは思わない。
だからこそ、リディアは自由に動ける。
リディアは、侍女に言った。
「ありがとうございます。後は、自分でできます」
「本当ですか? 髪は——」
「大丈夫です。簡単にまとめるだけで十分です」
侍女は、少し不安そうだったが、頷いた。
「わかりました。では、式典の開始時刻までに、大広間へお越しください」
「はい」
侍女は、部屋を出て行った。
リディアは、一人残された。
鏡の前で、リディアは自分の髪を簡単にまとめた。
地味に。
目立たないように。
リディアは、鏡の中の自分を見つめた。
そして、小さく呟いた。
「今度こそ、変える。全てを」
リディアの目に、決意の光が宿った。
大広間は、華やかだった。
天井から、巨大なシャンデリアが吊り下げられている。
壁には、豪華な絨毯が飾られている。
そして、貴族たちが、大広間中に集まっていた。
男性は、礼服を着ている。
女性は、豪華なドレスを纏っている。
宝石が、きらめいている。
笑い声が、響いている。
リディアは、大広間の入口に立っていた。
地味な、緑色のドレス。
簡素にまとめた、栗色の髪。
リディアは、周囲を見回した。
貴族たちが、リディアを見た。
「ああ、あれがリディア・アーシェンフェルトか」
「第3王子の婚約者だそうだ」
「地味だな」
「政略結婚の余り物だろう」
囁き声が、リディアの耳に届く。
リディアは、唇を噛んだ。
前回も、同じだった。
貴族たちは、リディアを軽蔑していた。
だが、今回は違う。
リディアは、この軽蔑を利用する。
リディアは、俯いて歩き始めた。
従順で、地味な令嬢。
それが、リディアの演じる役だ。
壇上へ、向かう。
壇上には、すでにアルヴィンが立っていた。
金髪が、シャンデリアの光を受けて輝いている。
整った顔立ち。
貴族たちは、アルヴィンを見て微笑んでいる。
リディアは、壇上に上がった。
アルヴィンは、リディアを一瞥した。
だが、すぐに視線を逸らした。
無関心。
リディアは、アルヴィンの隣に立った。
だが、一歩下がった位置。
まるで、アルヴィンの影に隠れるかのように。
貴族たちが、ざわめいた。
「やはり、目立たない娘だな」
「第3王子には、もったいない」
リディアは、俯いたまま、何も言わなかった。
司会者が、前に出た。
「皆様、本日はお集まりいただき、ありがとうございます」
司会者の声が、大広間に響く。
「ただいまより、第3王子アルヴィン・エルフィード殿下と、リディア・アーシェンフェルト様の、婚約発表式典を執り行います」
貴族たちが、拍手をした。
だが、その拍手は、形式的だ。
リディアは、顔を上げた。
貴族たちを見る。
そして、視線を動かした。
壇上の近く、前列に座っている女性を見つけた。
セレナ・ヴィオレット。
金髪が、美しく波打っている。
碧眼が、輝いている。
豪華なドレスを着て、優雅に微笑んでいる。
セレナは、壇上のアルヴィンを見ている。
その目には、野心の色が浮かんでいる。
リディアは、セレナを見つめた。
お前の手口は、全て知っている。
お前が、国王を毒殺しようとしていることも。
お前が、アルヴィンを操ろうとしていることも。
お前が、私を追放しようとすることも。
全て、知っている。
リディアは、心の中で呟いた。
だが、顔には出さなかった。
リディアは、再び俯いた。
従順で、地味な令嬢。
誰も、リディアを警戒しない。
誰も、リディアを脅威とは思わない。
それでいい。
司会者が、式典の言葉を述べている。
アルヴィンが、形式的に頷いている。
リディアも、形式的に頷いた。
式典は、滞りなく進んだ。
そして、終わった。
貴族たちが、拍手をした。
リディアとアルヴィンは、壇上を降りた。
貴族たちが、アルヴィンに近づいてくる。
「おめでとうございます、殿下」
「素晴らしい式典でした」
アルヴィンは、社交的に微笑んでいる。
だが、リディアには目もくれない。
リディアは、一人、壇上の端に立っていた。
誰も、リディアに話しかけてこない。
リディアは、それでいいと思った。
リディアは、静かに大広間を出た。
廊下を歩く。
リディアは、ある場所へ向かっていた。
王宮図書館。
リディアは、情報を集めなければならない。
セレナの秘薬について。
国王の病について。
そして、カイル侯爵について。
リディアは、全てを知っている。
だが、証拠がない。
証拠を集めなければ、誰も信じてくれない。
リディアは、図書館の扉を開けた。
中は、静かだ。
本棚が、壁一面に並んでいる。
リディアは、薬学の書棚へ向かった。
そして、一冊の本を手に取った。
「魔力薬学概論」
リディアは、本を開いた。
ページをめくる。
依存性薬物について、記されている箇所を探す。
リディアは、心の中で呟いた。
まずは、情報収集から。
そして、証拠を掴む。
セレナを、止める。
国王を、救う。
リディアは、本を読み始めた。
静かな図書館で、一人。
だが、リディアの心は、燃えていた。
リディアは、図書館の奥、薬学書の棚の前に立っていた。
本を次々と取り出し、ページをめくる。
依存性薬物。
魔力過多による副作用。
解毒法。
リディアは、必要な情報を探していた。
前世の知識と、この世界の薬学を照合する。
セレナの秘薬を暴くための、証拠を掴む。
リディアは、一冊の分厚い本を手に取った。
「魔力薬学と神経系疾患」
リディアは、本を開こうとした。
その時。
背後から、声が聞こえた。
「その本を、探していた」
冷たい声。
低い、男性の声。
リディアは、息を呑んだ。
振り返る。
そこに、一人の男が立っていた。
リディアは、目を見開いた。
銀髪。
長い、銀色の髪が、肩まで垂れている。
隻眼。
右目には、黒い眼帯。
左目だけが、リディアを見つめている。
鋭い、灰色の瞳。
長身。
黒い礼服を着ている。
傷跡。
顔の左側に、古い傷跡が走っている。
リディアは、その男を見つめた。
カイル・ヴァレンティス侯爵。
辺境を治める、冷酷な侯爵。
リディアは、前回の人生で彼と出会った。
彼の娘、エリスを救った。
そして、辺境に匿われた。
リディアは、心臓が高鳴るのを感じた。
カイルは、リディアを見下ろしている。
「お前が、第3王子の婚約者か」
カイルの声は、感情がない。
リディアは、頷いた。
「はい。リディア・アーシェンフェルトです」
カイルは、リディアの手元を見た。
「薬学に興味があるのは、珍しい」
リディアは、本を抱きしめた。
「はい。私は、薬学を学んでいます」
カイルは、値踏みするような視線でリディアを見た。
「お前のような、地味な令嬢が、薬学を?」
リディアは、唇を噛んだ。
地味。
やはり、そう見られている。
だが、それでいい。
リディアは、冷静に答えた。
「はい。人を救いたいと思っています」
カイルは、眉をひそめた。
「人を救う……?」
「はい」
リディアは、カイルの目を見た。
前世の記憶が、蘇る。
カイルの娘、エリス。
8年間、誰も治せなかった病。
魔力過多による、自己免疫暴走。
リディアは、それを治した。
そして、カイルは、リディアを信じた。
リディアは、心の中で確信した。
彼の娘を、救える。
今度も、必ず。
リディアは、慎重に言葉を選んだ。
「侯爵様は、何の本を探していらっしゃったのですか?」
カイルは、少し黙った。
そして、冷たく答えた。
「娘の、病についてだ」
リディアは、息を呑んだ。
やはり。
リディアは、静かに言った。
「お嬢様は、お加減が悪いのですか?」
カイルの目が、鋭くなった。
「何故、お前がそれを知っている」
「いえ、ただ……侯爵様がこの本を探していらっしゃるということは、そういうことかと」
カイルは、リディアを睨んだ。
だが、リディアは視線を逸らさなかった。
カイルは、ため息をついた。
「娘は、8年間病に臥せっている。どの薬師も、治せない」
リディアは、拳を握った。
これだ。
これが、リディアのチャンスだ。
リディアは、勇気を出して言った。
「私に、任せていただけますか?」
カイルは、驚いた顔をした。
「何?」
「お嬢様の病を、私に診させていただけませんか」
カイルは、リディアを見つめた。
そして、冷たく笑った。
「お前、正気か? 8年間、どの薬師も治せなかった病を、お前のような小娘が治せると?」
リディアは、震えた。
だが、引かなかった。
「はい。私には、方法があります」
カイルは、眉をひそめた。
「方法……?」
「はい。詳しくは、お嬢様を診察させていただいてからでないと、お話しできませんが」
カイルは、しばらくリディアを見つめていた。
その目は、懐疑的だ。
だが、同時に、わずかな希望の色も浮かんでいる。
カイルは、懐から名刺を取り出した。
「式典後、私の屋敷へ来い」
カイルは、名刺をリディアに渡した。
「だが、もし娘を治せなければ、お前の命はない」
リディアは、名刺を受け取った。
「わかりました」
カイルは、リディアを一瞥した。
そして、踵を返し、図書館を出て行った。
リディアは、一人残された。
リディアは、名刺を見た。
「カイル・ヴァレンティス侯爵」
住所が、記されている。
リディアは、名刺を握りしめた。
これが、私の新しい人生の始まり。
エリスを救う。
カイルの信頼を得る。
そして、辺境へ。
リディアは、心の中で誓った。
今度こそ、成功させる。
リディアは、名刺を懐にしまった。
そして、再び本を手に取った。
準備をしなければ。
エリスを救うための、知識を。
リディアは、本を読み始めた。
静かな図書館で、一人。
だが、リディアの心は、希望に満ちていた。
本当に、3年前に戻ったのか。
確かめなければ。
リディアは、机の引き出しを開けた。
中には、羊皮紙の束がある。
リディアは、その中から一枚を取り出した。
手紙だ。
アルヴィンからの、婚約通知の手紙。
リディアは、日付を見た。
「王暦1215年、3月15日」
リディアは、息を呑んだ。
3年前だ。
本当に、3年前に戻っている。
リディアは、手紙を机に戻した。
そして、壁を見た。
壁には、小さな暦がかけられている。
リディアは、それを見た。
「王暦1215年、3月15日」
今日の日付が、印をつけられている。
リディアは、震えた。
今日は、婚約発表式典の日だ。
アルヴィンとの、婚約が正式に発表される日。
リディアは、全てを思い出した。
この日から、全てが始まった。
セレナとの、出会い。
アルヴィンの、冷淡な態度。
国王の、病。
そして、追放。
リディアは、拳を握った。
手が、震えている。
前世の記憶。
製薬会社での、孤独。
薬害事件の、告発。
誰も信じてくれなかった、絶望。
そして、今世の記憶。
3年後の、記憶。
セレナの、陰謀。
国王の、毒殺。
追放され、毒を飲まされ、荒野で死んだ記憶。
全て、鮮明に残っている。
リディアは、頭を抱えた。
二つの人生の記憶が、頭の中で混在している。
だが、リディアは混乱していなかった。
むしろ、冷静だった。
これは、チャンスだ。
リディアは、全てを知っている。
何が起こるのか。
誰が敵なのか。
どうすれば、勝てるのか。
リディアは、深呼吸をした。
落ち着け。
今度こそ、変える。
全てを。
その時。
ノックの音が、聞こえた。
リディアは、扉の方を見た。
「リディア様、起きていらっしゃいますか?」
侍女の声だ。
リディアは、扉に近づいた。
「はい、起きています」
「式典の準備を、始めなければなりません。お支度を手伝わせてください」
リディアは、扉を見つめた。
式典。
婚約発表式典。
リディアは、唇を噛んだ。
あの式典で、リディアはセレナと初めて会った。
そして、カイル侯爵とも。
リディアは、決意した。
今度は、違う。
今度は、リディアが主導権を握る。
リディアは、扉を開けた。
侍女が、にこやかに立っている。
「おはようございます、リディア様」
「おはようございます」
リディアは、微笑んだ。
侍女は、部屋に入ってきた。
「さあ、お支度を。今日は大事な日ですから」
侍女は、クローゼットを開けた。
中には、ドレスがかけられている。
淡い緑色の、地味なドレス。
リディアは、それを見た。
あのドレスだ。
リディアが、式典で着たドレス。
地味で、目立たない。
まるで、リディアの存在そのものを象徴しているかのような。
侍女が、ドレスを取り出した。
「さあ、リディア様、こちらへ」
リディアは、侍女の方へ歩いた。
だが、心の中で、リディアは戦略を練っていた。
今度は、この地味さを武器にする。
リディアは、目立たないことで、セレナの警戒を解く。
そして、裏で動く。
証拠を集める。
味方を作る。
リディアは、鏡の前に立った。
侍女が、ドレスを着せてくれる。
リディアは、鏡の中の自分を見た。
地味なドレス。
栗色の、艶のない髪。
灰色の、疲れた瞳。
だが、リディアは微笑んだ。
この弱々しい姿も、今回は武器にする。
誰も、リディアを警戒しない。
誰も、リディアを脅威とは思わない。
だからこそ、リディアは自由に動ける。
リディアは、侍女に言った。
「ありがとうございます。後は、自分でできます」
「本当ですか? 髪は——」
「大丈夫です。簡単にまとめるだけで十分です」
侍女は、少し不安そうだったが、頷いた。
「わかりました。では、式典の開始時刻までに、大広間へお越しください」
「はい」
侍女は、部屋を出て行った。
リディアは、一人残された。
鏡の前で、リディアは自分の髪を簡単にまとめた。
地味に。
目立たないように。
リディアは、鏡の中の自分を見つめた。
そして、小さく呟いた。
「今度こそ、変える。全てを」
リディアの目に、決意の光が宿った。
大広間は、華やかだった。
天井から、巨大なシャンデリアが吊り下げられている。
壁には、豪華な絨毯が飾られている。
そして、貴族たちが、大広間中に集まっていた。
男性は、礼服を着ている。
女性は、豪華なドレスを纏っている。
宝石が、きらめいている。
笑い声が、響いている。
リディアは、大広間の入口に立っていた。
地味な、緑色のドレス。
簡素にまとめた、栗色の髪。
リディアは、周囲を見回した。
貴族たちが、リディアを見た。
「ああ、あれがリディア・アーシェンフェルトか」
「第3王子の婚約者だそうだ」
「地味だな」
「政略結婚の余り物だろう」
囁き声が、リディアの耳に届く。
リディアは、唇を噛んだ。
前回も、同じだった。
貴族たちは、リディアを軽蔑していた。
だが、今回は違う。
リディアは、この軽蔑を利用する。
リディアは、俯いて歩き始めた。
従順で、地味な令嬢。
それが、リディアの演じる役だ。
壇上へ、向かう。
壇上には、すでにアルヴィンが立っていた。
金髪が、シャンデリアの光を受けて輝いている。
整った顔立ち。
貴族たちは、アルヴィンを見て微笑んでいる。
リディアは、壇上に上がった。
アルヴィンは、リディアを一瞥した。
だが、すぐに視線を逸らした。
無関心。
リディアは、アルヴィンの隣に立った。
だが、一歩下がった位置。
まるで、アルヴィンの影に隠れるかのように。
貴族たちが、ざわめいた。
「やはり、目立たない娘だな」
「第3王子には、もったいない」
リディアは、俯いたまま、何も言わなかった。
司会者が、前に出た。
「皆様、本日はお集まりいただき、ありがとうございます」
司会者の声が、大広間に響く。
「ただいまより、第3王子アルヴィン・エルフィード殿下と、リディア・アーシェンフェルト様の、婚約発表式典を執り行います」
貴族たちが、拍手をした。
だが、その拍手は、形式的だ。
リディアは、顔を上げた。
貴族たちを見る。
そして、視線を動かした。
壇上の近く、前列に座っている女性を見つけた。
セレナ・ヴィオレット。
金髪が、美しく波打っている。
碧眼が、輝いている。
豪華なドレスを着て、優雅に微笑んでいる。
セレナは、壇上のアルヴィンを見ている。
その目には、野心の色が浮かんでいる。
リディアは、セレナを見つめた。
お前の手口は、全て知っている。
お前が、国王を毒殺しようとしていることも。
お前が、アルヴィンを操ろうとしていることも。
お前が、私を追放しようとすることも。
全て、知っている。
リディアは、心の中で呟いた。
だが、顔には出さなかった。
リディアは、再び俯いた。
従順で、地味な令嬢。
誰も、リディアを警戒しない。
誰も、リディアを脅威とは思わない。
それでいい。
司会者が、式典の言葉を述べている。
アルヴィンが、形式的に頷いている。
リディアも、形式的に頷いた。
式典は、滞りなく進んだ。
そして、終わった。
貴族たちが、拍手をした。
リディアとアルヴィンは、壇上を降りた。
貴族たちが、アルヴィンに近づいてくる。
「おめでとうございます、殿下」
「素晴らしい式典でした」
アルヴィンは、社交的に微笑んでいる。
だが、リディアには目もくれない。
リディアは、一人、壇上の端に立っていた。
誰も、リディアに話しかけてこない。
リディアは、それでいいと思った。
リディアは、静かに大広間を出た。
廊下を歩く。
リディアは、ある場所へ向かっていた。
王宮図書館。
リディアは、情報を集めなければならない。
セレナの秘薬について。
国王の病について。
そして、カイル侯爵について。
リディアは、全てを知っている。
だが、証拠がない。
証拠を集めなければ、誰も信じてくれない。
リディアは、図書館の扉を開けた。
中は、静かだ。
本棚が、壁一面に並んでいる。
リディアは、薬学の書棚へ向かった。
そして、一冊の本を手に取った。
「魔力薬学概論」
リディアは、本を開いた。
ページをめくる。
依存性薬物について、記されている箇所を探す。
リディアは、心の中で呟いた。
まずは、情報収集から。
そして、証拠を掴む。
セレナを、止める。
国王を、救う。
リディアは、本を読み始めた。
静かな図書館で、一人。
だが、リディアの心は、燃えていた。
リディアは、図書館の奥、薬学書の棚の前に立っていた。
本を次々と取り出し、ページをめくる。
依存性薬物。
魔力過多による副作用。
解毒法。
リディアは、必要な情報を探していた。
前世の知識と、この世界の薬学を照合する。
セレナの秘薬を暴くための、証拠を掴む。
リディアは、一冊の分厚い本を手に取った。
「魔力薬学と神経系疾患」
リディアは、本を開こうとした。
その時。
背後から、声が聞こえた。
「その本を、探していた」
冷たい声。
低い、男性の声。
リディアは、息を呑んだ。
振り返る。
そこに、一人の男が立っていた。
リディアは、目を見開いた。
銀髪。
長い、銀色の髪が、肩まで垂れている。
隻眼。
右目には、黒い眼帯。
左目だけが、リディアを見つめている。
鋭い、灰色の瞳。
長身。
黒い礼服を着ている。
傷跡。
顔の左側に、古い傷跡が走っている。
リディアは、その男を見つめた。
カイル・ヴァレンティス侯爵。
辺境を治める、冷酷な侯爵。
リディアは、前回の人生で彼と出会った。
彼の娘、エリスを救った。
そして、辺境に匿われた。
リディアは、心臓が高鳴るのを感じた。
カイルは、リディアを見下ろしている。
「お前が、第3王子の婚約者か」
カイルの声は、感情がない。
リディアは、頷いた。
「はい。リディア・アーシェンフェルトです」
カイルは、リディアの手元を見た。
「薬学に興味があるのは、珍しい」
リディアは、本を抱きしめた。
「はい。私は、薬学を学んでいます」
カイルは、値踏みするような視線でリディアを見た。
「お前のような、地味な令嬢が、薬学を?」
リディアは、唇を噛んだ。
地味。
やはり、そう見られている。
だが、それでいい。
リディアは、冷静に答えた。
「はい。人を救いたいと思っています」
カイルは、眉をひそめた。
「人を救う……?」
「はい」
リディアは、カイルの目を見た。
前世の記憶が、蘇る。
カイルの娘、エリス。
8年間、誰も治せなかった病。
魔力過多による、自己免疫暴走。
リディアは、それを治した。
そして、カイルは、リディアを信じた。
リディアは、心の中で確信した。
彼の娘を、救える。
今度も、必ず。
リディアは、慎重に言葉を選んだ。
「侯爵様は、何の本を探していらっしゃったのですか?」
カイルは、少し黙った。
そして、冷たく答えた。
「娘の、病についてだ」
リディアは、息を呑んだ。
やはり。
リディアは、静かに言った。
「お嬢様は、お加減が悪いのですか?」
カイルの目が、鋭くなった。
「何故、お前がそれを知っている」
「いえ、ただ……侯爵様がこの本を探していらっしゃるということは、そういうことかと」
カイルは、リディアを睨んだ。
だが、リディアは視線を逸らさなかった。
カイルは、ため息をついた。
「娘は、8年間病に臥せっている。どの薬師も、治せない」
リディアは、拳を握った。
これだ。
これが、リディアのチャンスだ。
リディアは、勇気を出して言った。
「私に、任せていただけますか?」
カイルは、驚いた顔をした。
「何?」
「お嬢様の病を、私に診させていただけませんか」
カイルは、リディアを見つめた。
そして、冷たく笑った。
「お前、正気か? 8年間、どの薬師も治せなかった病を、お前のような小娘が治せると?」
リディアは、震えた。
だが、引かなかった。
「はい。私には、方法があります」
カイルは、眉をひそめた。
「方法……?」
「はい。詳しくは、お嬢様を診察させていただいてからでないと、お話しできませんが」
カイルは、しばらくリディアを見つめていた。
その目は、懐疑的だ。
だが、同時に、わずかな希望の色も浮かんでいる。
カイルは、懐から名刺を取り出した。
「式典後、私の屋敷へ来い」
カイルは、名刺をリディアに渡した。
「だが、もし娘を治せなければ、お前の命はない」
リディアは、名刺を受け取った。
「わかりました」
カイルは、リディアを一瞥した。
そして、踵を返し、図書館を出て行った。
リディアは、一人残された。
リディアは、名刺を見た。
「カイル・ヴァレンティス侯爵」
住所が、記されている。
リディアは、名刺を握りしめた。
これが、私の新しい人生の始まり。
エリスを救う。
カイルの信頼を得る。
そして、辺境へ。
リディアは、心の中で誓った。
今度こそ、成功させる。
リディアは、名刺を懐にしまった。
そして、再び本を手に取った。
準備をしなければ。
エリスを救うための、知識を。
リディアは、本を読み始めた。
静かな図書館で、一人。
だが、リディアの心は、希望に満ちていた。