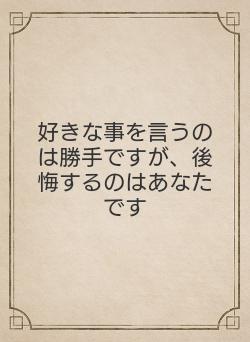婚約が決まった数日後、リリスの元にディルが訪ねてきた。午後から非番だったので、現在のミフォンたちの状況を彼女に伝えにきてくれたのだ。
ミフォンの両親は長年、マヤを虐げ、貴族であるコレットに詐欺行為を働いたとして、炭鉱で働くことを命じられた。期間は今のところは無期限で、更生すれば刑期が短くなる。
コレットから巻き上げたお金や、他人から物や金銭を奪うことで生活していた彼らは、働いたことがなかった。そのため、すぐに音を上げたが、働けない理由がないのに働かない場合は、食事を出してもらうことができず、現在は文句を言いながらも働いている。反省している様子がまったく見られないので、彼らは死ぬまで働かされることになるだろうというのが周りの考えだった。
「ミフォンの両親だと納得できる人たちですね」
「で、元レーヌ男爵令嬢の件なんだが」
先日、辺境伯が話してくれたのは、ミフォンに後ろ盾ができたかもしれないという簡単な話だった。そのため、改めてディルがわかったことを話そうとした。
「長いから呼び方を変えたらどうだ」
ディルの言葉を遮ったのはファラスだった。婚約は認めたが、自分の目の届く範囲では二人きりにさせるつもりはないらしく、一緒に話を聞いていたのだ。
「なんて呼ぶんだよ」
ディルの問いかけに、ファラスは少し考えてから大真面目に答える。
「自分がみんなに愛されていると勘違いしている動物」
「さっきよりも長くなってんじゃねえか」
「じゃあ動物」
「俺らも動物だよ」
「メス猿」
「一緒にしたらメスの猿に失礼だろ」
「それもそうか」
二人の会話をリリスが微笑ましく思いながら聞いていると、ディルに急に意見を求められる。
「リリスはどう思う?」
婚約が決まってから、ディルはリリスに敬称を付けなくなっていた。呼ばれ方に慣れずドキドキしつつも、リリスは思いついた言葉を口にする。
「あまり、人に嫌なあだ名をつけたくはないのですけど、こうなってはいけない見本のような女性なので、ミホンはどうでしょう」
「元々の名前に近いから良いんじゃないか。ミホンだけなら一概にけなしているとは思えないしな」
「そうだな。彼女は昔から男性に気のある素振りばかり見せて、多くの令嬢から嫌われていた。こうなってはいけない女性という見本だからな。さすがリリスだ」
「褒められることじゃないです。私はミフォンと呼びますから、それは許してくださいね」
ディルとファラスが頷くと、リリスは話題を戻す。
「彼女は今、どうしているんですか?」
「ジョード卿の従兄と一緒にいる」
「ジョード卿の従兄というと、ロタ・レイドン子爵ですか?」
「そうだ」
リリスは彼女が覚えている範囲のことを口に出してみる。
「たしか、私よりも三つ年上。すでに子爵の爵位を継いでおられて、たしかご結婚もされているのではなかったでしょうか」
「そうだ。妻を追い出して、彼女と一緒に暮らし始めた」
「奥様を追い出したんですか!?」
リリスが聞き返すと、ディルは今までに起きた出来事を簡単に彼女たちに話した。
ミフォンはロタに自分の希望を話したあと、彼に連れられ、レイドン子爵家を訪れていた。彼の妻は夫が女性を連れてきたことに驚いただけでなく、相手がミフォンだということにショックを受けた。レイドン夫人がミフォンの本性を知っていたため、屋敷内に住ませるなんてありえないと抗議したところ、問答無用でレイドン子爵から家から出ていけと言われてしまった。
「夫人が出て行けと言われた時、彼女は笑っていたらしい。こんな神経の持ち主がいるのかと恐ろしくなって、素直に離婚を認めざるを得なかったんだそうだ」
「関わりたくないという気持ちはわかります。あの人は何を考えているのかわかりませんし、倫理観が人と違いますから」
「元夫人が出て行くと同時に、使用人たちも夫人に付いていこうとしたんだが、何人か留まってもらい情報を流してもらうことにした。もちろん、報酬は渡すし無理強いはしてない。命の危険を感じた時や、精神的に耐えられなくなる前に辞めても良いということは伝えてる」
「腹が立ちすぎて、ミホンを殴った場合はどうなるんだ?」
ファラスに尋ねられたディルは眉根を寄せて答える。
「使用人たちはお前みたいにすぐに攻撃しようとは思わないから、そこまで想定はしてなかったが、そうなった場合も補償はするよ」
「そうしてやってくれ。あの女を相手にするのは苦痛でしかないだろうからな」
「お前は金を払ってでも殴りそうだな」
「殴りたい気持ちはあるが、破産するくらい殴っても怒りは収まらないだろうから殴らない。金の無駄だ」
ファラスの話を聞いたディルは苦笑して頷くと、リリスに視線を戻す。
「彼女はまだ俺と結婚したいらしくて、しかも結婚式にリリスを呼びたいんだと。よくわからないが、子爵は彼女の望みを叶えてあげたいと考えているが、自分も彼女と結婚したいから、かなり葛藤しているみたいだ」
「ミフォンがディル様を好きだという気持ちはわかっても、私にこだわる理由がわかりません。それに、子爵はミフォンのどこが良いのでしょうか」
リリスが大きな息を吐くと、ディルは眉尻を下げる。
「子爵が彼女のどこが好きなのかは俺もわからない。もしかしたら、感覚が似ているのかもしれないな。それから、リリスにこだわる理由だが、今までは優越感を得られるなら相手が誰でも良かったのに、今の彼女は君に限定しているように思える」
「それはどうしてでしょうか」
「リリスが我慢しすぎたからだろうな」
「……我慢しすぎた?」
聞き返すと、ディルは頷く。
「ああ。怒りで発散する人間よりも、怒りや悲しみを表すことを必死に我慢している人間を見るほうが満足するんだろう」
「……大人の対応をしていたつもりでしたが、それが駄目だったんですね」
「そういうわけじゃねえだろ。彼女の性格が変わってるだけだ」
「そうだ。あの女は悪い見本だからな」
「ありがとうございます」
慰めてくれたディルとファラスに礼を言い、リリスは決心する。
(ミフォンは私からディル様を奪って見せつけようとしているのね。ジョード卿の時と同じようにするつもりなんだわ。もう、彼女の思う通りにはさせない)
「もう、彼女を増長させません。これ以上、犠牲者を増やさないために引導を渡します」
今までのミフォンは周りに守られたおかげで、彼女自身が大して苦しむことはなかった。物理的に彼女を遠ざけ、ミフォンの自分への執着をなくさせることが自分の人生からミフォンを捨てる手段なのだと認識し、話し合えばわかるなどという甘い考えは捨てる。
リリスがそう考えた時、ステラとレイドン子爵夫人が訪ねてきたと連絡があった。
ミフォンとレイドン子爵の件を聞いたステラは、自分が以前の夜会でミフォンに甘い対応をしてしまったせいで、レイドン夫人を悲しませてしまったと感じた。そのため、実家に戻った子爵夫人に詫びを入れ、何とかすると伝えたところ、夫人がリリスに会いたいと望んだのだった。
ミフォンの両親は長年、マヤを虐げ、貴族であるコレットに詐欺行為を働いたとして、炭鉱で働くことを命じられた。期間は今のところは無期限で、更生すれば刑期が短くなる。
コレットから巻き上げたお金や、他人から物や金銭を奪うことで生活していた彼らは、働いたことがなかった。そのため、すぐに音を上げたが、働けない理由がないのに働かない場合は、食事を出してもらうことができず、現在は文句を言いながらも働いている。反省している様子がまったく見られないので、彼らは死ぬまで働かされることになるだろうというのが周りの考えだった。
「ミフォンの両親だと納得できる人たちですね」
「で、元レーヌ男爵令嬢の件なんだが」
先日、辺境伯が話してくれたのは、ミフォンに後ろ盾ができたかもしれないという簡単な話だった。そのため、改めてディルがわかったことを話そうとした。
「長いから呼び方を変えたらどうだ」
ディルの言葉を遮ったのはファラスだった。婚約は認めたが、自分の目の届く範囲では二人きりにさせるつもりはないらしく、一緒に話を聞いていたのだ。
「なんて呼ぶんだよ」
ディルの問いかけに、ファラスは少し考えてから大真面目に答える。
「自分がみんなに愛されていると勘違いしている動物」
「さっきよりも長くなってんじゃねえか」
「じゃあ動物」
「俺らも動物だよ」
「メス猿」
「一緒にしたらメスの猿に失礼だろ」
「それもそうか」
二人の会話をリリスが微笑ましく思いながら聞いていると、ディルに急に意見を求められる。
「リリスはどう思う?」
婚約が決まってから、ディルはリリスに敬称を付けなくなっていた。呼ばれ方に慣れずドキドキしつつも、リリスは思いついた言葉を口にする。
「あまり、人に嫌なあだ名をつけたくはないのですけど、こうなってはいけない見本のような女性なので、ミホンはどうでしょう」
「元々の名前に近いから良いんじゃないか。ミホンだけなら一概にけなしているとは思えないしな」
「そうだな。彼女は昔から男性に気のある素振りばかり見せて、多くの令嬢から嫌われていた。こうなってはいけない女性という見本だからな。さすがリリスだ」
「褒められることじゃないです。私はミフォンと呼びますから、それは許してくださいね」
ディルとファラスが頷くと、リリスは話題を戻す。
「彼女は今、どうしているんですか?」
「ジョード卿の従兄と一緒にいる」
「ジョード卿の従兄というと、ロタ・レイドン子爵ですか?」
「そうだ」
リリスは彼女が覚えている範囲のことを口に出してみる。
「たしか、私よりも三つ年上。すでに子爵の爵位を継いでおられて、たしかご結婚もされているのではなかったでしょうか」
「そうだ。妻を追い出して、彼女と一緒に暮らし始めた」
「奥様を追い出したんですか!?」
リリスが聞き返すと、ディルは今までに起きた出来事を簡単に彼女たちに話した。
ミフォンはロタに自分の希望を話したあと、彼に連れられ、レイドン子爵家を訪れていた。彼の妻は夫が女性を連れてきたことに驚いただけでなく、相手がミフォンだということにショックを受けた。レイドン夫人がミフォンの本性を知っていたため、屋敷内に住ませるなんてありえないと抗議したところ、問答無用でレイドン子爵から家から出ていけと言われてしまった。
「夫人が出て行けと言われた時、彼女は笑っていたらしい。こんな神経の持ち主がいるのかと恐ろしくなって、素直に離婚を認めざるを得なかったんだそうだ」
「関わりたくないという気持ちはわかります。あの人は何を考えているのかわかりませんし、倫理観が人と違いますから」
「元夫人が出て行くと同時に、使用人たちも夫人に付いていこうとしたんだが、何人か留まってもらい情報を流してもらうことにした。もちろん、報酬は渡すし無理強いはしてない。命の危険を感じた時や、精神的に耐えられなくなる前に辞めても良いということは伝えてる」
「腹が立ちすぎて、ミホンを殴った場合はどうなるんだ?」
ファラスに尋ねられたディルは眉根を寄せて答える。
「使用人たちはお前みたいにすぐに攻撃しようとは思わないから、そこまで想定はしてなかったが、そうなった場合も補償はするよ」
「そうしてやってくれ。あの女を相手にするのは苦痛でしかないだろうからな」
「お前は金を払ってでも殴りそうだな」
「殴りたい気持ちはあるが、破産するくらい殴っても怒りは収まらないだろうから殴らない。金の無駄だ」
ファラスの話を聞いたディルは苦笑して頷くと、リリスに視線を戻す。
「彼女はまだ俺と結婚したいらしくて、しかも結婚式にリリスを呼びたいんだと。よくわからないが、子爵は彼女の望みを叶えてあげたいと考えているが、自分も彼女と結婚したいから、かなり葛藤しているみたいだ」
「ミフォンがディル様を好きだという気持ちはわかっても、私にこだわる理由がわかりません。それに、子爵はミフォンのどこが良いのでしょうか」
リリスが大きな息を吐くと、ディルは眉尻を下げる。
「子爵が彼女のどこが好きなのかは俺もわからない。もしかしたら、感覚が似ているのかもしれないな。それから、リリスにこだわる理由だが、今までは優越感を得られるなら相手が誰でも良かったのに、今の彼女は君に限定しているように思える」
「それはどうしてでしょうか」
「リリスが我慢しすぎたからだろうな」
「……我慢しすぎた?」
聞き返すと、ディルは頷く。
「ああ。怒りで発散する人間よりも、怒りや悲しみを表すことを必死に我慢している人間を見るほうが満足するんだろう」
「……大人の対応をしていたつもりでしたが、それが駄目だったんですね」
「そういうわけじゃねえだろ。彼女の性格が変わってるだけだ」
「そうだ。あの女は悪い見本だからな」
「ありがとうございます」
慰めてくれたディルとファラスに礼を言い、リリスは決心する。
(ミフォンは私からディル様を奪って見せつけようとしているのね。ジョード卿の時と同じようにするつもりなんだわ。もう、彼女の思う通りにはさせない)
「もう、彼女を増長させません。これ以上、犠牲者を増やさないために引導を渡します」
今までのミフォンは周りに守られたおかげで、彼女自身が大して苦しむことはなかった。物理的に彼女を遠ざけ、ミフォンの自分への執着をなくさせることが自分の人生からミフォンを捨てる手段なのだと認識し、話し合えばわかるなどという甘い考えは捨てる。
リリスがそう考えた時、ステラとレイドン子爵夫人が訪ねてきたと連絡があった。
ミフォンとレイドン子爵の件を聞いたステラは、自分が以前の夜会でミフォンに甘い対応をしてしまったせいで、レイドン夫人を悲しませてしまったと感じた。そのため、実家に戻った子爵夫人に詫びを入れ、何とかすると伝えたところ、夫人がリリスに会いたいと望んだのだった。