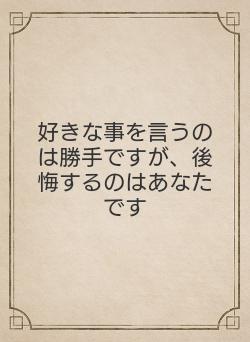急いで家に帰ったズーケは、マヤに悪い奴らがやって来るから階下が騒がしくなっても声は出すなと指示をし、彼女を地下室に移動させた。
当たり前だが窓はなく、光が差し込む場所は一切ない。ズーケが禁止されている賭け事を仲間とするための場所だったため、ベッドを運び入れることもできず、ソファーで寝かされることになった。
元々、この地下室は図面になく、ここに住み始めてからズーケが勝手に作ったものだ。そのため、地下室があるということは、レーヌ家の人間と地下室を作った人間しか知らない。
地下室を作ったのは、ズーケの悪友たちで家の設計に携わったことのない人間たちだった。絶対にバレることはない。そう思っていたが、さすがのマヤも黙ってはいなかった。
コレットに指示をされた人間が調査にやって来た時、マヤは自分を探していることに気がつき、必死になって声を上げた。
さすがのマヤも息子たちがおかしいことに気づいていたからだ。
だが、その声は足音にかき消されてしまう。絶望かと思われたその時、マヤはあるものが手元にあることに気がついた。食事や飲み物を運ぶ時に使われたシルバートレイがすぐ近くに置かれていたのだ。マヤはシルバートレイを手に取ると、近くの壁を叩き続けた。
マヤの願いは無事に届き、地下室に続く扉が発見され、彼女は無事に助け出されたのだった。
ミフォンたちはその場で捕まり、連行されて取り調べを受けることになったが、ミフォンには何のお咎めもなかった。
ミフォンは祖母の軟禁に関わっていないと判断されて釈放されたのだ。
「ひとりぼっちになっちゃった。……わたし、どうしたらいいのっ? ぜんぶ、リリスのせいだわっ! リリスがっ、わたしの面倒をみなくなったからっ!」
彼女以外誰もいない家の自室で、ミフォンが泣いていると、誰かが家の中に無断で入ってきた。
身なりの良い長身痩躯の若い男は、ミフォンの部屋までやって来ると、ノックもなしに扉を開けた。
「だ……、誰なの?」
怯えるミフォンに、金色の腰まである長い髪を一つにまとめた男は笑顔で答える。
「ミフォン、僕は君を愛している。僕と結婚してくれ」
「……嫌よ。あなたが誰だか知らないし、わたしはディルを愛しているの! ディル以外は嫌なのっ!」
「ああ、泣き顔も美しい」
恍惚の表情を浮かべ、男はミフォンに近づき、彼女の前で跪く。
「エイト卿の心を動かすのは僕には無理だが、その他に僕にできることなら何でもしよう。君の望みは他にないかな?」
「わたしの望みは……」
ミフォンは男性から愛の言葉を囁かれることに慣れていた。だから、相手が誰であろうが、大して疑うこともなく彼の言葉を受け入れ、望みを伝えたのだった。
素直に男に助けを求めるだけならば、彼女は新しい人生を歩めた。しかし、彼女はディルのこともリリスのことも諦めなかった。
これが自分自身の人生を破滅に導く行為だなんて思ってもいなかった。
このことはミフォンを陰で監視していた者によって、ディルに報告された。
******
マヤとコレットが無事に再会でき、契約が破棄されたことをリリスが知ったのは、マヤが助け出されて3日後のことだった。
ディルの父親であるエイト辺境伯とディルが、ノルスコット子爵家に足を運び、事の顛末を話してくれて、初めて知ることができた。
「ちょうど君があの場にいてくれたおかげで、母が我々に隠れてやっていたことを知ることができた。本当に感謝している」
エイト辺境伯が頭を下げると同時に、隣に座っていたディルも深く頭を下げた。リリスはそんな二人を見て恐縮する。
「あの、たまたまあの時にお約束をしていただけなんです。それに、ディル様に連絡しただけで、私は大したことはしていません」
「使用人たちはずっと、我々に連絡をしたいと思っていたが、母に口止めされて無理だったらしい。みんな、君に感謝していると言っていた」
「……コレット様は使用人に愛されているのですね」
(あの時のメイドは、もしかしたら私に助けを求めたくて、聞こえるように話をしたのかしら)
こんなことを口に出すわけにはいかないが、コレットの甘さも浅はかさも含めて、使用人たちにとっては、コレットは良い人間なのだろうとリリスは思った。
「変なところ頑固だから困ることもあるけど、心が純粋な困ったおばあちゃん扱いなんだろう」
「悪い使用人が仕えなくて本当に良かったです」
「2年前までは俺も一緒に暮らしていたから、変なのは排除したんだよ」
ディルに言われ、リリスが納得したところで辺境伯が話題を変える。
「私が今日ここに来たのは、母のことでのお礼と、もう一つお願いがあってなんだが……」
リリスからディルとの婚約の話が出ていると聞いていたファラスたちは、緊張した面持ちで辺境伯の言葉の続きを待つ。
「ステラ殿下からディルの新しい婚約者に、ぜひリリス嬢を薦めたいと連絡があった。勝手に調べさせてもらった結果、こちらとしては君の人柄も家柄も問題ない。リリス嬢にはもう心に決めた人物、もしくは婚約者候補がいるんだろうか」
「いません」
リリスが即答すると、辺境伯は微笑む。
「では、ディルとの婚約の話を前向きに考えてもらえるのだろうか」
「ディル様が良いのでしたらもちろんです!」
父とファラスにはすでに意見を聞いていたため、リリスは迷わずに答えた。すると、ディルが立ち上がる。
「リリス嬢、俺……、いや、私にとっては君との婚約はありがたい話だ。だから、俺、じゃない」
緊張しているのか、しどろもどろになっているディルに、リリスは微笑む。
「ディル様、俺でかまいませんよ」
「……ありがとう」
ディルはこほんと咳払いをしたあと、改めてリリスを見つめて口を開く。
「俺と婚約してもらえないでしょうか」
「喜んで」
この時のリリスとディルの間にあったのは、恋愛感情というよりも、彼女たちにも理由のわからない安堵感だった。
「では、婚約を結ぶ際の条件を決めていきたいんだが、その前に、元レーヌ男爵令嬢についての話をしておきたい」
「……ミフォンの?」
辺境伯の話に、リリスの気分は一気に重くなった。
リリスとディルの関係は、執拗にディルを求めリリスにマウントを取りたがる、陰湿なミフォンによって、彼女の思惑とは別に深まっていくことになる。
当たり前だが窓はなく、光が差し込む場所は一切ない。ズーケが禁止されている賭け事を仲間とするための場所だったため、ベッドを運び入れることもできず、ソファーで寝かされることになった。
元々、この地下室は図面になく、ここに住み始めてからズーケが勝手に作ったものだ。そのため、地下室があるということは、レーヌ家の人間と地下室を作った人間しか知らない。
地下室を作ったのは、ズーケの悪友たちで家の設計に携わったことのない人間たちだった。絶対にバレることはない。そう思っていたが、さすがのマヤも黙ってはいなかった。
コレットに指示をされた人間が調査にやって来た時、マヤは自分を探していることに気がつき、必死になって声を上げた。
さすがのマヤも息子たちがおかしいことに気づいていたからだ。
だが、その声は足音にかき消されてしまう。絶望かと思われたその時、マヤはあるものが手元にあることに気がついた。食事や飲み物を運ぶ時に使われたシルバートレイがすぐ近くに置かれていたのだ。マヤはシルバートレイを手に取ると、近くの壁を叩き続けた。
マヤの願いは無事に届き、地下室に続く扉が発見され、彼女は無事に助け出されたのだった。
ミフォンたちはその場で捕まり、連行されて取り調べを受けることになったが、ミフォンには何のお咎めもなかった。
ミフォンは祖母の軟禁に関わっていないと判断されて釈放されたのだ。
「ひとりぼっちになっちゃった。……わたし、どうしたらいいのっ? ぜんぶ、リリスのせいだわっ! リリスがっ、わたしの面倒をみなくなったからっ!」
彼女以外誰もいない家の自室で、ミフォンが泣いていると、誰かが家の中に無断で入ってきた。
身なりの良い長身痩躯の若い男は、ミフォンの部屋までやって来ると、ノックもなしに扉を開けた。
「だ……、誰なの?」
怯えるミフォンに、金色の腰まである長い髪を一つにまとめた男は笑顔で答える。
「ミフォン、僕は君を愛している。僕と結婚してくれ」
「……嫌よ。あなたが誰だか知らないし、わたしはディルを愛しているの! ディル以外は嫌なのっ!」
「ああ、泣き顔も美しい」
恍惚の表情を浮かべ、男はミフォンに近づき、彼女の前で跪く。
「エイト卿の心を動かすのは僕には無理だが、その他に僕にできることなら何でもしよう。君の望みは他にないかな?」
「わたしの望みは……」
ミフォンは男性から愛の言葉を囁かれることに慣れていた。だから、相手が誰であろうが、大して疑うこともなく彼の言葉を受け入れ、望みを伝えたのだった。
素直に男に助けを求めるだけならば、彼女は新しい人生を歩めた。しかし、彼女はディルのこともリリスのことも諦めなかった。
これが自分自身の人生を破滅に導く行為だなんて思ってもいなかった。
このことはミフォンを陰で監視していた者によって、ディルに報告された。
******
マヤとコレットが無事に再会でき、契約が破棄されたことをリリスが知ったのは、マヤが助け出されて3日後のことだった。
ディルの父親であるエイト辺境伯とディルが、ノルスコット子爵家に足を運び、事の顛末を話してくれて、初めて知ることができた。
「ちょうど君があの場にいてくれたおかげで、母が我々に隠れてやっていたことを知ることができた。本当に感謝している」
エイト辺境伯が頭を下げると同時に、隣に座っていたディルも深く頭を下げた。リリスはそんな二人を見て恐縮する。
「あの、たまたまあの時にお約束をしていただけなんです。それに、ディル様に連絡しただけで、私は大したことはしていません」
「使用人たちはずっと、我々に連絡をしたいと思っていたが、母に口止めされて無理だったらしい。みんな、君に感謝していると言っていた」
「……コレット様は使用人に愛されているのですね」
(あの時のメイドは、もしかしたら私に助けを求めたくて、聞こえるように話をしたのかしら)
こんなことを口に出すわけにはいかないが、コレットの甘さも浅はかさも含めて、使用人たちにとっては、コレットは良い人間なのだろうとリリスは思った。
「変なところ頑固だから困ることもあるけど、心が純粋な困ったおばあちゃん扱いなんだろう」
「悪い使用人が仕えなくて本当に良かったです」
「2年前までは俺も一緒に暮らしていたから、変なのは排除したんだよ」
ディルに言われ、リリスが納得したところで辺境伯が話題を変える。
「私が今日ここに来たのは、母のことでのお礼と、もう一つお願いがあってなんだが……」
リリスからディルとの婚約の話が出ていると聞いていたファラスたちは、緊張した面持ちで辺境伯の言葉の続きを待つ。
「ステラ殿下からディルの新しい婚約者に、ぜひリリス嬢を薦めたいと連絡があった。勝手に調べさせてもらった結果、こちらとしては君の人柄も家柄も問題ない。リリス嬢にはもう心に決めた人物、もしくは婚約者候補がいるんだろうか」
「いません」
リリスが即答すると、辺境伯は微笑む。
「では、ディルとの婚約の話を前向きに考えてもらえるのだろうか」
「ディル様が良いのでしたらもちろんです!」
父とファラスにはすでに意見を聞いていたため、リリスは迷わずに答えた。すると、ディルが立ち上がる。
「リリス嬢、俺……、いや、私にとっては君との婚約はありがたい話だ。だから、俺、じゃない」
緊張しているのか、しどろもどろになっているディルに、リリスは微笑む。
「ディル様、俺でかまいませんよ」
「……ありがとう」
ディルはこほんと咳払いをしたあと、改めてリリスを見つめて口を開く。
「俺と婚約してもらえないでしょうか」
「喜んで」
この時のリリスとディルの間にあったのは、恋愛感情というよりも、彼女たちにも理由のわからない安堵感だった。
「では、婚約を結ぶ際の条件を決めていきたいんだが、その前に、元レーヌ男爵令嬢についての話をしておきたい」
「……ミフォンの?」
辺境伯の話に、リリスの気分は一気に重くなった。
リリスとディルの関係は、執拗にディルを求めリリスにマウントを取りたがる、陰湿なミフォンによって、彼女の思惑とは別に深まっていくことになる。