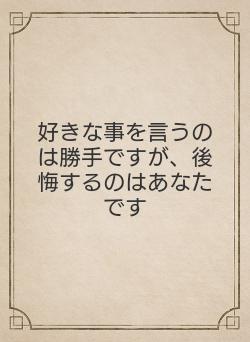リリスがコレットと話をした次の日には、ステラから彼女主催の夜会の招待状と手紙が届いた。手紙に目を通してみると、リリスの体調などを気遣う話、夜会を開くという連絡以外は謝罪の言葉が並べられていた。
同じく手紙が届いていた兄のファラスに、リリスはため息を吐いて話す。
「わざと伝えていなかったんだから、ステラ様が気にすることじゃないのに、なんてお返事をしたらいいのかしら」
「リリスのことを気にかけていたつもりだったのに、気づけていなかったことが悔しいんじゃないか。だから礼を伝えるだけでいいだろう」
「もし、本当にそうだとしたら余計に申し訳ないわ。こちらは気づかれないように隠していたんだもの」
「まあ、いいじゃないか。悔しいが爵位はあの無神経野郎のほうが上だ。うちは強く出られないが、王女殿下が相手なら奴らも文句は言えない」
ファラスは笑顔でそう答えたが、すぐに表情を暗くする。いつもと様子の違う兄が気になって、リリスは首を傾げた。
「どうかしましたか?」
「いや、夜会には僕も行かないといけなくなったんだ」
ファラスは人混みが嫌いだということもあるが、彼は独身で婚約者がいない。顔も整っているので、一部の令嬢に人気があり、彼に近づこうとする者も多いため憂鬱なのだ。
「申し訳ございません、お兄様」
「リリスが謝ることじゃない。お前が幸せになるのなら、僕は美しい人間のフリをした猛獣の檻の中にでも飛び込むことができる!」
「王女殿下を猛獣扱いするのはやめてください」
「まあ、彼女のことだ。僕に近づきそうな女性は呼ばないだろうし、招待客は年配の方が多いだろう。いつもほど憂鬱じゃないから、リリスは気にしなくていい」
リリスたちの中ではステラは猪突猛進で奔放な女性だが、王女としての仕事をしている時の彼女はまるで別人で落ち着いている。子供や老人には特に優しくて、多くの人に好かれており、表向きの顔があるから、ステラの両親も兄である王太子も彼女のファラスへの気持ちを止めることはない。ステラに目をつけられたファラスを気の毒に思っているところはあるが、彼に想い人ができない限りは、ステラを自由にさせるつもりだった。
今回の夜会の件も、ステラはもちろん両親たちに許可を得ていて、両陛下や王太子を巻き込んでの『みんなで浮気現場を押さえよう会』というふざけた名前が付けられて計画が練られているのだが、リリスたちはそれを知らない。
「そうですね。今回は私やディル様のために開いてくださる夜会ですし、きっと位の高い方たちが多いでしょう」
「それよりも、夜会ではどう動くか考えているのか?」
「はい。最近のシン様はパーティーがあれば、私ではなくミフォンを連れて行っていましたが、今回、ミフォンはディル様に誘われますので、シン様は私と行ってくれるはずです」
「それはそうだろう。それが当たり前だ」
「パーティー会場で、ミフォンと会い、彼女の前でシン様と仲の良いふりをするつもりです」
「それはいいんだが、さすがに脳内でいつもスキップしている野郎たちも警戒しているんじゃないか?」
ファラスに尋ねられたリリスは自信ありげな笑みを浮かべる。
「私にマウントを取られることを、ミフォンのプライドが許さないはずです。何としてでも奪いに来るでしょう。そして、シン様も最初は拒みはするでしょうけれど、ミフォンの誘惑に勝てるほど強い精神を持っているとは思えません」
「それはそうだが……」
ファラスは少し考えたあと、大きく頷く。
「そうだよな。あいつらは馬鹿だからな。少し後押しすれば尻尾を出すだろう」
「お兄様が心配なさる通り、絶対とは言えませんので、もし、思い通りに動かない場合は、二人きりになる状況を作るようにしたいと思っています」
(あの人たちだってお兄様の言うように警戒はしているでしょう。大丈夫だと思い込むのはやめよう)
リリスが気を引き締め直していると、メイドがやって来た。
「ジョード家の使いの方が来ておられます。お嬢様に手紙の内容を確認してもらい、すぐに返事をいただきたいとのことです」
「ありがとう。すぐに行くわ」
リリス宛のシンからの手紙には、ステラが主催する夜会に一緒に行ってほしいと書かれていた。
(昔はパーティーの誘いが来ても私の都合なんて聞いてくることはなかったのに、よっぽど前回のことが効いているのね。ご両親にこっぴどく怒られたってとこかしら。誘いに行く暇が省けて良かったわ。だけど、手紙で誘ってくるということは、今頃はミフォンに夜会に一緒に行けないことを伝えに行っているのかもしれない)
リリスは使いの人間を応接室で待たせておき、素早く返事を書いた。内容としてはこんなものだ。
『ステラ様のお誘いですから、必ず参加させていただきます。ただ、今回、シン様が私をパートナーとして誘ってくださったことで、あなたの大切な幼馴染の機嫌を損ねていないかが心配です。だって、いつもは婚約者の私ではなく、大切な幼馴染を誘っていらしたでしょう? この件で喧嘩になったからといって、私に当たらないでくださいませね。ご不満があるようでしたら、いつでもどうぞ。私のほうからステラ様にお話しさせていただきます』
手紙にステラ殿下と書かず、ステラ様と書いたのは、シンの反応を見るためだった。次の日、彼から届いた手紙にはこう書かれていた。
『ミフォンもディル様と出席するらしいから、何も言われなかったよ。それよりも君、ステラ殿下のことをステラ様と呼ぶなんて不敬だぞ。ステラ殿下は気に入った人物にしかステラ様と呼ばせないんだ』
手紙を読み終えたリリスは満足そうに微笑み、相手は目の前にいないが、返答を声に出す。
「そうですよ。そんなことは言われなくても知っています」
(やっぱり多くの貴族には、私とステラ様の仲は知られていないのね)
ステラが自分のことを気にかけてくれていると知った時、シンがどんな顔をするのか楽しみになったリリスは、零れてくる笑みをこらえるために深呼吸する。そして、お礼になるかはわからないが、ステラを少しでも喜ばせるために、夜会に着て行くためのファラスの服を選びに向かったのだった。
同じく手紙が届いていた兄のファラスに、リリスはため息を吐いて話す。
「わざと伝えていなかったんだから、ステラ様が気にすることじゃないのに、なんてお返事をしたらいいのかしら」
「リリスのことを気にかけていたつもりだったのに、気づけていなかったことが悔しいんじゃないか。だから礼を伝えるだけでいいだろう」
「もし、本当にそうだとしたら余計に申し訳ないわ。こちらは気づかれないように隠していたんだもの」
「まあ、いいじゃないか。悔しいが爵位はあの無神経野郎のほうが上だ。うちは強く出られないが、王女殿下が相手なら奴らも文句は言えない」
ファラスは笑顔でそう答えたが、すぐに表情を暗くする。いつもと様子の違う兄が気になって、リリスは首を傾げた。
「どうかしましたか?」
「いや、夜会には僕も行かないといけなくなったんだ」
ファラスは人混みが嫌いだということもあるが、彼は独身で婚約者がいない。顔も整っているので、一部の令嬢に人気があり、彼に近づこうとする者も多いため憂鬱なのだ。
「申し訳ございません、お兄様」
「リリスが謝ることじゃない。お前が幸せになるのなら、僕は美しい人間のフリをした猛獣の檻の中にでも飛び込むことができる!」
「王女殿下を猛獣扱いするのはやめてください」
「まあ、彼女のことだ。僕に近づきそうな女性は呼ばないだろうし、招待客は年配の方が多いだろう。いつもほど憂鬱じゃないから、リリスは気にしなくていい」
リリスたちの中ではステラは猪突猛進で奔放な女性だが、王女としての仕事をしている時の彼女はまるで別人で落ち着いている。子供や老人には特に優しくて、多くの人に好かれており、表向きの顔があるから、ステラの両親も兄である王太子も彼女のファラスへの気持ちを止めることはない。ステラに目をつけられたファラスを気の毒に思っているところはあるが、彼に想い人ができない限りは、ステラを自由にさせるつもりだった。
今回の夜会の件も、ステラはもちろん両親たちに許可を得ていて、両陛下や王太子を巻き込んでの『みんなで浮気現場を押さえよう会』というふざけた名前が付けられて計画が練られているのだが、リリスたちはそれを知らない。
「そうですね。今回は私やディル様のために開いてくださる夜会ですし、きっと位の高い方たちが多いでしょう」
「それよりも、夜会ではどう動くか考えているのか?」
「はい。最近のシン様はパーティーがあれば、私ではなくミフォンを連れて行っていましたが、今回、ミフォンはディル様に誘われますので、シン様は私と行ってくれるはずです」
「それはそうだろう。それが当たり前だ」
「パーティー会場で、ミフォンと会い、彼女の前でシン様と仲の良いふりをするつもりです」
「それはいいんだが、さすがに脳内でいつもスキップしている野郎たちも警戒しているんじゃないか?」
ファラスに尋ねられたリリスは自信ありげな笑みを浮かべる。
「私にマウントを取られることを、ミフォンのプライドが許さないはずです。何としてでも奪いに来るでしょう。そして、シン様も最初は拒みはするでしょうけれど、ミフォンの誘惑に勝てるほど強い精神を持っているとは思えません」
「それはそうだが……」
ファラスは少し考えたあと、大きく頷く。
「そうだよな。あいつらは馬鹿だからな。少し後押しすれば尻尾を出すだろう」
「お兄様が心配なさる通り、絶対とは言えませんので、もし、思い通りに動かない場合は、二人きりになる状況を作るようにしたいと思っています」
(あの人たちだってお兄様の言うように警戒はしているでしょう。大丈夫だと思い込むのはやめよう)
リリスが気を引き締め直していると、メイドがやって来た。
「ジョード家の使いの方が来ておられます。お嬢様に手紙の内容を確認してもらい、すぐに返事をいただきたいとのことです」
「ありがとう。すぐに行くわ」
リリス宛のシンからの手紙には、ステラが主催する夜会に一緒に行ってほしいと書かれていた。
(昔はパーティーの誘いが来ても私の都合なんて聞いてくることはなかったのに、よっぽど前回のことが効いているのね。ご両親にこっぴどく怒られたってとこかしら。誘いに行く暇が省けて良かったわ。だけど、手紙で誘ってくるということは、今頃はミフォンに夜会に一緒に行けないことを伝えに行っているのかもしれない)
リリスは使いの人間を応接室で待たせておき、素早く返事を書いた。内容としてはこんなものだ。
『ステラ様のお誘いですから、必ず参加させていただきます。ただ、今回、シン様が私をパートナーとして誘ってくださったことで、あなたの大切な幼馴染の機嫌を損ねていないかが心配です。だって、いつもは婚約者の私ではなく、大切な幼馴染を誘っていらしたでしょう? この件で喧嘩になったからといって、私に当たらないでくださいませね。ご不満があるようでしたら、いつでもどうぞ。私のほうからステラ様にお話しさせていただきます』
手紙にステラ殿下と書かず、ステラ様と書いたのは、シンの反応を見るためだった。次の日、彼から届いた手紙にはこう書かれていた。
『ミフォンもディル様と出席するらしいから、何も言われなかったよ。それよりも君、ステラ殿下のことをステラ様と呼ぶなんて不敬だぞ。ステラ殿下は気に入った人物にしかステラ様と呼ばせないんだ』
手紙を読み終えたリリスは満足そうに微笑み、相手は目の前にいないが、返答を声に出す。
「そうですよ。そんなことは言われなくても知っています」
(やっぱり多くの貴族には、私とステラ様の仲は知られていないのね)
ステラが自分のことを気にかけてくれていると知った時、シンがどんな顔をするのか楽しみになったリリスは、零れてくる笑みをこらえるために深呼吸する。そして、お礼になるかはわからないが、ステラを少しでも喜ばせるために、夜会に着て行くためのファラスの服を選びに向かったのだった。