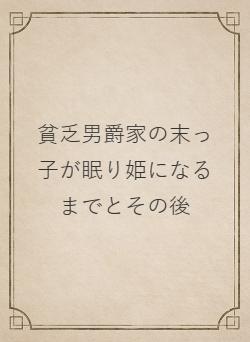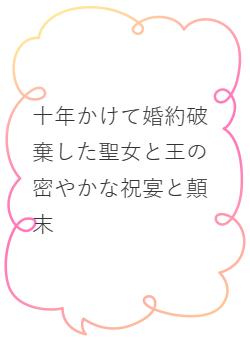結論から言うと、私は気絶しなかった。
広場からアデルさんの屋敷への魔術転移でも、レダの家がある空間への魔術転移でもだ。
広場からアデルさんの屋敷への魔術転移ではちょっとくらっとしたし、レダの家がある空間への魔術転移でもものすごいめまいがしたけれど、意識は失わないように耐えた。
めまいでふらふらと身体の力が抜けそうになる私を心配したレダが、私を抱えて家に――塔に戻るという一幕はあったものの、まあ、最悪の事態は避けられたと言えるだろう。
アデルさんとはアデルさんの屋敷でお別れしたので、帰り着いたレダの家には二人だけだ。
『ただいま』と『おかえり』のやりとりはできなかったけれど、レダの頭からそれは吹き飛んでいるようだったから、まあよし。
椅子に座らされて、冷たい果実水を渡された私は、それをちびちび飲みながら、向かいのレダの様子をうかがう。
……うん、とっても心配そうだ。ギリギリ泣いてないというレベルだ。
「……カーラ、やっぱり外はカーラには危ないよ」
「……だから、引きこもりのままでいよう、と言うつもりですか? だめです。私はもう決めました。この世界をもっと知って、常識を知って――」
「――そして、おれから離れるの?」
「…………」
「カーラのそれは、おれから離れる準備じゃないの?」
おおっと、濁してきた核心を突かれてしまった。
私はぱちりと瞬きして、その間にどう答えるのが一番いいかシミュレートする。
「……そうですね。いつかは、と思っています。いつかは、私がレダの元から巣立つというのは、とてもあり得る話でしょう?」
「おれを置いていくんだ……」
「そうではありません。円満な、家族関係においてはよくある巣立ちです。置いていくとか置いていかれるとか、そういうのじゃありません」
「でも、カーラがおれの前からいなくなろうとしてるのは同じだよ……」
そう言われてしまうとどうしようもない。だけど、思ったよりもレダが話を聞いてくれそうなので、私は言葉を重ねてみることにした。
「私は、レダの思いから、この世界に喚ばれましたよね」
自分が世界に与える影響を厭って、この空間に、家に、閉じこもって。長い長い年月を過ごして、過ごして――自分が老いることも死ぬこともないと知ってしまって。
レダの心は一度壊れた。壊れて、狂って――それにも疲れて、倦んで。
世界はそれでも、レダを愛していた。愛しているから不老不死にしたし、愛しているから、そんなふうになったレダに心を痛めていたのだろう。この世界には意思が、心があるから。
そうして、狂い果てた先に、レダがぼんやりと、「ひとりは、さみしい」と考えた――その思いを汲み取って、私をこの世界に墜とした。
この世界で生きる生命は、世界が愛するレダのいいように動きすぎる。それは植物も、動物も、人間も、ありとあらゆるものすべてが。
だから、異世界のものを混ぜ込んだ。身体こそこの世界に適合するように作り変えられたけれど、私の魂は異世界のものだ。レダの願いや思いを汲み取った世界に、どうこうされたりはしない。
そういう――ちゃんとした『他人』がレダには必要だったのだ。
家族すら、世界に愛されたレダを、本当の意味で愛せなかった。
愛してはいた。異常なくらい愛してはいた。だってレダは、世界が愛する存在だったから。
そういう、卵が先か鶏が先かみたいな問題が、レダにはつきまとっていて――そうして、そんな愛ですら、時間の果てに消えていった。
レダとともに生きてくれる人は、きっと望めばたくさん現れたのだろう。でもレダは望まなかった。望みたくなかったのだろう。そこに、本当に心があるのか、疑ってしまうから。
そんなふうな疑心暗鬼を宿すレダに都合がよすぎない存在として、私はこの世界に喚ばれたのだ。
レダは、喚ばれてしまった私を見て、泣いた。
すべてを理解して。世界がまた、自分のために動いてしまったと知って。
私は、レダのために自分が喚ばれたことを理解していた。それは世界にとって、当たり前すぎることだったから。
そうして私とレダはともに暮らし始めた。被保護者と保護者として。幼子と大人として。――そのかたちは、家族にしてはいびつで、だけど一番近いのがそれだった。レダが求めたのがそれだったから。
そうして十年。私はすくすくと育った。育ったということは、歳をとるということだ。不老不死のレダと違って。
それは、いつかは時の果てに、私がレダを置いていく可能性を示唆していた。
レダは私と暮らして、ずいぶん人間らしくなったと思う。
食べるという行為を忘れて久しいレダに、人間には食事が必要だと思い出させたのは私だし。
感情の希薄だったレダに、泣く以外の感情を思い出させたのも私だし。……その節はいろいろやんちゃしました。反省はしているが後悔はしていない。
レダは、自分のために喚ばれてしまった私に、罪悪感を抱いている。それとは別に、真っ当な『他人』として私のことを好んでいる。家族のように思っているし、保護者として庇護感情を抱いている。
私は、レダのために喚ばれた自分を知っているから、使命感……のようなものがある。それとは別に、ひととして放っておけないし、家族のように思っているし、被保護者として育ててもらった恩もある。
お互いに、一緒にいる理由はある。
だから、私の行く末には、可能性の高い未来が二つある。
一つは、レダの願いによって、私も不老不死になる未来。
もう一つは、レダに私が必要なくなって、穏便に離れる未来。
前者はちょっとよろしくないなと思うので、私は後者を狙っているのだ。
私の言葉にぎこちなく頷いたレダに、私は笑いかける。
「レダのために生きるのは、いいんです。私もレダのこと、好きですし、育ててもらった恩もありますし。ちょっと泣き虫な、頼りない弟を見ているような気持ちでいるところもあります。……この世界での、家族だと思っているので、それはいいんです」
「…………」
「でも、健全な家族関係というものがあります。いついつまでも一緒、というのは、ちょっと違うと思うんです」
レダは一瞬ためらって、だけどそれを口にした。
「……おれが、それがいいって言っても……?」
世界が、どれくらいのレダの気持ちを汲んで、何をしてしまうかはわからない。だからちょっぴりひやひやしながら、私は首を横に振った。
「レダが、そういう関係を望むのは、今、私しかそばにいないからです。私としか、真っ当な関係を築けていないからです」
……私との関係が真っ当の範疇かは疑義があるところだけど、それは置いておく。
「私は、レダにもこの世界との付き合い方を会得してほしいんです」
「……おれ、にも……?」
「そうです。つまるところ、レダが真っ当な人間関係を築けなかったのは、この世界がレダに忖度しすぎるからですよね。そこのところ、この世界のダメなところだと思っていて。レダを本当に愛しているのであれば、レダの望むように世界が変わるべきなんです」
レダを愛して、愛して、愛して。一方的に愛を押しつけ続けるんじゃなくて。
……この世界は、見守り、見送る愛を知らないのだ。
だからレダの一挙手一投足にいちいち反応してなんやかんやするし、レダが望まなくても生きていてほしいからって不老不死を押しつけるし――つまり、レダのことを考えているようで考えていない。
レダもこの世界に生きる存在として――世界に愛されてしまった存在として、それはそういうものなのだ、と諦観とともに生きているけど。
そうじゃないのだ。世界に意思がある、心があるというのなら、変化を望むこともできるはずなのだから。
そう言うと、レダは目をまあるく開いて、ぽかんと口を開けて。
それでも圧倒的な美貌のまま、呟くように言った。
「そんなの、考えたこともなかった……」
たぶん、世界は泣き出した子をあやすために玩具を与えるみたいに私をこの世界に喚んだ。それだけだった。
だから、この使命感というのは、私が勝手に感じているものだ。
――レダの、ほとほとと落ちる、宝石みたいな涙を見たときから。
こんなふうに泣くひとがいるなんて、なにもかもがまちがっている。
まちがいをすべて正して、このひとが笑えるようにしたい、と。
つまるところそれだけなのだ。
引きこもりに限界が、とか、冒険したいとか、世界を知りたいとか、そういうのは後付けで。
レダが、レダとして、何を憂うこともなく笑えるようにしたい。
そのために、ひとまず――私との関係を真っ当に終わらせる準備を始めたと、そういうわけなのだ。
レダの精神が未成熟なのはわかっている。だからこそ、いびつながらも『家族』としてある今を大事にしつつ、それを順当に発展させなければならない。
その先に、今のレダにとって、別れに見えるものがあるだけ。
――だって、家族は、離れていたって家族なんだから。
それをわかってもらえるだけの精神的成長の兆しは見えている。今回、私の話をちゃんと聞いてくれたのがそれだ。
一歩間違えると不老不死コースだったので、内心ハラハラしたけれど。
机の上にあったレダの手を、包み込むように握る。
「これから、考えましょう。私は、レダに、幸せになってほしいんです」
レダは、聞いたことがない言葉を聞いたように、目をぱちくりとさせた。
……本当に聞いたことがなかったのだとしたら、やっぱりこの世界は間違っている。
「……しあ、わせ……」
「一緒に幸せになってもいいし、別々に幸せになってもいい。家族って、そういうものだと私は思います。だから、幸せになりましょう、レダ。この世界で、生きていくんですから」
――そうして、私の『レダ幸せ計画』は、最初の一歩目を踏み出したのだった。