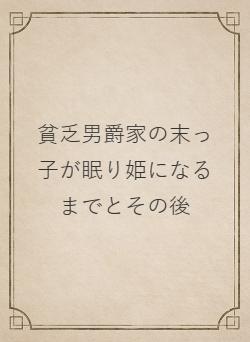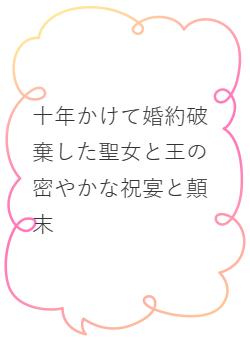さあ、あとはこの家を飛び出すだけ!
――と言いたいところだけど、実はまだ問題があるのである。
なんと、この家には、私が外に出るための扉が、ない。
じゃあ訪問者はどこからやってくるのかと疑問に思うだろう。あるのだ。出入り口たる扉は。
ただ、それを私は認識できないし、触れないし、なので開けられないし、出られないだけだ。
私にとっては、なんかいつもこの壁から人が出てくるし出て行くな……みたいな感じである。いろいろおかしい。
「レダ。私は異世界への第一歩を、この家の扉をくぐって踏み出したいと思うんですが……」
「…………」
レダは私の言葉に、眉根を寄せた。世にもうつくしい『考える人』のできあがりである。
「……ダメですか?」
「やっぱり家から出したくないな……」なんて言われそうなかなりダメ寄りの雰囲気を感じたので、私はレダにはてきめんに効く見上げての上目遣いで押してみる。私の身体は作り変えられたけど、見た目が変わったわけではないので、別にすごくかわいいとかではない。可もなく不可もなくの容姿なのだけど、レダは私がレダのための存在であることと、十年ともに過ごした欲目で、これが効くのだ。
「……っ……! カーラ、ずるい……」
「何にもずるくありませんよ。私はただ要望を伝えて、お願いしているだけです」
「おれがカーラのお願いをなんでも叶えたいの、知ってるくせに……」
「そう言いつつ、わりと叶えてくれないことありますよね」と思ったけれど、私は賢明にその言葉を胸にしまっておいた。
ともかくも、外に出よう計画の第一歩として、扉がないと話にならない。この家の外が地続きで外の世界につながっているかどうかはまだ不明だけど、この家から私が外に出られるというのが重要なのだ。
「記念すべき異世界への第一歩なんですよ。長年住んだこの家から初めて出る第一歩でもあります。なんかよくわからない魔術でパッとかシュンッとかじゃなくて、きちんと地に足着けて踏み出したいじゃないですか」
「…………」
レダはますます眉間のシワを濃くした。かなり深刻に考えているようだけど、もっと軽く考えてほしいものである。何事も。
「レダ、これは今生の別れでもなんでもないんですよ。レダは私の初めての異世界探検に同伴しますし、探検が終わったら私はこの家に帰ってきます。……私たちはともに住む者なら当然交わす『いってらっしゃい』とか『いってきます』とか、『ただいま』とか『おかえりなさい』とかを口にしたことがありませんでしたが、それができるチャンスですよ。家族っぽいこと、しましょう?」
この『家族っぽいこと』というワードは、レダの泣きどころである。レダは『家族』に飢えているので。それを、私で埋めようとしているので。
「……でも、おれも一緒に行くんだよ」
「せーので外に出るわけじゃあるまいし、誤差はあるでしょう? この家はレダのものですから、『いってらっしゃい』はレダに言ってもらいたいですね」
「…………」
レダは熟考した。それはもう熟考した。
それでも結局、私の言う『家族っぽいこと』をしてみたい方に心が傾いたようだった。
「……わかった」
レダが、よく人が現れる壁へと向かい、手を触れる。そうしてそこに大きな魔法陣みたいなものが浮かんで、そこに書かれた記号みたいなのとか文字みたいなのとかがぐにゃぐにゃと変化して、最後にカッと光った。
あまりの光量に一瞬目を閉じて、そうして目を開けた先には。
うつくしい木目の、重厚な両開きの扉があった。上部はアーチ状になっている。
「……! これが、この家の外への扉なんですね!」
「そう。……カーラ、うれしそう。そんなにこの家から出たかった? おれから……離れたかった?」
気付けばまた、レダがほとほとと宝石のような涙を流している。
情緒不安定である。レダがそんなだから私は喚ばれたのだけど、私という存在で安定したかというと、別にそうでもないのである。
「そうじゃありませんよ、レダ。これは純粋に、異世界という未知に対する好奇心が抑えられないだけです。この家以外の場所を見てみたいとは思っていましたが、レダから離れたいとか、そういう気持ちからの感情の発露ではありません」
「……本当に?」
「本当です。なんかよくわからない魔術とかで、思考が読めるなら読んでくれてもいいですよ」
レダはやらないだろうとわかっていながら、私はそう言う。もっともらしく。
「カーラにそんな負荷のかかる魔術を使うなんて、しない……。カーラは大切だから……」
それは逆説的に、それらしい魔術で情報をやりとりしたアデルさんのことは大切じゃないってことですね、とわかりきっていたことを再認識しながら、私はにっこり笑う。
「大切だと思ってくれてうれしいです。そんな大切な私がちょっとおかしくなる前に、異世界探検に出かけましょう!」
「……うん」
高い位置にあるレダのまなじりを拭いてあげれば、すぐにレダの涙は止まった。
さあ、お出かけの時間だ。
扉の取っ手に手をかける。慎重にぐっと押すと、扉は徐々に開いていって――外の空気が、私の頬を撫でていった。
いっぱいに開いた扉の向こうに広がるのは、一面の花畑。少し遠くには、きらきらと水面を光らせる泉らしきものもある。
「えっ、この家、浮いてませんか!?」
地上から、二メートルくらいだろうか。浮いている。
「もう少し待てば、高度が下がるよ」
聞きたいのはそういうことじゃなかったけれど、それも大事な情報だったので、私は「そうなんですね」とだけ言った。
レダの言うとおり、徐々に高度が下がっていって、ついには地面に着陸した。
なんということでしょう。レダの家は空飛ぶ家だったのです。
「い、……いきます」
本日のびっくりポイントその二によって、ちょっと調子が狂ってしまった私に、レダが声をかける。
「いってらっしゃい、カーラ」
それで、心が少し落ち着いた。私は振り返って、笑顔を浮かべる。
「はい、いってきます、レダ」
右足を、一歩、前に出す。
その動作がとてつもなく――勇気のいるものだった。
だけどそんな私の心をよそに、あっさりと玄関という境界を越えて。
もう片方の足も、同じように踏み出して、私の足は無事、花畑に着地した。
「……すごい、景色ですね。まるで、理想郷のような……」
私の後ろから同じように花畑に足を踏み入れたレダが、「そう……かな」と小首を傾げる。
この景色はレダにとっては当たり前すぎて、何の感慨も湧かないのかもしれない。
数歩進んで、振り返る。『レダの家』と私が呼んでいたものは、塔の形をしていた。
高い高い――天に届くような、塔。
「レダの家は、外観と内観が一致していないんですね……」
レダの気持ちで部屋が増えたり減ったり変わったりする時点でふつうじゃないとは思っていたけれど。
私の感想に、レダは目を伏せた。
「この、見た目は……おれが育った、塔と同じで……。どうしてか、変えられない……」
おっとまずい話題の気配。察するところトラウマ案件か何かですね?
察した私はさっくりと話を変えた。
「そうなんですね。――さて、記念すべき異世界への第一歩をこうして踏み出したわけですが、この景色を見るに、アデルさんの国へは歩いて行ける感じじゃないですね?」
「うん。……空間が、違う……」
「まあ予想通りなんですが、ではどうやってアデルさんの国まで行くんですか? 魔術ですかね、やっぱり」
「アデルがここに来るときに使っている陣がある。それを使えば、もう一つの陣の場所に出る……」
「なるほど。移動用の陣というのがあるんですね。それがどこにあるかは?」
「知ってる。こっち……」
さくさくと咲き乱れる花を踏み分けて、レダは少し離れた場所に移動した。何かの実がたわわになっている木が集まっている一角だ。
「この木になる果実を、アデルが好んでいる。だから、この木はここにある」
それはこの不思議空間の作用とかそういうやつで? と聞こうかと思ったけど、知ってても知らなくてもあんまり関係ないなと気付いたのでやめておく。どうやらこのたわわになっている果実は食べられるらしいということだけ覚えておこう。
「では、行きましょうか、アデルさんの国へ!」
私がそう言うと、レダは木々の中、不自然に丸く空いた空間へと足を踏み入れた。その瞬間、今まで見えなかった陣とやらが光って、私にも見えるようになる。
「……カーラ、手を」
促されて、おっかなびっくり陣に足を踏み入れた私は、レダに手を委ねた。ぎゅう、とちょっと痛いくらいの力で握られる。まるでこの手が離れたら二度と会えなくなるとでもいうように。……魔術での移動というのは、もしかしたらそういうものなのかもしれない。そうではないかもしれない。
ただ、その痛みとレダの手の温かさだけが確かで。
「行くよ」
短いレダの言葉のあと、陣がカッと光って――……私の意識は途切れた。