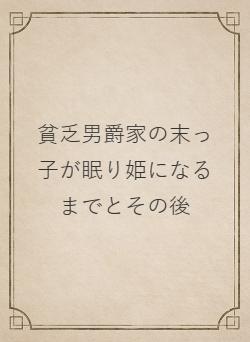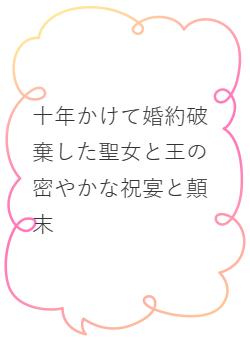その日、私は決意した。
決意したので、それをこの世界での私の保護者であるレダ――本当はダリウスという名前らしいのだけど、私にはそう呼んでほしいらしい――に表明した。
……朝食後、お茶を飲んでまったりしているような、そんな時に。
「レダ、私、この家を出ます!」
そう告げた途端、神が細部まで精魂こめてつくりあげたようなうつくしさを誇るレダの顔が、くしゃりと歪んだ。歪んでもなおとんでもないうつくしさは損なわれないからすごい。
感心する私をよそに、レダはほとほとと涙をこぼし始めた。落ちる雫がまるで宝石のようにきらめいている。レダが泣くときはいつもこうだ。たぶんそのうち涙が宝石になる日が来るのではないだろうか。
「そんな……カーラ、おれを置いていくの?」
世界でも終わったかのような悲壮な表情でレダが言う。もしくは置いていかれることに気付いた子どもの顔だ。
だけどどっちだとしても少々誤解が生じているようだったので、私は言葉を変え、言葉を尽くすことにした。
「レダ、私がレダに保護されてから十年です。十年経ちました。私は幼児から脱しましたね」
「そうだね……?」
そう、私がこの殻世界シャイアに墜ちて、レダに拾われて――保護されて十年。
この世界に適合するようにと作り変えられた身体が、とりあえずしゃべれるし歩けますけど、けど……な幼児のものになってから十年。
すくすく育ち直した私・カーラは、幼児を脱して、大体十三~十四歳かな?というところまで成長した。
さて、それまでの間、私はこのレダの家――それなりに広く、私の要望によって陽に当たれるようにとサンルームみたいなものもできたけれど、とにかく家的な空間――から出ることがなかった。
なんということでしょう。レダは魔術王とか呼ばれているうえに世界にとっても愛されている存在なので、それでも生活が可能だったのだ。
――だけど、可能であるということと、それに耐えられるかというのはまた違う。違うのだと、私は思い知った。わりと引きこもり適性ある方だと思っていたけれど、十年、代わり映えのしない景色――でもなかった、この家はある程度レダの気持ちで変化するので――こほん。代わり映えのしない面子で暮らして、私は悟ったのだ。
人間、刺激がないと倦む、と。
そういうわけで。
「十年、私はレダに合わせて引きこもって暮らしました。この世界の標準はよくわかりませんが、まあよい暮らしをさせてもらったとは思っています」
「うん……?」
とりあえず涙の止まったレダの目を見つめて、一言。
「――もう、冒険心が抑えられないんです!」
レダはぽかん、と口を開けて固まった。そんな間抜けなはずの顔が、芸術品のように見えるから、とんでもない美形(という言葉で括っていいかすら迷ううつくしいひと)というのはすごい。
しみじみと感じ入っていると、レダはゆっくりと瞬きして、口をぱくぱくと動かして――ようやく言葉を発した。
「……冒険?」
私は深く頷いた。
「せっかく未知にあふれた、好奇心を刺激しまくるひらけた世界があるのに、来る日も来る日も引きこもり。たまの訪問者から外の世界について伝え聞くだけという生活は飽きました! 冒険が、冒険がしたいんです!」
気分は演説だ。勢い余ってどん!と食卓に拳を叩きつける。
レダはびくっと肩を震わせた。叱られると思った大型犬のごとくだ。レダはたまにこう……無垢な動物のようだと思う。
「レダはもうこの世界なんて知り尽くして、あるいは興味がなくなっているのかもしれませんが、私にとってはそうではありません。気になることはたくさんあるし、知りたいこともたくさんあるし、何より、この世界で生きていくのなら知っておきたいことがたくさんあります。治安とか諸々。なので、この世界を知るために外に出たいんです」
レダは怒濤のように語った私の言葉の内容を、ゆっくりと咀嚼したようだった。
そして。
「外に出たいの……? 外はきみにはきっと危ないよ。引きこもっていれば死なないのだから、ずっとこの家で一緒にいようよ」
――なんて言ってきた。
なんということでしょう(二回目)。私の思いがちょっとしか伝わっていない。
「レダ。私は引きこもり生活に、限界を感じているんです」
「限界……?」
こてりとレダが首を傾げる。幼子のようなその仕草に、レダのいびつないとけなさを感じる。
「レダはレダなので大丈夫なのでしょう。でも私は、この世界に適合するように作り変えられただけの、ただの人間なんです。むしろ、よく十年ももったと思います。人間はですね、本当は十年も引きこもりするようにはできてないんですよ」
「そう……だったかな……?」
「そうなんだと、私は私の身をもって思い知りました。レダとの安穏とした生活も、もちろん悪いとは言いません。だけど十年も経てば、レダのびっくりポイントも知り尽くしてしまって――つまり、刺激が足りません。刺激がないと、人間は、……私は、ちょっとおかしくなるみたいです。その兆候を感じたので、私は私のためにも、冒険っぽいことをしようと思うのです!」
今度こそ、私の主張はレダに伝わったようだった。
レダは何度も何度も瞬きして、うろうろと視線を彷徨わせて――それから、眉尻を下げて、情けなくもやっぱりうつくしい顔で。
「どうしても……?」
と、往生際悪く聞いてきた。
「どうしてもです!」
私の即答に、レダはまたうろうろと視線を彷徨わせて、言葉を探すように口を開けては閉じて開けては閉じて。
「……おれと、一緒で……アデルのところに行くくらいの距離なら……」
いいよ、と続くはずだったのか、ゆるすよ、と続くはずだったのか。それはわからないけど、私は機を逃すまいと、勢い込んでお礼を言った。
「ありがとうございます、レダ! さすがにいきなり一人で外出は難しいと思っていたので、レダがついてきてくれるのはとっても助かります!」
私の笑顔につられるように、レダがふにゃりと笑う。後光が差すかのようなうつくしさに眩い思いをしつつ、「私がひとりで家から出るのはレダの許容範囲外らしい」と脳内にメモしたのだった。