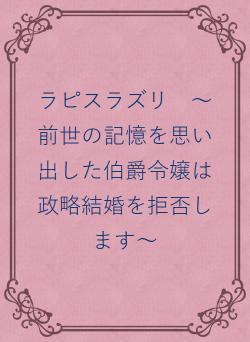俺は小林に手を伸ばした。
小林の頭をポンポンと撫でた。
「先生」
俺は小林から手を離す。
そして、ゆっくりと小林に思いを告げる。
好きだという気持ちではなく、小林が俺から離れていけるように。
俺は小林をフるのだ。
「小林はさ、青春を謳歌したらいいんだよ。
小林はまだ高校生で、卒業したら大学生になって社会に出て、いろんな人と出会って、恋をして、いろんな経験をしてくんだよ。
今は寂しかもしれない。
俺のことはああ、あんなひともいたなって思い出すとか、思い出すことも忘れちゃうくらいでいいんだよ」
「忘れたりなんかしない!」
「そんなの今だけの感情だよ」
「違う!
私が怪我して、バレーできなくなって辛い時に先生は一緒にいてくれた。
毎日毎日病室に来てくれて、勉強見てくれて、相談にも乗ってくれて、・・・・先生がいつもそばにいてくれたから頑張れた。
先生がポンポンって頭撫でてくれて、髪をぐしゃぐしゃってして、・・・いつも優しくて、温かくて・・・忘れたりなんかしないもん!」
「俺は、忘れられる」
「・・・・」
「俺は小林のことを忘れるよ」
「ひどい!!」
「そう、俺は酷いヤツなの。
先生だから、小林に優しくしてたけど、俺はもう先生じゃないからね。
小林も退院したんだし、俺のことより、部活や勉強や友達のことで悩みなさい。
そうだ、今年は受験もあるし、高校最後の年なんだから今をしっかり楽しんで」
涙をこぼしながら揺れる瞳を見つめる。
「君は本当に泣き虫だねえ」
涙が零れる目元にそっと触れる。
小林が片眼を閉じた。
「先生、私のこと好き?」
「え?・・・・ううん」
涙をなぞる。
「じゃ、・・・嫌い?」
「嫌いじゃない」
俺は小林の頬をボロボロと伝う涙を両掌で拭った。
ドンっ。
「あっ」
小林が俺に飛びついた。
俺はバランスを崩し、尻を床についた。
俺は反射的に片手を床につき、もう片方の手を小林の背中に回して彼女を受け止めた。
小林の頭をポンポンと撫でた。
「先生」
俺は小林から手を離す。
そして、ゆっくりと小林に思いを告げる。
好きだという気持ちではなく、小林が俺から離れていけるように。
俺は小林をフるのだ。
「小林はさ、青春を謳歌したらいいんだよ。
小林はまだ高校生で、卒業したら大学生になって社会に出て、いろんな人と出会って、恋をして、いろんな経験をしてくんだよ。
今は寂しかもしれない。
俺のことはああ、あんなひともいたなって思い出すとか、思い出すことも忘れちゃうくらいでいいんだよ」
「忘れたりなんかしない!」
「そんなの今だけの感情だよ」
「違う!
私が怪我して、バレーできなくなって辛い時に先生は一緒にいてくれた。
毎日毎日病室に来てくれて、勉強見てくれて、相談にも乗ってくれて、・・・・先生がいつもそばにいてくれたから頑張れた。
先生がポンポンって頭撫でてくれて、髪をぐしゃぐしゃってして、・・・いつも優しくて、温かくて・・・忘れたりなんかしないもん!」
「俺は、忘れられる」
「・・・・」
「俺は小林のことを忘れるよ」
「ひどい!!」
「そう、俺は酷いヤツなの。
先生だから、小林に優しくしてたけど、俺はもう先生じゃないからね。
小林も退院したんだし、俺のことより、部活や勉強や友達のことで悩みなさい。
そうだ、今年は受験もあるし、高校最後の年なんだから今をしっかり楽しんで」
涙をこぼしながら揺れる瞳を見つめる。
「君は本当に泣き虫だねえ」
涙が零れる目元にそっと触れる。
小林が片眼を閉じた。
「先生、私のこと好き?」
「え?・・・・ううん」
涙をなぞる。
「じゃ、・・・嫌い?」
「嫌いじゃない」
俺は小林の頬をボロボロと伝う涙を両掌で拭った。
ドンっ。
「あっ」
小林が俺に飛びついた。
俺はバランスを崩し、尻を床についた。
俺は反射的に片手を床につき、もう片方の手を小林の背中に回して彼女を受け止めた。