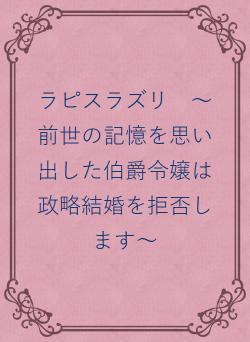それから俺たちはベンチに並んで座っておしゃべりをした。
小林が話をして、俺がうんうんと頷く。
俺が話して、小林が笑う。
どの位、そこにいたのだろうか。
シャボン玉を吹いてきた子供もいなくなり、花見をする人もほとんどいなくなっていた。
ぴゅうーっと強い風が吹いた。
ピクっと小林の肩が跳ねる。
昼間の天気が良かった分、夕方になるにつれて寒くなって来ていた。
「もう寒くなってきたな。
病室に戻ろうか」
「そうだね」
俺は立ち上がり、小林の腕をとってゆっくりと立ち上がらせた。
「ね、先生」
「ん?」
「何かあったの?」
「え?」
俺の腕を支えに立つ小林の瞳が俺のすぐ目の前にあった。
「いつもと何か違う。
いつもより…優しいし、話し方だって違うから…何かあったのかなって」
俺は顔を傾け、小林にゆっくりと近づけた。
ふわり。
俺は小林にキス・・・・・・する手前で止まる。
触れそうで触れない距離。
「・・・え・・・・・・」
消えそうなくらい小さな声がした。
「‥‥悪い・・・・・」
頭を戻し、俺は小林を車椅子に座らせた。
「あ、あの・・・・先せ「応援してる!!」
「え?」
「俺は小林のこと応援してるから。
バレーも、勉強も、友達も、将来の夢も、人生も、全部!」
「は?」
「応援してる」
「え?あ、うん」
「だから、頑張れ!」
「う、うん」
俺は小林の頭をポンポンと撫でて、車椅子を動かした。
小林が話をして、俺がうんうんと頷く。
俺が話して、小林が笑う。
どの位、そこにいたのだろうか。
シャボン玉を吹いてきた子供もいなくなり、花見をする人もほとんどいなくなっていた。
ぴゅうーっと強い風が吹いた。
ピクっと小林の肩が跳ねる。
昼間の天気が良かった分、夕方になるにつれて寒くなって来ていた。
「もう寒くなってきたな。
病室に戻ろうか」
「そうだね」
俺は立ち上がり、小林の腕をとってゆっくりと立ち上がらせた。
「ね、先生」
「ん?」
「何かあったの?」
「え?」
俺の腕を支えに立つ小林の瞳が俺のすぐ目の前にあった。
「いつもと何か違う。
いつもより…優しいし、話し方だって違うから…何かあったのかなって」
俺は顔を傾け、小林にゆっくりと近づけた。
ふわり。
俺は小林にキス・・・・・・する手前で止まる。
触れそうで触れない距離。
「・・・え・・・・・・」
消えそうなくらい小さな声がした。
「‥‥悪い・・・・・」
頭を戻し、俺は小林を車椅子に座らせた。
「あ、あの・・・・先せ「応援してる!!」
「え?」
「俺は小林のこと応援してるから。
バレーも、勉強も、友達も、将来の夢も、人生も、全部!」
「は?」
「応援してる」
「え?あ、うん」
「だから、頑張れ!」
「う、うん」
俺は小林の頭をポンポンと撫でて、車椅子を動かした。