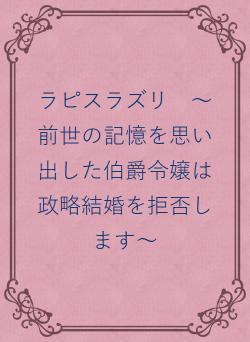「付き合うわけがありませんよ!」
と周囲に聞こえるように大きな声で返事をした。
「でも、小林と二人っきりでいちゃついてたんだろ?」
「付き合ってないのにそんなことしちゃダメじゃん」
ヘラヘラと笑う彼らに、
「勉強を教えていたんです。
君たちも来ればいくらでも教えますよ」
イライラしながらも自分の感情を抑え込んで微笑んだ。
「いらねえし」
「つーか、小林ってスポーツ推薦の特待生じゃん。
勉強なんてしなくていいんじゃね?」
「え、お前知んねえの?
小林もうバレーできねえんだよ」
「え?なんで?」
「足やったんだって」
「まじかー。
・・・それなら学校やめるのかな?」
「えー、俺、小林のことかなり好きだったのに」
「そーなのか?」
「だって、かわいいじゃん。
なー、先生。小林って学校やめるの?」
はぁっっ!!?
「お前らもスポーツ科だろう?
それなら今の小林の気持ちとか分かるだろう?
かわいいとか、学校辞めるとかそういうのじゃなくて、もっと心配とか応援とかさ、こう・・・あるだろう?」
「自己管理ができてないんじゃね?」
「だって、俺ら怪我しないようにいろいろ習ってるじゃん、な」
「うん。それでも怪我しちゃったなら、ストレッチとか体のメンテを怠ったのか運が悪かったとしか言えないよ」
「小林は勝つために努力してたんだ。
頑張って練習して、練習して、その結果怪我をしてしまったんだ。
それが自己管理ができてないで済ますのは、冷たいだろう?」
「俺らは部活したくて高校に来てんだから努力するのは当たり前のことだよ。
特に小林さんは特待生だったんだから俺らよりもっと努力するのは当然だと思う。
怪我したのはかわいそうだとは思うけど、俺らにはどうしようもねえじゃん。
先生、俺たちに何求めてるわけ?」
「・・・・・・そうだよな、感情的になってすまなかった」
俯く俺の肩に手がのった。
「浅倉先生も昔膝を壊して、スポーツを諦めた経験があるんだよ」
見ると、そこにはバレー部の顧問の伊達先生がいた。
伊達先生は、
「だから、つい感情移入してしまったんだと思うぞ。
ほら、分かったらさっさと試合の応援に行きなさい」
と生徒たちを追い払った。
「ありがとうございます」
と言うと、
「浅倉先生、顔恐いよ!笑って笑って」
と肩を叩かれた。
「いてて」
「ははははっ!」
笑いながら片手を上げて歩いていく姿を見送った。
そして。
コンコン。
「失礼します。
教頭先生、今よろしいですか?」
俺はスーツの内ポケットから「退職願」を取り出した。
と周囲に聞こえるように大きな声で返事をした。
「でも、小林と二人っきりでいちゃついてたんだろ?」
「付き合ってないのにそんなことしちゃダメじゃん」
ヘラヘラと笑う彼らに、
「勉強を教えていたんです。
君たちも来ればいくらでも教えますよ」
イライラしながらも自分の感情を抑え込んで微笑んだ。
「いらねえし」
「つーか、小林ってスポーツ推薦の特待生じゃん。
勉強なんてしなくていいんじゃね?」
「え、お前知んねえの?
小林もうバレーできねえんだよ」
「え?なんで?」
「足やったんだって」
「まじかー。
・・・それなら学校やめるのかな?」
「えー、俺、小林のことかなり好きだったのに」
「そーなのか?」
「だって、かわいいじゃん。
なー、先生。小林って学校やめるの?」
はぁっっ!!?
「お前らもスポーツ科だろう?
それなら今の小林の気持ちとか分かるだろう?
かわいいとか、学校辞めるとかそういうのじゃなくて、もっと心配とか応援とかさ、こう・・・あるだろう?」
「自己管理ができてないんじゃね?」
「だって、俺ら怪我しないようにいろいろ習ってるじゃん、な」
「うん。それでも怪我しちゃったなら、ストレッチとか体のメンテを怠ったのか運が悪かったとしか言えないよ」
「小林は勝つために努力してたんだ。
頑張って練習して、練習して、その結果怪我をしてしまったんだ。
それが自己管理ができてないで済ますのは、冷たいだろう?」
「俺らは部活したくて高校に来てんだから努力するのは当たり前のことだよ。
特に小林さんは特待生だったんだから俺らよりもっと努力するのは当然だと思う。
怪我したのはかわいそうだとは思うけど、俺らにはどうしようもねえじゃん。
先生、俺たちに何求めてるわけ?」
「・・・・・・そうだよな、感情的になってすまなかった」
俯く俺の肩に手がのった。
「浅倉先生も昔膝を壊して、スポーツを諦めた経験があるんだよ」
見ると、そこにはバレー部の顧問の伊達先生がいた。
伊達先生は、
「だから、つい感情移入してしまったんだと思うぞ。
ほら、分かったらさっさと試合の応援に行きなさい」
と生徒たちを追い払った。
「ありがとうございます」
と言うと、
「浅倉先生、顔恐いよ!笑って笑って」
と肩を叩かれた。
「いてて」
「ははははっ!」
笑いながら片手を上げて歩いていく姿を見送った。
そして。
コンコン。
「失礼します。
教頭先生、今よろしいですか?」
俺はスーツの内ポケットから「退職願」を取り出した。