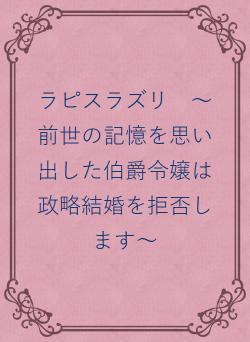「先生」
「ん?」
「そこにあるティッシュ取って」
小林は俯いたまま俺の方を指さした。
俺は小林の頭から手を放し、背面にある机の上のティッシュボックスを渡した。
俺の視線を避けるように俯いたまま顔ごとティッシュで涙を拭いた小林は、
「ふわー!またフラれちゃった!」
と顔を上げた。
「ごめんね、先生。
せっかくお見舞いに来てくれたのに」
「いや。 俺の方こそ、ごめんな」
「先生が謝らないでよ。
怪我してフラれて、やつあたっちゃった」
「八つ当たりくらい、いつでもしていいよ」
「うん。また八つ当たりする。
だから、今度は避けたりしないでね」
「ああ。わかった」
ふふふっと、小林は悲しげに笑った。
「あのね。私、膝の炎症が落ち着いたから、手術するんだ。
そしたらリハビリ。
多分新学期からは学校に行けるみたい」
「そうか。3年だもんな。
クラス替えのある新学期に間に合ってよかったな」
「うん。この前さ、担任が来たんだよ。
普通科に編入することもできるって言われててさ。
だけど、このままスポーツ科に残ってバレー続けたいって、担任に言った」
小林はまっすぐ前を見つめて、ゆっくりと話し続ける。
「バレーの特待生じゃなくなるって。
でも、それでもいい。
それでもいいからバレーをしたい。
私、バレーが好きなんだよ。
だから・・・自分から諦めたくない。
リハビリも、筋トレも頑張る!
頑張って、頑張って、頑張ったら・・・前みたいに打てるようになるよね」
横にいる俺を見上げ、力強い目でじっとこちらを見つめている。
泣きじゃくってしまって真っ赤に充血して晴れた目をしているくせに、なんて力強い瞳をしているのだろう。
「お前・・・かっこいいな」
そう呟いたら、小林は手を振り回し、殴りかかってきた。
「もう!女子高生相手にかっこいいとかありえない!!ムカつく!!」
「褒めてんだろー」
「全然褒めてない!!
失礼すぎ!!」
ブンブン振ってくる両腕を捕まえても、まだ暴れようとするので、両方の手首を持ったまま引っ張った。
「あっ」
頭が俺の胸にぶつかり、小林はピタッと止まって、固まった。
胸にぶつかったまま動かなくなった小林の体をを離すことはできなかった。
だからといって、抱き寄せることもできない。
俺は、掴んでいた手首をゆっくりと離した。
小林の両手が布団に落ちた。
俺の腕も落ちたまま、動けなかった。
唯一触れている、彼女の頭を見下ろした。
好きだ。
心の中で呟いた。