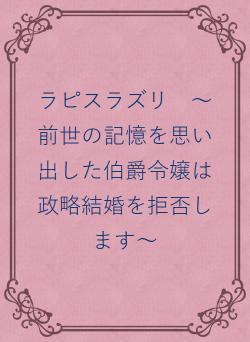随分とたった頃、小林さんは泣き止んだ。
「落ち着いたか?」
「・・・うん。・・・ごめんね、先生」
「いいよ、別に。
送っていく。これ持って」
弁当と鞄を持たせ、小林に背を向けて跪いた。
「え?」
「ほら、おんぶ」
「えー!無理!!重いもん!!」
「大丈夫。俺こう見えて元バスケ部」
「あ。運動してたんだ」
「ほら、早く乗れ!弟、待ってるんだろ?」
「そうだけど」
「お姫様抱っこなんてしねえからな」
「されないからッ!
恥ずかしすぎるよッ!」
小林は恥ずかしそうに俺の背中に乗った。
俺は小林を背負った。
小林は俺の胸の前で鞄を持っていた。
「ちゃんと病院に行って診てもらえ」
「・・・やだ」
「でも歩けないんだろ?
歩けないから、さっき座り込んでいたんだろ?」
「う・・・」
ゆっくりと歩いた。
「俺も、膝壊したんだよ」
「え?」
「俺、小学校からミニバスやっててさ、背も高かったし、結構うまかったんだよ。
でも高校入って俺より背の高いヤツとかゴロゴロいてさ。
必死になって練習した。
2年の時やっとスタメンになれてさ、めちゃくちゃ嬉しかったんだ。
でも、そんなときに試合中に膝をやっちゃってさ。
やっと試合に出れるようになったのに出れませんなんて言いたくなくてさー。
膝が痛くても痛み止め飲んで、シップして・・・誤魔化して練習してた」
「・・・・・」
「でも、結局スタメンもベンチ入りメンバーからも外された。
そんで俺は観客席から3年の引退試合を応援した。
悔しかったなー。
あの時きちんと病院行ってたらって何度も思ったよ」
「・・・」
「小林さんに俺と同じにはなって欲しくない」
「・・・」
「自分でも分かってるんだろ?」
「・・・・」
「行っとけ、病院」
「・・・・・・でも・・・・」
「ん?」
「怖い・・・一人で病院行くの、怖い・・・」
「ついていってやるから」
「本当に?」
「ああ。明日。一緒に行こう」
「うん。ありがとう・・・」
小林さんはぎゅっと俺に抱き着いた。
俺はドキッとしてしまった。
俺は慌てて、それをごまかす。
「首、しまってる」
「あ!ごめん」
小林も慌てて急に俺から離れようとしたから、俺はバランスを崩してしまった。
「危なッ!」
「きゃあ!」
体勢を整えた二人はふうっと息を吐いた。
「じっとしてなさい!」
「はーい」
小林さんはおとなしくおんぶされた。
このまま小林さんの家に着かなければいいのにと思ってしまう。
そして、この気持ちが…『恋』とよく似たこの気持ちを、『恋ではない』と自分に言いきかせる事ができなくなっていたのだった。
「落ち着いたか?」
「・・・うん。・・・ごめんね、先生」
「いいよ、別に。
送っていく。これ持って」
弁当と鞄を持たせ、小林に背を向けて跪いた。
「え?」
「ほら、おんぶ」
「えー!無理!!重いもん!!」
「大丈夫。俺こう見えて元バスケ部」
「あ。運動してたんだ」
「ほら、早く乗れ!弟、待ってるんだろ?」
「そうだけど」
「お姫様抱っこなんてしねえからな」
「されないからッ!
恥ずかしすぎるよッ!」
小林は恥ずかしそうに俺の背中に乗った。
俺は小林を背負った。
小林は俺の胸の前で鞄を持っていた。
「ちゃんと病院に行って診てもらえ」
「・・・やだ」
「でも歩けないんだろ?
歩けないから、さっき座り込んでいたんだろ?」
「う・・・」
ゆっくりと歩いた。
「俺も、膝壊したんだよ」
「え?」
「俺、小学校からミニバスやっててさ、背も高かったし、結構うまかったんだよ。
でも高校入って俺より背の高いヤツとかゴロゴロいてさ。
必死になって練習した。
2年の時やっとスタメンになれてさ、めちゃくちゃ嬉しかったんだ。
でも、そんなときに試合中に膝をやっちゃってさ。
やっと試合に出れるようになったのに出れませんなんて言いたくなくてさー。
膝が痛くても痛み止め飲んで、シップして・・・誤魔化して練習してた」
「・・・・・」
「でも、結局スタメンもベンチ入りメンバーからも外された。
そんで俺は観客席から3年の引退試合を応援した。
悔しかったなー。
あの時きちんと病院行ってたらって何度も思ったよ」
「・・・」
「小林さんに俺と同じにはなって欲しくない」
「・・・」
「自分でも分かってるんだろ?」
「・・・・」
「行っとけ、病院」
「・・・・・・でも・・・・」
「ん?」
「怖い・・・一人で病院行くの、怖い・・・」
「ついていってやるから」
「本当に?」
「ああ。明日。一緒に行こう」
「うん。ありがとう・・・」
小林さんはぎゅっと俺に抱き着いた。
俺はドキッとしてしまった。
俺は慌てて、それをごまかす。
「首、しまってる」
「あ!ごめん」
小林も慌てて急に俺から離れようとしたから、俺はバランスを崩してしまった。
「危なッ!」
「きゃあ!」
体勢を整えた二人はふうっと息を吐いた。
「じっとしてなさい!」
「はーい」
小林さんはおとなしくおんぶされた。
このまま小林さんの家に着かなければいいのにと思ってしまう。
そして、この気持ちが…『恋』とよく似たこの気持ちを、『恋ではない』と自分に言いきかせる事ができなくなっていたのだった。