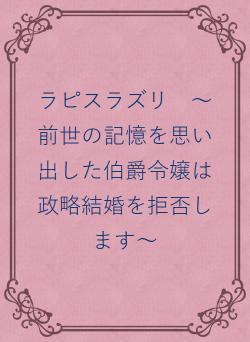夏休みが終わり新学期が始まった。
いつものように仕事帰りにスーパーへ寄って、ビールと弁当を買った。
スーパーを出てしばらく歩いたところで、公園の入り口近くにあるベンチに座り込んでいる小林さんを見つけた。
「小林さん?」
俺の声に驚き、肩をびくっと震わせた小林は、
「もう、先生か。驚かさないでよ」
俺を見上げて恨めしそうに言う。
「もう真っ暗だぞ。こんなところに座り込んで、危ないだろ」
「こんな時間に、こんなところに、好きで座り込むわけないじゃない」
「そりゃ、そうか」
右膝を摩る小林の横にしゃがむ。
「膝が痛むのか?」
「うん・・・」
制服のスカートから覗く足に目をやるが、傷はなかった。
「痛いのもあるんだけど・・・」
「?」
「時々、膝がカコンって抜けそうにになるの」
膝が抜ける・・・
「病院は?」
「行ってない」
「なんで?」
「行ったら『安静に』とか『練習を休め』とか言われるもん」
「分かっているなら、練習を休んで安静にしたらいいんじゃないか?」
「そんなの、無理!!
だって、あたしのせいで負けたんだよ!」
小林さんはイラっとしたのか声を荒げた。
「・・・小林さんのせいって、どういう意味だ?」
彼女の顔を見つめた。
・・・・小林さんは大きな瞳に涙を浮かべて、歯を食いしばっていた。
「小林さんのせいで負けたって?」
「……あたしがブロックに掴まったから…スパイクが決まんなくて…先輩の最後の試合だったのに…」
「・・・県予選のことか?」
小林さんはこくんと小さく頷いた。
そして流れる涙を掌で拭った。
「小林さんのせいじゃないだろ・・・」
拭っても拭ってもボロボロと溢れだしてくる涙を止めることができないのか、小林さんは顔を両手で覆って俯いた。
震える指先に気付く。
座っている小林さんの向かいに膝をつき、肩に触れた。
震える肩をポンポンと叩く。
「うううううう」
振り絞るような小声で唸りながら泣き続ける小林さんに、ポンポンとゆっくり背中を叩いた。
「なぁ、小林さんの仲間はお前を責めたのか?」
ブンブンと首を振って否定した。
「きっと誰も小林さんのせいだなんて思ってないんだよ」
ずっと苦しかったんだろうな。
彼女が落ち着くまで、俺はずっとその背を優しく叩いた。
いつものように仕事帰りにスーパーへ寄って、ビールと弁当を買った。
スーパーを出てしばらく歩いたところで、公園の入り口近くにあるベンチに座り込んでいる小林さんを見つけた。
「小林さん?」
俺の声に驚き、肩をびくっと震わせた小林は、
「もう、先生か。驚かさないでよ」
俺を見上げて恨めしそうに言う。
「もう真っ暗だぞ。こんなところに座り込んで、危ないだろ」
「こんな時間に、こんなところに、好きで座り込むわけないじゃない」
「そりゃ、そうか」
右膝を摩る小林の横にしゃがむ。
「膝が痛むのか?」
「うん・・・」
制服のスカートから覗く足に目をやるが、傷はなかった。
「痛いのもあるんだけど・・・」
「?」
「時々、膝がカコンって抜けそうにになるの」
膝が抜ける・・・
「病院は?」
「行ってない」
「なんで?」
「行ったら『安静に』とか『練習を休め』とか言われるもん」
「分かっているなら、練習を休んで安静にしたらいいんじゃないか?」
「そんなの、無理!!
だって、あたしのせいで負けたんだよ!」
小林さんはイラっとしたのか声を荒げた。
「・・・小林さんのせいって、どういう意味だ?」
彼女の顔を見つめた。
・・・・小林さんは大きな瞳に涙を浮かべて、歯を食いしばっていた。
「小林さんのせいで負けたって?」
「……あたしがブロックに掴まったから…スパイクが決まんなくて…先輩の最後の試合だったのに…」
「・・・県予選のことか?」
小林さんはこくんと小さく頷いた。
そして流れる涙を掌で拭った。
「小林さんのせいじゃないだろ・・・」
拭っても拭ってもボロボロと溢れだしてくる涙を止めることができないのか、小林さんは顔を両手で覆って俯いた。
震える指先に気付く。
座っている小林さんの向かいに膝をつき、肩に触れた。
震える肩をポンポンと叩く。
「うううううう」
振り絞るような小声で唸りながら泣き続ける小林さんに、ポンポンとゆっくり背中を叩いた。
「なぁ、小林さんの仲間はお前を責めたのか?」
ブンブンと首を振って否定した。
「きっと誰も小林さんのせいだなんて思ってないんだよ」
ずっと苦しかったんだろうな。
彼女が落ち着くまで、俺はずっとその背を優しく叩いた。