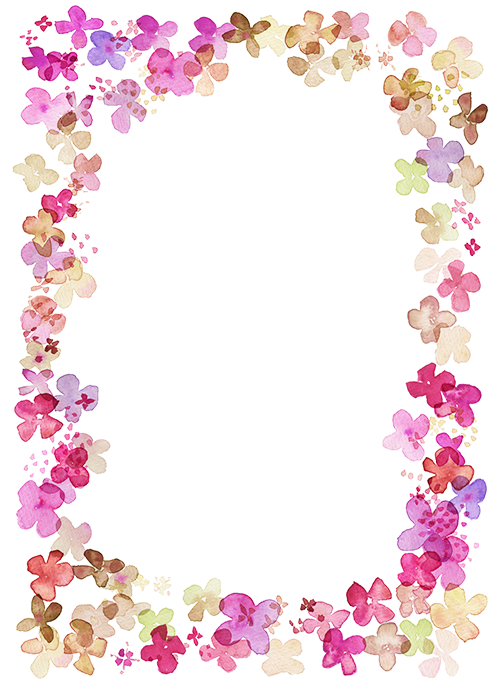「これは政略結婚になる。俺からの愛情は期待しないで欲しい」
クロード・ヴェリタス侯爵は、その言葉を精巧な彫像のような完璧な顔立ちで冷たく言い放った。
高価な王宮の応接室の一室。陽光が、彼の銀糸のようなブロンドに複雑な輝きを与えている。その絶世の美貌は、本来ならば相対する女性を赤面させ、動揺させるには十分すぎる威圧感があるはずだった。
しかし、侯爵と向かい合うアデリーナ・フォレスト辺境伯令嬢は、事務仕事の合間にここに来たのか、くすんだ焦げ茶色の文官の制服姿のままだ。襟元はしっかりとボタンで留められ、その顔には化粧っ気一つない。濃いこげ茶色の髪はぼさぼさで、適当に寄り集められた落ち葉のようだった。
「それは分かりました。政略結婚であることに異論はありません」
アデリーナは、王宮御用達の陶器で出された紅茶のカップを静かに持ち上げ、一口啜った。
「で、私からの条件については、準備して頂けましたか?」
彼女は、給料交渉でもするかのように淀みなくそう告げた。その瞳には侯爵の美貌ではなく、紙幣や領地の帳簿を眺める時と同じ真剣さだけが宿っている。クロードは、一瞬言葉を失った。これほどまでに、自分の美しさが無効化されたのは初めてかもしれない。
「いや、それはこれから……」
クロードが弱々しく答えると、アデリーナは静かに紅茶をテーブルに置いた。カタン、と小さな音が響く。そして、彼女は膝の上で両手を揃え、まるで上官への報告をするかのように姿勢を正した。
「そうですか……では、侯爵様」
アデリーナは、普段の書類仕事では見せないような、清々しいほどの満面の笑みを浮かべた。その表情に、クロードは背筋に冷たいものを感じた。
「条件が整うまで婚約はしない、ということでよろしいですね?」
その笑顔は、「契約が完了するまでサービスの提供は始めません」と告げる、凄腕の商人のようだった。
クロードは自分の美貌に目がくらんで大騒ぎする女たちを避けるため、貧しく堅物で男に興味のない、無害な女を選んだはずだった。しかし、目の前の女性は美貌に動じるどころか、自分の立場すら利用して実利のみを追求する、恐るべき相手だったのだ。
(早まった……か?)
その事実に気付き、クロードは思わず額に手を当てた。
クロード・ヴェリタス侯爵は、執務室の扉を開けるなりよろめいた。
(あれは、なんだったんだ……?)
絶世の美貌と、侯爵という高い地位。若くして宰相という地位に付き、王宮で熱心に働く彼の人生は、“女性が自分に恋焦がれ、自ら寄ってくる”という極めて偏った常識で構成されていた。だからこそ、女性からの過剰なアプローチに辟易し、噂にたがわぬ「男に興味のない真面目な堅物」を結婚相手に選んだのだ。だが、今日初めて、彼の常識は根本から覆された。
執務室の奥で書類を整理していた側近のユーリ・ハーディンは、主人の異変にすぐ気が付いた。
「どうしたんですか、クロード様? まるで幽霊でも見たような青い顔をして」
彼は軽口を叩きながら、椅子から立ち上がった。ユーリはクロードの数少ない理解者であり、女性問題に悩む彼のために、アデリーナの噂を嗅ぎつけてきた張本人だ。
「まさか……やはり、あの令嬢もダメでしたか?」
ユーリはいつものように訊ねた。この質問を何度繰り返したことか。これまでクロードが見合いと称して会ってきた女性の誰もが、彼の顔を見た瞬間に冷静さを失い、ひどい時には抱きついて騒ぎ出す者までいた。そのたびにクロードは恐怖に慄いては、影でユーリに「この世に、俺の顔を見て動じない女はいないのか!」と愚痴を言うのだ。
クロードは返事をせず、壁際に置かれた高級な一人掛けソファに深く腰を沈めた。
「……断られた」
絞り出したその言葉は、ほとんどかすれていた。ユーリは動きを止め、眉間に皺を寄せた。主の言葉が、あまりにも予想外だったからだ。
「はい?」
「断られたんだ!」
クロードはソファの上で勢いよく身じろぎ、頭を抱えながら叫んだ。
「この俺が! 女性から! 断られたんだ! まさか、顔を見ただけで断られるとは……いや、顔は関係なかった!」
ユーリは困惑した。
自分の美貌に目が眩まれて錯乱されるのならともかく、断られる? それは完全な計算外だった。確かに、あの女性の求めた“条件”とは今まで聞いたこともないような突拍子もないものだった。しかし、クロードの美貌を見れば話は変わると思っていたのだ。
ユーリに話の続きを促され、クロードは王宮の応接室での一部始終を、トラウマを語るかのように詳しく話し始めた。
「……今、婚約はしない、と言ったのか?」
クロードが驚いて聞き返した時、アデリーナは当然でしょうと言いたげな顔で、つらつらと冷静な理屈を述べた。
「政略結婚と言うことは、そういうお仕事、依頼と言う事でしょう? それならば報酬がつきものです。報酬も準備されていない方と契約なんて出来ません」
彼女は最高の笑顔を浮かべた。その笑顔は、侯爵の美貌に引き寄せられた女達とは違う冷酷さをたたえていた。
「本当に、あんな条件を満たせと?」
「はい。“私の弟妹達に良い結婚相手を用意する”……侯爵様ほどの地位も人脈もあれば、可能ではないでしょうか?」
そう。この目の前の女性が出した条件とは、自分の六人の弟妹達の縁談だった。調べたところによると、彼女の両親は二年前に他界している。おせっかいな親戚がしゃしゃり出て来ない限り、彼女自身の縁談さえ準備してくれる人はいないのだ。自分達で何とか頑張るしかない。それが自分が縁談を申し込んだことで、一人分解消された。それだけで感謝されるくらいだ。
それが、縁談の打診をしてみれば“他の弟妹の分もお願いします”と来たもんだ。てっきり婚約後にでも手伝って欲しい程度の話だと思い、顔を合わせて話してみようとすればこれ。
「私の弟妹の誰か一人でも、お見合いさせる準備が整ったらまたいらして下さい」
そう言いながら、アデリーナはさっさと身支度を済ませて立ち上がる。
「あ、弟妹の情報をリストに纏めてありますので、必要でしたらお声掛け下さいね」
家に置いてありますので、今は手元にありません。何分、今朝出勤後に急に来たお話でしたから、という嫌味も忘れない。ずかずかと出入り口のドアに向かって歩きながら、彼女は思い出したようにこちらへ振り向く。
「では、私は仕事に戻りますので」
彼女はクロードの返答を待たず、あっという間に応接室からいなくなってしまったのだ。
「あれは、女ではない……書類と帳簿で出来た機械だ……」
クロードはソファに沈み込み、ぐったりと項垂れた。その美しい顔には、精神的な疲労が濃く張り付いている。女性たちの過激なアプローチは、彼の優秀な頭脳と集中力を削ぐ最大の重荷だった。それを解消するための話が、こんな面倒ごとになってしまうとは。
ユーリは、目の前で項垂れる完璧な美貌の主と、冷徹に契約を破棄した文官令嬢の姿を想像し、思わず吹き出しそうになるのを必死で耐えた。
「なるほど……それで、アデリーナ嬢の条件を受けますか?」
「受けるしかない、だろうな……」
クロードは天を仰いだまま答えた。
「俺の美貌にかこつけて、感情的にあれこれしてこないだけマシだ。あんな女性は、他にはいない」
彼の言葉には妥協と諦観が入り混じっていた。自分の美貌に当てられて事件すら起こしかねない女性達と、徹底的に自分の利益を追求する冷血漢のアデリーナ。どちらがマシかと言われれば、どう考えても後者の方だ。しかも、今まで何度かお見合いはしていたが全敗。もう他に、ある程度の地位がある妙齢の女性など残ってはいない。
「では、頑張るしかないですね。縁談のリスト作成と、相手方との交渉ですね」
「……」
クロードはユーリの言葉を受けながら、再び深く天を仰いだ。自分の結婚相手すら満足に探せないというのに、いきなり他人の縁談を六件も纏めなければならないなんて。
「この国に、まともな女はいないのか……?」
その問いは、己の美貌に対する、クロードの深い呪いにも似た独り言だった。
クロード・ヴェリタス侯爵は、その言葉を精巧な彫像のような完璧な顔立ちで冷たく言い放った。
高価な王宮の応接室の一室。陽光が、彼の銀糸のようなブロンドに複雑な輝きを与えている。その絶世の美貌は、本来ならば相対する女性を赤面させ、動揺させるには十分すぎる威圧感があるはずだった。
しかし、侯爵と向かい合うアデリーナ・フォレスト辺境伯令嬢は、事務仕事の合間にここに来たのか、くすんだ焦げ茶色の文官の制服姿のままだ。襟元はしっかりとボタンで留められ、その顔には化粧っ気一つない。濃いこげ茶色の髪はぼさぼさで、適当に寄り集められた落ち葉のようだった。
「それは分かりました。政略結婚であることに異論はありません」
アデリーナは、王宮御用達の陶器で出された紅茶のカップを静かに持ち上げ、一口啜った。
「で、私からの条件については、準備して頂けましたか?」
彼女は、給料交渉でもするかのように淀みなくそう告げた。その瞳には侯爵の美貌ではなく、紙幣や領地の帳簿を眺める時と同じ真剣さだけが宿っている。クロードは、一瞬言葉を失った。これほどまでに、自分の美しさが無効化されたのは初めてかもしれない。
「いや、それはこれから……」
クロードが弱々しく答えると、アデリーナは静かに紅茶をテーブルに置いた。カタン、と小さな音が響く。そして、彼女は膝の上で両手を揃え、まるで上官への報告をするかのように姿勢を正した。
「そうですか……では、侯爵様」
アデリーナは、普段の書類仕事では見せないような、清々しいほどの満面の笑みを浮かべた。その表情に、クロードは背筋に冷たいものを感じた。
「条件が整うまで婚約はしない、ということでよろしいですね?」
その笑顔は、「契約が完了するまでサービスの提供は始めません」と告げる、凄腕の商人のようだった。
クロードは自分の美貌に目がくらんで大騒ぎする女たちを避けるため、貧しく堅物で男に興味のない、無害な女を選んだはずだった。しかし、目の前の女性は美貌に動じるどころか、自分の立場すら利用して実利のみを追求する、恐るべき相手だったのだ。
(早まった……か?)
その事実に気付き、クロードは思わず額に手を当てた。
クロード・ヴェリタス侯爵は、執務室の扉を開けるなりよろめいた。
(あれは、なんだったんだ……?)
絶世の美貌と、侯爵という高い地位。若くして宰相という地位に付き、王宮で熱心に働く彼の人生は、“女性が自分に恋焦がれ、自ら寄ってくる”という極めて偏った常識で構成されていた。だからこそ、女性からの過剰なアプローチに辟易し、噂にたがわぬ「男に興味のない真面目な堅物」を結婚相手に選んだのだ。だが、今日初めて、彼の常識は根本から覆された。
執務室の奥で書類を整理していた側近のユーリ・ハーディンは、主人の異変にすぐ気が付いた。
「どうしたんですか、クロード様? まるで幽霊でも見たような青い顔をして」
彼は軽口を叩きながら、椅子から立ち上がった。ユーリはクロードの数少ない理解者であり、女性問題に悩む彼のために、アデリーナの噂を嗅ぎつけてきた張本人だ。
「まさか……やはり、あの令嬢もダメでしたか?」
ユーリはいつものように訊ねた。この質問を何度繰り返したことか。これまでクロードが見合いと称して会ってきた女性の誰もが、彼の顔を見た瞬間に冷静さを失い、ひどい時には抱きついて騒ぎ出す者までいた。そのたびにクロードは恐怖に慄いては、影でユーリに「この世に、俺の顔を見て動じない女はいないのか!」と愚痴を言うのだ。
クロードは返事をせず、壁際に置かれた高級な一人掛けソファに深く腰を沈めた。
「……断られた」
絞り出したその言葉は、ほとんどかすれていた。ユーリは動きを止め、眉間に皺を寄せた。主の言葉が、あまりにも予想外だったからだ。
「はい?」
「断られたんだ!」
クロードはソファの上で勢いよく身じろぎ、頭を抱えながら叫んだ。
「この俺が! 女性から! 断られたんだ! まさか、顔を見ただけで断られるとは……いや、顔は関係なかった!」
ユーリは困惑した。
自分の美貌に目が眩まれて錯乱されるのならともかく、断られる? それは完全な計算外だった。確かに、あの女性の求めた“条件”とは今まで聞いたこともないような突拍子もないものだった。しかし、クロードの美貌を見れば話は変わると思っていたのだ。
ユーリに話の続きを促され、クロードは王宮の応接室での一部始終を、トラウマを語るかのように詳しく話し始めた。
「……今、婚約はしない、と言ったのか?」
クロードが驚いて聞き返した時、アデリーナは当然でしょうと言いたげな顔で、つらつらと冷静な理屈を述べた。
「政略結婚と言うことは、そういうお仕事、依頼と言う事でしょう? それならば報酬がつきものです。報酬も準備されていない方と契約なんて出来ません」
彼女は最高の笑顔を浮かべた。その笑顔は、侯爵の美貌に引き寄せられた女達とは違う冷酷さをたたえていた。
「本当に、あんな条件を満たせと?」
「はい。“私の弟妹達に良い結婚相手を用意する”……侯爵様ほどの地位も人脈もあれば、可能ではないでしょうか?」
そう。この目の前の女性が出した条件とは、自分の六人の弟妹達の縁談だった。調べたところによると、彼女の両親は二年前に他界している。おせっかいな親戚がしゃしゃり出て来ない限り、彼女自身の縁談さえ準備してくれる人はいないのだ。自分達で何とか頑張るしかない。それが自分が縁談を申し込んだことで、一人分解消された。それだけで感謝されるくらいだ。
それが、縁談の打診をしてみれば“他の弟妹の分もお願いします”と来たもんだ。てっきり婚約後にでも手伝って欲しい程度の話だと思い、顔を合わせて話してみようとすればこれ。
「私の弟妹の誰か一人でも、お見合いさせる準備が整ったらまたいらして下さい」
そう言いながら、アデリーナはさっさと身支度を済ませて立ち上がる。
「あ、弟妹の情報をリストに纏めてありますので、必要でしたらお声掛け下さいね」
家に置いてありますので、今は手元にありません。何分、今朝出勤後に急に来たお話でしたから、という嫌味も忘れない。ずかずかと出入り口のドアに向かって歩きながら、彼女は思い出したようにこちらへ振り向く。
「では、私は仕事に戻りますので」
彼女はクロードの返答を待たず、あっという間に応接室からいなくなってしまったのだ。
「あれは、女ではない……書類と帳簿で出来た機械だ……」
クロードはソファに沈み込み、ぐったりと項垂れた。その美しい顔には、精神的な疲労が濃く張り付いている。女性たちの過激なアプローチは、彼の優秀な頭脳と集中力を削ぐ最大の重荷だった。それを解消するための話が、こんな面倒ごとになってしまうとは。
ユーリは、目の前で項垂れる完璧な美貌の主と、冷徹に契約を破棄した文官令嬢の姿を想像し、思わず吹き出しそうになるのを必死で耐えた。
「なるほど……それで、アデリーナ嬢の条件を受けますか?」
「受けるしかない、だろうな……」
クロードは天を仰いだまま答えた。
「俺の美貌にかこつけて、感情的にあれこれしてこないだけマシだ。あんな女性は、他にはいない」
彼の言葉には妥協と諦観が入り混じっていた。自分の美貌に当てられて事件すら起こしかねない女性達と、徹底的に自分の利益を追求する冷血漢のアデリーナ。どちらがマシかと言われれば、どう考えても後者の方だ。しかも、今まで何度かお見合いはしていたが全敗。もう他に、ある程度の地位がある妙齢の女性など残ってはいない。
「では、頑張るしかないですね。縁談のリスト作成と、相手方との交渉ですね」
「……」
クロードはユーリの言葉を受けながら、再び深く天を仰いだ。自分の結婚相手すら満足に探せないというのに、いきなり他人の縁談を六件も纏めなければならないなんて。
「この国に、まともな女はいないのか……?」
その問いは、己の美貌に対する、クロードの深い呪いにも似た独り言だった。