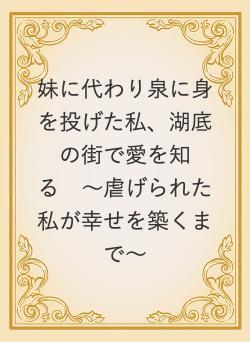紅茶の二杯目を半分ほど飲んだ時、最初に案内してくれた執事が現れた。どうやら、ガメス公爵様の仕事がひと段落したようで、お会いになるのだとか。
私が立ち上がると同時に、部屋の扉が開かれる。そして部屋に入室してきた屈強な男性と目が合った……あら?
予想よりも随分と若い男性である。確か公爵様は六十歳と聞いていたのだけれど。
公爵様も私の顔を見ているが……あら、耳が少し赤いような……いえ、気のせいね。
……けれど、公爵を見ていた執事のほうが、むしろ驚いた顔をしているように見える。
表情をあまり変えない方なのかしら。もしかして、公爵様が珍しい顔をしたのだろうか? 私には分からないわね。
私が礼を執ると、呆然としていた彼は正気を取り戻したのか、口を開いた。
「……ご足労いただき感謝する。私が現当主であるレオネル・エドワード・ガメスだ」
礼をとった後、私は隣にやってきた執事から手帳とペンを手渡された。
ありがたいわ、これで筆談ができるわね。私は彼に軽く頭を下げると、手帳に文字を書いていく。
ふと気がつけば、私の書く姿を見ていた公爵様が首を傾げていた。大きな熊さんのようで可愛らしいく見えるわね。
ただ、次に紡いだ彼の言葉で私は書く手を止めた。
「書いている途中に済まない。君は、本当にブレンダ嬢なのか?」
「旦那様! 失礼ではありませんか!」
血の気の引いた顔で執事が声を上げる。まあ、普通は失礼な行動でしょうけれど……私にとっては、渡りに船。私は頁をめくり、白紙の部分に書き始めた。
『どうしてそう思われたのですか?』
その部分を見せると、公爵様は少しだけ悩みながら話してくれた。
「いや……そうだな、私はかつて、皇帝陛下の護衛として王国に招かれた。その際に顔を揃えていた王侯貴族達のような視線――あれは異物を見るようなものだったな……。君はそのような目で我々を見ていないからだ。そしてもうひとつの違和感だが、私は君をどこかで見た事がある気がしてならなかった。……ああ、そうだ、思い出したぞ。我が国の王城にある絵画が、君の面差しとそっくりなのだ。王国の公爵家へ嫁がれた、皇女様にな」
私が立ち上がると同時に、部屋の扉が開かれる。そして部屋に入室してきた屈強な男性と目が合った……あら?
予想よりも随分と若い男性である。確か公爵様は六十歳と聞いていたのだけれど。
公爵様も私の顔を見ているが……あら、耳が少し赤いような……いえ、気のせいね。
……けれど、公爵を見ていた執事のほうが、むしろ驚いた顔をしているように見える。
表情をあまり変えない方なのかしら。もしかして、公爵様が珍しい顔をしたのだろうか? 私には分からないわね。
私が礼を執ると、呆然としていた彼は正気を取り戻したのか、口を開いた。
「……ご足労いただき感謝する。私が現当主であるレオネル・エドワード・ガメスだ」
礼をとった後、私は隣にやってきた執事から手帳とペンを手渡された。
ありがたいわ、これで筆談ができるわね。私は彼に軽く頭を下げると、手帳に文字を書いていく。
ふと気がつけば、私の書く姿を見ていた公爵様が首を傾げていた。大きな熊さんのようで可愛らしいく見えるわね。
ただ、次に紡いだ彼の言葉で私は書く手を止めた。
「書いている途中に済まない。君は、本当にブレンダ嬢なのか?」
「旦那様! 失礼ではありませんか!」
血の気の引いた顔で執事が声を上げる。まあ、普通は失礼な行動でしょうけれど……私にとっては、渡りに船。私は頁をめくり、白紙の部分に書き始めた。
『どうしてそう思われたのですか?』
その部分を見せると、公爵様は少しだけ悩みながら話してくれた。
「いや……そうだな、私はかつて、皇帝陛下の護衛として王国に招かれた。その際に顔を揃えていた王侯貴族達のような視線――あれは異物を見るようなものだったな……。君はそのような目で我々を見ていないからだ。そしてもうひとつの違和感だが、私は君をどこかで見た事がある気がしてならなかった。……ああ、そうだ、思い出したぞ。我が国の王城にある絵画が、君の面差しとそっくりなのだ。王国の公爵家へ嫁がれた、皇女様にな」