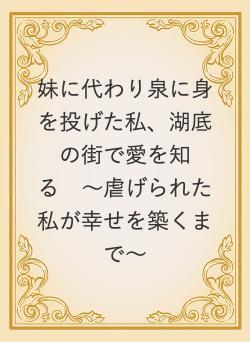しかしその日から一週間。私は四個目の壁を越える事ができていない。魔法陣を魔宝石に書き込むのが困難を極めていたのである。
セヴァルに教えてもらった方法は、魔宝石のカットの部分にひとつひとつ魔法陣を書き込むやり方だ。正面と裏部分はそのまま置いて魔法陣を書き込む事ができるので問題ない。しかし、三つ目以降は斜めの面に書き込まなくてはならなくなるのだ。
魔法陣は繊細で、少しの誤差も許されない。ズレがあると、正しく動作しない可能性が高いためだ。
そのため三つまでは集中力が続いても、四つ目になると魔法陣が上手く描けずに失敗するという事が多くなっていた。正しいと思っていても、何らかの歪みがあるためか、魔法陣が定着しないのである。
私たちは行き詰っていた。
その日、所長たち含めた研究員たちで、他に良い方法がないかと案を出し合っていた。私も参加していたのだけれど、昼食になったので一度解散したのだ。食堂へ行くと、ヘンリーが公爵様を呼びに行こうとしていたところだったらしい。折角だからと私が彼を呼びに行くことにした。
執務室にたどり着き扉を叩くと、中から公爵様の声が聞こえたため、私は部屋へと入っていく。
「少々待ってくれ」と言われた私は、執務机の手前にあるソファーへと座り、公爵様を待つことにした。公爵様の執務机には大量の書類が積まれている。彼は一枚取って内容を確認後、ペンで何かを書いてから反対の山へと乗せていく。以前私も行っていた業務を懐かしく思う。
しばらくして目処が付いたのか、公爵様はペンを置いて伸びをした。私も書類仕事をしていたから分かるけれど、どうしても肩が凝ってしまうのよね。そんな時に公爵様と私の視線が交わった。「あ」という表情で私を見ている。集中されていて、私がいる事に気が付かなかったらしい。
「いや……すまない。みっともなかったな」
「いえ、私も書類仕事の後はよく両手を伸ばしていましたから」
「同じ姿勢ばかり取っていると、肩が凝るからな」
どうやら公爵様も私と同じような悩みを抱えていたらしい。しばらく肩の凝りと書類仕事の大変さを共有する私たち。そんな中、彼は書類の山を見ながら肩をすくめて言った。
「本当にこの書類の束には参るな。この束がこう圧縮されたら、山が少なく見えて気持ちだけでも軽くなるだろうか?」
公爵様は書類の束を上から押すような仕草をする。彼の行動に私は目を丸くした後、思わず声を上げて笑ってしまった。彼もこんな冗談みたいな事を言うんだな、と思ったのだ。
「書類の枚数は変わらず山が小さくなるだけでしたら、山が減らずに疲れてしまいませんか?」
「……うむ、そ、そうかも……しれない」
勢いよく顔を逸らした公爵様。心なしか狼狽いているように見えるのは気のせいだろうか。そしてふと、思っていた事を話した。
「それか書類のサインの位置が全て同じ場所にあれば、楽かもしれませんね。今だとサイン欄を探すのが大変そうですから」
しばらく公爵様を見ていて、サインを書いている位置が違うように思えたのだ。思えば王国も一緒だった。いつもサインの位置がどこか探したものだ。一度そう告げたのだが、話すら聞いてくれなかった記憶があった。
公爵様も紙の上部に書いている事もあれば、右下、左下に書いている事もあった。そこが一致していれば、少しくらいは時間の短縮になりそうだ。
そう無意識に呟いていたのだが、返事がこない。どうしたのだろうか、と思って見ると、公爵様は私を見たまま固まっていた。
セヴァルに教えてもらった方法は、魔宝石のカットの部分にひとつひとつ魔法陣を書き込むやり方だ。正面と裏部分はそのまま置いて魔法陣を書き込む事ができるので問題ない。しかし、三つ目以降は斜めの面に書き込まなくてはならなくなるのだ。
魔法陣は繊細で、少しの誤差も許されない。ズレがあると、正しく動作しない可能性が高いためだ。
そのため三つまでは集中力が続いても、四つ目になると魔法陣が上手く描けずに失敗するという事が多くなっていた。正しいと思っていても、何らかの歪みがあるためか、魔法陣が定着しないのである。
私たちは行き詰っていた。
その日、所長たち含めた研究員たちで、他に良い方法がないかと案を出し合っていた。私も参加していたのだけれど、昼食になったので一度解散したのだ。食堂へ行くと、ヘンリーが公爵様を呼びに行こうとしていたところだったらしい。折角だからと私が彼を呼びに行くことにした。
執務室にたどり着き扉を叩くと、中から公爵様の声が聞こえたため、私は部屋へと入っていく。
「少々待ってくれ」と言われた私は、執務机の手前にあるソファーへと座り、公爵様を待つことにした。公爵様の執務机には大量の書類が積まれている。彼は一枚取って内容を確認後、ペンで何かを書いてから反対の山へと乗せていく。以前私も行っていた業務を懐かしく思う。
しばらくして目処が付いたのか、公爵様はペンを置いて伸びをした。私も書類仕事をしていたから分かるけれど、どうしても肩が凝ってしまうのよね。そんな時に公爵様と私の視線が交わった。「あ」という表情で私を見ている。集中されていて、私がいる事に気が付かなかったらしい。
「いや……すまない。みっともなかったな」
「いえ、私も書類仕事の後はよく両手を伸ばしていましたから」
「同じ姿勢ばかり取っていると、肩が凝るからな」
どうやら公爵様も私と同じような悩みを抱えていたらしい。しばらく肩の凝りと書類仕事の大変さを共有する私たち。そんな中、彼は書類の山を見ながら肩をすくめて言った。
「本当にこの書類の束には参るな。この束がこう圧縮されたら、山が少なく見えて気持ちだけでも軽くなるだろうか?」
公爵様は書類の束を上から押すような仕草をする。彼の行動に私は目を丸くした後、思わず声を上げて笑ってしまった。彼もこんな冗談みたいな事を言うんだな、と思ったのだ。
「書類の枚数は変わらず山が小さくなるだけでしたら、山が減らずに疲れてしまいませんか?」
「……うむ、そ、そうかも……しれない」
勢いよく顔を逸らした公爵様。心なしか狼狽いているように見えるのは気のせいだろうか。そしてふと、思っていた事を話した。
「それか書類のサインの位置が全て同じ場所にあれば、楽かもしれませんね。今だとサイン欄を探すのが大変そうですから」
しばらく公爵様を見ていて、サインを書いている位置が違うように思えたのだ。思えば王国も一緒だった。いつもサインの位置がどこか探したものだ。一度そう告げたのだが、話すら聞いてくれなかった記憶があった。
公爵様も紙の上部に書いている事もあれば、右下、左下に書いている事もあった。そこが一致していれば、少しくらいは時間の短縮になりそうだ。
そう無意識に呟いていたのだが、返事がこない。どうしたのだろうか、と思って見ると、公爵様は私を見たまま固まっていた。