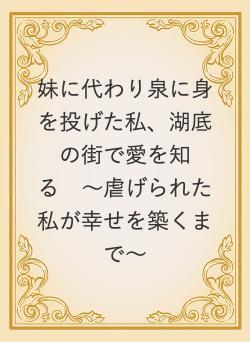「私の母はいつも『頑張りなさい、そうすれば貴女に幸せがやってくる』と私に言い聞かせていました。正直にいいますと、私が義妹の身代わりとして帝国に嫁ぐと聞いた時は、母の言葉を疑いましたが……今は違います」
心からここへと来て良かったと思っている。微笑んで伝えれば、ユーイン殿下は良かったと言わんばかりに胸を撫で下ろす。彼は私の境遇を報告で知っていたらしい。何もできなかった事が一番心苦しかった、と言ってくれた。それだけで過去の私の心は救われた気がする。
そんな気持ちを受け入れる事ができるのも、公爵家の皆さん……特に公爵様のお陰なのかもしれない。
ユーイン殿下は私の表情で、何かを伝える決意をしたのか一通の手紙を出した。それは見慣れた紋章が封筒に押されている。それは、デヴァイン王国のものだった。
「エスペランサ嬢ならこの手紙の内容を察する事ができるだろうが……数日前に王国で王太子とエスペランサ嬢の結婚が数年後に行われると発表された。まあ、このエスペランサ嬢と書かれているのは、義妹のブレンダという娘で間違いないと報告が来ている。エスペランサ嬢もその認識で良いだろうか?」
「はい。私が婚約を白紙にされた時は、そのような話でした」
今も変わっていなければ、ブレンダが王太子妃のはずだ。
「そうか、元々はこちらに来る予定だったのは、義妹だったか。姿絵もエスペランサ嬢のものだったから、名前は忘れていたな……」
公爵様が思わず、と言ったように呟く。
「本当にブレンダという女がこちらに来られても困惑しただろうけど。まぁ、念には念を入れて公爵家の代替わりは情報統制を行なっていたから、あちらには先代に嫁ぐと思われていただろうがな」
ユーイン殿下は軽く身をすくめる。予言の通りに準備をしていたのだから、その根底がひっくり返る……なんて事になったら、帝国も混乱に陥っていた可能性もあったでしょうね。最終的には、予言の通りに事が運んでいるようだけれど。
やはり衝突は避けられないのだな、と私は思った。まあ、仕方ないわよね……王国の者は歩み寄りを一切しないもの。
「今後、王国と帝国の関係に溝が入るのは確実だ。まあ、あちらさんは禁呪が効いていると誤認しているままでいてもらうよう私たちも取り計らう予定なのだが……ひとつ問題があってな。二ヶ月後から社交界が始まるだろう? そこに王国と連なる者が参加するようだ」
「王国に連なる者?」
最初は密偵かと思ったのだが、どうやらそうではないらしい。帝国に王国の放った斥候はいないのだとか。
王国の者は周辺国を『デヴァイン大帝国の血を継がない野蛮な者』と認識しており、そんな彼らが何をしていようとも、大帝国の正式な血統を維持している王国の者に敵うはずがないと考えているのだ。そのため、周辺国が行うような情報収集の類は行わないのだという。
「傲慢ですね」
「まあ、私たちはあっちが勝手に油断してくれているのをありがたいと思うだけだ。お陰で王国へと入り込む事ができているし、諜報活動も順調だからな」
内緒だ、と言わんばかりにユーイン殿下は人差し指を唇の前に立てていた。ちなみに、セヴァルが最初に持参した魔法書にデヴァイン王国のものがあったのだが、あれは諜報の手によって書き写された物が複製されているそうだ。
「排他主義が充満している王国で活動ですか……」
あの様子を見る限り、他国出身の者が王城に入ったら、目の敵にされそうな気がする。そう考えていた私の声が無意識のうちに漏れていたらしい、ユーイン殿下は笑って仰った。
「どの国も一枚岩ではないからな。そこを突けば諜報員を潜り込ませる事はできる」
そう断言する殿下に、私は納得する。きっと私が知らないだけで、そういう貴族はいるのだろう。先代と今代国王陛下の方針が違うように。
「話を戻すが、その者の尻尾を掴みたい。エスペランサ嬢たちには協力を依頼する」
ユーイン殿下の言葉に、私たちは頷いた。
心からここへと来て良かったと思っている。微笑んで伝えれば、ユーイン殿下は良かったと言わんばかりに胸を撫で下ろす。彼は私の境遇を報告で知っていたらしい。何もできなかった事が一番心苦しかった、と言ってくれた。それだけで過去の私の心は救われた気がする。
そんな気持ちを受け入れる事ができるのも、公爵家の皆さん……特に公爵様のお陰なのかもしれない。
ユーイン殿下は私の表情で、何かを伝える決意をしたのか一通の手紙を出した。それは見慣れた紋章が封筒に押されている。それは、デヴァイン王国のものだった。
「エスペランサ嬢ならこの手紙の内容を察する事ができるだろうが……数日前に王国で王太子とエスペランサ嬢の結婚が数年後に行われると発表された。まあ、このエスペランサ嬢と書かれているのは、義妹のブレンダという娘で間違いないと報告が来ている。エスペランサ嬢もその認識で良いだろうか?」
「はい。私が婚約を白紙にされた時は、そのような話でした」
今も変わっていなければ、ブレンダが王太子妃のはずだ。
「そうか、元々はこちらに来る予定だったのは、義妹だったか。姿絵もエスペランサ嬢のものだったから、名前は忘れていたな……」
公爵様が思わず、と言ったように呟く。
「本当にブレンダという女がこちらに来られても困惑しただろうけど。まぁ、念には念を入れて公爵家の代替わりは情報統制を行なっていたから、あちらには先代に嫁ぐと思われていただろうがな」
ユーイン殿下は軽く身をすくめる。予言の通りに準備をしていたのだから、その根底がひっくり返る……なんて事になったら、帝国も混乱に陥っていた可能性もあったでしょうね。最終的には、予言の通りに事が運んでいるようだけれど。
やはり衝突は避けられないのだな、と私は思った。まあ、仕方ないわよね……王国の者は歩み寄りを一切しないもの。
「今後、王国と帝国の関係に溝が入るのは確実だ。まあ、あちらさんは禁呪が効いていると誤認しているままでいてもらうよう私たちも取り計らう予定なのだが……ひとつ問題があってな。二ヶ月後から社交界が始まるだろう? そこに王国と連なる者が参加するようだ」
「王国に連なる者?」
最初は密偵かと思ったのだが、どうやらそうではないらしい。帝国に王国の放った斥候はいないのだとか。
王国の者は周辺国を『デヴァイン大帝国の血を継がない野蛮な者』と認識しており、そんな彼らが何をしていようとも、大帝国の正式な血統を維持している王国の者に敵うはずがないと考えているのだ。そのため、周辺国が行うような情報収集の類は行わないのだという。
「傲慢ですね」
「まあ、私たちはあっちが勝手に油断してくれているのをありがたいと思うだけだ。お陰で王国へと入り込む事ができているし、諜報活動も順調だからな」
内緒だ、と言わんばかりにユーイン殿下は人差し指を唇の前に立てていた。ちなみに、セヴァルが最初に持参した魔法書にデヴァイン王国のものがあったのだが、あれは諜報の手によって書き写された物が複製されているそうだ。
「排他主義が充満している王国で活動ですか……」
あの様子を見る限り、他国出身の者が王城に入ったら、目の敵にされそうな気がする。そう考えていた私の声が無意識のうちに漏れていたらしい、ユーイン殿下は笑って仰った。
「どの国も一枚岩ではないからな。そこを突けば諜報員を潜り込ませる事はできる」
そう断言する殿下に、私は納得する。きっと私が知らないだけで、そういう貴族はいるのだろう。先代と今代国王陛下の方針が違うように。
「話を戻すが、その者の尻尾を掴みたい。エスペランサ嬢たちには協力を依頼する」
ユーイン殿下の言葉に、私たちは頷いた。